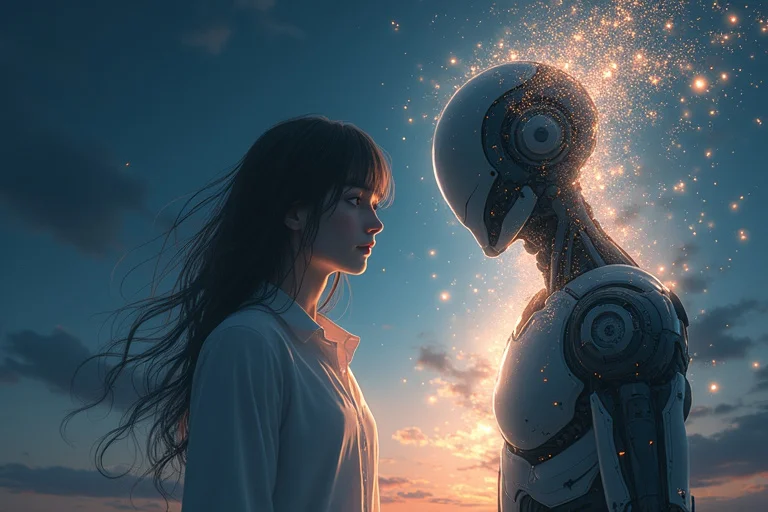第一章 幻色のノイズ
リヒトの世界は、沈黙で満たされていた。人々は唇を動かさず、身振り手振りと携帯端末に表示されるテキスト、そして床や空気を伝わる微かな振動だけで意思を疎通する。音という概念は、古の災害と共に失われたと教えられてきた。大気を震わせる乱暴なエネルギーは、文明を崩壊させた禁忌の力。それが、この世界の常識だった。
だが、リヒトには秘密があった。彼は、時折、世界に「色」を見る。それは物質が持つ固有の色ではない。何もない空間に、突如として現れては消える、光の粒子のような幻。風が壁の隙間を抜ける時、彼はそこに淡い青緑色のさざ波を見る。人々が足早に行き交う広場では、無数の鈍い黄土色の点が明滅する。リヒトはこれを「幻色(げんしょく)」と呼び、自分だけの狂気として胸の内に秘めていた。他人に話せば、きっと精神の異常を疑われるだけだろう。
記録官として働くリヒトの仕事は、過去の映像アーカイブを整理し、劣化したデータを修復することだった。もちろん、それらの映像にも音はない。建国以前の古い記録でさえ、音声トラックは意図的に消去されている。彼は、ガラス張りの静かなオフィスで、歴史から抹消されたはずのざわめきを、意味不明な色のノイズとして日々眺めていた。
その日、リヒトは業務外の調査で、立ち入りが禁止されている旧市街の廃墟区画に足を踏み入れていた。数週間前、この場所で彼は生涯で最も鮮烈な「幻色」を目撃したのだ。それは、まるで夜空を切り裂くオーロラのように、七色の光が渦を巻きながら天に昇っていく、壮大で暴力的なまでの美しさだった。恐怖と同時に、魂の根源を揺さぶられるような歓喜があった。あの奔流は何だったのか。その正体を知りたいという渇望が、彼を危険な区域へと駆り立てていた。
崩れかけたコンクリートの建物の間を、リヒトは息を殺して進む。埃っぽい空気に、錆びた鉄と湿った土の匂いが混じり合う。彼の視界の端々で、自分の足音が立てるくすんだ茶色の点が、ぽつり、ぽつりと生まれては消える。
そして、例の広場跡にたどり着いた時、それは再び現れた。
前回よりも微かだが、しかし確かに存在する色の流れ。金管楽器の輝きを思わせる黄金色の閃光、弦を弾くような紫紺の軌跡、そして、深く、優しく響くチェロのような緋色の調べ。それらは複雑に絡み合い、一つの巨大なタペストリーを織り上げていく。リヒトは息を呑んだ。これは単なるノイズではない。そこには明確な秩序と、感情と、そして何よりも――物語があった。
彼は、その色の奔流が発生している中心、瓦礫の山に埋もれた地下への入り口を見つけた。錆びついた鉄の扉が、わずかに開いている。好奇心と恐怖がせめぎ合う中、リヒトは意を決して、その暗闇へと続く階段に足を踏み入れた。彼の人生が、この沈黙の世界が、根底から覆されようとしていることなど、まだ知る由もなかった。
第二章 静寂のレジスタンス
地下に広がっていたのは、旧時代のデータサーバーが並ぶ、広大な保管庫だった。空気はひんやりと冷たく、機械油の匂いが鼻をつく。リヒトが見た「幻色」は、中央に鎮座する巨大な球形のコンソールから漏れ出していた。どうやら、何らかのシステムが自己修復と再起動を繰り返しているらしい。
彼がコンソールに近づいた、その時だった。
「そこで何をしている」
背後からかけられた声に、リヒトは心臓が凍りつく思いをした。いや、声ではない。彼の脳に直接響くような、指向性の高い振動波だった。振り向くと、暗がりから一人の女性が姿を現した。ノアと名乗る彼女は、鋭い眼光でリヒトを射抜きながら、警戒を解いていない。
「君も…『聴こえる』のか?」
ノアの問いに、リヒトは戸惑った。「聴こえる」とはどういう意味だ? 彼には何も聴こえていない。ただ、「見えて」いるだけだ。
リヒトが自分の幻色の体験を恐る恐る語ると、ノアの表情が驚きに変わった。
「色で見える…? それが、君の『音』なのか」
ノアは、自分たちが「音を取り戻す」ことを目的とするレジスタンスの一員であることを明かした。彼女たちの話によれば、この世界の沈黙は、かつて為政者が民衆を支配するために「音響兵器」の恐怖を捏造し、音を奪った結果だという。音は感情を煽り、人々を団結させる力を持つ。それを恐れた支配者層が、文化ごと音を根絶したのだ、と。
「私たちが探しているのは、『シンフォニア』と呼ばれる、失われた音楽のアーカイブよ。このサーバーのどこかに眠っているはず。それがあれば、世界に音を、感情を、自由を取り戻せる」
リヒトは衝撃を受けた。自分の見ていた幻色の正体は、「音」という失われた感覚だったのだ。そして、あの美しい色の奔流は「音楽」というものだった。彼は初めて、自分の特異な能力に意味を見出した。孤独な狂気だと思っていたものは、世界を変える鍵なのかもしれない。
ノアたちに協力することを決めたリヒトは、彼の共感覚を頼りに、サーバーの深層を探査し始めた。彼の網膜に映る色のパターンを解析することで、通常の探査では見つけられない隠されたデータ領域を特定していく。彼は生まれて初めて、誰かと秘密を共有し、同じ目標に向かう高揚感を感じていた。
数日後、ついに彼らは目的のデータを発見する。『原初の音源:プロジェクト・シンフォニア』と名付けられたアーカイブ。ノアたちが歓喜の声を上げる中、リヒトはデータを開放するための最終プロトコルを起動した。彼の目の前に、純粋な音楽データが、これまで見たこともないほど複雑で、精緻で、神々しいまでの色彩となって溢れ出した。それは宇宙の誕生を思わせるような、至高の美しさだった。この光景を、世界中の人々と分かち合いたい。リヒトは心の底からそう願った。しかし、アーカイブと共に解凍されたもう一つのファイルが、彼の純粋な願いを絶望の淵へと突き落とすことになる。
第三章 響きの黙示録
そのファイル名は、『警告:ハーモニーの捕食者について』と記されていた。それは、シンフォニア計画の最高責任者が、未来の誰かに向けて遺した最後の記録だった。リヒトがファイルを開くと、彼の視界に、今まで見てきたどんな色とも違う、おぞましい光景が広がった。
記録は語っていた。
音響兵器など、はじめから存在しなかった、と。
人類が音を捨てた本当の理由は、支配や圧政のためではない。それは、宇宙から飛来した、音をエネルギー源とする高次元生命体から逃れるための、唯一の生存戦略だったのだ。
その生命体は、研究者たちから『コーラス・ワーム』と呼ばれていた。彼らは物理的な実体を持たず、音の振動――特に、複数の周波数が調和した「ハーモニー」に強く引き寄せられる。そして、音源に集まると、その周辺の空間ごと、あらゆる物質をエネルギーに変換し、捕食してしまうのだという。
映像記録には、コーラス・ワームが都市を飲み込む様が、「色」として記録されていた。それは、美しい音楽の色彩とは真逆の、光を吸収する漆黒の亀裂だった。あらゆる色が、音が、命が、その絶対的な無に吸い込まれていく。それは、絶望そのものを可視化したような、身の毛もよだつ光景だった。
建国以前の大災害の正体は、これだったのだ。当時の人々は、音楽や話し声、あらゆる生活音で溢れた世界で、知らず知らずのうちに捕食者を呼び寄せてしまった。生き残った為政者たちは、人類を存続させるために、苦渋の決断を下した。音を世界から完全に消し去り、その概念ごと封印することで、コーラス・ワームの餌場ではないことを示す。沈黙は、支配の道具ではなく、人類を守るための盾だったのである。
リヒトは全身から血の気が引くのを感じた。ノアたちがやろうとしていることは、正義の革命などではなかった。それは、人類の滅亡を招く、無邪気な自殺行為だ。彼が追い求めていた美しい音の世界は、同時に世界を終わらせるためのトリガーだった。
「リヒト、どうしたの? 顔が真っ白よ」
コンソールの光に照らされたノアが、不思議そうに彼を見た。彼女はまだ何も知らない。仲間たちと共に、数時間後に街の中心にある旧時代の放送塔をジャックし、この「シンフォニア」を全世界に響かせる計画を着々と進めている。
リヒトの心は引き裂かれそうだった。真実を話すべきか? だが、どうやって信じさせる? 自分の見る「色」以外に証拠はない。彼らを止めなければ、世界は終わる。しかし、それは同時に、あの至高の美しさを持つ音楽を、永遠に葬り去ることを意味していた。一度だけでもいい、あの色彩が世界に満ちる瞬間を見てみたい。そんな悪魔的な欲望が、彼の心にかすかに芽生えた。
いや、だめだ。彼は首を振った。自分が見た漆黒の絶望を、他の誰にも味わわせてはならない。彼は決意を固めた。たとえ憎まれようとも、裏切り者と呼ばれようとも、この静寂の世界を守らなければならない。
第四章 心に鳴るシンフォニア
放送塔の頂上は、風が強く吹き付けていた。ノアと数人の仲間が、巨大なアンテナにシンフォニアのデータを接続し、最終調整を行っている。街の灯りが、眼下に静かな光の海となって広がっていた。
「あと数分で、世界は変わるわ」
ノアが晴れやかな表情でリヒトに言った。彼女たちの長年の夢が、今まさに叶おうとしている。
その瞬間、リヒトはノアの前に立ちはだかった。
「やめるんだ、ノア」
彼の言葉は、振動となって彼女に伝わった。
「何を言っているの? リヒト。あなたも望んだはずでしょう?」
仲間たちが訝しげにリヒトを見る。裏切り者を見る目だった。
言葉では伝えられない。信じてもらえない。リヒトに残された手段は一つだけだった。彼は、自分の能力を極限まで集中させた。彼はもう、音を色として「見る」だけではなかった。彼は、自分の記憶にある「色」を、他人の脳に直接投影する術を、この数日間の探査の中で無意識に会得していたのだ。
「僕が見てきたものを、君にも見せる」
リヒトはノアの額に手をかざした。そして、彼の記憶の中にある二つの光景を、彼女の精神に直接送り込んだ。
最初に、シンフォニアの色彩がノアの意識に流れ込む。宇宙の創造にも似た、神々しいまでの光と色の洪水。生命の歓喜、愛の煌めき、悲しみの深い藍色。ノアは息を呑み、その美しさに涙を流した。これが、音。これが、音楽。
だが、その感動は一瞬で塗り替えられた。
次にリヒトが送ったのは、コーラス・ワームがすべてを飲み込む、あの漆黒の絶望のビジョンだった。美しい音楽の色が、汚され、引き裂かれ、絶対的な「無」に吸い込まれていく。生命の叫びは色を失い、世界そのものが黒く塗りつぶされていく。それは、死よりも深い、存在の完全な消滅。ノアの精神は、その根源的な恐怖に絶叫した。
「やめて…!」
リヒトが手を離すと、ノアは膝から崩れ落ちた。彼女は震えながら、何も言えずにリヒトを見上げている。彼女の瞳には、先ほどまでの革命家の輝きはなく、ただ深い恐怖と理解が宿っていた。彼女は悟ったのだ。リヒトが見ていたものの真実を。そして、自分たちが犯そうとしていた過ちの大きさを。
計画は中止された。レジスタンスは解体され、シンフォニアのデータはリヒトの手によって、再びサーバーの最も深い階層に封印された。世界は何も変わらず、静寂を保ったまま救われた。
リヒトは、記録官としての静かな日常に戻った。しかし、彼の見る世界は、もう以前と同じではなかった。街を行き交う人々の無言のざわめきの中に、彼は時折、シンフォニアの色の残響を見る。風の音に、雨の雫に、誰かの微かな寝息に、失われた音楽の断片が、美しい光の粒子となってきらめいている。
この世界の沈黙は、決して空っぽではない。それは、無数の奏でられることのない音楽を、その内に秘めているのだ。リヒトは、その美しさと、それがもたらす破滅を知る、世界で唯一の人間となった。
誰にも共有できない、至高の音楽。誰にも話すことのできない、世界の秘密。それは彼にとって、あまりにも重く、そして、あまりにも美しい孤独だった。彼の心の中だけでは、静寂の世界に、今も壮大なシンフォニアが鳴り響いている。永遠に。