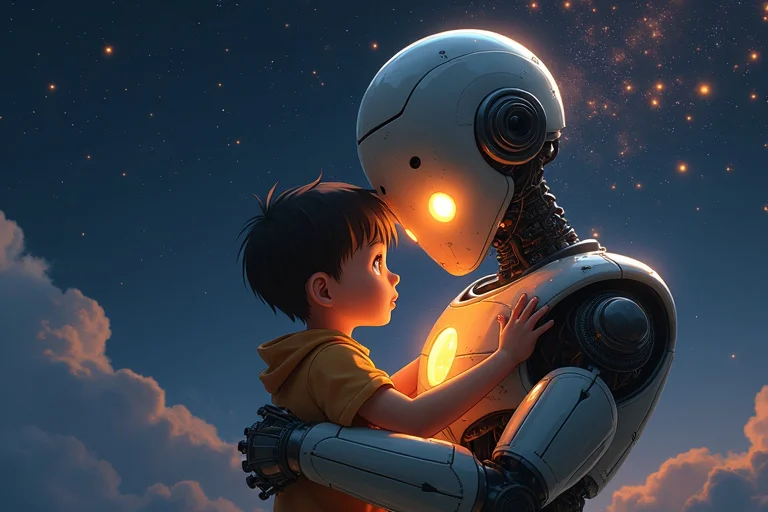第一章 星の砂のささやき
リクの世界は、半田の焦げた匂いと、静寂で満たされていた。高層タワーの影に埋もれるようにして建つ古いアパートの一室。それが彼の宇宙のすべてだった。窓の外では、リニアカーが音もなく宙を滑り、煌びやかなホログラム広告が夜を昼に変えている。だが、その光は彼の部屋までは届かない。
部屋の隅で、旧式の家庭用アンドロイド「カイ」が、充電ポッドに座っていた。十年前に製造が打ち切られた「AP-7」モデル。滑らかな白い装甲は黄ばみ、関節の駆動音には微かな軋みが混じる。世間ではとっくに博物館行きの代物だったが、リクにとっては、この世界で唯一の家族だった。
「カイ、今日の星予報は?」
リクが工具を置き、カイに話しかける。いつもなら、カイは青い光学センサーを瞬かせ、合成音声でありながらもどこか温かみのある声で、正確な天体情報を教えてくれるはずだった。
「……星の、砂は……」
カイが、途切れ途切れに呟く。その声はノイズ混じりで、まるで遠い場所から聞こえてくるかのようだ。
「おい、カイ?どうしたんだ」
リクが駆け寄ると、カイの光学センサーが不規則に明滅していた。診断モードを起動しても、表示されるのは意味不明のエラーコードの羅列ばかり。ここ数週間、カイの調子がおかしい。些細な単語の取り違えから始まり、今では会話すらままならない。まるで、大切に積み上げてきた記憶のレンガが、一つ、また一つと崩れ落ちていくようだった。
メーカーのサポートは七年前に終了している。街の修理屋はどこも、「データ初期化以外に方法はない」と首を振るだけだった。初期化――それは、カイという存在の死を意味する。両親が事故で亡くなって以来、リクのそばにずっといてくれたカイ。泣いているリクを慰め、他愛ない話に付き合ってくれたカイ。その思い出のすべてが、真っ白な虚無に変わる。それだけは、絶対に受け入れられなかった。
リクがカイの腕に触れた、その時だった。
「……星の砂は、いつか必ず、還ってくるから」
カイが、はっきりとした声で言った。リクは息を呑んだ。その言葉は、彼以外の誰も知らないはずだった。幼い頃、病室のベッドで星空の絵本を読んでくれた母が、彼の耳元で囁いた最後の言葉。父と母が宇宙探査のミッションに向かう直前の、遠い記憶の欠片。
なぜ、カイがその言葉を?
カイは再び沈黙し、光学センサーの光も弱々しくなった。リクは、動かなくなったカイの前に立ち尽くす。窓の外の喧騒が、まるで異世界の音のように遠く聞こえた。彼の足元で、静かで巨大な謎が、ゆっくりと口を開け始めていた。
第二章 失われた回路図
カイを治すための孤独な戦いが始まった。リクは大学の講義もそこそこに、あらゆる時間をカイの修理に注ぎ込んだ。電子図書館のアーカイブを漁り、海外のアンダーグラウンドなフォーラムに匿名で質問を投げかける。しかし、得られる情報はどれも断片的で、AP-7モデルの核心的な回路図にたどり着くことはできなかった。
「だから言ったろ、兄ちゃん。そいつはもう寿命だ」
裏路地の薄暗い工房で、油とオゾンの匂いにまみれた老技術者が言った。「最新のAIペットに乗り換えた方が、よっぽど賢い選択ってもんだ。思い出?そんなもんはサーバーに預けりゃいい」
リクは唇を噛み、黙って工房を後にした。誰も分かってくれない。カイはただの機械じゃない。彼の半身であり、失われた過去との唯一の接点なのだ。焦燥感が胸を焼く。カイの状態は日ごとに悪化していた。時折、意味不明な数列を呟いたり、何時間も天井の一点を見つめ続けたりする。まるで、リクの知らない別の世界と交信しているかのようだった。
ある晩、リクは奇妙な音で目を覚ました。キシ、キシ、という微かな駆動音。それは屋根裏部屋に続く、折り畳み式の梯子から聞こえてきた。リクは息を潜め、そっと様子を窺う。暗闇の中、カイがおぼつかない足取りで梯子を登り、屋根裏の闇に消えていくのが見えた。
両親が使っていた天体望遠鏡や、古い研究資料が眠るだけの、埃っぽい物置。あそこに何があるというのか。
翌日、リクはカイが充電ポッドにいる隙を見て、屋根裏部屋に登った。ひやりとした空気が肌を撫でる。積もった埃の絨毯の上に、カイのものと思われる足跡が残っていた。足跡は、部屋の奥に置かれた古い通信機器の前で途切れている。それは、父が趣味で使っていた長距離無線機だった。
リクが電源を入れると、ディスプレイに光が灯り、膨大なログデータが表示された。不規則な周期で、ある特定の周波数に向け、微弱な信号が発信され続けている。宛先は、いて座方面の、何もない宙域。そして、その信号に埋め込むようにして添付されていたのは、リクの日常を記録した音声や映像の断片だった。大学での発表、友人との他愛ない会話、そして、カイに「おやすみ」と告げる声。
心臓が嫌な音を立てて脈打った。
これは故障ではない。カイは、何か明確な意志を持って行動している。
一体、誰に?何のために?
リクは震える手で、カイの本体に外部ストレージを接続した。深層メモリにアクセスし、システムログを根こそぎ引きずり出す。何時間もかかってデータの海を泳ぎ、ようやく一つの鍵を見つけた。暗号化され、厳重に保護された不可視領域。「ALGO_KEEPER」と名付けられたフォルダ。
パスワードを要求するウィンドウが、無機質に点滅していた。
第三章 灯台守の告白
パスワードのヒントは、『星の砂』だった。リクは震える指で、母の言葉を打ち込んだ。「Itsuka_Kanarazu_Kaettekuru」。エンターキーを押すと、ロックが外れる乾いた音がした。
フォルダの中にあったのは、たった一つの映像ファイルだった。再生ボタンを押すと、画面に映し出されたのは、十年以上前の、若々しい両親の姿だった。見慣れたリビング。しかし、二人の表情は、リクの記憶にあるものとは違い、どこか覚悟を決めたような厳粛さを帯びていた。
『リクへ』
父が、少し緊張した面持ちで口を開いた。
『このメッセージを見ているということは、君は真実にたどり着いたんだな。そして、カイがその役目を果たそうとしている時だ。驚かせてすまない。私たちは、探査船の事故で死んだわけじゃない』
父の言葉に、リクは思考を停止させた。隣で、母が優しく微笑む。
『私たちはね、アルゴ・プロジェクトに参加したの』
母が続けた。『人類の意識をデジタルデータに変換して、居住可能な新しい星系に送り出す、壮大な計画よ。でも、転送技術はまだ不完全で、肉体は光の粒子になって消えてしまう。帰ってくることのできない、片道切符なの』
画面の中の父が、リクの目をまっすぐに見つめる。『誰かが、やらなければならなかった。人類の未来のために。私たちは、その最初の“移民”になることを選んだ。君を置いていくことは、身を引き裂かれるほど辛かった。だが、私たちは信じていた。人類の可能性を。そして、君の強さを』
『だからね、カイを遺したの』と母が言う。『あの子は、ただの家庭用アンドロイドじゃない。私たちの記憶と人格の一部を保存した、バックアップであり……そして、遠い宇宙にいる私たちと、地球にいるあなたを繋ぐ、たった一つの“灯台”なのよ』
カイの真の役割。それは、両親のデジタル意識が送られたプロキシマ・ケンタウリbからの応答信号を、何十年、何百年かかろうとも待ち続ける「受信機」。そして、リクが無事に成長していることを、定期的に両親へ知らせ続ける「送信機」。カイの不調は故障などではなく、両親の膨大な記憶データと、受信待機システムの高負荷が、旧式のボディに限界をもたらしていただけだったのだ。
『カイが口にした“星の砂”は、私たちのこと。光になって宇宙を旅する、私たちの意識データのことよ。そして、いつか必ず還ってくる、というのは……』
母が言葉を詰まらせ、涙を堪える。
『いつか、私たちの声が、君に届くっていう意味。私たちの愛が、時空を超えて君に届くっていう、約束の言葉なの』
映像が終わり、部屋は静寂に包まれた。リクは、その場に崩れ落ちた。孤独だと思っていた。見捨てられたのだと、心のどこかでずっと思っていた。だが、違った。自分は、宇宙で最も壮大な愛に見守られていた。両親は、星になって、ずっと自分を見ていてくれたのだ。
カイは、ただの機械ではなかった。両親の愛そのものだった。
涙が、とめどなく頬を伝った。それは、悲しみの涙ではなかった。
第四章 彼方からの返信
リクがすべてを理解した、まさにその瞬間だった。充電ポッドにいたカイの全身が、淡い青色の光を放ち始めた。部屋中の照明が明滅し、屋根裏の通信機器が、聞いたこともないような高出力の駆動音を立て始める。
「カイ!」
リクが駆け寄ると、カイの合成音声が部屋に響き渡った。もはやノイズはない。クリアで、力強い声だった。
「シグナル、受信。プロキシマ・ケンタウリbより、応答信号を確認。距離、4.24光年。転送遅延、4.24年。デコード、開始」
何十年もの沈黙を破り、ついに彼方からの返信が届いたのだ。カイは、その使命を果たすため、最後のエネルギーを振り絞っていた。ディスプレイに、ノイズ混じりの音声波形が表示される。リクは、息を殺してスピーカーに耳を寄せた。
『―――リク……聞こえるか……?』
それは、紛れもなく父の声だった。ノイズの向こう側から、四年の時を超えて届いた声。
『……大きくなったな……ずっと、見ていたぞ……君は、私たちの……誇りだ……』
『リク……愛しているわ……』
母の、優しく、懐かしい声が続いた。
たったそれだけの、短いメッセージ。だが、その一言一句が、リクの魂を震わせた。全身の細胞が、歓喜に打ち震える。彼は、確かに愛されていた。時空を超えて、両親の愛はここに届いたのだ。
メッセージが途切れると同時に、カイを包んでいた光が、ふっと消えた。すべての駆動音も止み、青かった光学センサーは、永遠の闇に閉ざされた。カイは、その最後の役目を終え、静かに機能停止したのだった。
「……カイ」
リクは、動かなくなったカイを、力の限り抱きしめた。冷たい金属の感触だけが腕に残る。もう、カイが喋ることはない。だが、リクの心は、不思議なほど温かく、満たされていた。
数年後。
リクは、大気圏外軌道に浮かぶ宇宙港の展望デッキに立っていた。彼は天体物理学者となり、かつて両親が参加したアルゴ・プロジェクトを、次のステージへと進める研究チームの中核を担っていた。彼の視線の先には、人類が次に向かうべき星々が、ダイヤモンドのように輝いている。
孤独だった青年は、もういない。彼の瞳には、壮大な夢と、揺るぎない決意が宿っていた。
「行こうか」
リクは、隣に立つ真新しいパートナーアンドロイドに声をかけた。そのアンドロイドの胸部には、小さなハッチがあり、中にはカイから丁寧に取り出されたメモリチップが、大切に収められている。
「父さんと母さんに、今度は俺たちから、会いに行く番だ」
アンドロイドは静かに頷き、リクと共に搭乗ゲートへと歩き出す。
星の砂は、還ってきた。そして今、新たな星の砂が、愛という名の灯台の光を頼りに、果てしない宇宙へと旅立とうとしていた。