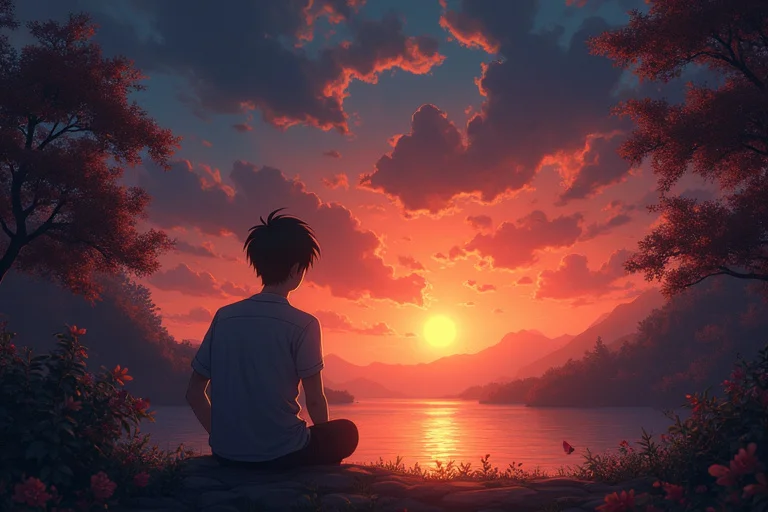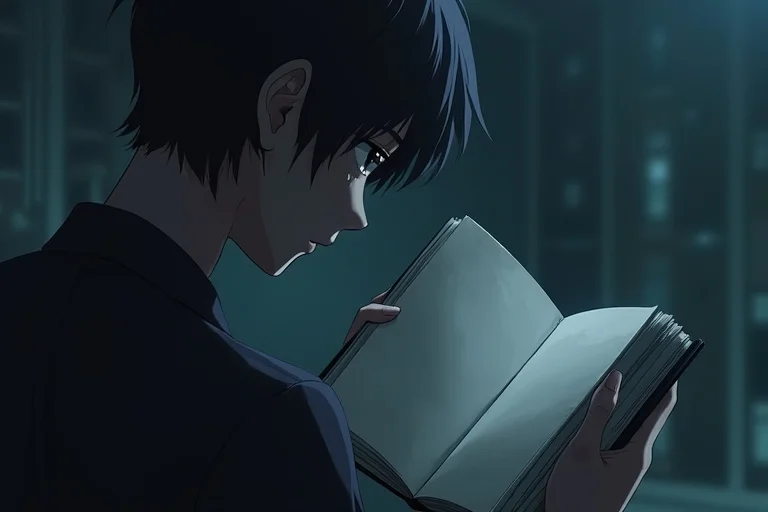第一章 予言の活字
高槻亮(たかつき りょう)の日常は、鉛の匂いと、インクの微かな甘さが混じり合った空気の中で、静かに時を刻んでいた。祖父から受け継いだ活版印刷所『月光堂』の扉は、現代の喧騒から彼を守るための結界のように重々しい。客のほとんどは、昔馴染みの老人か、物好きな若者だけ。亮は、デジタル化の波に取り残されたこの場所で、時代の化石のような活字を拾い、組むだけの退屈な日々を送っていた。
その日も、夕暮れの光が埃の舞う室内に斜めに差し込む頃、亮は店の片付けを始めていた。扉の郵便受けに、ことり、と軽い音がした。いつものダイレクトメールだろうと気にも留めずに手を伸ばした亮は、その封筒の手触りに僅かな違和感を覚えた。ざらりとした厚手の紙。宛名はなく、ただ『月光堂様』とだけ、美しい明朝体で記されている。
封を切ると、中から一枚のカードが現れた。そこに印刷されていたのは、一篇の短い詩だった。インクのかすかな凹凸が指先に伝わる。紛れもない、活版印刷だ。
「十二月の雪が、記憶のインクを溶かす時、
一番星は地に落ちるだろう。
その輝きは、忘れられた恋歌となる。」
詩の下には、小さく『十二月七日』と日付が添えられていた。亮は眉をひそめた。使われている活字は、祖父が晩年に心血を注いでデザインしたオリジナルの書体『月詠(つくよみ)』に酷似している。しかし、この活字は祖父の死後、誰にも使わせていないはずだった。悪趣味ないたずらか。亮は舌打ちし、そのカードを机の引き出しの奥にしまい込んだ。
それから三日後の十二月七日。街は冷たい雨に濡れていた。亮がラジオから流れるローカルニュースをぼんやりと聞いていると、アナウンサーが淡々とした口調で告げた。
「昨夜遅く、市内の天文台の展望デッキから、著名な天文写真家である星野一樹(ほしの かずき)さんが転落し、亡くなりました。警察は事故と見て調べています」
その瞬間、亮の背筋を氷の指がなぞった。「一番星は地に落ちるだろう」。脳裏に、あの詩の一節が雷鳴のように響き渡る。星野氏は、その美しい星の写真から「一番星を撮る男」として地元では有名人だった。偶然か。いや、偶然にしては出来すぎている。引き出しの奥で眠るカードが、まるで生き物のように、不気味な存在感を放ち始めた。亮の退屈だった日常は、その日を境に、静かに軋み始めたのだった。
第二章 消えた鋳造家
最初の詩が届いてから一週間後、再び郵便受けに同じ手触りの封筒が置かれていた。亮は唾を飲み込み、震える手で封を切った。
「錆びついた時計の針が、偽りの時を刻む時、
銀色の魚は川に還る。
その鱗は、盗まれた旋律を奏でる。」
日付は『十二月十五日』。今度は、明確な殺意や悪意ではなく、どこか物悲しい謎かけのような響きがあった。亮は混乱した。これは単なる偶然なのか、それとも誰かが仕組んだ劇場型の犯罪予告なのか。
亮は警察に相談したが、担当した刑事は「詩の内容と事件を結びつけるのは、あなたの思い込みでしょう」と、まともに取り合ってはくれなかった。孤独な恐怖の中、亮は自ら謎を解くしかないと決意する。手がかりは、この『月詠』の活字だ。
『月光堂』の活字棚の奥深く、埃をかぶった木箱が眠っている。祖父が遺した『月詠』の母型(ぼけい)と、鋳造された活字のセットだ。祖父は腕利きの鋳造家でもあった。亮は虫眼鏡を片手に、送られてきた詩と、木箱の中の活字を丹念に比較する。文字の止めや跳ね、インクの乗り具合まで寸分違わない。間違いなく、この印刷所の活字が使われている。しかし、厳重に管理しているこの活字を、誰がどうやって持ち出したというのか。
亮の思考は、自然と祖父へと向かった。物静かで、仕事一筋だった祖父。晩年は少しずつ記憶が曖昧になり、昔話を繰り返すことが多かった。その祖父が、何かを隠していたのだろうか。亮は、祖父の遺品がしまわれたままになっている屋根裏部屋の扉を開けた。黴と古い紙の匂いが、過去からの使者のように亮を包み込む。段ボール箱を一つ一つ開けていくと、その底から、革張りの古びた日記帳が一冊、姿を現した。
第三章 日記の中の恋歌
日記は、亮が生まれるずっと前、若き日の祖父の筆跡で綴られていた。そこには、亮が知らない祖父の姿があった。活字への情熱、印刷所の経営の苦悩、そして――一人の女性への思慕。
彼女の名前は、月島小夜子(つきしま さよこ)。儚げで、美しい詩を紡ぐ女性だった。祖父は彼女の詩に魅せられ、彼女の言葉を世界で一番美しい形で残したいと願い、オリジナルの書体『月詠』を作り上げた。日記には、小夜子の詩を初めて印刷した日の、燃えるような喜びが記されていた。
『彼女の言葉が、鉛の活字となって生まれ変わる。インクの匂いと共に、彼女の魂が紙の上に定着する。これ以上の幸福があるだろうか』
二人の仲は深まり、将来を誓い合うまでになった。しかし、幸せは長くは続かなかった。ある雨の日、小夜子は交通事故に遭い、一命は取り留めたものの、過去の記憶の大部分を失ってしまった。祖父のことも、自らが詩人であったことさえも。
祖父は絶望しなかった。彼は信じていた。自らが作った『月詠』で、彼女が紡いだ詩を印刷して送り続ければ、いつか彼女の記憶が蘇るはずだと。日記は、それから何年にもわたり、小夜子に宛てて詩を送り続けた記録で埋め尽くされていた。「一番星は地に落ちるだろう」も、「銀色の魚は川に還る」も、すべて小夜子が作った詩だったのだ。
しかし、日記の最後のページは、悲痛な一文で締めくくられていた。
『小夜子さんが亡くなった。五年前に。遠い親戚の方から、知らせがあった。私の声は、私の活字は、最後まで彼女には届かなかった』
亮は愕然とした。小夜子さんは既にこの世にいない。祖父も三年前に亡くなっている。では、一体誰が、今になってこの詩を送りつけてくるのか。犯人は、祖父と小夜子の過去を知る、何者かに違いない。謎は解けるどころか、より深く、より切実なものとなって亮の心に突き刺さった。
第四章 十二月の雪が溶かすもの
途方に暮れた亮は、もう一度、祖父の日記を手に取った。パラパラとページをめくるうち、最後のページに何か厚いものが挟まっていることに気づいた。それは一枚の便箋だった。インクが滲んだ、見慣れた筆跡。それは、十年前に家を出て以来、疎遠になっていた父、高槻誠(まこと)からの手紙だった。亮の心臓が大きく跳ねた。
手紙は、祖父に宛てられていた。
『父さんへ。
最近、父さんの物忘れがひどくなっているのが心配です。さっき話したことも、すぐに忘れてしまう。でも、小夜子さんの詩のことだけは、時々、ふと思い出したように口にするね。
だから、僕が代わりにやろうと決めました。父さんが生涯をかけて愛した人の詩を、父さんが心血を注いで作った活字で、父さんに届けることにします。
たとえ父さんが、小夜子さんのことも、この手紙を書いた僕のことさえも忘れてしまっても。父さんが愛した記憶の欠片だけは、僕が届け続けるから。
父さん、あなたの息子より』
亮は、その場に崩れ落ちた。全身から力が抜け、手紙がはらりと床に落ちる。
そうか、そういうことだったのか。
詩を送っていたのは、父だったのだ。認知症が進み、愛する人の記憶さえ失いかけていた祖父のために。祖父が愛した詩を、祖父自身の記憶を呼び覚ますために、送り続けていたのだ。
星野写真家の転落事故も、古い時計店の閉店も(「銀色の魚」は店主の名字が「銀鱗」だった)、すべては偶然だった。亮が、詩の世界に現実を無理矢理こじつけていただけだったのだ。ミステリーなど、どこにも存在しなかった。そこにあったのは、父の、不器用で、しかしあまりにも深い愛情の物語だった。
活版印刷を古臭いと嫌い、家を飛び出した父。そんな父を、亮は心のどこかで軽蔑していた。しかし、父は誰よりも、祖父の仕事と、その想いを理解していたのだ。無価値だと思っていたこの場所に、これほどまでの愛が満ちていたことに、亮は初めて気づいた。
翌日、亮は活字棚から『月詠』を手に取った。一文字、一文字、まるで祈るように拾い上げ、版を組んでいく。それは、誰の詩でもない、亮自身の言葉だった。
「乾かないインクが、時を超える。
鉛の星屑は、あなたの愛を語る。
父から子へ、そして僕へと。」
インクローラーを滑らせ、ハンドルに体重をかける。ガチャン、という重い音と共に、真っ白な紙に、くっきりと文字が刻まれた。インクの匂いが、不思議と涙の匂いに似ていた。
亮は、そのカードを父に送ることはしなかった。ただ、印刷所の壁の一番目立つ場所に、大切に飾った。
謎は解けた。犯人は見つかった。しかし、それは誰かを断罪するためのものではなく、失われた記憶と、受け継がれていく想いを確認するための、切なくも温かい旅だった。
鉛の匂いが満ちる静かな印刷所で、亮は静かに微笑んだ。彼の日常はもう、退屈な灰色ではなかった。そこには、愛という名の、決して乾くことのないインクの色が、鮮やかに満ちているのだった。