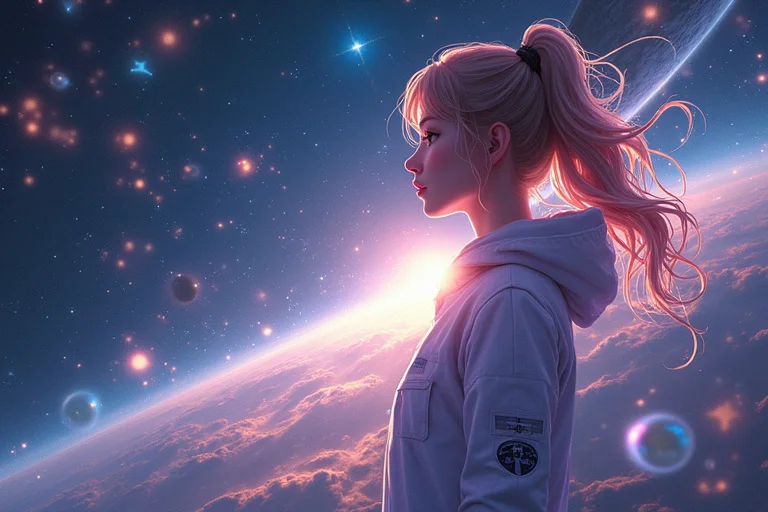第一章 残響の街
カイの視界は、常に砕け散ったガラスのようだった。太陽が放つスペクトルの一条一条が、彼の生体光学センサーに触れるたび、無限に分岐する未来の可能性へと炸裂する。右に曲がれば車に轢かれる未来、左に曲がれば旧友と再会する未来、立ち止まれば酸性雨に打たれる未来。それらが数千、数万の奔流となって同時に流れ込み、彼の思考を飽和させる。
「ノイズが……ひどい」
漏れた声は、機械部品が軋むような乾いた音を立てた。彼の身体は、失われた生体組織を補うために組み込まれた機械と、かろうじて残った有機部分が不協和音を奏でるキメラだ。街の喧騒は、可能性の洪水に拍車をかける。昨日までそこにあったはずの時計塔は跡形もなく、代わりにねじれた金属のオブジェが空を突き刺している。すれ違う人々の記憶は、彼の知る過去とは微妙に食い違い、その矛盾が彼の精神を削り取っていく。
宇宙が絶えずその姿を変えているのだと、カイは知っていた。恒星が命を終える遠い宇宙の片隅で時間軸が融合し、ブラックホールが双子を飲み込む深淵で歴史が分離する。人々は、書き換えられた現実に無意識に適応し、昨日の記憶との齟齬を「気のせい」として処理してしまう。だが、カイにはできなかった。彼の知覚は、その「ズレ」そのものを捉えてしまうのだ。
そんな地獄のような現実の中で、ただ一つ、彼に安らぎを与えるビジョンがあった。
それは、あらゆる分岐の果て、どの選択肢を選んでも決して辿り着けない場所に存在する、静かな海辺の光景。白い砂、穏やかな波、地平線に沈むアプリコット色の太陽。その風景だけは、時間軸がどれほど揺らごうとも、彼の知覚の中で常に変わらず、静謐な光を放ち続けていた。到達不可能な、聖域。
彼はその風景を「ゼロ」と名付けた。あらゆる可能性が収束し、そして消失する場所。
第二章 揺らぐ座標
自室の冷たい床に座り込み、カイは自身の左腕を見つめた。金属と合成皮膚で覆われた腕が、一瞬、陽炎のように揺らぎ、向こう側の壁が透けて見える。自己存在の希薄さ。彼は、この流動する世界における、不確かな座標の一つに過ぎないのかもしれない。
「私は……いつからここにいる?」
問いは虚空に溶ける。彼の記憶もまた、世界の再構築の度に上書きされ、断片化している。確かなのは、この情報過多による絶え間ない苦痛と、脳裏に焼き付いて離れない「ゼロ」の光景だけだった。
なぜ、あの場所へは行けないのか。
あらゆる未来を視ることができるのなら、そこへ至る道筋もまた、無数に存在するはずだ。しかし、カイがどれだけ可能性の枝をたどっても、「ゼロ」は常に地平線の彼方にあり、決して手の届く現実にはならない。まるで、この世界の法則そのものに拒絶されているかのように。
ならば、法則を捻じ曲げるしかない。
カイは立ち上がり、部屋の中央に投影されたデータコンソールを起動した。指先から伸びる光の糸が、膨大な情報の海へと接続する。彼は、この世界の根幹を成す物理法則の歪み、歴史の狭間に埋もれた禁断の技術を探し始めた。苦痛から逃れるためではない。ただ一つの確かなものを、その手で掴むために。
何日も、何週間も続いた探索の果てに、彼は一つの単語を発見した。それは、古代の物理言語で記された、忘れ去られた物質の名だった。
――無時間結晶(アクロナル・クリスタル)。
第三章 無時間結晶
「無時間結晶」とは、時間軸の変動から完全に隔絶された物質。それは、観測された情報、特に未来の可能性の一つを、その流動性から切り離し、絶対的な「現実」として凍結させる力を持つという。
「これだ……」
カイの機械の心臓が、かすかに鼓動を速めた。これさえあれば、「ゼロ」のビジョンを奔流する可能性の中から釣り上げ、現実世界に固定できるかもしれない。
データが示す結晶の在り処は、かつて「旧首都」と呼ばれ、大規模な時間軸震災によって放棄された汚染区域の地下深くに位置する、物理学研究所の跡地だった。
カイは錆びついたリニアモーターカーを駆り、灰色の大地を疾走した。空には二つの月が浮かんでいた。昨日までは一つだったはずだ。そんな些細な変化は、もはや彼の心を揺さぶらない。目指す場所は、ただ一つ。
研究所の入り口は巨大な瓦礫で塞がれていたが、彼の腕の駆動力がコンクリートをたやすく粉砕した。内部に足を踏み入れると、ひやりとした空気が肌を撫でる。埃の匂いと、微かなオゾンの香り。何世紀もの間、誰の介入も受けずに眠っていた時間の澱が、そこには満ちていた。
暗闇の中を、自身の光学センサーだけを頼りに進む。崩れた通路、停止した機械の残骸。やがて彼は、研究所の最深部、球状の巨大なチャンバーへとたどり着いた。
その中央に、それはあった。
台座の上で、周囲の闇を吸い込むかのように鎮座する、拳ほどの大きさの黒い結晶。それは光を反射せず、ただ純粋な「無」としてそこに存在していた。
第四章 結晶の共鳴
カイはゆっくりと、無時間結晶に手を伸ばした。指先がその冷たい表面に触れた瞬間、世界が爆発した。
彼の知覚は無限に増幅され、宇宙開闢から終焉までの、ありとあらゆる時間軸の、全ての可能性が一斉に彼の意識へと雪崩れ込んできた。星が生まれ、死んでいく音。文明が興り、滅びていく光景。愛と憎悪、歓喜と絶望。森羅万象の情報が、彼の精神を焼き切ろうとする。
「ぐっ……あ……!」
悲鳴にならない声が漏れる。身体中の回路がショートし、有機部分の神経が悲鳴を上げた。だが、彼は屈しなかった。意識が途切れる寸前、彼は脳裏に浮かぶたった一つの光景に全神経を集中させる。
――静かな海辺。白い砂。穏やかな波。アプリコット色の太陽。
そのイメージを、祈りのように結晶へと注ぎ込む。すると、情報の嵐が嘘のように凪いでいった。カイの手の中にある黒い結晶が、内側から淡い、柔らかな光を放ち始める。それは、彼がずっと見続けてきた「ゼロ」の光と同じ色をしていた。
光は一条の筋となり、チャンバーの壁を貫いて、虚空へと伸びていく。それは道だった。決して到達できなかったはずの、あの場所へと続く、唯一の道筋。カイはふらつく足で立ち上がり、光に導かれるまま、一歩を踏み出した。
第五章 境界線
光の道を歩き続けると、やがて視界が開けた。
目の前に広がっていたのは、まさしく彼が焦がれ続けた「ゼロ」の風景だった。どこまでも続く白い砂浜。寄せては返すさざ波の、心地よい音。肌を撫でる潮風は、ほんのりと塩の香りを運んでくる。空には、穏やかな光を放つ太陽が浮かんでいる。
ついに、たどり着いた。
情報過多の地獄から解放される、安息の地。カイの胸に、かつて感じたことのない歓喜が込み上げた。彼は砂浜へと一歩、足を踏み出そうとした。
その瞬間。
ピシッ、と。世界がガラスのように軋む音が響いた。
目の前の完璧な風景に、一本の亀裂が走る。空に、海に、砂浜に、黒い線が広がっていく。波の音はしているのに、波は動いていない。鳥の影は空を舞っているのに、その姿は見えない。全てが完璧に描かれた、「絵」だったのだ。
亀裂の向こう側は、絶対的な無。光も闇も、時間も空間も存在しない、ただの虚無が広がっていた。そして、その虚無の奥から、カイは「何か」に見られている気配を感じた。
第六章 閲覧限界
それは、意志ではなかった。感情も、知性も、敵意も善意もない。ただ、そこにあるという圧倒的な事実。まるで、本を読む読者の視線、絵画を眺める鑑賞者の眼差し。この世界全体を、一つの作品として「観測」している、高次の存在。
カイは全てを悟った。
この宇宙は、巨大なシミュレーションだったのだ。時間軸の融合も分離も、全ては計算に基づいたイベントに過ぎない。そして、彼が焦がれ続けた「ゼロ」の風景は、このシミュレーション世界の果て、これ以上は描画されていない「世界の境界」だったのだ。到達不可能だったのではない。そもそも、そこは「世界」ではなかったのだ。
あらゆる未来を視る彼の能力もまた、このシミュレーションにおける特異なバグか、あるいは意図的に設定された観測装置だったのかもしれない。彼の苦しみも、渇望も、全てはプログラムされたデータの一つに過ぎなかった。
亀裂の向こう側の「観測者」は、何も語らない。ただ、静かにこちらを見ている。境界線を越えようとするイレギュラーな存在を、無感情に眺めているだけだった。
第七章 初期値としての再起動
絶望がカイの全身を支配した。だが、それはすぐに、奇妙な安らぎへと変わっていった。
もう、無限の可能性に苛まれることはない。偽りの記憶に苦しむこともない。全てが虚構だというのなら、この苦痛もまた、虚構なのだ。
彼は、目の前の亀裂を見つめた。
この境界線を越えれば、どうなる? おそらく、このシミュレーションはエラーを起こし、停止するだろう。この宇宙、この世界、そこに生きる全てがリセットされる。
それは、世界の終わりを意味する。
だが、カイにとっては、唯一の解放でもあった。
彼は、静かに微笑んだ。それは、生体部品と機械部品が組み合わさってできた顔が、初めて見せた自然な表情だった。彼は、この虚構の世界で出会った、数少ない温かい記憶の断片を思い浮かべた。もし、次があるのなら。もし、このシミュレーションが再起動されるのなら。
「もっと、優しい世界でありますように」
その呟きは、誰に届くでもなく虚空に消えた。
カイは、世界の境界線へと、その身を投じた。
瞬間、世界は真っ白な光に塗りつぶされる。音も、色も、感覚も、全てが消失し、絶対的な静寂が訪れた。シミュレーションは、終了した。
――そして。
果てしない無の中に、ぽつり、と。
新たな宇宙の始まりを告げる、最初の光の粒子が、一つだけ煌めいた。それは、カイの最後の願いを宿した、次なる世界の「初期値」だった。