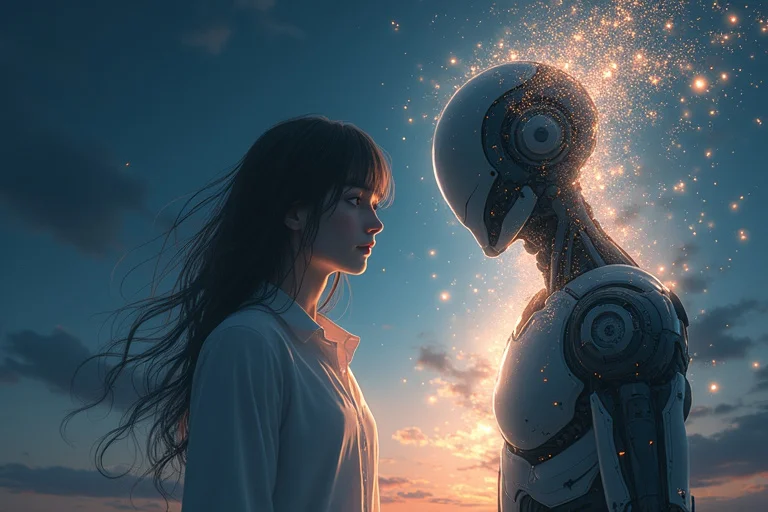第一章 揺らぐ鏡像
僕、高槻カイの朝は、鏡の中の他人と挨拶を交わすことから始まる。今日の彼は、昨日の僕より少しだけ目つきが鋭く、唇の端に微かな嘲笑が浮かんでいるように見えた。僕は洗面台に両手をつき、深く息を吐く。まただ。選択の代償。昨夜、眠る前に「明日は早く起きよう」と決めた。その選択が、早起きできなかった怠惰な僕を可能性の霧の向こう側へと追いやった。そして今、ここにいる僕は、ほんのわずかに違う存在へと変容したのだ。
街に出ると、世界との齟齬はさらに顕著になる。肩がぶつかりそうになった男は、僕の存在に気づかないかのように虚空を睨んだまま通り過ぎていった。僕の身体が、この物理世界からほんの一瞬だけ、位相をずらしたかのようだ。存在の不確かさは、孤独の匂いを連れてくる。
空を見上げると、奇妙な光景が広がっていた。街中の人々が「今日は晴れるべきだ」と強く願ったのだろう、雲一つない青空が広がっている。だが、その集合意識がもたらした歪みの代償として、街路樹から落ちるはずの葉が、空中でぴたりと静止していた。まるで時間が琥珀に閉じ込められたかのように。世界は静かに、だが確実に狂い始めていた。そしてその不協和音は、僕の存在の揺らぎと奇妙に共鳴している気がしてならなかった。
第二章 観測者のレンズ
「あなたのこと、以前から気づいていました」
声をかけてきたのは、白衣を着た女性だった。彼女は、霧島エラと名乗った。僕が時折、他者から認識されなくなる瞬間を、彼女は特殊なセンサーで捉えていたという。古びた図書館の奥室、埃とインクの匂いが混じり合う静寂の中で、彼女は僕に一つの小さな箱を差し出した。
「あなたは、ただの人間じゃない。自己の存在を量子的に認識している、極めて稀有な観測者です」
箱の中には、真鍮の縁に水晶がはめ込まれた、片眼鏡のようなレンズが収められていた。古代の遺物だというそれは、『観測者のレンズ』と呼ばれているらしい。
「世界は今、集合意識の暴走によって崩壊の危機に瀕しています。このレンズを使えば、物理法則を歪ませている『想い』の残滓を視ることができるはず。あなたにしか、この世界の歪みの本質は見えません」
エラの真剣な眼差しに、僕は唾を飲み込んだ。孤独だと思っていた僕の特異性が、世界の運命と繋がっているというのか。震える指でレンズを手に取り、そっと右目に当てがう。途端に、世界は色を変えた。
第三章 残響の街
レンズ越しの世界は、幻影と残響で満ちていた。空中で静止した葉には、「終わらないで」と願う恋人たちの切ない想いが陽炎のようにまとわりついている。水たまりが重力を無視して壁を登る路地裏には、「ここから逃げ出したい」という無数の絶望が、青黒い靄となって渦巻いていた。人々の強い願いや恐怖が、この世界の物理法則を書き換えるインクそのものだったのだ。
僕は街を彷徨い、歪みの源流を辿った。時間を遡るように車が逆走する交差点。そこには事故で愛する者を失った人々の、「あの時に戻れたら」という悲痛な叫びが、耳鳴りのように響き渡っていた。
レンズを覗くたびに、僕自身の輪郭もまた、曖昧になっていく感覚があった。幻影として見える「あり得たかもしれない現実」の中に、時折、僕自身の姿が混じるのだ。あの時、別の道を選んでいれば、僕は今頃、あの交差点で泣き崩れる一人になっていたのかもしれない。その可能性が、現実の僕を侵食してくる。足元がおぼつかなくなり、僕は壁に手をついて喘いだ。世界の歪みは、僕の心を映す鏡のようだった。
第四章 同期の兆候
世界の異常は、日に日にその凶暴性を増していった。ある日の午後、街の中心部で、巨大なオフィスビルがその重さを失い、ゆっくりと空へ向かって「落下」を始めた。砕けた窓ガラスや書類が、まるで無重力空間のように宙を舞う。人々の悲鳴が、遅れて僕の耳に届いた。
現場に駆けつけた僕がレンズを覗くと、空に昇るビルの周囲には、巨大な感情の渦が巻き起こっていた。それは「この重苦しい現実から解放されたい」「何もかも捨てて、自由になりたい」という、途方もない強さの集合的願望だった。
その幻影の中に、僕は見てしまった。
高層ビルの屋上で、風に髪をなびかせ、翼もないのに空を見上げて笑っている、僕の姿を。
それは、あらゆるしがらみから解放され、自由になった「あり得たかもしれない僕」だった。
ぞくり、と背筋に冷たいものが走った。偶然ではない。この世界の破滅的な歪みは、僕の存在と、僕の内に秘めた願望と、確かに同期している。僕が観測者? 違う。僕は……。
第五章 空ろな中心
「見つけたわ、歪みの震源地を」
研究所に戻った僕に、エラは厳しい顔で一枚の立体マップを見せた。そこに表示されていたのは、この街を中心とした世界の歪み発生データ。赤い点が、異常の発生地点を示している。そして、無数に点滅するその点の中心には、ただ一つの青い光点があった。それは、僕の位置情報を示すカーソルだった。
「どういう……ことだ?」
声が震える。
エラは目を伏せ、静かに告げた。「歪みは、すべてあなたを中心に同心円状に広がっている。そして、あなたの存在が最も大きく揺らいだ瞬間……あなたが何かを『選択』した瞬間に、最大規模の物理法則の変容が起きている。世界の歪みは、誰かの悪意じゃない。システムのバグでもない。原因は……あなた自身よ、カイ君」
言葉が、思考を凍らせた。僕の不安が、僕の孤独が、僕の「ここではないどこかへ行きたい」という無意識の渇望が、増幅器となって集合意識を捻じ曲げ、世界をこの形に作り変えていたのだ。僕は、この世界のバグそのものだった。空ろな存在である僕が、世界を空虚へと引きずり込んでいた。足元から崩れ落ちていく感覚に、僕はなすすべもなく立ち尽くした。
第六章 最後の選択
世界の終わりは、荘厳なほどに静かだった。空には亀裂が走り、そこから過去と未来の光景が万華鏡のように漏れ出している。時間は意味を失い、あちこちで空間が引き裂かれ、虚無が顔を覗かせていた。
「選択の時が来たのよ」
エラは、崩壊する世界の中で、ただ一人、まっすぐに僕を見つめていた。その瞳には、恐怖も絶望もなく、ただ悲しいほどの静けさがあった。
「あなたには二つの道がある。一つは、あなたの持つ無限の可能性、そのすべてを受け入れること。量子的な存在として拡散し、あなたの不確かさそのもので、世界の歪みを中和する。あなたは世界と一つになるけれど、個としての高槻カイは消滅する」
「……もう一つは?」
「無数の可能性から、たった一つの『自分』を選び、この世界に『定着』すること。そうすれば、あなたは特異性を失い、ただの人間になる。世界の歪みは収まるけれど、あなたはもう、あり得たかもしれない自分を見ることはできなくなる」
自己の消滅か、可能性の喪失か。
僕の周囲に、あり得たかもしれない無数の僕たちの幻影が浮かび上がった。画家になった僕。宇宙飛行士になった僕。誰かを愛し、家庭を築いた僕。孤独に打ちひしがれ、自ら命を絶った僕。彼らは皆、僕であり、僕ではなかった。彼らは僕の選択の残滓であり、僕が捨て去ってきた未来の亡霊だった。彼らと一つになるのか、それとも彼らを永遠に葬り去るのか。それが、僕に与えられた最後の選択だった。
第七章 ただ、ひとりの僕として
僕は、ゆっくりと目を開けた。幻影の中に、泣きそうな顔でこちらを見つめるエラの姿が見えた。そうだ。僕は、この不確かで、狂ってしまった世界で、彼女と出会ったのだ。無数の可能性の中で、この現実だけが、彼女との繋がりを与えてくれた。
失うのは、怖かった。無限の可能性を失い、ただ一人になるのは、何よりも恐ろしかった。だが、それ以上に怖かったのは、この温かな繋がりさえも失ってしまうことだった。
「僕は……選ぶよ」
僕は、レンズを外した。
「僕は、ここにいる。揺らぎ、迷い、それでも霧島エラと出会った、今の僕として、ここにいる」
強く、ただ強く、そう願った。意識した。その瞬間、僕の身体から放たれていた無数の可能性の光が、急速に僕自身の内側へと収束していくのが分かった。まるでブラックホールに吸い込まれる星々のように、画家も、宇宙飛行士も、幸せな僕も、不幸な僕も、すべてが一つの点――今の僕へと還っていく。
世界から、音が消えた。そして次の瞬間、全ての歪みが、まるで張り詰めていた糸が切れるように、一斉に解けていった。空の亀裂は塞がり、時間は再び正しく流れ始め、街路樹の葉は、ようやく重力に従って地面へと舞い落ちた。
僕は鏡の前に立っていた。そこに映っているのは、どこにでもいる、ごく普通の青年の顔だった。もう、揺らぐことはない。足の裏に、初めて感じる確かな大地と、自分の重み。僕は、普遍的な一人になったのだ。
エラが、そっと僕の隣に立ち、冷たくなった僕の手を握った。その温もりが、僕が失ったものの大きさと、得たもののかけがえのなさを、同時に伝えていた。
もう、あり得たかもしれない自分を見ることはない。だが、僕の心の中には、無数の僕たちが生きた人生の残響が、静かに息づいている。僕はこれから、このたった一つの人生を、その全ての重みを引き受けて、歩いていくのだ。