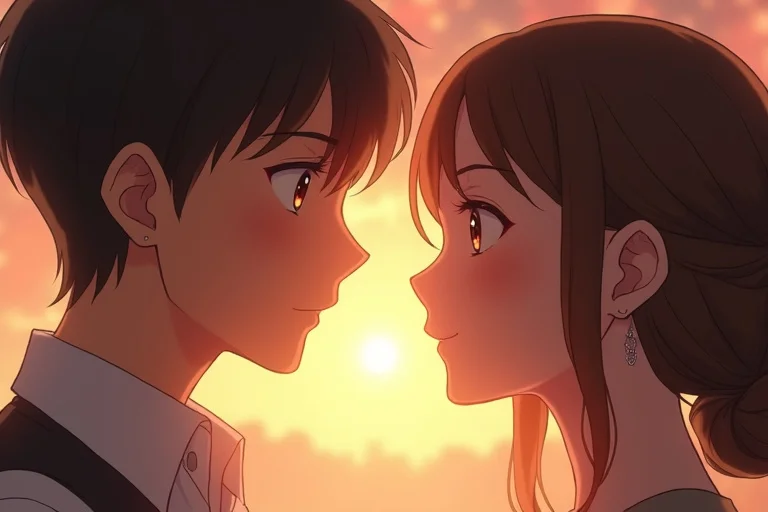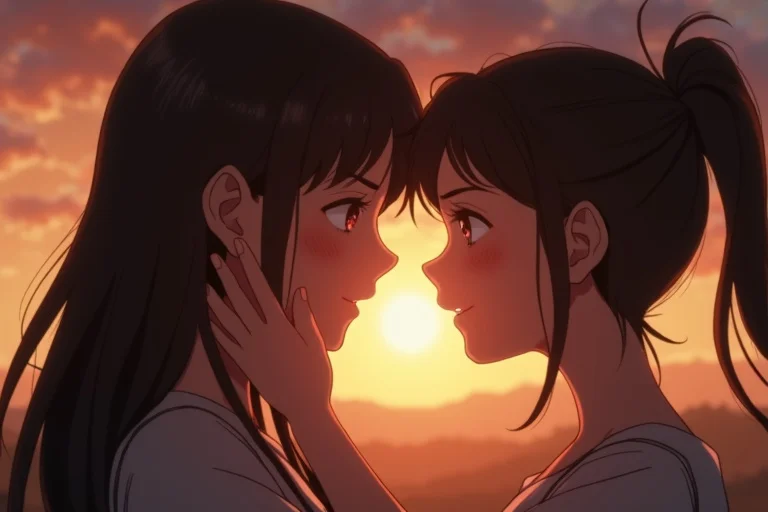第一章 無明の調律師
俺、水脈朔(みお さく)の仕事は、愛を計ることだ。
路地裏にひっそりと佇む古物店『水脈堂』の奥、磨き込まれた楡のカウンターが俺の仕事場。客が持ち込むのは、壊れた時計でもなければ、曰く付きの壺でもない。彼らが差し出すのは、目に見えない、しかし確かに存在する「愛」という名の感情だ。
俺の右目には、他者が抱く愛が、特定の周波数で振動する透明な粒子として映る。愛が深ければ深いほど、その粒子の密度は増し、輝きは強くなる。そして、この掌サイズの真鍮製『無明の天秤(むみょうのてんびん)』こそが、その輝きを物理的な質量へと変換する唯一無二の道具だった。
「彼の愛、少し、重すぎるんです」
目の前の女性は、俯きながらカップの縁をなぞっている。彼女の背後には、恋人から注がれるであろう、重厚で粘性の高い愛の粒子が渦を巻いていた。俺は静かに天秤をかざす。金の針がゆっくりと振れ、やがて一つの数値を指し示した。
「31.4グラム。確かに、情熱的だが少しばかり束縛が強い重さだ」
この世界では、愛が成就した瞬間、人々の内なる「色彩エネルギー」が解放され、周囲の風景を染め上げる。恋人たちの口づけで街灯が薔薇色に灯り、親子の抱擁で公園の芝生が萌黄色に輝く。だが、愛は常に美しいわけではない。重すぎる愛は世界を濁らせ、軽すぎる愛は色彩を褪せさせる。俺は、その均衡を微調整する、いわば「愛の調律師」だった。
女性にいくつかの助言を与え、彼女が少しだけ晴れやかな顔で店を出ていくのを見送った。夕暮れの光が埃を金色に照らす静寂の中、不意に、店のドアベルがちりんと乾いた音を立てた。
そこに立っていたのは、少年とも少女ともつかない、中性的な容姿の人物だった。淡い色の髪が、逆光の中で輪郭を曖昧にしている。その人物――零(れい)は、店の中をゆっくりと見回し、やがて俺のカウンターに歩み寄った。その足音は、まるで床に触れていないかのように静かだった。
第二章 零グラムの存在
「綺麗な天秤」
零は、俺の手元にある無明の天秤を指して、鈴が鳴るような声で言った。その瞳はどこまでも澄んでいて、底が見えない湖のようだった。
「これは……ただの飾りじゃない」
「知ってる。あなたは、それで心を計るんでしょう?」
言葉を失った。俺の能力を知る者は、ごく僅かなはずだ。零は悪戯っぽく微笑むと、カウンターにそっと肘をついた。その仕草には不思議な引力があり、俺は知らず知らずのうちに見入っていた。
気づけば、俺はとんでもないことを口にしていた。
「君の……君が抱くものを、計らせてくれないか」
職業柄の好奇心か、あるいは、ただこの不可思議な存在に触れてみたかったのか。零は少し驚いたように目を瞬かせたが、やがて静かに頷いた。
俺はごくりと唾を飲み込み、無明の天秤を零にかざした。心臓が早鐘を打つ。彼女の中から放たれるであろう愛の粒子を、右目に集中して捉えようとした。
しかし、何も見えない。
粒子の一つたりとも、だ。
天秤の皿は、まるで虚空そのものを映し出したかのように透き通り、金の針は始まりのゼロを指したまま、ぴくりとも動かない。
ゼログラム。
故障か?いや、この天秤が狂ったことは一度もない。では、この人物は、誰のことも、何一つ愛していないというのか。そんなことがあり得るのだろうか。
呆然とする俺の視線の先で、零は窓の外へ目をやっていた。彼女の横顔を見つめていると、奇妙なことに気づいた。今までずっと煤けた灰色だった向かいの煉瓦壁が、夕陽の色とは違う、温かな杏色にほんのりと染まっているように見えたのだ。
第三章 色づき始める世界
零は、それから時折、水脈堂に顔を出すようになった。古書の匂いが好きだと言って、店の隅で静かに本を読んでいることもあれば、俺の仕事を手伝うでもなく、ただカウンターの向こうで俺を眺めていることもあった。
俺たちはよく、日が落ちた後の街を散歩した。零と一緒にいると、世界はまるで生まれ変わったかのように輝き始めた。アスファルトの湿った匂い、遠くで響く電車の走行音、街灯に集まる羽虫の影。そのすべてが、かつてないほど鮮明に感じられた。
そして、何よりも世界の色が違った。
錆びついていたはずの公園のブランコは燃えるような緋色に、街路樹の葉は一枚一枚がエメラルドのように煌めき、見上げた夜空には、見たこともない瑠璃色の星が瞬いていた。
それは、俺自身の内側に蓄えられた色彩エネルギーが、零という存在に触発されて、かつてないほど活性化している証拠だった。俺は、零を愛している。心の底から、どうしようもなく。
その想いが確信に変わるたび、俺は無明の天秤を取り出した。だが、結果はいつも同じだった。天秤の皿は虚ろに透き通り、針は頑なにゼロを指し示す。
歓喜と絶望が、交互に胸を締め付けた。
俺の世界は、これほどまでに色彩で満たされているというのに。君の世界には、俺という色は一滴も存在しないのか?
愛している。なのに、愛されていない。その残酷な事実を、天秤は冷徹に突きつけてくるのだった。
第四章 虚空の真実
冷たい雨が窓ガラスを叩く夜だった。俺は、カウンターに置かれた天秤を睨みつけ、ついに耐えきれずに叫んだ。
「どうしてなんだ、零! 君の心には、本当に何もないのか!?」
「僕を愛しているのかと、そう聞きたいの?」
静かに本を閉じた零が、まっすぐに俺を見つめ返した。その瞳の深さに、俺は吸い込まれそうになる。
「ああ、そうだ! なぜ君はゼロなんだ!?」
零は悲しげに微笑むと、カウンターを回り込み、俺の震える手を取った。彼女の指は、氷のように冷たいのに、触れた場所から不思議な温もりが広がっていく。
「朔。私は、誰か一人だけを愛することはできないの」
静かな声が、雨音に溶けていく。
「なぜなら、私が『愛そのもの』だから」
脳が理解を拒んだ。愛そのもの?何を言っているんだ。
「この世界に生まれるすべての愛は、一度、私の中を通り抜けていく。私はそれを吸収し、浄化し、そして再び世界へと還すための器。サイクルそのものなの。だから、私自身が誰かのために愛を『所有』することはない。私の内側は、常に空(くう)。だから、あなたの天秤はゼロを指す」
つまり、俺が感じていた鮮やかな色彩は、俺が零に注いだ愛が、彼女という触媒を通して増幅され、世界に還元されていた光だというのか。俺は、世界を愛していたのか?
零は、俺の手をそっと握りしめた。
「あなたの能力は素晴らしいわ。でも、愛を『重さ』で計る限り、人々はその呪縛から逃れられない。重い、軽い、足りない、多すぎる……。もしあなたが、本当に私を信じてくれるなら」
彼女は、俺の目をじっと見つめて言った。
「その天秤を、手放して」
第五章 選択の刻
零の言葉は、俺の存在そのものを揺るがした。
天秤を手放す?それは、この右目の能力を捨てるのと同じことだ。愛を計ることで成り立っていた水脈朔という人間が、空っぽになってしまう。俺は、その恐怖から逃れるように店を飛び出した。
雨上がりの街は、俺が放った色彩エネルギーで、狂ったように輝いていた。ネオンは虹色に滲み、水たまりは銀河を映していた。美しい。だが、その美しさの奥で、人々が愛の重さに喘いでいるのが分かった。
カフェの窓越しに見えるカップル。男の重すぎる愛が、女の周りの空気を鉛色に淀ませている。
公園のベンチで肩を落とす老人。去っていった家族への軽くなった愛を嘆き、世界から色を失っている。
俺は、調律師として彼らを救ってきたつもりだった。だが、本当にそうだったのか?
「愛はこれくらいの重さが丁度良い」などと、誰が決めた? 俺が天秤で示した数値が、彼らを新たな檻に閉じ込めていたのではないか。
計量できるという傲慢。数値化できるという安心。それにしがみついていたのは、俺自身だった。
俺は悟った。零が言ったことの意味を。
真の愛は、計れない。
計ろうとすること自体が、愛を不自由にする。
俺は踵を返し、水脈堂へと走り出した。零が、俺の帰りを待っている。
第六章 無色の宝石
店のドアを開けると、零は最初に出会った時と同じ場所に、静かに立っていた。俺は息を切らしながら、彼女の前に進み出る。そして、懐から無明の天秤を取り出し、高く掲げた。
「もう、計らない」
俺の声は、決意に満ちていた。
「重さなんて、いらない。俺はただ、君を信じる。君が愛そのものだというなら、この世界すべてを、愛する」
その瞬間、天秤が甲高い音を立てて震え始めた。真鍮の表面から、 눈부신 빛이 뿜어져 나왔다.それは、これまで俺が計ってきたすべての愛の輝きを集めたような、凄まじい光の奔流だった。
光は俺の手の中で急速に収縮していく。世界のすべての色彩を飲み込み、凝縮し、やがて一点に集束した。
光が消えた時、俺の手のひらに残されていたのは、すべての光を吸収した結果、完全に無色透明になった小さな宝石だけだった。
同時に、俺の右目から、愛の粒子を視る力は永遠に失われていた。
世界が変わる音がした。
街の色彩が一度失われるのではない。人々を縛っていた「重さ」という概念から解放され、一つ一つの色が、より純粋な、固有の輝きを放ち始めたのだ。見返りを求めない微笑み、名前のない優しさ、計量不能な温もりが、新たな色彩として世界に生まれ落ちていく。
「ありがとう、朔」
零の声が聞こえた。見ると、彼女の身体が少しずつ透き通り、周囲の光に溶け始めている。
「これで、愛はもっと自由になれる」
その微笑みは、慈愛に満ちていた。消えゆく彼女に手を伸ばす。だが、指先は空を切るだけだった。
第七章 無限の色彩の中で
零の姿は、もうどこにもない。
俺は、愛を計る能力を失った。
だが、俺の見る世界は、かつてないほど豊かで、美しく、無限の色彩に満ち溢れていた。誰か特定の愛が成就したから輝くのではない。世界そのものが、そこに存在するすべてのものが、計ることのできない愛で満ちているから輝いているのだ。
風が頬を撫でる感触に、零の優しさを感じる。
木漏れ日の暖かさに、零の温もりを感じる。
街の喧騒、人々の笑い声、そのすべてに、零が還元した愛の響きが聞こえる気がした。
俺は水脈堂のカウンターに立ち、窓の外を眺める。手の中には、あの無色の宝石が握られている。それはもう何も計らない。ただ、静かに、無限の光をその内に宿して、俺の手のひらで永遠に輝き続けている。
天秤を失い、俺は初めて、本当の愛を知った。
計れないからこそ、それは無限なのだと。
俺はそっと微笑み、色彩に満ちた新しい世界へ、一歩を踏み出した。