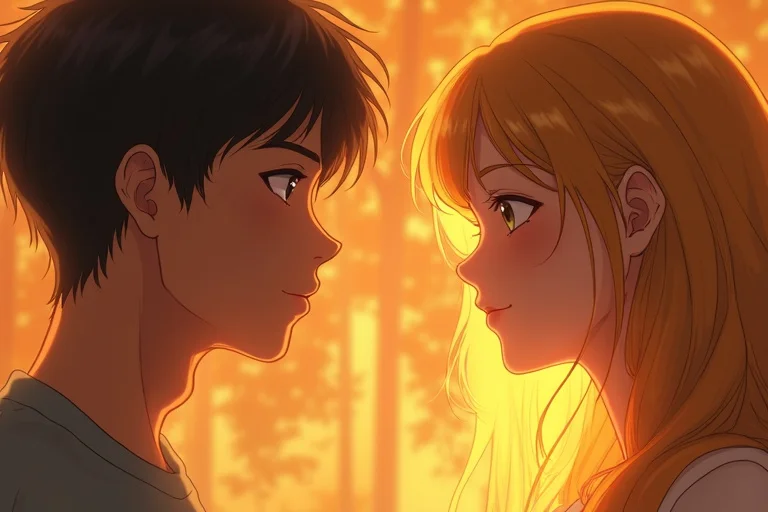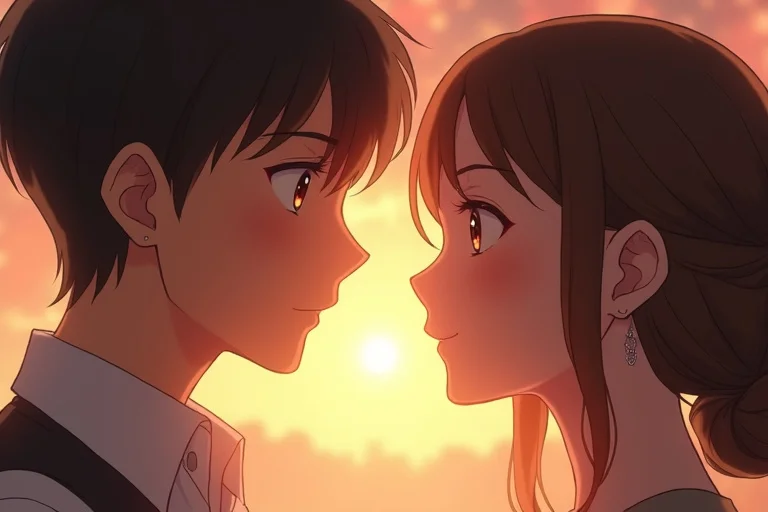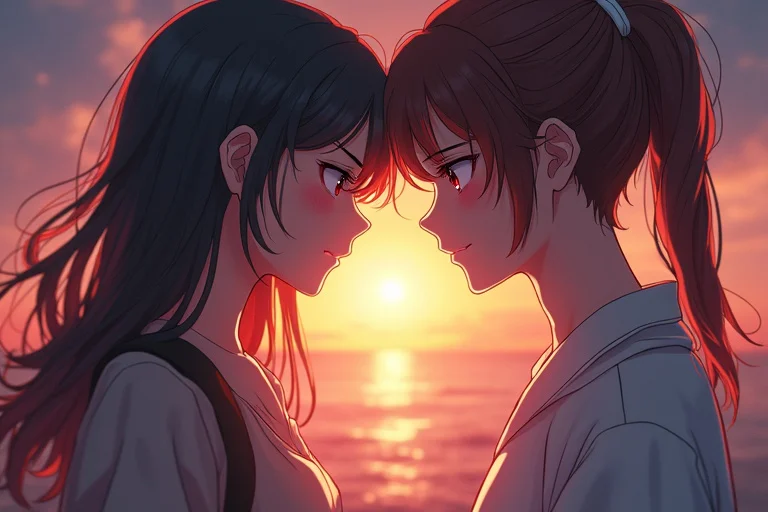第一章 色のない僕と、光を纏う君
僕、水野蒼(みずの あお)の世界は、人々の秘密の色で満ちている。
物心ついた頃から、僕には他人の「恋心」が、その人の周りを漂うオーラとして見えた。情熱的な恋は燃えるような緋色、始まったばかりの甘い恋は桜貝のような淡いピンク、長年連れ添った夫婦の慈愛は、深く穏やかな森の緑色。街を歩けば、そこは感情のプリズムが乱反射する万華鏡のようだった。人々は無自覚に、その最も無防備な感情を僕にだけ晒している。
古書店『彷徨堂』のカウンターに立つ僕の目にも、様々な恋の色が映る。ミステリー小説の棚の前で同じ本に手を伸ばし、指が触れた瞬間にふわりと生まれるライラック色の光。レジに並ぶカップルの、互いに絡み合うオレンジと黄色のオーラ。それらは美しい光景であると同時に、僕にある種の諦念を抱かせた。
なぜなら、僕自身には色がなかったからだ。鏡を覗き込んでも、自分の手を見つめても、そこにオーラの兆候はない。他人の鮮やかな感情を見れば見るほど、自分の内側はがらんどうの空洞のように思えた。僕は恋の色を知っている。だが、僕自身がその色を放つことはない。僕は、他人の物語を眺めるだけの、無色の観客なのだ。
そんなある雨の日、彼女は現れた。
鈴の音のように軽やかなドアベルと共に、濡れた傘を畳みながら入ってきた女性。月島燈(つきしま あかり)と名乗った彼女の周りには、僕がこれまで見たことのない、不思議な光が揺らめいていた。それは特定の誰かに向かうベクトルを持たない、温かな黄金色の光。まるで彼女の内側から、小さな太陽が世界を照らしているかのようだった。
「あの、人文書の棚はどちらですか?」
静かで、澄んだ声だった。僕は一瞬、言葉を失い、ただ彼女を包む金色の光に見惚れていた。それは恋の色ではない。だが、どんな恋の色よりも強く、僕の心を惹きつけた。
「あちらの、一番奥の棚です」
我に返って指し示すと、彼女は「ありがとうございます」と小さく会釈して歩き出した。彼女が通り過ぎた後には、まるで陽だまりのような温かい気配が残った。
それから、燈さんは彷徨堂の常連になった。週に二、三度、決まって夕暮れ時に現れ、一冊の本をじっくりと選んで買っていく。僕たちは少しずつ言葉を交わすようになった。好きな作家が同じだったこと、雨の日の匂いが好きなこと、コーヒーは浅煎りが好きなこと。些細な共通点を見つけるたび、僕の心臓はトクンと微かな音を立てた。
けれど、いくら彼女に惹かれても、僕の周りには色が現れない。僕はやはり空っぽのままだった。彼女の纏う黄金色の光は、僕ではない誰か、あるいは世界そのものに向けられた、壮大な愛の形なのかもしれない。そう思うと、胸の奥がちくりと痛んだ。無色の僕が、太陽のような彼女に手を伸ばす資格など、あるのだろうか。
第二章 金色のさざなみと見えない輪郭
燈さんと過ごす時間は、僕にとって唯一、自分が無色であることを忘れられる時間だった。僕たちは書店の外でも会うようになった。公園のベンチで、彼女が選んだ詩集を一緒に読んだり、川沿いの道をあてもなく散歩したりした。
彼女といると、世界がいつもより少しだけ優しく見える気がした。道端に咲く名もなき花、空を流れる雲の形、風が運ぶパン屋の甘い香り。普段なら気にも留めない風景の一つひとつが、特別な意味を持って輝き出す。
「水野さんって、すごく優しい目をしていますね」
ある日、カフェで向かい合って座っていると、燈さんがふと言った。
「見てるだけで、こっちまで穏やかな気持ちになります」
僕はどきりとして、コーヒーカップに視線を落とした。僕の目には、彼女の顔の周りでさざなみのように揺れる金色の光が見えている。それは相変わらず、誰かに向けられたものではなく、彼女自身から発せられているように見えた。
「月島さんこそ、いつも…なんていうか、温かい雰囲気ですよね」
僕は精一杯の言葉を紡いだ。「太陽みたいだなって、いつも思います」
彼女は少し驚いたように目を丸くして、それから嬉しそうに微笑んだ。「太陽だなんて、初めて言われました。ありがとうございます」
その笑顔を見るたびに、僕の胸の空洞が何かで満たされていくような感覚があった。でも、それが恋だという確信は持てなかった。僕にはそれを証明する「色」がないのだから。街ですれ違う恋人たちの、互いに溶け合うようなオーラを見るたびに、僕と彼女の間には透明な壁が存在するような気がしてならなかった。僕のこの感情は、ただの憧れや、彼女の持つ光への羨望に過ぎないのではないか。
そんな疑念が渦巻く中、僕は一つの決心をした。この曖昧な関係に、僕自身の感情に、輪郭を与えなければならない。たとえそれが無色だとしても、この想いを伝えるべきだ。
「あの、月島さん。今度の週末、よかったら…映画でも見に行きませんか」
勇気を振り絞って口にした言葉は、自分でも驚くほど震えていた。燈さんは一瞬きょとんとした後、ふわりと花が綻ぶように笑った。
「はい、ぜひ。楽しみにしていますね」
その返事を聞いた瞬間、目の前の世界が、ほんの少しだけ鮮やかになった気がした。もちろん、それは気のせいだ。僕の周りには、依然として何の色もなかったのだから。
第三章 反転するプリズム
デートの日は、快晴だった。僕の心とは裏腹に、世界は祝福するように光に満ちていた。映画館の暗闇の中、隣に座る彼女の気配をすぐそこに感じながらも、僕はスクリーンに集中できなかった。上映が終わり、明るいロビーに出ると、手をつないで出てくるカップルのオーラが目に飛び込んでくる。鮮やかな赤とピンクが混じり合い、きらきらと光の粒子を撒き散らしていた。それに比べて、僕たちはどうだ。僕の隣で微笑む彼女は黄金色に輝いているけれど、僕は空っぽのまま。そのコントラストが、僕の心を鋭く抉った。
帰り道、夕暮れの公園のベンチに並んで座った。橙色に染まる空を見上げながら、僕はもう限界だと感じていた。このままでは、いつか僕のこの空虚さが彼女を傷つけてしまうかもしれない。
「月島さん」
僕は意を決して彼女の名前を呼んだ。
「僕が、あなたのことをどう思っているか…話しても、いいですか」
燈さんは黙って僕の方を向き、静かに頷いた。彼女の金色の光が、夕陽を受けてより一層輝いて見える。
「僕は、あなたのことが好きです。初めて会った時から、ずっと惹かれていました。でも…」
僕は言葉を詰まらせ、俯いた。「僕には、自信がないんです。僕のこの気持ちが、本物なのかどうか…。他人の恋はあんなに色鮮やかなのに、僕には何もないから」
そして、僕は堰を切ったように、自分の特異な能力について打ち明けた。恋心がオーラとして見えること。そして、自分自身が無色であること。こんな非現実的な話を、彼女は信じてくれないかもしれない。それでも、伝えなければならなかった。
話し終えた僕に、彼女は驚いた顔をしていた。だが、そこには軽蔑や拒絶の色はなかった。しばらくの沈黙の後、彼女は信じられないようなことを、静かに、しかしはっきりとした声で告げた。
「水野さん。私…色が見えないんです」
「え…?」
「生まれつきの全色盲で、私の世界は白と黒と、その濃淡だけでできています。だから、あなたが言う『緋色』や『ピンク』がどんな色なのか、私には想像することもできません」
僕は衝撃に言葉を失った。彼女の世界には、色が存在しない? では、僕がずっと見てきた彼女の周りのあの黄金色の光は、一体何だったというんだ。僕の混乱を読み取ったかのように、彼女は続けた。
「でも、私にも、あなたと同じような、少し変わった感覚があるんです。私には、人の感情が『光の強さ』として感じられます。怒りはチカチカと痛い光、悲しみは弱く消え入りそうな光。そして…強い好意や愛情は、とても温かい光として感じられるんです」
彼女はそこで一度言葉を切り、真っ直ぐに僕の目を見て、優しく微笑んだ。
「水野さん。あなたの周りには、いつも光が見えますよ。私が今まで感じた中で、一番穏やかで、澄みきった…綺麗な光が。もしそれに名前をつけるとしたら、きっとそれは『青色』なんだろうなって、いつも思っていました。空や海のような、静かで、どこまでも深い青色の光が」
世界が、反転した。
僕には色がないのではなかった。僕の恋心は、僕自身には見えなかっただけだ。僕が空っぽだと思っていたこの場所には、澄んだ青色の光が満ちていた。そして、僕が彼女の光だと思っていたあの黄金色は、違ったのだ。あれは、彼女というプリズムが、僕の青い光を反射して見せてくれていた、温かい黄金色の輝きだったのだ。
第四章 ふたりだけの色彩
涙が溢れて止まらなかった。それは悲しみの涙ではなかった。長い間、空っぽだと思い込んでいた自分の心が、本当は豊かな色で満たされていたことを知った、歓喜の涙だった。僕はずっと、他人の色ばかりを追いかけて、自分の内側を見つめる方法を知らなかっただけなのだ。
「僕の色は…青、だったんですね」
掠れた声で呟くと、燈さんはこくりと頷き、そっと僕の手に自分の手を重ねた。その小さな手の温もりが、僕の心の奥深くまで沁みわたっていく。
「はい。とても、綺麗な青色です」
彼女もまた、僕に自分の秘密を打ち明けてくれた。色が見えない世界で、彼女は光の濃淡だけを頼りに生きてきた。人の感情が光として感じられることは、彼女にとって救いであると同時に、孤独の証でもあった。誰もその感覚を理解してはくれなかったから。
「でも、水野さんといると、私の世界はすごく豊かになるんです」と彼女は言った。「あなたが話してくれる色の話を聞いていると、白黒の世界に、少しだけ色が差すような気がするから」
僕たちは、互いの欠けた部分を補い合うために出会ったのかもしれない。僕は彼女を通して、初めて自分の心の色を知った。彼女は僕を通して、名前のなかった光に「色」という名前を与えられた。
僕たちは不完全な二人だ。僕は自分の心を見ることができず、彼女は世界の色彩を見ることができない。けれど、二人でいれば、世界は完璧な姿を取り戻す。
僕たちはゆっくりと立ち上がり、手をつないで歩き始めた。街灯が灯り始めた公園には、まだ寄り添うカップルたちのオーラが瞬いている。赤も、ピンクも、緑も。それらは今も変わらず美しい。でも、もう僕が羨むことはない。僕には僕だけの色があることを、隣にいる彼女が教えてくれたから。
「ねえ、水野さん」
燈さんが僕の手をきゅっと握りながら、楽しそうに言った。
「今のあなたの光、すごくきらきらしていますよ。嬉しそうな色をしています」
僕は微笑んで、彼女の手を握り返した。自分の内側で、澄みきった青色の光が、温かく、力強く脈打っているのを感じる。
自分の心の色は、自分一人では見つけられないのかもしれない。それは、愛する人がその瞳に映してくれて、初めて気づくものなのだ。僕たちの世界は、これから二人で彩っていく。不揃いな僕たちが手を取り合って見る世界は、きっと誰にも見ることのできない、ふたりだけの豊かな色彩に満ちているだろう。