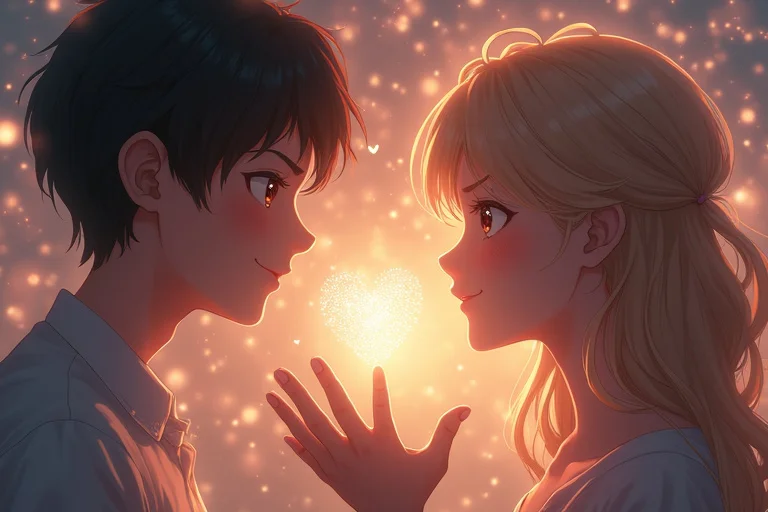第一章 黄金色の定規
僕、桐谷カイトには、秘密の能力がある。共感覚の一種なのだろうか、人々の間の「関係性」が、オーラのような色として見えるのだ。恋人たちの間には燃えるような薔薇色が、仲の良い家族には陽だまりのような橙色が、そして憎しみ合う者たちの間には、コールタールのように淀んだ黒がまとわりついている。
この能力は、僕の人生の羅針盤であり、同時に呪いでもあった。言葉とは裏腹に、濁った色を放つ人間を何人も見てきた。おかげで僕は、人を心から信じるということができなくなり、いつしか深い関係を築くことを避けるようになった。
そんな僕にとって、唯一の例外が親友の相葉ハルキだ。
彼との間には、出会った頃からずっと、一点の曇りもない、純粋で力強い「黄金色」の光が輝いていた。それはまるで、冬の朝の光を溶かし固めたような、暖かく、そして絶対的な色。僕はこの黄金色を「友情の絶対証明」だと信じていた。僕の世界における、唯一揺るがない定規だった。
その日も、僕らは駅前の馴染みのカフェで、とりとめのない話をしていた。窓から差し込む西日が、ハルキのミルクティーの表面をきらきらと照らしている。彼の屈託のない笑顔と、僕たちの間に揺らめく美しい黄金色を眺めながら、僕は心の底から安らいでいた。この光がある限り、僕の世界は大丈夫だ、と。
「ごめん、カイト。ちょっと電話してくる」
ハルキがスマホを片手に席を立った、その瞬間だった。
ぐにゃり、と。僕たちの間にあったはずの黄金色の光が、まるで陽炎のように歪んだ。そして一瞬、ほんの一瞬だけ、光は色を失い、煤けたような鈍い灰色に変わった。
「え……?」
僕は思わず声を漏らした。瞬きをすると、光は元の美しい黄金色に戻っていた。しかし、僕の心臓は嫌な音を立てて早鐘を打ち始める。網膜に焼き付いた灰色の残像が、淹れたてのコーヒーに落とされた氷のように、僕の安らぎを急速に冷やしていく。
気のせいだ。疲れているんだ。そう自分に言い聞かせようとしても、一度見てしまった異常な光景は、僕の心の奥深くに、小さな、しかし消えない染みとなって広がっていくのだった。僕の絶対的な定規に、初めて見えた、微かな亀裂だった。
第二章 ひび割れたプリズム
あの日を境に、僕の世界は静かに、しかし確実に狂い始めた。ハルキとの間に見える黄金色は、日を追うごとにその輝きを失っていったのだ。
最初は、ほんの些細な変化だった。光の輪郭がぼやけたり、彩度が少しだけ落ちて見えたり。僕はそれを自分の体調のせいだと思い込もうとした。だが、変化は止まらなかった。一週間も経つ頃には、あの力強かった黄金色は、まるで色褪せた古い写真のように、くすんだセピア色にしか見えなくなっていた。
僕の心は疑念で満たされていく。ハルキが、僕に何か隠しているのではないか?
彼の何気ない言葉の端々が、棘のように僕の心を刺した。「最近、仕事で新しいプロジェクトを任されてさ」という彼の言葉は、「お前には関係ない世界の話だ」という拒絶に聞こえた。僕の知らない誰かと楽しそうに電話で話している姿を見れば、僕の悪口を言っているのではないかと、胸がざわついた。
僕の能力は、嘘を見抜く。この色褪せた光は、彼の心変わりを、友情の終わりを告げているに違いない。そう思うと、いてもたってもいられなくなった。
「ハルキ、最近何か隠してないか?」
ある晩、僕はついに彼を問い詰めた。僕の言葉に、ハルキはきょとんとした顔でこちらを見た。彼の周りの光は、今やほとんど輝きのない、薄汚れた灰色に見えた。
「隠し事? 何のことだよ、カイト」
「とぼけるなよ。お前、何か変わっただろ。僕に対して、何か思うところがあるんじゃないのか」
僕の苛立った声に、ハルキは困惑したように眉を寄せた。「変わったのはお前のほうだろ。最近ずっと、何かに怯えてるみたいだぞ。何かあったなら、話してくれよ」
その言葉すら、僕には空々しい言い訳にしか聞こえなかった。灰色の光が、彼の言葉の無意味さを証明しているように思えた。僕は自分の能力のことは誰にも話していない。この苦しみを、どう説明すればいい?
「……もういい」
僕はそれだけ言うと、彼に背を向けた。追いかけてくる声も聞こえないふりをした。僕が見ている灰色の世界が、現実になりつつあった。僕の疑念が、僕たち二人のかけがえのない関係を、本当に破壊しようとしていた。僕の心のプリズムは、もう美しい光を映し出すことはできず、ただひび割れた隙間から、冷たい光を漏らすだけだった。
第三章 モノクロームの告白
決定的な出来事は、突然訪れた。
ハルキを避け始めてから二週間後の週末。僕は偶然、街で彼を見かけた。彼は僕の知らない数人の男女と、楽しそうに笑いながらカフェに入っていく。その手には、大きな画材店の紙袋が提げられていた。僕の誕生日は、来週だ。僕は絵を描くのが趣味で、ずっと欲しがっていた高価な画材セットがあった。
――僕へのプレゼントを、他の奴らと選んでいる? なぜ、僕に隠れて?
その光景は、僕の疑念に最後のとどめを刺した。怒りと裏切られたという思いで、頭が真っ白になる。僕は震える手でスマホを取り出し、ハルキにメッセージを送った。
『もう、お前とは会わない。さようなら』
送信ボタンを押すと同時に、僕の視界の中で、ハルキとの関係性を示していた最後の光が、ぷつりと音を立てて消えた。完全な、無機質な灰色。僕たちの友情は、終わった。
絶望に打ちひしがれ、僕は当てもなく街を彷徨った。雨が降り始め、傘も持たない僕の体を濡らしていく。冷たい雨粒が頬を伝うのが、涙なのか雨なのか、もう分からなかった。
ふと顔を上げた時、僕は信じられない光景に息を呑んだ。
交差点で信号を待つ、寄り添い合うカップル。彼らの間には、いつもなら鮮やかな薔薇色が見えるはずだった。しかし、今はただの濃淡の違う灰色があるだけ。公園のベンチで孫に絵本を読む老婦人と幼い少女。陽だまりのような橙色も、今はどこにもない。
街から、色が消えていた。
人々の関係性を照らしていたはずのすべての光が、まるで古いモノクロ映画のように、色を失っていたのだ。
そこで、僕は悟った。雷に打たれたような衝撃と共に。
間違っていた。
色褪せたのは、ハルキとの友情ではなかった。僕の世界そのものから、色が消え失せていたのだ。問題はハルキじゃない。僕だ。僕の「心の目」が、壊れてしまったんだ。
最近の過酷な仕事のプレッシャー。そして、心の奥底に封じ込めていた、幼い頃に唯一の親友に裏切られた古い記憶。それらが混ざり合い、僕の精神を蝕み、世界から色を奪う「心の色覚異常」を引き起こしていたのだ。
ハルキは何も変わっていなかった。変わってしまったのは、僕の方だった。彼はきっと、僕の誕生日を祝うために、サプライズを計画してくれていただけなんだ。僕が欲しがっていた、あの画材を。
「ああ……なんてことを……」
僕はその場に膝から崩れ落ちた。降りしきる雨の中、僕は自分の愚かさと、取り返しのつかない過ちを犯してしまったことを悟り、ただ嗚咽するしかなかった。僕が信じてきた絶対的な定規は、僕自身の心が生み出した、あまりにも脆い幻だったのだ。
第四章 夜明けの色彩
僕は走った。雨で重くなった体も、凍えるような寒さも忘れて、ただ一心不乱にハルキのアパートへ向かった。アスファルトを蹴る音と、激しい呼吸だけが、僕の存在を証明していた。
アパートの前に着くと、ちょうど部屋の明かりが消えるところだった。もう遅いかもしれない。それでも、僕はインターホンを押した。何度も、何度も。
やがて、ドアがゆっくりと開いた。パジャマ姿のハルキが、驚きと戸惑いの入り混じった顔で僕を見ている。
「カイト……? どうしたんだ、こんな時間に、ずぶ濡れで」
僕は言葉を発することができなかった。ただ、彼の顔を見つめたまま、涙が溢れてくる。そんな僕を見て、ハルキは何も言わず、僕の腕を引いて部屋の中に入れてくれた。
温かいタオルを渡され、ソファに座らされても、僕は震えが止まらなかった。しばらくの沈黙の後、僕は絞り出すように、すべてを告白した。
僕には、関係性の色が見えること。ハルキとの間に輝く黄金色が、僕の唯一の支えだったこと。その色が灰色に見えるようになり、彼を疑ってしまったこと。そして、それが僕自身の心の病のせいだったこと。
僕の拙い告白を、ハルキは黙って聞いていた。彼の表情は読めなかった。軽蔑されるだろうか。気味悪がられるだろうか。僕が長年抱えてきた秘密は、あまりにも奇妙で、独りよがりだった。
話し終えた僕に、ハルキはふっと息を吐いて、そして、少しだけ笑った。
「そうか。お前、そんなモン背負って生きてたのか。大変だったな」
彼の声は、どこまでも穏やかだった。
「お前の目に見える色がどうだっていい。黄金色だろうが、灰色だろうが、そんなの俺には関係ない。俺が見てるお前は、初めて会った日からずっと、俺の大事な親友だよ。それだけは、何も変わらない」
その言葉が、僕の心に染み渡った瞬間。
ぽっ、と。
僕とハルキの間に、小さな光が灯った。それは以前のような力強い光ではなかった。頼りなく、儚い、でも間違いなく暖かい、黄金色の光。まるで、分厚い雲の隙間から差し込む、夜明けの最初の光のようだった。
僕の世界に、ほんの少しだけ、色が戻ってきた。
僕の心の回復には、きっと長い時間がかかるだろう。世界はまだ、ほとんどモノクロームのままだ。でも、もう怖くはなかった。僕は、目に見える「色」という不確かな指標に頼るのをやめた。代わりに、目の前にいる親友の言葉と、その温もりを、ただ信じることにした。
窓の外では、いつの間にか雨が上がっていた。濡れたアスファルトの匂いが、夜明けの澄んだ空気と共に部屋に流れ込んでくる。僕たちの間に灯る、その小さな黄金色の光を見つめながら、僕は、目に見えるものだけが真実ではないのだと、生まれて初めて、心の底から理解したのだった。