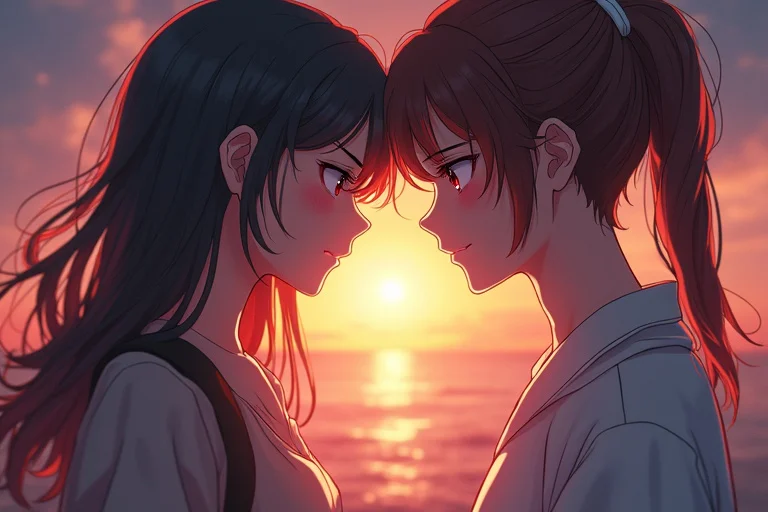神保町の古書店「霧とインク」の店主代理である私、水野美咲の時間は、埃と紙の匂いに満ちていた。背表紙の褪せた本棚に囲まれ、インクの染みついた指先でページをめくる日々。それは静かで、満ち足りていた。ただ、時折、心の書架の片隅で眠る一冊の本が、不意に開かれることがあった。大学時代の友人、相葉湊という名の、未読のままの本が。
雨がアスファルトを濃紺に染める、ある日の午後だった。店のドアベルがちりん、と鳴り、雨粒を払う男性が入ってくる。見覚えのある、少し癖のある黒髪。冗談めかして笑うときの、細められる目元。息が、止まった。
「……湊?」
絞り出した声は、自分でも驚くほどか細かった。彼は傘を畳む手を止め、驚いたように顔を上げる。
「え、美咲? 水野美咲? うわ、久しぶり! ここ、君の店だったのか」
数年ぶりに聞く彼の声は、記憶の中より少しだけ低くなっていた。心臓が古時計のように、ぎしぎしと不規則な音を立て始める。大学時代、彼の隣で笑うだけで精一杯で、喉まで出かかった「好き」の一言を、ついに言えなかった。それが私の課題であり、卒業以来ずっと抱えてきた後悔だった。
再会をきっかけに、私と湊は時々会うようになった。彼が設計したという、ガラス張りのモダンなカフェでコーヒーを飲んだり、私の働く古書店街を二人で散策したり。彼は建築家として、未来を描く仕事をしている。古い物語の中に安らぎを見出す私とは、まるで正反対だ。それでも、彼と過ごす時間は、色褪せた日常に鮮やかなインクを落とすように、心を彩っていった。
「この本、面白いよ。結末が意外でさ」
私が薦めたミステリを手に、彼は楽しそうに笑う。その笑顔を見るたび、胸の奥がきゅっと締め付けられる。言いたい。今度こそ、この気持ちを伝えたい。でも、言葉はいつも、唇の手前で迷子になる。彼にとって私は、ただの「懐かしい友人」なのだろう。そう思うと、見えない壁が私たちの間にそびえ立っているように感じられた。彼の隣は心地良いのに、遠い。まるで、手の届かない美しい建築模型を眺めているような、もどかしい気持ちだった。
ある週末、「大事な話があるんだ」と、湊から連絡があった。いつものカフェで私を待っていた彼の表情は、少し硬かった。私の心臓が、期待と不安で大きく脈打つ。もしかしたら、彼も同じ気持ちでいてくれたのかもしれない。ガラス越しに見える街路樹が、緊張する私を応援するように揺れている。
「実はさ、決まったんだ。来月から、ロンドンに行くことになった」
彼の言葉は、私の鼓膜を通り過ぎ、意味を結ぶのに数秒かかった。
「……ロンドン?」
「ああ。大きなプロジェクトの責任者としてね。ずっと夢だったんだ。最低でも、三年は向こうかな」
彼はそう言って、寂しそうに、でも誇らしげに笑った。世界が、音を立ててモノクロームに変わっていく。期待が粉々に砕け散り、心に冷たい風が吹き抜けた。「おめでとう」と口では言いながら、目の前が滲んでいくのを必死で堪えた。
「行く前に、美咲に会えてよかったよ」
その言葉が、残酷な杭となって私の胸に打ち込まれた。彼の優しさは、いつだって友人としてのものだったのだ。カフェを出て、一人歩く帰り道。後悔が冷たい雨のように、全身に降り注いでいた。また、言えなかった。このまま、私の恋は誰にも知られず、古書に積もった埃のように忘れられていくのだろうか。
店に戻り、明かりもつけずに椅子に座り込んだ。諦めが心を支配しようとした、その時だった。ふと、書棚の一角が目に入る。そこにあるのは、かつて湊が「どうしても見つからないんだ」と探していた、絶版の建築写真集。偶然、市場で見つけて仕入れたものの、彼に連絡する勇気がなくて、ずっとそこに置いたままだった。
私は、吸い寄せられるようにその本を手に取った。震える指で、表紙をめくる。最初の、何も書かれていない真っ白なページ。――見返し。
気づけば、私はカウンターから愛用の万年筆を取り、インクを吸わせていた。もう、失うものは何もない。後悔だけは、もうしたくない。私は、その真っ白なページに、祈るように言葉を綴った。
湊が旅立つ日。私は空港の出発ロビーにいた。雑踏の中から彼を見つけ出し、息を切らしながら駆け寄る。
「……忘れ物」
そう言って、紙袋に入れた写真集を突き出した。
「え?」
「昔、探してたでしょ。読んでみて」
言いたいことは、それだけだった。彼の驚いた顔を最後まで見ることができず、私は踵を返して人混みの中へと走り去った。涙が溢れて、前が見えなかった。
それから三ヶ月が過ぎた。季節は移ろい、街は秋の装いを始めていた。もう、彼から連絡はないだろう。私のしたことは、ただの自己満足だったのだ。そう思いながら店のカウンターで本を整理していると、一通のエアメールが届いた。差出人は、相葉湊。
震える手で封を切ると、中から一枚の絵葉書が滑り落ちた。テムズ川にかかる、美しい橋の写真。裏返すと、そこには見慣れた彼の文字があった。たった一言だけ。
『君のいる未来の設計図も、考えてる』
その瞬間、止まっていた私の時間が、再び優しく流れ始めた。窓から差し込む午後の光が、絵葉書を持つ私の指先を暖かく照らしている。私はその葉書をそっと胸に抱きしめ、静かに、でも確かに微笑んだ。私の恋は、ようやく最初のページをめくることができたのだ。