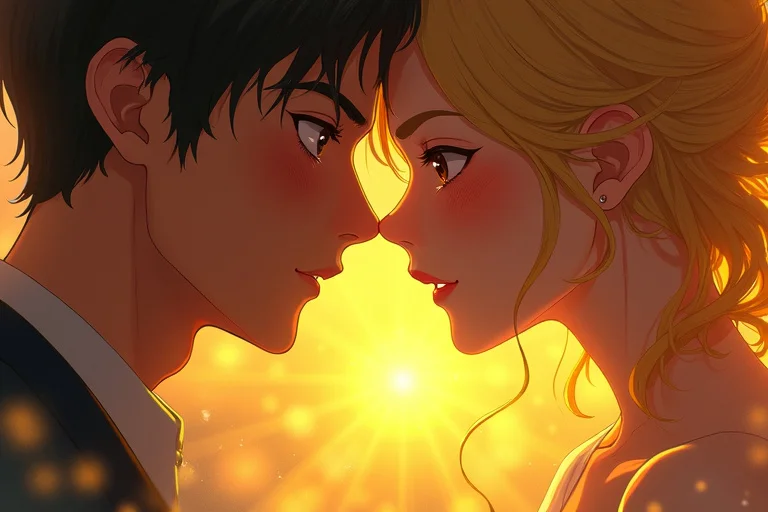神保町の古書店「雨読文庫」の埃っぽい静寂が、水野栞のすみかだった。インクと古い紙の匂いが混じり合う空気の中で、彼女は物語の世界に逃げ込むのが得意だった。現実の世界、特に恋愛においては、栞はいつも脇役だった。
主人公は、店の向かいにあるカフェ「豆灯舎」の店長、湊さん。彼がガラス越しに見せる柔らかな笑顔や、常連客と楽しげに話す声、そして何より、彼が淹れるコーヒーの深く香ばしい香りが、栞の単調な日々の彩りだった。彼に恋をして、もう三年が経つ。毎朝、勇気を振り絞って彼の店でコーヒーを買うのが、二人の世界のすべて。交わす言葉は「ブレンドひとつ」「ありがとうございます」だけ。それ以上、関係が進む気配はなかった。
ある雨の日の午後、栞は買い取ったばかりの古書の山から、一冊の文庫本を手に取った。何の変哲もない、ありふれた恋愛小説。だが、ページをめくると、そこには几帳面な男文字で、びっしりと感想や心情が書き込まれていた。
『主人公の気持ちが痛いほどわかる。好きな人を前にすると、どうしてこんなに言葉が出てこないんだろう』
余白に綴られた言葉は、まるで栞自身の心の声を代弁しているかのようだった。栞はその書き込みにたちまち夢中になった。物語の展開に合わせて、書き込みの主は一喜一憂し、時に鋭いツッコミを入れ、時に登場人物に深く共感する。栞は心の中で、彼を「筆跡さん」と名付けた。ページをめくるたび、「筆跡さん」との対話が深まっていくような気がした。彼の言葉は、栞が湊さんに対して抱く、口に出せない切なさやもどかしさ、そのすべてを肯定してくれているようだった。
『彼女の笑った顔を見るだけで、一日が輝く。単純だと笑うかい?』
その一文に、栞の胸はきゅっと締め付けられた。湊さんの笑顔を思い浮かべ、頬が熱くなる。この本を読み終えてしまったら、「筆跡さん」とのささやかな繋がりも消えてしまう。それが寂しくて、栞は最後の数ページをなかなか読み進められなかった。
数日後、ついに物語は終わりを迎えた。栞は名残惜しさを感じながら、最後のページをそっとめくる。すると、ページの間に一枚の古びた栞が挟まっているのに気づいた。押し花が施された、趣味の良い栞。その裏には、見慣れた、それでいて今まで気づかなかった、あの「筆跡さん」の文字でこう書かれていた。
『この物語の結末が、君の勇気になりますように。 湊』
「え……?」
声にならない声が漏れた。湊。まさか。震える指で、栞は慌てて本文の書き込みを読み返す。『向かいの窓から見える彼女』『本の埃を払う横顔が綺麗だと思った』『彼女が好きなラベンダーの香りのハンドクリーム』。点と点が繋がり、一本の線になった瞬間、栞の世界は反転した。書き込みの主は、湊さんだった。そして、彼が綴っていた想いの相手は、紛れもなく、古書店で働く自分自身だったのだ。三年間、ただ見つめるだけだと思っていた。見つめられていたのは、自分の方だった。
心臓が早鐘を打ち、呼吸が浅くなる。気づけば、栞は店を飛び出していた。閉店時間をとうに過ぎた「豆灯舎」のドアを、ためらいがちに押す。カラン、と寂しげなベルの音が鳴り、片付けをしていた湊さんが驚いたように顔を上げた。
「水野さん? どうかしたんですか、こんな時間に」
言葉が出てこない。代わりに、栞は胸に抱えてきたその文庫本を、カウンターの上にそっと置いた。湊さんは一瞬きょとんとした顔をしたが、本の表紙と、栞の潤んだ瞳を見て、すべてを悟ったようだった。彼の頬が、店の温かな照明の下で、ゆっくりと赤く染まっていく。
「……気づいて、くれたんだ」
彼の声は、栞がずっと夢見ていたよりも、ずっと優しく、少しだけ震えていた。
「ずっと……言えなかったんだ。君が本を読んでいる姿が好きで、邪魔しちゃいけないって思って」
沈黙が落ちる。でもそれは、気まずいものではなかった。今まで交わしたどんな言葉よりも雄弁に、二人の想いを伝えている。栞は小さく頷き、ようやく微笑んだ。
「私も、言えませんでした」
湊さんが、カウンターからそっと手を伸ばし、栞の手に重なる。三年間、余白に綴られ続けたラブレターが、今、ようやく本当の宛先に届いた。窓の外では、いつの間にか雨が上がり、月が二人の新しい物語の始まりを、静かに照らしていた。