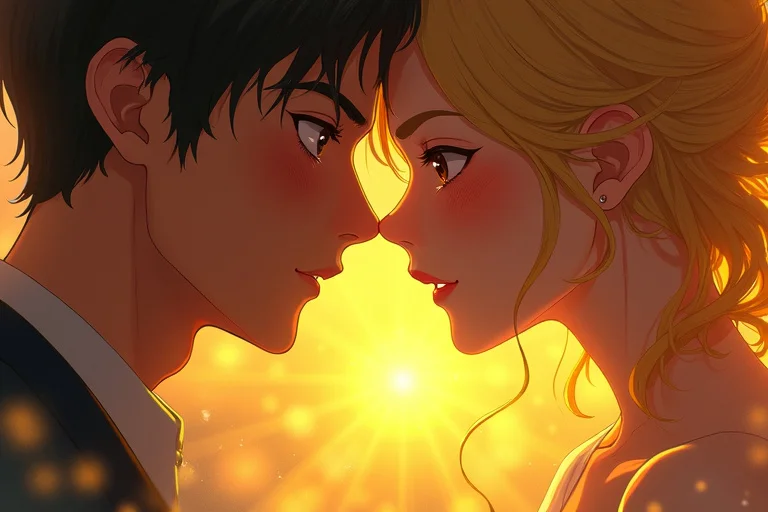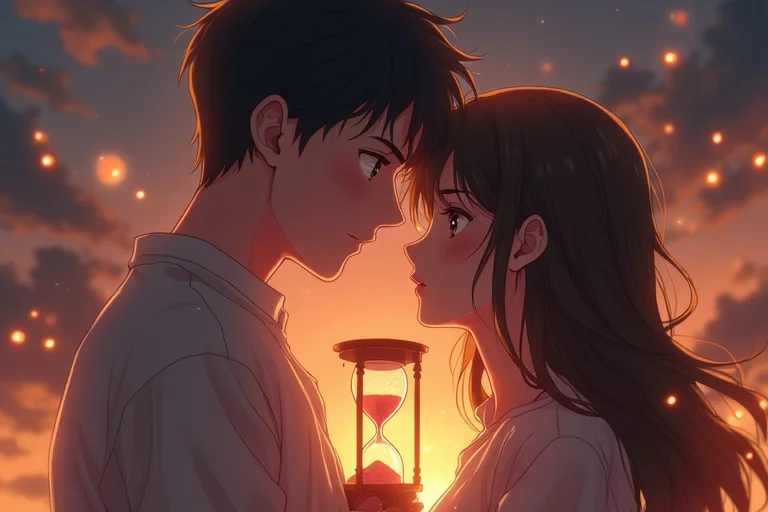私、水野結衣には、ちょっとした秘密がある。人の恋愛感情が、オーラみたいな色として見えるのだ。
淡いピンクは芽生えたばかりの好意。燃えるような赤は情熱的な愛。嫉妬はどす黒い緑で、失恋の悲しみは冷たい青。街を歩けば、世界はカラフルな感情で溢れかえっている。おかげで他人の恋の駆け引きにはやたらと詳しいけれど、自分のこととなると、色が見えすぎるせいでかえって臆病になっていた。
そんな私の日常に、色のない男が現れた。
彼、斎藤蒼太さんは、私が働くカフェの常連客だ。いつも窓際の席で静かに本を読んでいる。彼だけが、何度見ても、どんな時でも、まったく色をまとっていない。完全な「無色」。それは、私が知る限り「完全な無関心」を意味するはずだった。
なのに、私は日に日に彼に惹かれていった。無表情の裏には何があるんだろう。私みたいに、感情でごちゃごちゃした人間には興味がないのかな。知りたい、という好奇心は、いつしか淡い恋心に変わっていた。私から彼に向かって、きっと頼りないピンク色のオーラが伸びているに違いない。もちろん、彼にそれが吸収される気配はまるでないのだけど。
ある日、勇気を振り絞って彼に話しかけた。
「あの…いつも何を読んでるんですか?」
彼は一瞬驚いたように顔を上げたけど、すぐに穏やかな声で答えてくれた。
「古いミステリー小説です。犯人が分かっていても、つい何度も読んでしまう」
その日から、私たちは少しずつ言葉を交わすようになった。彼が薦めてくれた本を読み、感想を言い合うのが私の何よりの楽しみになった。それでも、彼の色は相変わらず「無色」のまま。会話が弾んでも、笑顔を交わしても、何も見えない。
「もう諦めようかな」。そう思った矢先のことだった。私が新作ケーキの試食で悩んでいると、「僕はこっちのレモンタルトが好きだな。君の雰囲気に合ってる」と、彼がぽつりと言った。私がレモン好きだなんて、一度も言ったことはないのに。彼は私の些細な好みや変化に、誰よりも早く気づいてくれた。
色なんて見えなくてもいい。彼の行動や言葉が、何よりの答えじゃないか。私は、色に頼らない恋をしようと決めた。
そして今日。外は土砂降りの雨。店じまいを終えた私を、彼は傘を差して待っていた。
「送るよ」
一つの傘の下、触れ合いそうな肩の距離がもどかしい。沈黙が心臓の音を大きくする。もう、限界だった。私は立ち止まって、彼の目を見つめた。
「蒼太さん。私、あなたのことが好きです」
雨音に負けないよう、はっきりと告げた。
「あなたからは、いつも何の色も見えないんです。だから、あなたがどう思ってるか、全然分からない。でも、もう色なんてどうでもいい。私が、あなたを好きなんです」
言い切った瞬間だった。
彼の全身から、今まで見たこともない、眩いばかりの光が放たれた。それはまるで、溶かした純金を夜空に散りばめたような、荘厳で、温かい「金色」のオーラだった。
呆然とする私に、彼は驚いたように目を見開き、そして、ふっと優しく微笑んだ。
「…やっぱり、そうだったんだ」
「え…?」
「僕もだよ、結衣さん。僕も、人の感情が色で見えるんだ」
信じられない言葉に、思考が止まる。
「君だけだったんだ。僕の世界で、唯一、色を持たない人は。だから気になって、目が離せなくて…いつの間にか、君がいないと物足りなくなっていた。君から色が何も見えないから、僕も自分の気持ちが分からなかった。でも、今なら分かる」
蒼太さんは一歩近づくと、私の濡れた手をそっと握った。
「これは、僕たちの色なんだね」
金色の光に包まれて、私たちは見つめ合った。色に頼らず、心と心で確かめ合ったこの気持ちは、きっと何よりも強い。雨上がりの街が、私たちの始まりを祝うようにキラキラと輝いて見えた。