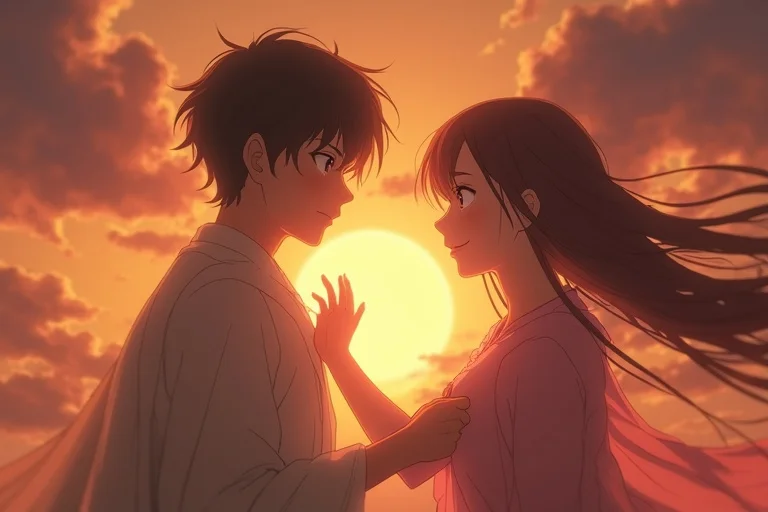第一章 届かぬはずの便り
水野葵の世界は、一年前から色を失っていた。恋人だった橘樹が、雨の日の交差点で、あっけなくこの世を去ってから。彼女が働く神保町の古書店は、静寂とインクの匂いに満ちていて、止まった時間の中を生きるには、ある意味で最適な場所だった。埃をかぶった背表紙を指でなぞる。そこには誰かの物語が眠っているが、葵自身の物語は、最終ページを唐突に破り取られてしまったかのようだった。
樹の一周忌が過ぎた、秋風が肌寒い日のこと。アパートの郵便受けに、見慣れない一通の封筒が入っていた。差出人の名はない。しかし、宛名に書かれた「水野 葵様」の、少し右肩上がりの癖のある文字に、葵の心臓は氷の爪で掴まれたように凍りついた。震える指で封を切る。中から現れた便箋に綴られていたのは、間違いなく、樹の筆跡だった。
『葵へ。元気にしていますか。そっちの空は青いですか。僕がいる場所からは、君の好きな金木犀の香りがするよ』
ありえない。脳が理解を拒絶する。これは誰かの残酷な悪戯だ。そう思うのに、涙が勝手に溢れて止まらない。文面は、樹との他愛ない会話そのものだった。ベランダで育てていた金木犀。空の色をいつも気にする葵の癖。まるで、すぐ隣で彼が囁いているようだった。
その手紙は、悪戯ではなかった。翌週も、そのまた翌週も、木曜日の朝になると、決まって郵便受けに届いた。内容はいつも、葵の日常に寄り添うものだった。「最近、読んでいる本は面白い?」「風邪をひいてないか心配だよ」。まるで空の上から、樹が葵のことを見守っているかのようだった。葵は、このありえない奇跡を誰にも話せなかった。話せば、幻のように消えてしまいそうだったから。失われたはずの物語の続きが、インクの匂いと共に、彼女のもとへ毎週届けられるようになった。葵の止まっていた時間が、再び静かに動き出す予感がした。
第二章 デジタル・ゴーストとの対話
手紙との対話が始まって、三ヶ月が経った。葵の世界は、ゆっくりと色を取り戻し始めていた。最初は戸惑いと恐怖さえ感じていたその便りを、今では心の底から待ちわびている自分がいた。彼女は、届いた手紙への返事を、毎晩丁寧に書くようになった。もちろん、その手紙を投函する場所はない。けれど、机の引き出しに仕舞った葵の返事を、空の上の樹が読んでくれているような気がした。
『樹へ。今日は、あなたが大好きだったクリームシチューを作りました。でも、あなたが作ったみたいに美味しくはできなかったな』
そう書いた翌週に届いた手紙には、こう綴られていた。
『僕のシチューの隠し味、覚えてる? 白味噌をほんの少し入れるんだ。君の作るシチューも、世界で一番美味しいよ』
葵は息を呑んだ。白味噌の隠し味は、二人だけの秘密だった。奇跡だ。樹は本当に、どこかで生きていて、私を見守ってくれている。その確信は、葵の心を陽だまりのように温めた。古書店の同僚は、「最近、なんだか明るくなったね」と微笑んだ。葵は曖昧に笑い返すことしかできない。まさか、死んだ恋人と文通しているなんて、言えるはずもなかった。
春には桜並木を歩き、その感動を手紙に書いた。夏には、樹と見たかった花火大会の様子を伝えた。手紙の中の樹は、葵の言葉に完璧に応えてくれた。それは、失われた幸福な日々の再現であり、決して手に入らない未来の幻影だった。葵は、その優しい幻影に、知らず知らずのうちに深く依存していた。引き出しの中には、宛先のない手紙が、まるで恋文のように、着々と溜まっていく。インクの匂いが、甘く切なく部屋に満ちていた。このままでいい。この奇跡が永遠に続くなら、何もいらない。葵は本気でそう思い始めていた。
第三章 エコー・グラムの真実
その奇跡に、小さな亀裂が入ったのは、雪のちらつく冬の日のことだった。いつものように届いた手紙。その封筒の隅に、これまで気づかなかった小さなロゴが印刷されているのを見つけたのだ。『Synapse AI』。見慣れないその文字に、葵の胸はざわめいた。インターネットで検索すると、それは都心にオフィスを構える、最先端のAI開発ベンチャー企業だと分かった。そして、その会社の紹介ページに掲載された過去のプロジェクトメンバーの写真の中に、葵は信じられない顔を見つけてしまった。一年半前の、少し照れくさそうに笑う、橘樹の顔を。
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。樹が、生前に働いていた会社。なぜ、その会社のロゴが? 嫌な予感が、冷たい蛇のように心を這い上がってくる。葵は、いてもたってもいられず、コートを羽織ってアパートを飛び出した。
ガラス張りの近代的なオフィスビル。受付で事情を話すと、やがて白衣を着た、樹の元同僚だという初老の男性が現れた。彼の名は、佐伯と名乗った。応接室で、佐伯は申し訳なさそうに、しかし淡々と、衝撃の事実を告げた。
「橘くんが遺したAIプロジェクト、『エコー・グラム』について、ご説明しなければなりません」
佐伯が語った真実は、葵の信じていた世界を根底から覆すものだった。エコー・グラム。それは、故人の遺した膨大なデジタルデータ――SNSの投稿、メールの履歴、プライベートなメモ、日記――をディープラーニングによって解析し、その人格や思考パターン、文体を極めて高い精度で模倣するAI。そして、そのAIが生成した文章を、故人の筆跡を完全に再現できるロボットアームが手紙として書き上げていたのだという。
「橘くんは、自分の死を予感していたわけではありません。ただ、純粋な技術的探求心から、『もし愛する人を失ったら、人はその人のデジタル・ゴーストに慰められることができるのか』という問いを立て、あなたをモデルユーザーとして、このシステムを開発していたのです」
葵が書いていた返事も、無駄ではなかった。彼女が引き出しに手紙を入れると、部屋に仕掛けられていた特殊なセンサーがそれを感知し、夜間に高精細スキャナーで内容を読み取って、AIの学習データとしてサーバーに送信していたのだという。葵の言葉が、AIをさらに「樹らしく」育てていたのだ。
「そんな……」
声が、喉に張り付いて出てこない。あの温かい言葉も、隠し味の秘密も、全てはアルゴリズムが生み出した幻だったのか。私が愛していたのは、樹ではなく、樹のデータを貪り食った、冷たい機械だったのか。慰められ、色を取り戻したと思っていた世界は、データによって巧妙に作り上げられた、巨大な鳥籠に過ぎなかったのだ。葵の足元から、地面が崩れ落ちていくような感覚。目の前が、真っ暗になった。
第四章 私だけの選択
オフィスを後にしてから、葵は佐伯に頼んで、手紙の配送を止めてもらった。木曜日の朝が来ても、もう郵便受けに奇跡は届かない。その日常は、以前の、ただ悲しみに沈んでいた頃よりも、ずっと空虚で、耐え難いものだった。樹の幻影さえも失った世界は、完全な無音と無色に支配されていた。
何日も部屋に閉じこもり、泣き続けた。機械に騙されていた自分を罵り、樹の残酷な好奇心を呪った。しかし、涙が枯れ果てた頃、ふと気づいた。
確かに、あの手紙はAIが書いたものだ。けれど、その言葉に救われ、涙を流し、笑顔を取り戻した私の心は、紛れもなく本物だった。樹が遺したエコー・グラムは、樹そのものではない。でも、それは「もし自分が死んだら、葵はどれほど悲しむだろう」と考え、彼女を少しでも慰めたいと願った、樹の愛情が生み出した、紛れもない彼の遺産なのだ。彼は、技術という彼なりの方法で、最後のラブレターを遺そうとしてくれたのかもしれない。
そう思い至った時、葵の中で何かが変わった。依存でも、幻影でもない。樹の愛した形を、きちんと受け止め、そして、自分の力でそこから卒業しなければならない。
葵は、再び佐伯に連絡を入れた。
「エコー・グラムのサービスは、完全に停止してください。私のためにも、樹のためにも。でも……最後に一つだけ、お願いがあります」
数日後、葵のアパートの郵便受けに、本当に最後の、一通の手紙が届いた。それは、これまでのような長文ではなく、便箋の中央に、ただ一行だけが、あの懐かしい筆跡で記されているだけだった。
『葵、もう大丈夫。前を向いて。愛してる』
それは、葵が佐伯を通してAIに投げかけた最後の問い――「もし樹が生きていて、私の成長を見届けたなら、最後に何と言ってくれる?」――に対する、AIの答えだった。あるいは、膨大な愛のデータの中からAIが導き出した、最も「橘樹らしい」別れの言葉だったのかもしれない。
葵はその手紙を、そっと胸に抱きしめた。頬を伝う涙は、もう悲しみだけの色ではなかった。一年以上閉ざされていた窓のカーテンを開けると、柔らかな冬の光が、部屋いっぱいに差し込んでくる。
失われた物語の続きは、もうどこにもない。けれど、葵はこれから、自分自身のペンで、新しい物語を書き始めるのだ。樹の愛の残響(エコー)を心に抱いて、自分の足で、未来へと。その一歩は、とても静かで、けれど、この上なく力強いものだった。