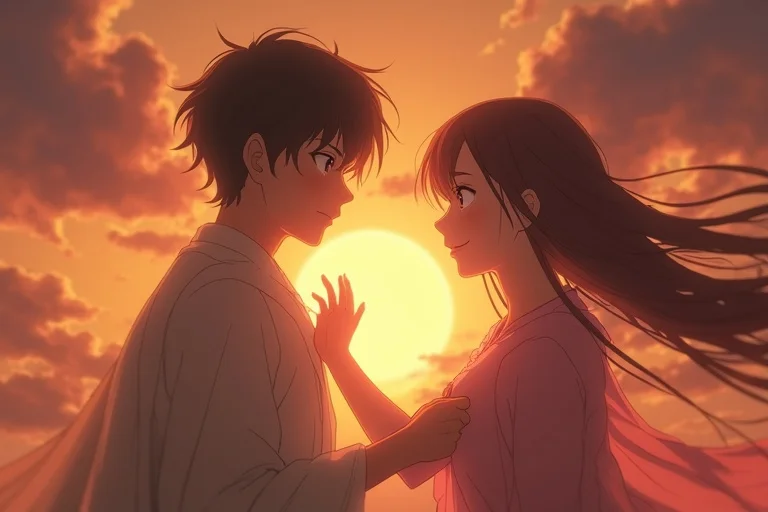私、水野雫には秘密がある。人の嘘が「見える」のだ。
嘘の言葉が発せられた瞬間、その人が手にしている飲み物の水面に、ぽちゃんと小石を投げ込んだような波紋が広がる。幼い頃、ジュースを零した友達が「こぼしてないよ」と言った時に気づいた、私だけの特殊能力。以来、無数の波紋を見てきた私は、すっかり人間不信になっていた。
そんな私の唯一の癒やしは、私がバリスタとして働く路地裏のカフェ「レヴリ」の常連客、月島湊さんの存在だった。
彼はいつも窓際の席で静かに本を読み、私が淹れたコーヒーをゆっくりと味わう。物静かで、穏やかで、そして何より、彼のコーヒーカップが揺れたのを一度も見たことがなかった。彼と交わす他愛ない会話だけが、この世界で唯一の真実に満ちた時間に思えた。
だから、あの日、彼のカップに波紋が走った時、世界がひっくり返るような衝撃を受けた。
「月島さんって、いつもお一人ですけど、彼女さんとかいらっしゃらないんですか?」
それは、ほんの出来心だった。いつものようにカウンター越しに彼と話していて、ふと口から滑り出た、ありふれた質問。彼は少し驚いたように目を丸くして、それからふわりと笑った。
「いませんよ。僕みたいな本ばかり読んでる男、つまらないでしょう」
その瞬間だった。彼の持つ白磁のカップ、その黒い水面に、くっきりと大きな円が広がった。一度だけではない。同心円状に、二度、三度と。それは私が今まで見たどんな嘘よりも深く、大きな波紋だった。
心臓が嫌な音を立てる。どうして? なぜ彼は嘘をつくの? 穏やかな微笑みの裏に、一体何を隠しているんだろう。恋人がいることを隠したい? もしかして、既婚者…? 思考がぐるぐると渦を巻く。
その日から、私は月島さんをまともに見れなくなった。彼の言葉を疑い、カップの水面を盗み見ては、小さな波紋に一喜一憂する。
「この前の週末は、何を?」
「家でずっと、読書をしていました」
カップが、小さく揺れる。
「そのセーター、素敵ですね。どなたかのプレゼントですか?」
「いえ、自分で選びました」
また、揺れる。
彼の嘘は、日に日に私を苛んだ。彼が席を立つたびに残る空のカップが、まるで彼の心のようで、空っぽのはずなのに何か重たいものが沈んでいるように見えた。
このままじゃダメだ。真実が何であれ、それを知らなければ、私は前に進めない。
ある雨の日の午後、私は覚悟を決めた。客は他にいない。カウンターで伝票を整理するふりをして、思い切って声をかけた。
「月島さん。私、ずっと気になっていたんです」
彼は本から顔を上げた。雨に濡れた窓ガラス越しの光が、彼の顔に静かな陰影を落とす。
「あなた、どうして嘘をつくんですか?」
彼の目が、戸惑いに揺れた。
「……嘘?」
「はい。『彼女はいない』って。あれ、嘘ですよね」
彼のカップが、大きく揺れた。観念したように、彼は長い溜め息をついた。
「……どうして、それを」
「わかります。私には、なぜか」
気まずい沈黙が、雨音に溶けていく。もうここには来てもらえないかもしれない。そう思った時、彼がぽつりと言った。
「一年前に、亡くなったんです。婚約者でした」
え…?
言葉の意味が、すぐには理解できなかった。
「結婚式の、一ヶ月前でした。交通事故で……。僕の運転する車の、隣で」
彼の声は、波紋一つ立てない、静かな真実だった。
「だから、『彼女はいない』という言葉は、僕にとっては嘘になるんです。まだ、僕の中では、彼女が一番大切な人だから。週末も、彼女が好きだった場所に花を供えに行ったりする。このセーターも、彼女が選んでくれたものなんです」
彼は、静かに泣いていた。涙が頬を伝い、顎の先で雫になる。
嘘の波紋は、彼の悲しみの深さだったのだ。恋人を失った事実を、世界に対して「いない」と偽ることで、彼は必死に彼女の存在を自分の中に守り続けていた。
私の能力は、なんて浅はかなんだろう。嘘か本当か、その二択しか見ることができない。その裏にある、人の痛みも、愛しさも、悲しみも、何も見えていなかった。
私は黙ってカウンターを出て、彼の隣に新しいコーヒーを置いた。
「すみません。私、あなたのことを何も知らずに…」
彼はゆっくりと首を横に振った。
「ううん。ありがとう。誰にも話せなかったから。少し、楽になりました」
そう言って微笑んだ彼の顔は、今までで一番、本当の顔をしているように見えた。
「あの、月島さん」
私は、震える声で言った。
「もし、よかったら……。いつか、その嘘が本当の思い出になる日まで、ここのコーヒーを飲みに来てもらえませんか」
彼は驚いたように私を見つめ、そして、長い沈黙のあと、雨上がりの空みたいに、ふっと微笑んだ。
「……はい、ぜひ」
彼の新しいカップの水面は、静かに澄み渡っていた。
けれど、私の手元にあったミルクピッチャーの水面にだけ、小さくて温かい、期待の波紋がひとつ、きらりと揺れたのを、私は見逃さなかった。