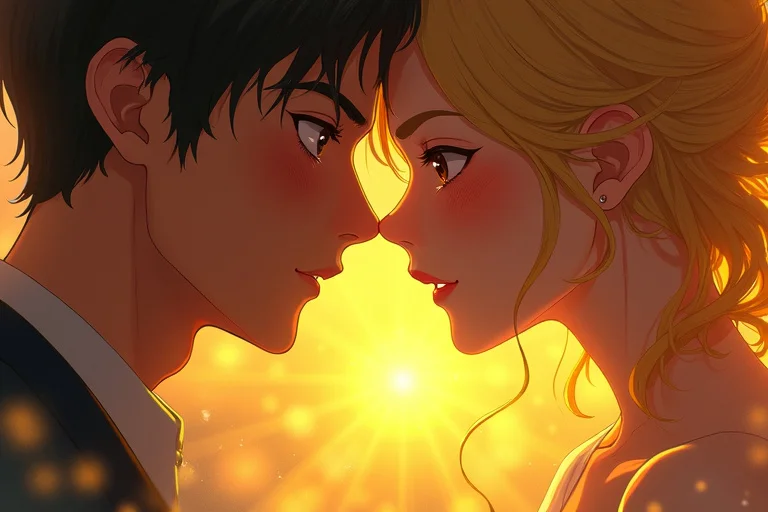神保町の古書店街、その片隅に佇む「時雨堂書店」の埃っぽい空気とインクの匂いが、私の世界のすべてだった。水野栞、二十歳。私の指先には、ちょっとした秘密がある。古書に触れると、その最後の持ち主が抱いていた強い感情が、痺れるような熱と共に流れ込んでくるのだ。
その日、私が店の奥深くで見つけたのは、一冊の古びた洋書だった。深い藍色の装丁に、銀の箔押しで『星屑のソNET』と題された詩集。そっと指を滑らせた瞬間、電流が走った。
――会いたい。今すぐ、この想いを伝えなければ。
胸を締め付けるような、焦がれるほどの恋心。そして直後、叩きつけられたのは絶望にも似た深い後悔だった。果たせなかった約束、伝えられなかった言葉。あまりに鮮烈な感情の奔流に、私は思わず本を落としそうになった。こんなにも心を揺さぶられたのは初めてだった。この本の持ち主は、一体誰なのだろう。
気づけば私は、大学の図書館でその詩集について調べていた。手掛かりは、見返し部分にインクで書かれた「K.I」というイニシャルだけ。
「その本、探してるんだ」
不意に背後から声をかけられ、心臓が跳ねた。振り返ると、同じ学部の講義で時々見かける、一ノ瀬湊が立っていた。色素の薄い髪と、すべてを見透かすような静かな瞳が印象的な人。
「何か知ってるんですか?」
「少しね。それ、ただの詩集じゃない。ある物語の、最後のページみたいなものだから」
彼の言葉は謎めいていた。吸い寄せられるように、私は自分の秘密を打ち明けてしまった。触れたものから感情を読み取る、この奇妙な力を。すると彼は驚くでもなく、ただ静かに頷いた。
「俺は、物に宿った記憶を映像として見ることができる」
信じられない告白だった。私たちはお互いの存在に驚きながらも、まるでパズルのピースが嵌まるような不思議な感覚を覚えていた。
こうして、私たち二人の奇妙な共同調査が始まった。私が詩集から「焦燥感」や「期待」といった感情を読み取り、湊が指を触れて断片的な映像を拾い上げる。
「古い大学のキャンパスだ。銀杏並木……あ、今の図書館の旧館かもしれない」
「この感情、高揚してる。きっと、これから誰かに会うんだ」
「男が、この詩集を胸に抱えて走ってる……誰かを待たせてるみたいだ」
私たちは、数十年前の恋人たちの足跡を辿った。感情と映像を突き合わせる作業は、まるで失われた恋物語を二人で書き起こしていくようだった。調査と称して、古いカフェに入ったり、夕暮れのキャンパスを歩いたり。共有する秘密は急速に私たちの距離を縮め、気づけば私は、湊の隣にいる自分を当たり前のように感じていた。彼の指が偶然私の手に触れた時、流れ込んできたのは穏やかで温かい感情。私の胸は、詩集の持ち主とは違う、確かな熱を帯び始めていた。
調査の末、詩集の持ち主「K.I」が、湊の祖父である一ノ瀬航平だということが判明した。そして、彼が詩集を渡そうとしていた相手は、湊の祖母だった。
「でも、どうして渡せなかったんだろう……」
私の呟きに、湊は悲しげに目を伏せた。
「祖父は、大学卒業を目前にした雨の日、交通事故で亡くなったんだ。祖母にプロポーズする、その日に」
息を呑んだ。私が読み取ったあの強烈な後悔は、死の瞬間のものだったのだ。
さらに、湊は衝撃の事実を口にした。
「事故の相手の車を運転していたのが……水野という姓の男性だったらしい」
世界から、音が消えた。私の祖父だ。偶然であってほしいと願う心とは裏腹に、記憶の断片が繋がっていく。過去の因縁が、氷の壁となって私たちの間に立ちはだかった。
「ごめん……」
謝るしかなくて、私はその場から逃げ出した。湊に会う資格なんてない。私たちの間に生まれたこの温かい気持ちは、許されないものなのだと。
数日後、湊から連絡があった。「最後に、一緒に見てほしい映像がある」と。時雨堂書店で再会した私たちは、気まずい沈黙の中、再び詩集に向き合った。湊が深く息を吸い、その指を最後のページに置く。
彼の瞳を通して、映像が流れ込んできた。雨の交差点。滑るタイヤ。衝撃の瞬間。しかし、湊の祖父・航平の最後の記憶は、憎しみではなかった。
彼の視線の先には、傘もささずに駆け寄り、必死に彼を助けようとする若い男――私の祖父の姿があった。
『君のせいじゃない……頼む、これを……彼女に……』
途切れ途切れの意識の中、航平は血濡れの手で詩集を私の祖父に託そうとしていた。彼の最後の想いは、事故の相手への赦しと、愛する人への伝言だったのだ。
映像が終わると、湊は私の手を強く握った。
「これは、俺たちの物語じゃない。でも、俺たちが終わらせる物語だ」
彼の瞳は、もう迷っていなかった。
私たちは、湊の祖母の家を訪ねた。湊が震える手で『星屑のソネット』を差し出すと、祖母はすべてを察したように、静かに涙を流した。
「……やっと、会えたのね、航平さん」
皺の刻まれた指で優しく詩集を撫でる彼女の姿に、数十年の時を超えて、一つの恋が完結するのを見た。
帰り道、夕日が私たちをオレンジ色に染めていた。
「栞」
湊が立ち止まり、私の手を取った。
「過去は過去だ。俺は、君と未来のページをめくりたい」
流れ込んできたのは、誠実で、どこまでも優しい、確かな愛情だった。
私は頷き、彼の手に自分の手を重ねる。指先から伝わる温もりが、私たちの新しい物語の始まりを告げていた。埃っぽい古書店の片隅で見つけた恋物語は、今、私たちのラストページ・ロマンスへと姿を変えたのだ。