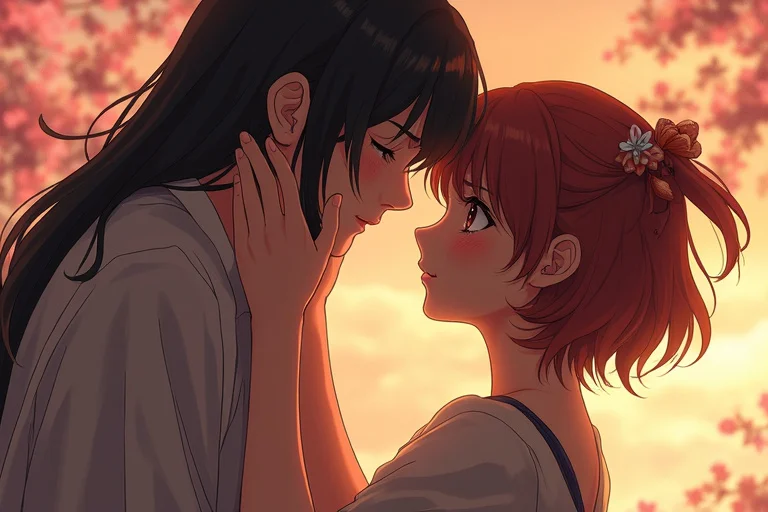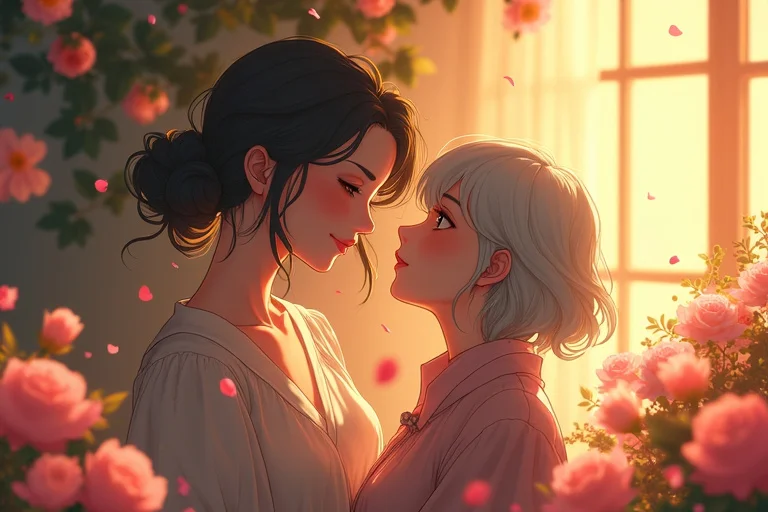僕、佐藤健太の耳には、生まれつき特殊なフィルターが搭載されている。それは、他人の「心の声」を拾ってしまうという、迷惑千万な代物だ。
満員電車は悪意と欲望の不協和音だし、大学の講義室は建前と本音のデスメタルが鳴り響くライブ会場だ。だから僕は、いつもノイズキャンセリング機能付きのヘッドホンで耳を塞ぎ、大音量の音楽で世界を遮断して生きている。恋愛なんて、もってのほか。相手の心の声が「退屈だな」なんて呟いているのを聞いてしまって以来、僕の恋は永久凍結中だ。
そんな僕の灰色の日々に、異変が起きたのは、ある春のことだった。
いつものように講義室の隅でうんざりしていると、ふと、世界から音が消えた。いや、正確には、僕のすぐ隣の一角だけが、完全な「無音」になったのだ。驚いて顔を上げると、そこにいたのは、同じゼミの高槻雫さんだった。
彼女は、色素の薄い髪をさらりと揺らし、ただ静かにノートを取っている。彼女の周りだけ、まるで深海のように穏やかで、静かだった。僕の能力が、彼女にだけは通用しない。
その日から、僕は高槻さんに惹きつけられた。彼女の隣は、僕にとって世界で唯一の安息地帯だった。
「あの、この前のレジュメ、見せてもらえないかな」
勇気を出して話しかけると、彼女はふわりと微笑んで「どうぞ」と差し出してくれた。その表情から、感情は読み取れない。もちろん、心の声も聞こえない。僕は、生まれて初めて、相手の言葉と表情だけを頼りに、手探りでコミュニケーションを取るという難題に直面していた。
「高槻さんって、いつも何を考えてるの?」ある日の帰り道、僕はつい、そんな馬鹿な質問をしてしまった。
彼女は少し目を丸くして、それからくすりと笑った。「さあ、何でしょうね。佐藤くんは、どう思う?」
返ってくるのは、いつもそんなふうに、ふわりとしたボールだけ。もどかしい。けれど、そのもどかしさが、不思議と心地よかった。心の声というズルができない分、彼女の一挙手一投足に集中し、言葉の裏にある本当の意味を必死で探る。それはまるで、難解なパズルを解くような、胸が躍る体験だった。
転機は突然訪れた。
ゼミの打ち上げで訪れたカフェは、他人の自意識と嫉妬のノイズで満ちていた。『あいつ、なんで高槻さんと仲良いんだよ』『二人、付き合ってんのかな』。耳障りな心の声が頭に突き刺さり、僕は思わず顔をしかめた。
その時、テーブルの下で、そっと僕の手に柔らかな感触が触れた。高槻さんの指だった。
指が触れた瞬間、嘘のように、僕の世界から全てのノイズが消え去った。嵐が過ぎ去ったあとのような、完璧な静寂。驚いて彼女を見ると、彼女は少しだけ悲しそうに微笑んでいた。
「……うるさかったでしょ」小さな、けれどはっきりとした声で彼女は言った。「ごめんね、気づいてあげられなくて。あなたも、”聞こえる”人だったんだね」
僕らはカフェを飛び出し、夜の公園のベンチに座っていた。
「私の能力は、心を閉ざすこと」彼女はぽつりぽつりと語り始めた。「完璧な壁を作って、誰も私の心に入れないようにする。それが強すぎたみたいで、いつからか、周りの人の能力まで遮断するようになったの」
彼女はずっと、その能力のせいで孤独だった。誰も本当の自分を理解してはくれない。心を閉ざすことでしか、自分を守れなかったのだ。
「だから、私の心は空っぽなの。誰にも聞こえないし、届かない」
うつむく彼女を見て、僕はたまらなくなった。僕はいつも耳に当てていたヘッドホンを外し、彼女の手に重ねた。
「違うよ」
僕の声が、静かな公園に響く。
「君の隣は、世界で一番穏やかで、優しい場所だ。俺は、君の心の声なんて聞こえなくてよかった。だから、必死で君のこと、知ろうとしたんだから」
僕は一度、息を吸う。
「心の声じゃなくて、高槻さん自身の言葉が聞きたい。君が何を考えて、何が好きで、何に笑うのか。俺に、教えてくれないかな」
顔を上げた彼女の瞳が、月明かりを反射してきらりと光る。そして、ゆっくりと、僕が今まで見たことのない、心の底からの花が咲くような笑顔を見せた。
「……健太くんって、呼んでもいい?」
その瞬間、僕の耳に、微かに聞こえた気がした。トクン、という、温かくて優しい、世界でたった一つの音。僕と彼女の恋が、今、始まった音だった。