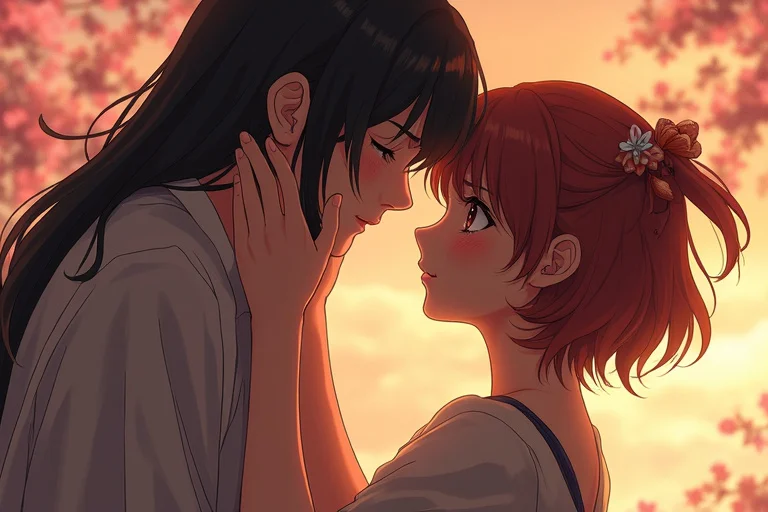第一章 幻の本と雨の女
古びたインクと紙の匂いが満ちる僕の城、「時雨堂古書店」。祖父から受け継いだその場所は、僕にとって世界のすべてだった。高い天井まで届く書架に囲まれ、背表紙の森を彷徨う時間は、現実の煩わしさから僕を遠ざけてくれる。過去の失恋が残した心の疼きも、ここでは静かに眠りについてくれるのだ。
その女性、月島遥が初めて店に現れたのは、梅雨の気配が街を濡らし始めた六月の雨の日だった。ドアベルがちりん、と澄んだ音を立て、彼女は雨の雫を弾くように入ってきた。透明なビニール傘の向こうに見えた横顔が、やけに印象的だったのを覚えている。
「いらっしゃいませ」
声をかけると、彼女はゆっくりと僕の方を向いた。色素の薄い瞳が、店内の薄暗がりの中で静かに光っているように見えた。
「あの、お探しします。一冊の本を」
その声は、雨音に溶けてしまいそうなほど繊細だった。
「『空白のラブレター』という本、ご存知ありませんか」
『空白のラブレター』。
聞いたことのないタイトルだった。僕は店の全ての在庫を把握している自負がある。データベースで検索をかけても、国内外のどの出版社の記録にも、そんな本は存在しなかった。
「申し訳ありませんが、その本は記録にありませんね。作者名はわかりますか?」
「……わかりません。でも、きっとここにあるはずなんです」
彼女はそう言って、諦めたように微笑んだ。その笑顔はどこか寂しげで、僕の心の隅を微かに揺さぶった。
それからだった。遥さんは、毎週火曜日の午後三時、まるで時計のように正確に店を訪れるようになった。雨の日も、灼けつくような夏の日も、彼女は必ずやって来ては、同じ問いを繰り返した。
「『空白のラブレター』、入りましたか?」
「いえ、まだ……」
その短いやり取りが、僕たちの間の儀式になった。彼女は決して長居はしない。店内をゆっくりと一周し、書架の背表紙を指でなぞり、そして小さなため息と共に出ていく。僕は、そんな彼女の後ろ姿を、いつもカウンターの内側から見送っていた。
彼女が探す幻の本とは一体何なのか。なぜ、この店にあると信じているのか。謎は深まるばかりだったが、それ以上に、僕は月島遥という存在そのものに強く惹きつけられていた。週に一度、数分間だけ交わされる儀式が、僕の単調な日常を鮮やかに彩り始めていたのだ。止まっていたはずの時間が、彼女の来訪を心待ちにすることで、再びゆっくりと動き出しているのを感じていた。
第二章 重なる時間、芽生える想い
季節は夏を越え、秋風が書店の隙間を吹き抜けるようになった頃、僕たちの関係に変化が訪れた。いつものように遥さんが訪れた日、僕は思い切って声をかけた。
「もしよろしければ、僕も一緒に探させていただけませんか。古書組合の仲間にも声をかけてみます」
僕の申し出に、彼女は驚いたように目を丸くした。そして、ふわりと花が咲くように微笑んだ。
「……ありがとうございます。水野さん」
初めて名前を呼ばれ、心臓が大きく跳ねた。
それから僕たちは、本の捜索を口実に、多くの時間を共にするようになった。僕は全国の古書店に手紙を書き、インターネットの古書コミュニティにも情報を求めた。遥さんはその手伝いをしながら、彼女自身のことを少しずつ話してくれた。亡くなった祖母が、彼女にとってどれほど大切な存在だったか。その祖母が、生前よく口にしていたのが『空白のラブレター』の物語だったということ。
「お祖母様は、その本を読んだことがあると?」
「いいえ。ただ、その本のことを話す時、とても幸せそうだったんです。『それはね、世界で一番素敵な恋文なのよ』って。だから、私も読んでみたいんです。おばあちゃんが見ていた世界を」
僕たちは休日に、神保町の古書店街を一緒に歩いた。彼女と並んで歩くと、街の風景がいつもと違って見えた。アスファルトの匂い、人々のかすかなざわめき、ショーウィンドウに反射する夕陽の光。そのすべてが、彼女の存在によって特別な意味を持つように感じられた。
内向的で、人と深く関わることを避けてきた僕が、彼女の前では自然に笑えていることに気づく。遥さんの儚げな横顔を守りたい、彼女の探す本を必ず見つけ出して、あの寂しげな微笑みを本当の喜びに変えたい。それは紛れもなく恋心だった。臆病風に吹かれていた僕の心に、確かな熱が灯り始めていた。
ある日の夕暮れ、調査に行き詰まり、店の隅で肩を落とす僕に、遥さんが温かい紅茶を淹れてくれた。湯気の向こうで、彼女の瞳が優しく揺れていた。
「水野さん、無理なさらないでください。こうして一緒に探してくれるだけで、私はとても嬉しいんです」
その言葉が、乾いた心にじんわりと沁みた。僕は、この温もりを手放したくないと、強く思った。幻の本が見つかっても見つからなくても、この関係が続いてほしい。そんな身勝手な願いが胸に芽生えていた。
第三章 空白の真実
冬の気配が色濃くなった十二月、事態は思わぬ形で動いた。祖父の代から付き合いのある老舗古書店の店主から、一本の電話が入ったのだ。先日亡くなった無名の作家の遺品整理を手伝っていたところ、奇妙な草稿の束が見つかったという。表紙には、拙い手書きの文字で『空白のラブレター』と記されていた、と。
僕は逸る心を抑えきれず、遥さんと共にその場所へ向かった。古いアパートの一室。埃っぽい部屋の片隅に置かれた桐の箱の中に、それはあった。和紙で丁寧に装丁された一冊の本。表紙には、確かに『空白のラブレター』と書かれている。僕たちは顔を見合わせ、息を呑んだ。
しかし、ページをめくった瞬間、僕たちは言葉を失った。
そこには、一行の文字もなかった。ただ、真っ白なページが延々と続いているだけ。それは、タイトルだけが記された、完全な「空白」の本だったのだ。
愕然とする僕の横で、遥さんは静かに涙を流していた。
失望だけではない、何か別の感情がその涙には含まれているように見えた。混乱する僕の目に、草稿の束の底にあった一枚の紙が飛び込んできた。それは古ぼけた手紙で、差出人の名前を見て、僕は全身の血が凍りつくのを感じた。
「水野 健吾」。僕の祖父の名前だった。
震える手で手紙を読み、日記を辿り、僕はすべての真実を知った。
祖父には、心から愛した女性がいた。彼女こそ、遥さんの祖母だったのだ。しかし、彼女は若くして記憶を失っていく病を患った。愛しい人との思い出が、砂の城のように崩れていく絶望の中で、祖父は一つの決意をした。
もし、君が僕との記憶をすべて失ってしまっても、僕たちはまた新しく恋をすればいい。何度でも、最初から始めればいい。その想いを込め、祖父は「これから二人で物語を紡いでいくため」の、何も書かれていない本を彼女に贈った。それが『空白のラブレター』だった。
それは、失われた記憶への哀悼ではなく、未来への約束の証だったのだ。
遥さんが探していたのは、物理的な本ではなかった。祖母が語ってくれた「世界で一番素敵な恋文」の記憶、その象徴そのものだった。そして、彼女は告白した。自分もまた、祖母と同じ病気の診断を受けたと。記憶が薄れ始める前に、愛の記憶の原点であるこの「時雨堂」で、その証に触れたかったのだと。
「ごめんなさい。ずっと、黙っていて」
涙声で謝る彼女を見て、僕は自分の無力さを痛感した。同時に、彼女が抱えてきた孤独と不安の大きさに胸が張り裂けそうになった。僕が感じていた彼女の儚さの正体は、これだったのだ。僕の価値観が、世界が、根底からガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。これは、単なる恋愛物語ではなかった。もっと深く、切実な、愛と記憶をめぐる物語だった。
第四章 君と綴る物語
数日後、僕は遥さんを「時雨堂」に招いた。カウンターの上に、あの『空白のラブレター』を置く。僕がこれから何をすべきか、答えはもう出ていた。
「遥さん」
僕は彼女の目をまっすぐに見つめて言った。
「僕の祖父は、君のお祖母さんと、この本を物語で満たすことはできなかった。でも、僕たちならできるかもしれない」
僕は空白のページを開き、万年筆を手に取った。
「君がこれから忘れてしまうかもしれない、たくさんのこと。僕が全部、ここに書き留める。君が好きな花の色も、好きな音楽も、僕と笑い合った日のことも。もし君が何もかも忘れてしまったら、僕がこの本を最初から読んで聞かせる。そうすれば、僕たちはまた、何度でも恋に落ちることができる」
それは、臆病だった僕が、人生で初めて下した、最も勇敢な決断だった。未来への計り知れない不安も、病という現実も、すべて引き受けて彼女を愛し抜くという誓いだった。
遥さんの瞳から、大粒の涙がいくつもこぼれ落ち、空白のページに小さな染みを作った。だが、その顔には、僕がずっと見たかった、心からの安らかな微笑みが浮かんでいた。それは、僕たちの物語の、最初のインクの跡となった。
あれから、五年が経った。
「時雨堂」の片隅には、客人の邪魔にならないようにと置かれた、小さなテーブルと二脚の椅子がある。僕はそこで、日に日に記憶が曖昧になっていく遥の手を握りながら、一冊の本を読み聞かせている。
『第一章。雨の降る日、彼女は透明な傘をさして、僕の城を訪れた……』
僕が日々書き綴っている、僕たちだけの物語。世界に一冊しかない、『空白のラブレター』だ。遥は、物語の続きを思い出せないかもしれない。僕の名前すら、時々おぼつかなくなる。それでも、僕が本を読み始めると、彼女は決まって幸せそうに目を細めるのだ。その表情を見るたび、僕は確信する。
愛とは、記憶の完璧な保存記録ではない。それは、たとえすべてが失われても、目の前の相手を想い、その瞬間に新しい物語を共に紡ごうとする、絶え間ない意志そのものなのだと。
窓の外では、また雨が降り始めている。僕たちの物語は、まだ始まったばかりだ。インクの匂いに混じって、遥さんの淹れてくれる紅茶の香りが、この古書店を優しく満たしている。