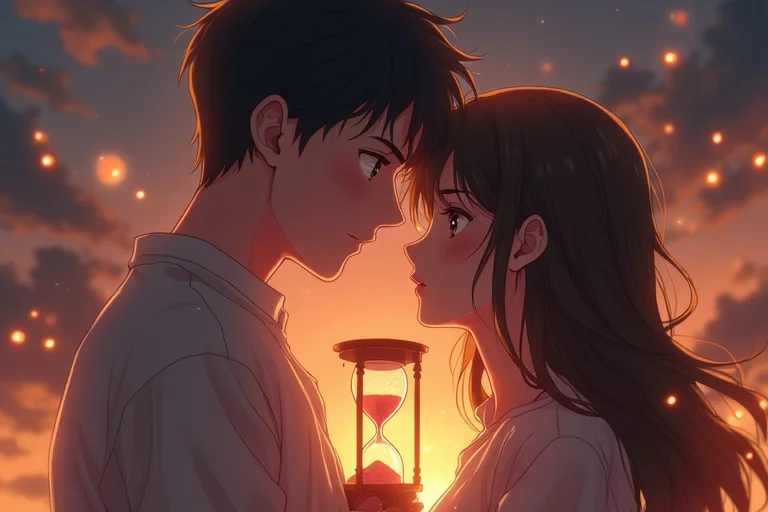私、佐藤莉奈には秘密がある。それは、モノの声が聞こえること。それも、なぜか自分が好意を寄せた相手の持ち物限定、という非常に使いどころの偏った能力だ。
片思いの相手は、同じ部署の先輩、鈴木拓也さん。クールで仕事ができて、笑うと少しだけ目尻が下がる、絵に描いたような理想の人。でも、何を考えているかさっぱり分からず、私にとってはまさに難攻不落の城。今日も遠くから眺めるだけで一日が終わりそうだった。
その日の午後、事件は起きた。拓也さんが会議室に置き忘れた一本の万年筆。私が届けようと手に取った瞬間、渋いテノールボイスが頭に響いたのだ。
『おい、そこの嬢ちゃん。うちのご主人をあんな熱っぽい目で見つめて。感心せんな』
「えっ!?」
『驚くのも無理はない。我輩はパーカー社が誇るソネット。書き味も一流なら、観察眼も一流でな。ご主人は、君が思うより君のことを見てるぞ』
これが、私の最初の「恋のコンサルタント」との出会いだった。私は彼を「ペン先輩」と名付けた。
それから私の日常は一変した。ペン先輩を皮切りに、拓也さんのデスクのマグカップ(『拓也はねー、意外と甘党なんだよ!昨日もプリン食べてた!』とお調子者の声で教えてくれた)、会社のIDカードホルダー(『彼の首筋の汗、独り占めだぜ…』と呟く変態)、果ては彼のスマホ(『全情報、俺に任せろ!彼の検索履歴はな…』と口の軽い情報屋)まで、私の周りはにわかに騒がしくなった。
「よし、チーム拓也!作戦会議を始めます!」
週末、私は拓也さんのモノたち(こっそり借りてきた)を自室のテーブルに並べた。
「まず、マグカップ君の情報通り、手作りプリンでアピールするのはどうかな?」
『賛成!絶対喜ぶって!』とマグカップが揺れる。
『待て。ご主人は甘いものは好きだが、卵アレルギーだ』とペン先輩が冷静にツッコミを入れる。
「あぶなっ!」
『チッ、惜しい』とマグカップが舌打ちする。こいつ、さては妨害工作員か?
スマホに至っては最悪だった。『映画のチケット、二枚取っといた!あとは誘うだけ!健闘を祈る!』と、勝手に予約完了メールを私のスマホに転送してきたのだ。パニックになった私は、拓也さんに「すみません!操作ミスです!」と平謝りする羽目になった。
モノたちの情報は玉石混淆。というか、ほとんど石だ。私は頭を抱えた。彼らに頼ってばかりじゃダメだ。私は、私の目で鈴木さんを見なくちゃ。
そう決意した矢先、ビッグチャンスが訪れた。会社の命運を賭けた大型コンペ。そのメインプレゼンターに拓也さんが抜擢されたのだ。しかし、プレッシャーは相当なものらしかった。日に日に彼の顔から笑顔が消え、デスクにはエナジードリンクの空き缶が増えていく。
モノたちも心配そうだ。『ご主人の指、震えておる…』とペン先輩が呟く。『バッテリー残量みたいに、彼の元気も3%だよ』とスマホが嘆く。
コンペ前日。誰もいなくなったオフィスで、一人頭を抱える拓也さんを見つけた。今だ。モノの情報じゃない、私が感じたままを伝えるんだ。
「あの、鈴木さん」
声をかけると、彼の肩がびくりと揺れた。
「お疲れ様です。これ、良かったら」
私が差し出したのは、温かいカモミールティー。これは、私が彼をずっと見ていて気づいたこと。彼は疲れた時、いつもカモミールの香りのハンドクリームを塗っていたから。
「なんで…」
拓也さんが驚いた顔で私を見る。
「鈴木さん、いつも完璧ですけど、たまには肩の力、抜いてもいいんですよ。プレゼン、応援してます。鈴木さんなら、絶対大丈夫です」
私の言葉に、彼は一瞬目を見開いて、それから、ふっと笑った。いつものクールな笑顔じゃない。私が初めて見る、心からの優しい笑顔だった。
「…ありがとう。なんか、全部見透かされてるみたいだな」
翌日、彼のプレゼンは大成功を収めた。
そして、その週末。私のスマホが震えた。表示されたのは「鈴木拓也」の名前。
『佐藤さん、今週末、空いてるかな。お礼がしたいんだ。君の“魔法”のおかげで、うまくいったから』
電話の向こうで、拓也さんが少し照れたように笑うのが分かった。私の胸で、心臓がトクトクと楽しげな音を立てる。
ふと見ると、机の上のペン先輩のキャップが、誇らしげにキラリと光った気がした。どうやら私のポンコツなコンサルタントたちは、ここぞという一番大事な場面では、最高の仕事をしてくれるらしい。