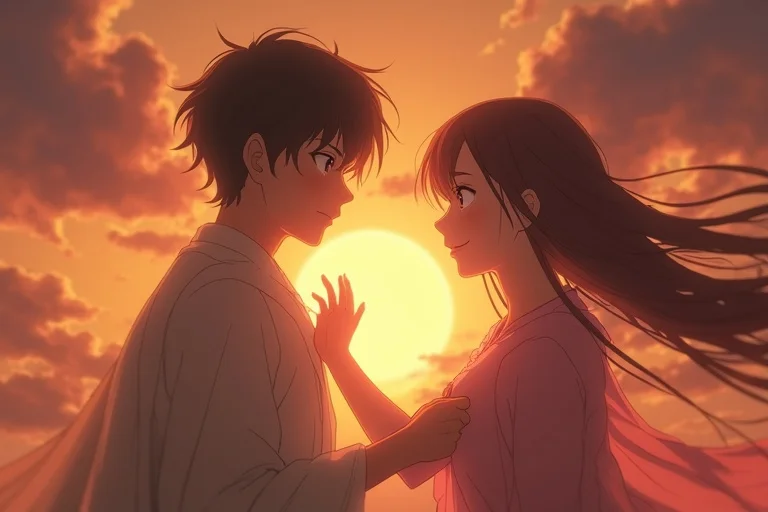私の渾身の恋愛小説は、出版からわずか三日で、ネットの海で処刑された。
執行人は、正体不明の覆面書評家『ノワール』。彼のレビューサイトは、出版業界を震撼させるほどの鋭利な言葉で埋め尽くされている。そして、私の新作に向けられたのは、その中でもとりわけ冷酷な一文だった。
『砂糖菓子を煮詰めただけの空虚な物語。登場人物たちは愛ではなく、作者の自己満足を囁き合っている』
頭が真っ白になり、次いで全身の血が沸騰するような怒りがこみ上げた。どうしようもない衝動に駆られ、私はコートを羽織ってアパートを飛び出した。
行き着いた先は、路地裏にひっそりと佇む深夜営業のカフェ『ルナ・コーヒー』。古びた木の扉を開けると、焙煎された豆の香ばしい匂いが私を迎えた。
「……いらっしゃいませ」
カウンターの奥から、低い声がした。店主の月島湊さん。彼はいつも無口で、少し影のある人だ。彼が黙って差し出すエスプレッソの、深く苦い味が、今の私には唯一の慰めだった。
「ひどいと思いませんか!?顔も知らないくせに!」
カップをカウンターに叩きつけるように置き、私は湊さんに捲し立てた。ノワールの正体を絶対に突き止めて、あのレビューがいかに見当違いか、目に物見せてやるのだと。
湊さんは黙って私の話を聞いていたが、やがて静かに口を開いた。
「……彼の言葉には、本への愛があるように聞こえるが」
「愛!?どこに!あれはただの悪意です!」
思わぬ反論に、私はさらに声を荒らげた。しかし湊さんは表情を変えず、ただ私の空になったカップを下げた。
それから数週間、私はノワール探しに没頭した。彼のレビューに頻出するマイナーな古典文学、マニアックなコーヒーの銘柄。それらを手がかりに古書店を巡り、ネットの海を彷徨った。
行き詰まるたび、私は『ルナ・コーヒー』のカウンターに座った。そして驚くべきことに、私が探している知識のほとんどを、目の前の寡黙なバリスタが持っていることに気づき始めたのだ。
「その作家なら、初期の短編にこそ本質があります」「その豆は浅煎りだと、隠れた酸味が顔を出す」
湊さんの言葉は、ノワールのレビューの文体と、どこか重なって聞こえた。まさか、という疑念が胸をよぎる。でも、こんなに優しい人が、あんな辛辣な言葉を書くはずがない。
ある晩、調査が完全に手詰まりになり、私は店のカウンターで突っ伏していた。もう小説家なんてやめてしまおうか。弱音が涙と一緒にこぼれそうになった時、目の前にそっとガラスの器が置かれた。
真っ白なバニラアイスに、小さなピッチャーが添えられている。
「……アフォガートだ」
「苦いものだけじゃ、やってられないだろ」
ぶっきらぼうな口調とは裏腹に、その声には確かな温かさがあった。ピッチャーから、湯気の立つ熱いエスプレッソをアイスにかける。じゅわ、と音を立てて溶けていく白と黒のコントラスト。甘さと苦さが混じり合う、複雑で豊かな味わいが口の中に広がり、強張っていた心がゆっくりと解けていくのを感じた。
その日から、私の心はノワールへの怒りよりも、湊さんへの想いで満たされるようになっていった。
決定的な瞬間は、突然訪れた。
ノワールが最新のレビューで、ある幻のコーヒー豆について触れていたのだ。『樹齢百年の木から、満月の夜にのみ手摘みされるその豆は、まるで夜の静寂を液体にしたような味がする』
その詩的な表現に、私は息を呑んだ。それは先日、湊さんが豆の蘊蓄を語ってくれた時に、目を輝かせながら使った言葉と、一言一句同じだったから。
全てのピースが、カチリと音を立ててはまった。
私は震える足で『ルナ・コーヒー』へ向かった。
「湊さん」
カウンター越しに彼と対峙する。私の声は、自分でも驚くほど静かだった。
「あなたが、ノワールなんでしょう?」
一瞬の沈黙。彼はゆっくりと顔を上げ、私を真っ直ぐに見つめると、静かに頷いた。
「……ああ」
怒りよりも先に、どうして、という疑問が湧き上がった。すると彼は、まるで私の心を見透かしたかのように語り始めた。
「君の文章には、才能の片鱗が見えたからだ。でも、君は自分に嘘をついていた。本当に書きたいことから逃げているように見えた。だから、あえて厳しい言葉を選んだ」
彼は続ける。
「君の小説には、いつも苦くて冷たいエスプレッソのような孤独が隠れている。なのに、甘いクリームで無理やり蓋をしている。俺は、その苦さごと味わってみたかったんだ」
それは、誰にも見せたことのない、私の心の奥底を正確に抉る言葉だった。気づけば、頬を涙が伝っていた。
「じゃあ、あのレビューは……」
「君に宛てたラブレターのつもりだったんだが……書き方を間違えたらしい」
湊さんは、初めて見る困ったような顔で笑った。
その不器用な笑顔を見て、私の心にあった怒りも悔しさも、全てが氷解していくのを感じた。ただ、目の前の愛おしい男のことで、胸がいっぱいになった。
「……最低のラブレターね。でも、今までで一番、心に響いたかも」
湊さんは黙って、新しいアフォガートを作り始めた。真っ白なアイスに、深く、黒いエスプレッソを注ぎながら、彼は私に言った。
「苦さと甘さ。混ざり合って初めて、本当の味になる。……俺たちみたいに」
私たちは見つめ合い、微笑んだ。店の古時計が午前零時を告げる鐘の音が、私たちの新しい物語の始まりを祝福するように、静かな店内に優しく響き渡った。