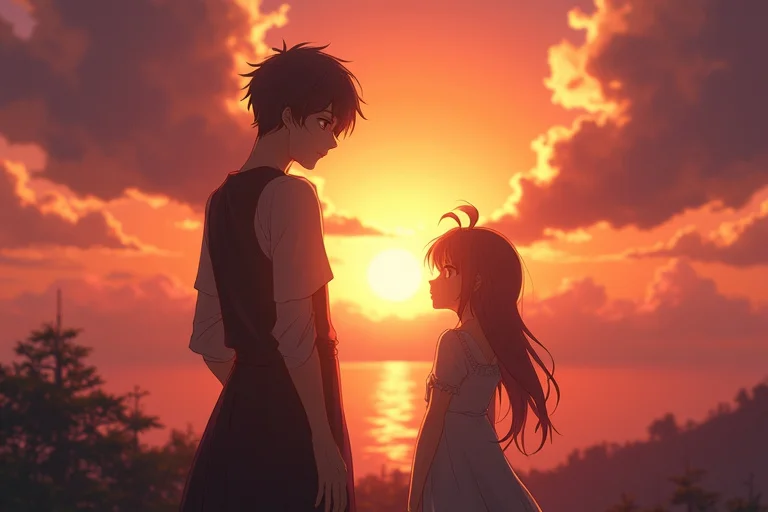王立魔術院において、リアムの魔法は常に嘲笑の的だった。彼が操るのは「奏魔法」。リュートを爪弾き、音色を増幅させたり、特定の音階で小石を震わせたりするだけの、およそ実戦向きとは言えない地味な魔法だった。火球を放ち、氷の槍を生成する同級生たちは、彼のことを「宮廷楽団にでもなればいい」と揶揄した。
「いいかリアム。魔法とは、世界に干渉する力そのものだ。お前の音遊びは、その本質からあまりにかけ離れている」
教官の言葉は、いつも彼の胸に重くのしかかった。それでもリアムは、自分の魔法の可能性を信じ、来る日も来る日もリュートの弦を弾き続けた。彼の奏でる音色だけが、唯一の慰めだった。
その日、王都を震撼させる厄災は、何の前触れもなく訪れた。
古代遺跡「静寂の迷宮」から、灰色の霧が溢れ出したのだ。後に「無音の瘴気」と呼ばれるそれは、触れた世界のあらゆる音を喰らい尽くした。人々の悲鳴は喉の奥で霧散し、建物の崩れる轟音も、騎士の剣がぶつかる金属音も、すべてが吸い込まれるように消えた。
さらに絶望的だったのは、瘴気が魔法すら無力化したことだ。エリート魔術師団が放つはずの炎も氷も、詠唱の声が生まれる前にかき消され、魔法陣は光ることなく霧の中へと溶けていった。王国最強と謳われた戦力は、まるで音のない滑稽な芝居を演じる役者のように、なすすべもなく倒れていった。
王都が深淵のような静寂に包まれ、誰もが希望を失いかけたその時だった。
広場の隅で、リアムは恐怖に震えながらも、無意識に愛用のリュートを抱えていた。彼は祈るように弦を弾いた。
ポロロン……。
か細く、しかし、凛として響き渡る一筋の音色。
その音は、すべてを飲み込むはずの瘴気の中を突き抜け、人々の耳に届いた。すると、リアDムの周囲の瘴気が、まるで陽光に晒された朝霧のように、わずかに後退したのだ。
どよめきが起こる。いや、声にならないはずの心の動きが、確かにその場の空気を揺らした。
リアムの奏魔法は、「音」という結果を生む他の魔法とは違った。それは「音そのものを生み出し、世界に存在させる」根源的な魔法だったのである。
嘲笑の的だった落ちこぼれの魔法が、世界を救う唯一の鍵となった瞬間だった。
リアムは王の勅命を受け、騎士団と魔術師数名の精鋭部隊と共に、「静寂の迷宮」の中心部を目指すことになった。部隊の中には、常日頃から彼を馬鹿にしていた炎の魔術師、カイの姿もあった。カイは苦虫を噛み潰したような顔で、リアムから距離を取っていた。
迷宮の内部は、異様というほかなかった。完全な無音の世界では、敵の気配を探ることすらできない。音を糧とする異形の怪物「音喰らい」が、静寂の中から突如として現れ、騎士たちに襲いかかった。
「リアム、音を!」
隊長が叫ぶ。リアムはリュートを激しくかき鳴らした。鋭い不協和音が響き渡ると、怪物は苦しげに身をよじらせる。その隙を突き、騎士の剣が閃いた。
リアムは戦いの中で、自分の魔法の新たな可能性を見出していく。低周波の振動で脆い壁を崩して道を作り、高音の障壁で仲間を守る。それはもはや音遊びなどではなかった。世界そのものを指揮する、壮大な交響曲のようだった。
カイもまた、リアムの奏でる音を頼りに戦う術を編み出していた。リアムが放つリズミカルな旋律に合わせ、カイは最適なタイミングで炎を放つ。音という指標を得た彼の魔法は、以前とは比べ物にならないほどの精度と威力を発揮した。
「悪くないな、お前の音楽も」
戦いの後、カイはぶっきらぼうに言った。その横顔には、もう侮蔑の色はなかった。
迷宮の最深部。そこには、すべての元凶である巨大な黒水晶「沈黙の核」が不気味な光を放っていた。それは古代文明が生み出した、魔力と音を無限に吸収し、無に変換する禁断の魔法装置だった。そして、その核を守るように、完全な静寂をまとった巨大なガーディアンが立ちはだかった。
ガーディアンは音も気配もなく襲いかかってくる。騎士たちの剣は空を切り、カイの炎もその巨体を捉えきれない。仲間たちが次々と倒れていく。
「もう、終わりなのか……」
リアムが膝をつきかけたその時、カイが彼の前に立ち、炎の壁を張った。
「諦めるな、楽団長!お前の音楽が終わらない限り、俺たちの戦いは終わらない!」
カイの叫び声は瘴気に消されたが、その意志はリアムの心に確かに届いた。
リアムは覚悟を決めた。彼は目を閉じ、リュートを静かに構える。指先に、自身の生命力すべてを込めた。
これは破壊の音じゃない。争いの音でもない。
世界が生まれた時に響いたという、始まりの音色。
リアムの指が、最後のメロディを紡ぎ始める。
それは、かつて誰も聴いたことのない、荘厳で、どこまでも優しい「創生のメロディ」だった。
音色は静寂の闇を切り裂き、光の波紋となって広がっていく。「沈黙の核」は調和の律動に共鳴し、その黒い輝きを穏やかな白光へと変えていった。暴走を止めたのだ。絶対的な静寂の中で生まれた絶対的な音は、無音の化身たるガーディアンの存在そのものを消し去った。
灰色の瘴気は晴れ、空から柔らかな光が差し込む。風のそよぐ音、鳥のさえずり、人々の歓喜の声。失われた音が、世界に還ってきたのだ。
リアムは王国の英雄となった。「奏魔法」は、世界を救った至高の魔法として、後世まで語り継がれることになる。王立魔術院には新たに「奏魔法科」が設立され、リアムはその初代学部長として、未来の奏者たちを育てることになった。
復興した王都の広場で、リアムはリュートを手に、穏やかな曲を奏でていた。彼の隣には、今や親友となったカイが、満足げな顔でその音色に耳を傾けている。
世界はまだ、こんなにも美しい音で満ちている。リアムの奏でる希望のメロディが、新しい時代の幕開けを告げていた。