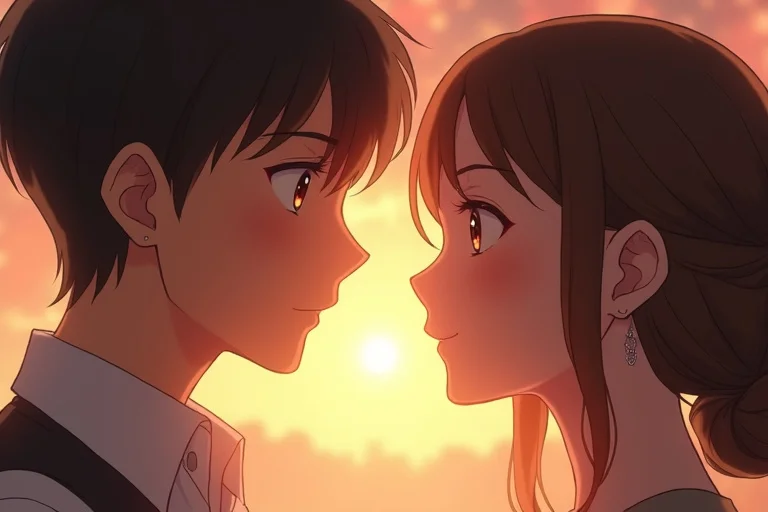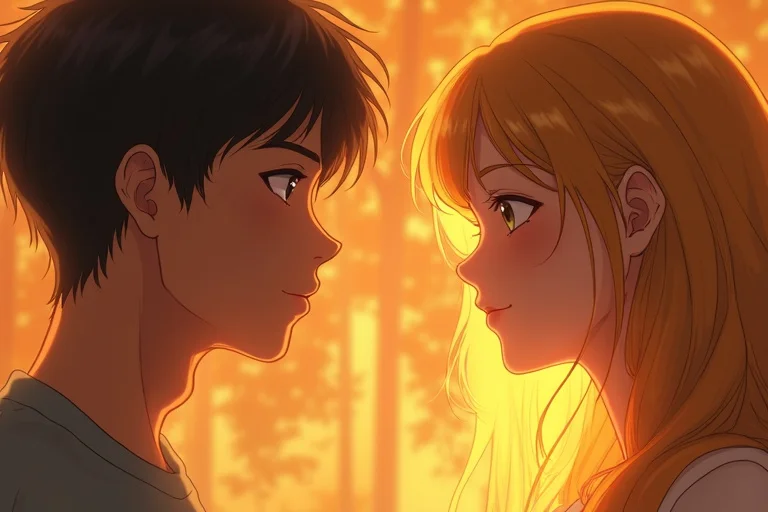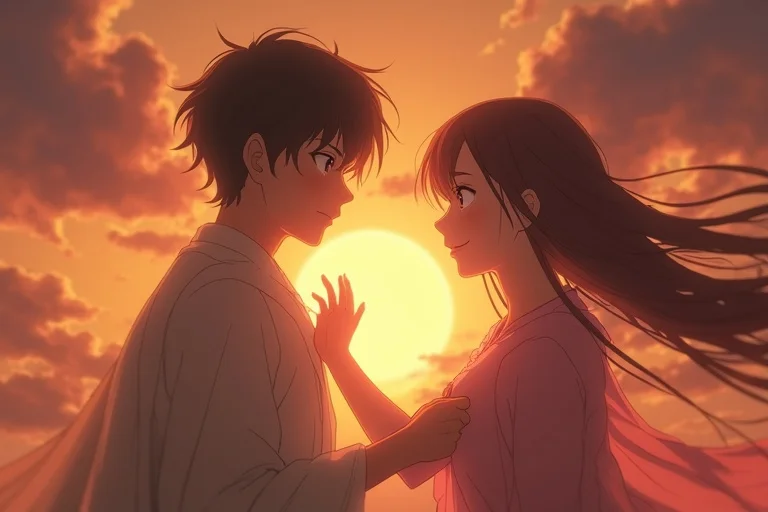第一章 千年図書館の住人
古びた紙の匂いと、インクの微かな甘さが混じり合う。私が働く「みかづき書房」は、時間の流れが少しだけ緩やかになる場所だ。埃をかぶった背表紙の列は、さながら言葉の墓標のようでもあり、揺り籠のようでもあった。失恋の傷を抱えてこの街に来てから二年、私はこの静寂の世界に安らぎを見出していた。
その日、店の奥、誰も気に留めないような棚の隅で、私は見慣れない一冊の本を見つけた。革張りのその本には、タイトルも著者名もない。ただ、くすんだ金色の箔押しで『君と僕の千年図書館』とだけ記されていた。好奇心に駆られてページをめくると、万年筆で書かれたであろう、流麗な文字が目に飛び込んできた。
『未来の君へ。
もし君が、忘れられた言葉たちの眠るこの場所で、僕の本を見つけてくれたなら。どうか、僕の物語を始めてはくれないだろうか。僕は時雨。この図書館の、孤独な住人だ』
それは、交換日記のようだった。しかし、次のページは白紙。まるで、誰かの返事を待っているかのように。馬鹿げている、と頭では思った。誰かの悪戯だろう。けれど、その美しい文字と、行間に滲む静かな孤独に、私の心は奇妙なほど惹きつけられた。インクの匂いはまだ新しく、まるで昨晩書かれたかのようだ。私はまるで魔法にかけられたように、カウンターから愛用の万年筆を取り出すと、インク瓶の蓋を開けた。
『時雨さんへ。
あなたの本を、見つけました。私は咲といいます。この図書館の、住人というよりは番人でしょうか。あなたの物語、少しだけ聞かせてもらえませんか』
心臓が少しだけ速く鼓動するのを感じながら、私はその本を元の場所へそっと戻した。日常を覆す、というほど大袈裟なことではない。けれど、私の止まっていた時間が、ほんの少しだけ、カチリと音を立てて動き出したような気がした。
第二章 インクに滲む面影
翌日、店の開店準備を終えた私は、逸る気持ちを抑えながら例の本を手に取った。ページをめくった瞬間、息を呑んだ。昨日私が書いた文章の下に、見覚えのある流麗な文字が増えていたのだ。
『咲さんへ。
返事をありがとう。君は、夜に咲く花のような、美しい名前だね。僕の物語は、大したものではないんだ。ただ、誰かと、言葉を交わしたかった。君は、どんな本が好きだい?』
信じがたい現象だった。けれど、恐怖よりも先に、胸の奥から温かいものが込み上げてくるのを感じた。それから、私と時雨の、不思議な文通が始まった。彼は古い映画や、今では絶版になった詩集について語った。その言葉遣いはどこか古風で、けれど知的で、優しさに満ちていた。私は彼に、仕事のこと、好きな小説のこと、そして誰にも話せなかった、心の奥底にしまい込んでいた失恋の痛みを、少しずつ打ち明けるようになっていた。
『君の心に降る雨が、いつか虹をかけることを、僕は信じている』
時雨の言葉は、どんな慰めよりも深く私の心に染み渡った。顔も知らない、声も知らない。けれど、彼の文字を通して伝わってくる人柄に、私は確実に惹かれていった。この古書店が、私と彼だけがアクセスできる「千年図書館」になったかのようだった。
そんな日々の中、私の日常にもう一つの変化が訪れた。週に二、三度、店にやってくる物静かな男性客。相葉奏さん。彼はいつも、特定の古い詩集を探していた。すらりとした長身に、どこか儚げな雰囲気をまとう彼は、時雨のイメージと重なって見えた。
「今日も、見つかりませんか」
私が声をかけると、彼は少し寂しそうに微笑んだ。
「ええ。でも、いつかきっと、ここで出会える気がするんです」
彼が探しているのは、『海辺のソネット』というマイナーな詩集だった。そして、ある日、私は日記の中で時雨もまた、同じ詩集を探していることを知った。
『僕にとって、それはとても大切な本なんだ。愛しい人に渡したかった、約束の本だから』
心臓が、大きく跳ねた。まさか。時雨さんの正体は、相葉さんなのではないだろうか。内気な彼が、私と話すきっかけを作るために、こんな回りくどい方法を?そう思った途端、頬が熱くなるのを感じた。私の灰色だった世界が、一瞬で色づき始める。この謎めいた恋の相手は、すぐそこにいるのかもしれない。私は、次の彼が来店した日、勇気を出して尋ねることを心に決めた。
第三章 時を超えたラブレター
雨上がりの午後、窓から差し込む光が店内の埃をきらきらと照らしていた。ドアベルが鳴り、相葉さんが入ってくる。私は深く息を吸い込み、カウンターから出た。
「相葉さん、あの……一つ、お聞きしてもいいですか?」
私の緊張が伝わったのか、彼は少し驚いた顔でこちらを見た。
「はい、なんでしょう?」
「あなたが……時雨さん、ですか?」
私の言葉に、相葉さんはきょとんと目を丸くした。そして、数秒の沈黙の後、困惑したように首を横に振った。
「しぐれ…?人違いだと思いますが…」
私の期待は、音を立てて崩れ落ちた。顔から血の気が引いていくのが分かる。慌てて事情を説明すると、相葉さんの表情が徐々に険しいものへと変わっていった。
「その日記、見せてもらえますか」
私たちは店の奥へ行き、例の本を開いた。時雨の文字を見た瞬間、相葉さんの目が大きく見開かれた。彼は震える手で、鞄から古い手帳を取り出す。そこに書かれていた文字は、日記の筆跡と寸分違わぬものだった。
「これは……曽祖父の日記です」
相葉さんの声は、微かに震えていた。
「僕の曽祖父の名前は、相葉時雨。彼は…僕が生まれるずっと前、戦争で亡くなりました」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。時雨さんは、もうこの世にいない?じゃあ、この文通は一体……?
「曽祖父は、出征前にこの交換日記を古書店にこっそり隠したと、祖母から聞いていました。『いつか、時を超えて僕の心を受け取ってくれる人が現れるかもしれない』と、冗談めかして言っていたそうです。まさか、本当に……」
相葉さんが見せてくれたセピア色の写真には、軍服姿の、穏やかな瞳をした青年が写っていた。日記の中で語られた彼の面影が、そこに確かに存在していた。そして、彼が探していた詩集『海辺のソネット』は、出征前に曽祖母…彼の婚約者に渡すはずだったものだという。しかし、彼はそれを渡すことなく、戦地へ向かい、二度と帰らなかった。
私は、自分が恋をしていた相手が、七十年以上も前に生きていた人物だったという事実を、すぐには受け止められなかった。時を超えた奇跡。それは同時に、決して手が届かないという残酷な宣告でもあった。インクの匂いが、急に遠い過去の遺物のように感じられた。私の恋は、始まる前に、もうずっと昔に終わっていたのだ。涙が、日記のページにぽつりと落ちた。
第四章 私の物語を始めよう
その夜、私は一人、店に残った。震える手でペンを取り、時雨への最後の返事を書いた。
『時雨さん。
あなたの正体を、知りました。驚いたけれど、悲しいとは思いませんでした。あなたと過ごした時間は、私の宝物です。あなたの言葉が、私の凍っていた心を溶かしてくれました。本当に、ありがとう。どうか、安らかに』
書き終えたインクが乾くのを待って、私は日記の最後のページをめくった。そこには、今まで気づかなかった、小さな文字が書き込まれていた。それは、未来の誰かに向けて、何十年も前に彼が遺した、最後の手紙だった。
『これを読んでいる未来の君へ。
もし、僕の言葉が君の心に届いたのなら、僕はもうこの世にはいないだろう。けれど、それでいいんだ。僕が生きた証は、君の心の中にあるのだから。僕の時間はここで終わるけれど、君の時間はこれからも続く。どうか、君の時間を大切に生きてほしい。僕の分まで、たくさん笑って、恋をして、幸せになっておくれ。さよなら、僕の愛しい人』
涙が、今度はとめどなく溢れた。それは失恋の痛みからくるものではなく、温かくて、どうしようもなく切ない、感謝の涙だった。彼は、私の幸せを、七十年も前から願ってくれていたのだ。
数日後、私は相葉さんと共に、隣町の古本市を訪れていた。そして、埃をかぶった段ボールの底から、奇跡のように『海辺のソネット』を見つけ出したのだ。その足で、私たちは郊外にある墓地へ向かった。相葉時雨と刻まれた墓石の前に、二人でその詩集を供える。風が吹き抜け、木々の葉がさわさわと音を立てた。まるで、時雨さんが「ありがとう」と言ってくれているようだった。
店に戻った私は、窓際の席に座り、新しいノートを開いた。夕暮れの光が、真っ白なページを優しく照らしている。私は万年筆を手に取り、その表紙に、ゆっくりと文字を綴った。
『私の物語を始めよう』
時を超えた恋は、終わった。けれど、それは私を縛る鎖ではなく、未来へ歩き出すための翼になってくれた。古書店の窓から見える空は、澄み渡っていた。私の時間もまた、ここから新しく始まっていくのだ。