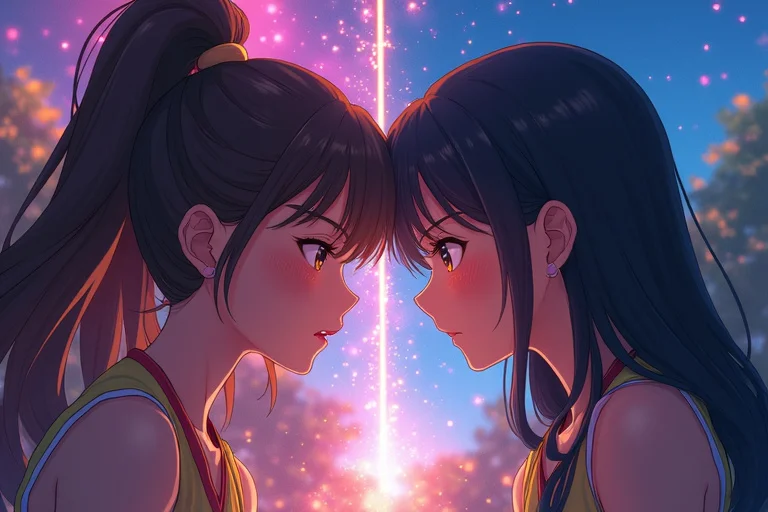第一章 色褪せた約束
月曜の朝、高層ビルの23階にあるオフィスで、俺、神崎健太は冷めたコーヒーを啜っていた。窓の外には、精密な模型のように広がる灰色の都会。あらゆるものが数字と効率で測られるこの世界で、俺はそれなりにうまくやっているつもりだった。感情はノイズだ。感傷は時間の無駄だ。そう自分に言い聞かせ、心をコンクリートで塗り固めて生きてきた。
その日、一通の奇妙な郵便物が届くまでは。
差出人の名はない。厚みのある古びた封筒を開けると、中から転がり出てきたのは、ずしりと重い年代物のフィルムカメラだった。使い込まれて角が丸くなった黒いボディ。その無骨な感触が、指先に遠い記憶の欠片を呼び覚ます。そして、一枚の折り畳まれた紙。広げると、それは手描きの、稚拙で、しかし妙に温かみのある地図だった。
『健太へ。久しぶり。このカメラで、俺たちの地図を完成させてくれ。 陽介』
陽介。その名前を見た瞬間、俺の心臓を覆っていたコンクリートに、鋭い亀裂が入った。三年前に、置き手紙ひとつ残さず、煙のように姿を消した唯一無二の親友。合理主義の俺とは正反対の、夢見がちで、いつも突拍子もないことばかりする男だった。彼の失踪は、俺の日常にぽっかりと空いた、唯一埋められない穴だった。
地図には、いくつかの地点に赤い×印が記されている。見覚えのある地名ばかりだ。なぜ今になって? 完成させてくれとは、どういう意味だ? 謎が頭の中を渦巻く。迷惑だ、と切り捨てようとする合理的な自分がいる。だが、それ以上に、指先に残るフィルムカメラの冷たい感触が、俺の心を強く揺さぶっていた。
週末、俺は三年間袖を通していなかったくたびれたパーカーを羽織り、陽介のカメラを首から下げて、アパートのドアを開けた。最初の×印が示す場所へ向かうために。それは、非合理で、感傷的で、全くもって俺らしくない行動だった。
第二章 錆びついたシャッター
地図が示す最初の場所は、街外れの丘の上に立つ、今はもう使われていない小さな天文台だった。錆びついた鉄の扉を開けると、ひやりとした黴の匂いが鼻をつく。俺と陽介が高校生の頃、よく二人で忍び込んだ秘密の場所だ。
ドームの中央には、埃を被った巨大な望遠鏡が、静かに空を見上げていた。ここで俺たちは、将来の夢を語り合った。俺は現実的な成功を、陽介は「誰も見たことのない星を見つける」という馬鹿げた夢を。
「健太はさ、いつも正しいよな。でも、正しさだけじゃ、星は見えないぜ」
そう言って笑った陽介の顔が、網膜の裏に焼き付いている。
俺はカメラを構え、ファインダーを覗いた。レンズ越しに見る天文台は、ただの廃墟ではなく、俺たちの時間が閉じ込められた琥珀のように見えた。カシャッ、と重たいシャッター音がドームに響く。フィルムが巻き上げられる微かな音。その瞬間、忘れていたはずの、胸が締め付けられるような切なさがこみ上げてきた。
次の×印は、俺たちが初めてバンドを組んだ、地下のライブハウスだった。ステージに立ち、シャッターを切る。汗とタバコの匂い、耳鳴りがするほどの大音量が蘇るようだった。その次は、些細なことで大喧嘩した、冬の海辺。荒々しい波頭にレンズを向け、シャッターを切った。潮風の冷たさが頬を撫で、陽介の怒鳴り声と、その後の気まずい沈黙までが聞こえてくる気がした。
場所を巡り、シャッターを切り続けるうちに、俺の心は少しずつ解きほぐされていった。仕事の締め切りも、株価の変動も、ここでは何の意味も持たない。陽介との記憶をなぞる旅は、効率や損得では測れない、温かい何かを俺の中に灯し始めていた。
だが、同時に疑問は深まるばかりだった。陽介は、俺に何をさせたいんだ? この感傷的な旅の果てに、何が待っているというのか。俺はただ、陽介に会って、文句の一つでも言ってやりたかった。なぜ、何も言わずに消えたんだ、と。
第三章 最後のファインダー
地図の最後の×印は、陽介が失踪直前まで住んでいた、古い木造アパートを示していた。ギシギシと鳴る階段を上り、203号室の前に立つ。ドアノブに手をかけたが、鍵がかかっていた。途方に暮れていると、階下からひょっこりと顔を出した大家のおばあさんが、俺に声をかけた。
「あら、神崎さんかい? 陽介くんのお友達の」
彼女は俺の顔を覚えていた。そして、まるで俺が今日ここに来ることを知っていたかのように、一通の分厚い封筒を差し出した。
「陽介くんから、あんたが来たら渡してくれって、預かってたんだよ」
封筒を受け取ると、ずしりと重かった。中には、何本もの現像済みフィルムのネガと、便箋が数枚。震える手で、俺は陽介からの最後のメッセージを読み始めた。
『健太へ。この手紙を読んでいるってことは、お前は律儀に、俺の馬鹿げたお願いを聞いてくれたんだな。ありがとう。そして、ごめん』
手紙に綴られていたのは、俺の想像を遥かに超える、残酷な真実だった。
陽介は、若年性アルツハイマー病を患っていた。診断されたのは、失踪する半年前。医師からは、いずれ記憶が混濁し、大切な人の顔さえも忘れてしまうだろうと告げられたという。
『怖かった。何もかも忘れてしまうことが。特に、健太、お前との思い出を失うことが、死ぬことよりも怖かった。俺のくだらない夢を、お前だけは馬鹿にしながらも聞いてくれた。お前との時間は、俺の人生そのものだったんだ』
彼は、醜く壊れていく自分を俺に見せたくなかった。迷惑をかけたくなかった。だから、消えたのだと。そして、彼は自分の記憶がまだ鮮明なうちに、俺たちの思い出の場所を地図に記した。
『このカメラは、俺の記憶なんだ。俺が忘れてしまう前に、俺たちの時間を閉じ込めたかった。お前がファインダーを覗き、シャッターを切る。その行為で、俺の記憶はお前の記憶に上書きされる。俺が全部忘れても、健太、お前が覚えていてくれれば、俺たちの時間は、永遠にそこにある。俺たちの地図は、それで完成するんだ』
便箋を持つ手が、震えて止まらなかった。涙が次から次へと溢れ出し、手紙のインクを滲ませていく。馬鹿野郎、と心の中で叫んだ。なんて自分勝手で、そして、なんて優しい嘘なんだ。俺は、陽介の苦しみに全く気づかず、彼を自分勝手な自由人だと決めつけていた。俺の合理主義は、たった一人の親友の、悲痛なSOSさえも見抜くことができなかったのだ。
部屋の隅で、俺は子供のように声を上げて泣いた。フィルムカメラの冷たいボディを、ただ強く、強く握りしめながら。
第四章 未完成の地図
どれくらい泣き続いただろうか。涙が枯れた頃、俺はゆっくりと立ち上がった。窓から差し込む西陽が、床に落ちたネガをキラキラと照らしている。それはまるで、陽介が見たがっていた、誰も見たことのない星屑のようだった。
後悔と自己嫌悪が渦巻く。だが、それ以上に、陽介への途方もない愛しさが胸を満たしていた。彼は一人で、病という絶望的な孤独と戦いながら、俺との友情を守ろうとしたのだ。
完成? 馬鹿を言え、陽介。俺たちの地図は、まだ始まったばかりじゃないか。
俺はスマートフォンを取り出し、震える指で検索を始めた。若年性アルツハイマー、患者の会、専門施設。陽介の痕跡を、今度は俺が辿る番だ。数時間後、俺は陽介が入所していると思われる、隣県の海に近い施設の名前を突き止めた。
翌朝、俺はアパートを出た。首には、陽介のカメラ。その隣には、俺自身のデジタルカメラもぶら下げた。カバンの中には、陽介が残した古い地図と、俺が新しく用意した真っ白な地図が入っている。
陽介、お前は俺の記憶になってくれと言ったな。なら今度は、俺がお前の記憶になる番だ。お前が忘れてしまった星空も、ライブハウスの熱気も、海の匂いも、俺が何度でも話してやる。そして、これから二人で、新しい場所にたくさんの×印を付けていこう。真っ白な地図が、俺たちの新しい思い出で埋め尽くされるまで。
施設へ向かう電車の窓から、流れる景色を眺める。俺の目に映る世界は、もう昨日までのような灰色の世界ではなかった。すべての風景が、これから陽介と共に紡いでいく物語の、最初の1ページのように鮮やかに色づいて見えた。
再会が、どんなものになるかは分からない。陽介は、もう俺の顔を覚えていないかもしれない。それでもいい。俺は行く。ファインダーの向こうにではなく、この腕で、親友を抱きしめるために。
カシャッ。俺は窓の外の青い空にカメラを向け、シャッターを切った。新しい地図の、最初の目印を刻むために。その音は、俺の心の再出発を告げる、力強い号砲のように聞こえた。