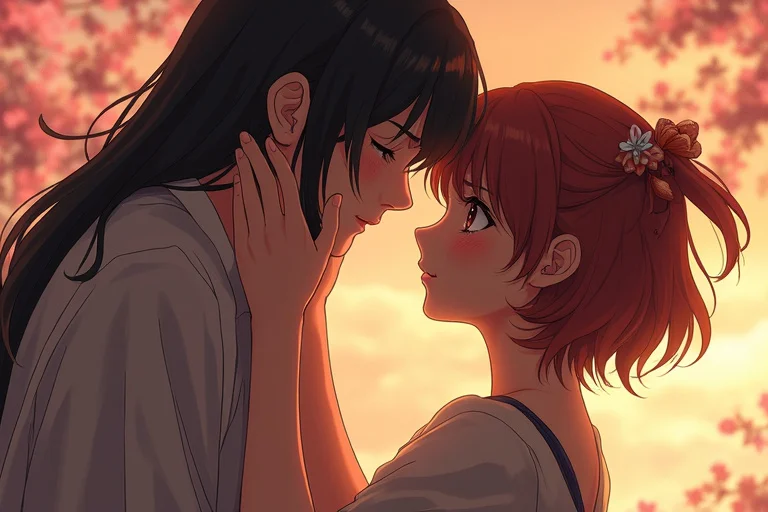第一章 未知のフレーバー
水島湊(みなと)の世界は、味で満ちていた。それは、彼がパティシエだからというだけではない。幼い頃から、湊には他人の強い感情が「味」として舌の上に広がる、一種の共感覚があった。怒りは焦げた鉄のように錆びつき、喜びは弾ける炭酸のように喉を焼く。人の多い場所は、不快な味の洪水でしかなく、彼はいつしか人との間に透明な壁を作り、繊細な味覚が唯一の慰めとなるケーキ作りの世界に逃げ込んだ。
湊の店『Le Goût Silencieux(静かな味)』は、町の片隅でひっそりと営業している。彼が作るケーキは、甘さや酸味のバランスが絶妙で、素材の持つ囁き声まで聞こえてきそうなほど繊細だと評判だった。客の「美味しい」という純粋な感情は、上質な和三郎のように品良く溶けていくので、湊にとって心地良いものだった。
その日、彼女はやってきた。夕暮れの光が店内に斜めに差し込む時間。カラン、とドアベルが鳴り、一人の女性が入ってくる。橘沙耶(さや)。週に一度、決まって金曜日に訪れる常連客だ。長く艶やかな黒髪、どこか遠くを見ているような澄んだ瞳。彼女はいつも静かで、感情の「味」がほとんどしない。それが湊にとっては、嵐の後の凪のように心地よかった。
「いらっしゃいませ、橘さん」
「こんにちは。今日も、あの『月の雫』を」
『月の雫』は、洋梨のコンポートを包んだレアチーズムースのケーキだ。淡い甘さと柔らかな酸味が特徴で、彼女はいつもそれしか頼まなかった。
湊は手際よくケーキを皿に乗せ、彼女のテーブルへ運ぶ。沙耶は小さく会釈すると、銀のフォークをそっとムースに入れた。
その瞬間だった。
湊の口の中に、今まで経験したことのない、複雑で芳醇な「味」が奔流のように広がった。
それは、完熟した果実の蜜のような甘さを核に持ちながら、朝露に濡れた若草のような瑞々しい香り、そして後から追いかけてくる、微かにビターなチョコレートを思わせる切なさが幾重にも重なっていた。それは単なる「幸福」や「美味しい」という味ではない。物語そのものを味わっているような、深遠で、官能的ですらあるフレーバーだった。
湊は息を呑んだ。全身が粟立つような衝撃。味のしないはずの彼女から、なぜこんなにも豊潤な味が?
沙耶はただ静かにケーキを味わっている。その表情は穏やかで、特に変わった様子はない。だが、彼女が一口運ぶごとに、湊の世界はその未知の味で満たされていく。この味の正体は何だ? もっと知りたい。もっと、味わいたい。
人付き合いを避けてきた湊の心に、初めて烈しい好奇心の炎が灯った。それは、完璧なレシピを求めるパティシエの探究心にも似て、抗いがたい引力を持っていた。
第二章 重ねる味、深まる想い
あの日以来、湊の日常は沙耶から薫り立つ「味」を中心に回り始めた。彼は彼女が来店する金曜日が待ち遠しくてたまらなかった。そして、どうすればあの味をより深く、より鮮明に感じられるだろうかと、そればかりを考えるようになった。
「橘さん、もしよろしければ、試作品を召し上がっていただけませんか」
ある金曜日、湊は勇気を出して声をかけた。彼が沙耶のためだけに作った、特別なケーキだった。彼女が好きな『月の雫』をベースに、隠し味としてエルダーフラワーのシロップと、ほんの少しだけピンクペッパーを効かせたものだ。
沙耶は少し驚いたように目を瞬かせたが、こくりと頷いた。湊が緊張しながらケーキを差し出すと、彼女はフォークを手に取る。そして、一口。
湊の舌に広がるのは、いつもの芳醇なフレーバーに、花畑を吹き抜ける風のような爽やかさと、ピリリとした刺激が加わった、新しい味の協奏曲だった。
「……美味しい。なんだか、少しだけ、心が躍るような味がします」
沙耶がぽつりと呟いた言葉に、湊は胸を突かれた。「味がする」という彼女の比喩表現が、自分の秘密の能力と共鳴したように感じられたのだ。
「あなたのケーキを食べていると、色々なことを思い出すんです。昔のこととか、大切な人のこととか」
そう語る彼女の横顔は、少し寂しげで、その時、湊が感じたのは雨上がりの土のような、しっとりとした苦味だった。
二人の距離は、ケーキを介してゆっくりと縮まっていった。湊は沙耶と話すたびに、彼女から立ち上る味が様々に変化することに気づいた。彼が冗談を言うと、弾ける柑橘の酸味にも似た明るい味がし、彼女が自分のことを少しだけ話してくれる時には、丁寧に淹れた紅茶のような温かい味がした。
湊は、もはや自分が何に惹かれているのか分からなくなっていた。沙耶という女性そのものなのか、それとも彼女がもたらす未知の味覚になのか。だが、どちらであれ、彼女が愛おしいことに変わりはなかった。この感情は、彼が作るどんなドルチェよりも甘く、複雑だった。
初めて、自分の能力を肯定できた。この感覚があるからこそ、言葉にならない彼女の心の機微を、誰よりも深く味わうことができる。湊は、沙耶に恋をしている自分と、彼女の感情の味に恋をしている自分を、分けることができなかった。それは、彼にとって同じことだったのだ。
第三章 無味という絶望
季節は巡り、木々の葉が赤や黄色に染まる秋になった。湊と沙耶の関係は、恋人と呼んでも差し支えないほど親密なものになっていた。湊は、自分の人生がこれほど色彩と味覚に満ちたものになるとは、想像もしていなかった。沙耶といるだけで、世界は極上のフルコースに変わった。
ある晩、公園のベンチで並んで月を見ていた時、湊は決意を固めた。この幸福な味を、永遠に自分のものにしたい。
「沙耶さん」
湊が名前を呼ぶと、彼女は静かにこちらを向いた。彼女の瞳に映る月が、小さく揺れている。湊の口内には、期待と緊張が入り混じった、シャンパンのようなシュワシュワとした味が広がっていた。
「君が好きだ。僕と、付き合ってほしい。君のそばに、ずっといたい」
精一杯の告白だった。沈黙が流れる。湊の心臓は、これまで感じたことのないほど強く脈打っていた。やがて、沙耶はふわりと微笑んだ。それは、夜に咲く花のように儚く、美しい微笑みだった。
「はい。私も、湊さんと一緒にいたいです」
その言葉を聞いた瞬間。
湊の世界から、すべての味が消え失せた。
甘さも、苦さも、香りも、何もかも。まるで良質の水を口に含んだかのような、完全な「無味」。それは、静寂ですらなかった。あらゆる感覚が剥奪されたかのような、虚無。
「……え?」
湊は混乱した。どうして? 幸福の絶頂であるはずのこの瞬間に、なぜ味覚は沈黙する?
沙耶は、何かを決心したように、まっすぐに湊を見つめた。
「湊さん。あなたに、話しておかなければいけないことがあります」
彼女の告白は、湊の築き上げてきた世界を根底から破壊するものだった。
「私には、生まれつき、感情というものがほとんどないんです」
沙耶は淡々と語り始めた。嬉しいとか、悲しいとか、そういう感覚が、他人よりずっと希薄なのだと。彼女が唯一、豊かだと感じられるのは、五年前に亡くなった、双子の姉の思い出だけだった。
「姉は、私とは正反対で、とても感情豊かな人でした。よく笑い、よく泣き、何にでも感動するような人で……。私は、姉のことが大好きでした」
湊が感じていたあの芳醇な味。それは、沙耶自身の感情ではなかった。
それは、沙耶が心の中で大切に反芻していた、亡き姉の「感情の記録」だったのだ。
湊のケーキを食べる時、沙耶はいつも想像していたという。「もし姉が生きていたら、このケーキを食べてどんな顔で笑うだろうか。どんな言葉で美味しいと伝えてくれるだろうか」。彼女は、姉の視点、姉の感情を借りることで、世界を彩り、味わっていたのだ。
湊が感じていたのは、沙耶を通して追体験される、今はもうこの世にいない誰かの、幸福や切なさの残滓だった。
「あなたの告白を受けて、私、初めて……姉の思い出からじゃなく、自分の心で何かを感じたいと思ったんです。あなたのことを、私自身の気持ちで受け止めたい、と」
その結果が、この「無味」だった。彼女が初めて「自分自身」になろうとした瞬間、姉の思い出は後ろへ下がり、彼女の本来の、まだ何も描かれていないキャンバスのような心が、湊の前に現れたのだ。
湊は愕然とした。自分が恋い焦がれていた、あの複雑で甘美な味は、沙耶のものではなかった。自分は、幽霊の感情に恋をしていたのか? では、目の前にいる沙耶へのこの気持ちは、一体何なんだ?
味を失った世界で、湊は自分の愛の在り処さえ見失い、ただ立ち尽くすしかなかった。
第四章 始まりのテイスト
それから数日、湊は厨房に閉じこもった。沙耶に合わせる顔がなかった。自分が愛したものは幻だったという事実が、鉛のように重くのしかかる。どんなに美しいケーキを作っても、口に含むものはすべて灰のように味気なかった。彼にとって、感情の味を失うことは、世界そのものの色を失うことと同義だった。
彼は自問自答を繰り返した。自分は、ただ珍しい味覚体験に酔っていただけではないのか。沙耶本人ではなく、彼女を通して見える華やかな幻影を愛していただけではないのか。答えは出なかった。ただ、胸にぽっかりと空いた穴が、冷たい風を呼び込むだけだった。
そんな時、ふと、沙耶と出会う前の自分を思い出した。他人の感情の味を疎ましく思い、殻に閉じこもっていた自分。そんな自分が、初めて他人の味を「知りたい」と渇望した。きっかけは、幻の味だったかもしれない。だが、その扉を開けてくれたのは、紛れもなく沙耶という存在だった。
そして、あの告白の瞬間の「無味」を、もう一度注意深く思い出してみる。
あれは本当に、虚無だったのだろうか。
違う。
あれは、何も混ぜ物がされていない、生まれたての純粋な水のような味だった。これからどんな色にも染まる可能性を秘めた、ゼロの味。それは絶望ではなく、始まりだったのではないか。
沙耶が、初めて自分の足で、自分の心で、感情の世界に一歩を踏み出した、その瞬間の味だったのではないか。
湊は気づいた。
自分が求めていたのは、完成された極上のフレーバーではなかった。刺激的な味の探求でもなかった。たとえ味がしなくても、感情が希薄でも、不器用でも、それでも懸命に自分と向き合おうとしてくれる、橘沙耶という一人の人間。彼女と共にいること。それこそが、自分の本当の願いだったのだ。
味があろうがなかろうが、関係ない。
これから二人で、新しい味を、ゼロから創り上げていけばいい。
湊はエプロンを外し、店を飛び出した。沙耶のアパートへ、息を切らしながら走る。
ドアを開けてくれた沙耶は、不安そうな顔をしていた。
「沙耶さん」
湊は彼女の両肩を掴んだ。
「君から、どんな味がするかなんて、もうどうでもいい。味がしなくてもいいんだ。僕が好きなのは、君自身だ。だから、これから僕たちが作る味を、一緒に見つけていきたい。二人で、ゼロから」
沙耶の大きな瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。彼女は何も言わず、ただ、こくりと頷いた。
その瞬間。
湊の口の中に、ほんのりと、温かいミルクのような、優しくて、まだ少し頼りない、けれど確かな甘みが、じんわりと広がった。
それは、これまでに味わったどんな複雑なフレーバーよりも、深く、愛おしい味だった。
沙耶自身の感情が、世界で初めて生まれた瞬間だったのかもしれない。
二人の物語の、本当の始まり。そのテイストは、どこまでも優しく、未来への希望に満ちていた。