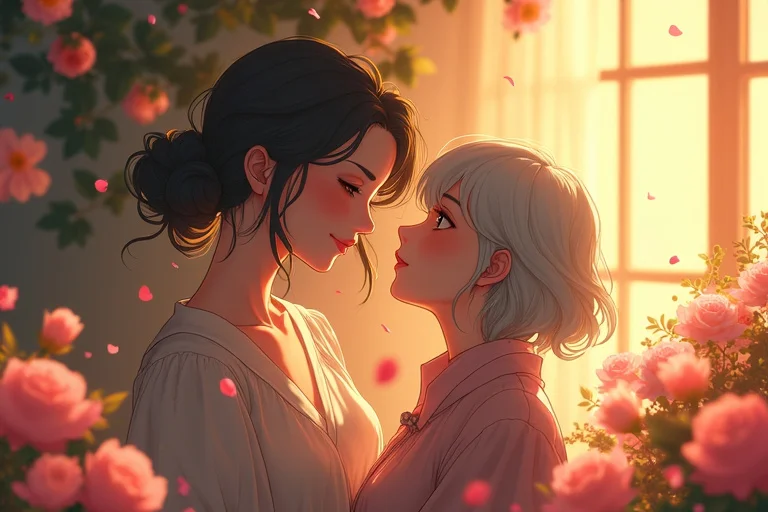第一章 モノクロームの観測者
俺の世界は、音と、匂いと、感触だけで出来ていた。生まれつき、俺の視界には色がなかった。灰色の濃淡が織りなす、無限のグラデーション。人々はそれを不幸だと言ったが、知らないものを渇望することはできない。俺にとって、世界とはそういうものだった。ただ、恋をすると、世界は変わる。
初めて少女の手を握った日、彼女の頬が淡い桜色に染まるのを幻視した。図書館で同じ本に手を伸ばした先輩の髪が、夕陽のような茜色に輝いたこともあった。恋という感情の奔流が、俺の脳内にだけ存在するパレットをかき混ぜ、世界に仮初めの色彩を与えるのだ。しかし、その恋はいつも短く、終わりと共に色は急速に褪せていく。相手の笑顔も、交わした言葉の記憶も、全てが色を失い、再びモノクロの静寂が訪れる。
胸ポケットには、いつも空の写真立てが入っている。祖父の形見だという、世界で唯一、俺が知る限り最初から完全に色が失われた木製のフレーム。恋が始まるたび、その縁に象徴的な色がほんのわずかに滲み、そして恋が終わると跡形もなく消える。まるで、俺の心を映す鏡のようだった。
そんな日々の中、彼女に出会った。
古いジャズが低い音量で流れる喫茶店のカウンター席。俺の隣に、ふわりと彼女が座った。カモミールの柔らかな香りが鼻をかすめる。
「いいお天気ですね」
彼女が窓の外を見上げながら、独り言のように呟いた。その声が、心地よい鈴の音のように鼓膜を揺らす。俺が彼女の方を向いた瞬間、世界が、息を呑んだ。
彼女の唇からこぼれた吐息が、窓から差し込む光の筋を揺らし、その粒子が、ほんのりと琥珀色に輝いた。それは、今まで経験したどんな色の発現とも違っていた。鮮烈ではない。だが、確かな熱量を持った、生まれて初めて見る、本物の『色』の息吹だった。
第二章 滲み出す色彩
彼女の名前はユキ。週に三度、あの喫茶店で本を読むのが習慣らしかった。俺たちは自然と話すようになり、会うたびに俺の世界は色彩を増していった。
ユキが笑うと、テーブルの上の角砂糖がキラキラと金色に輝いた。彼女が悲しい物語の一節を読み上げると、窓の外の空は悲しみを帯びた深い藍色に染まった。彼女という存在が、俺の世界のあらゆるものに意味と色を与えていく。セピア色から始まった世界は、やがて鮮やかなフルカラーの交響曲を奏で始めた。胸ポケットの写真立ての縁には、彼女の瞳の色によく似た、澄んだ空の色が滲んでいた。
「アキトさんの世界は、どんな風に見えるんですか?」
ある晴れた午後、公園のベンチでユキが尋ねた。
俺は正直に話した。恋をすると色が見えること。そして、それが終わると全てが消えてしまうこと。
「じゃあ、今、私のことは何色に見えますか?」
悪戯っぽく笑う彼女の髪は、陽光を浴びて艶やかな黒。頬は健康的な薔薇色。そして瞳は、どこまでも吸い込まれそうな空の色。
「……全部の色だ。君がいるだけで、世界中の色が集まってくるみたいだ」
そう答えると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。だが、その笑顔には、春の雪のような儚い翳りが一瞬よぎった。
その時からだった。彼女の存在がおぼろげに感じられるようになったのは。隣を歩いているはずの彼女の輪郭が、陽炎のように揺らめく。伸ばした指が、彼女の肩に触れる寸前、僅かに空を切るような奇妙な感覚。世界がこれほどまでに色鮮やかなのに、その中心にいるはずの彼女だけが、少しずつ透明になっていく気がした。
第三章 消滅の法則
不安に駆られた俺は、古い伝承や歴史書を漁った。そして、この世界の残酷な法則に行き着いた。『魂のペア』。人は生まれながらに運命の相手が定められており、その者同士が出会うことで、永続的な色彩と幸福を得る。しかし、万が一『ペア』ではない相手と深く愛し合ってしまった場合、その愛の強さに比例して、お互いの存在がこの世界から希薄になっていく。互いが互いを想うほどに、世界の記憶から消滅していくのだという。
ユキは、俺の『魂のペア』ではない。
そして彼女のあの儚さは、過去に誰かと深く愛し合った名残なのだと直感した。彼女は、俺と出会う前から、消えかけていたのだ。
雨がアスファルトを叩く音だけが響く部屋で、俺はユキに尋ねた。彼女は何も言わず、ただ静かに頷いた。その体は、以前よりずっと透けて見えた。
「あなたといると、色が戻ってくる気がしたの。でも、同時に、自分が消えていく速度も速くなっているのがわかった」
彼女の声は、雨音に溶けてしまいそうなくらい、か細かった。
「怖かった。あなたと出会って、初めて……消えるのが、怖くなったのよ」
その告白は、俺の心を締め付けた。彼女を愛することが、彼女をこの世界から消し去る行為そのものだったなんて。俺が手に入れたこの鮮やかな世界は、彼女の存在そのものを犠牲にして成り立っていたのだ。
第四章 写真立ての光
絶望が俺を支配した。ユキを救う方法は見つからない。ただ、無情に時間だけが過ぎていく。ユキの体は日に日に透明度を増し、俺は彼女の温もりさえ、満足に感じられなくなっていた。
嵐の夜だった。稲光が部屋を白く照らすたび、ユキの姿がほとんど見えなくなる。パニックに陥った俺は、消えゆく彼女の幻影を、壊れ物を抱くように強く、強く抱きしめた。
「行くな! 消えないでくれ、ユキ!」
叫びが、雷鳴に掻き消される。
その瞬間だった。
胸ポケットの写真立てが、灼けるような熱を帯び、凄まじい光を放った。それは単なる光ではない。俺が過去に経験し、そして失ってきた恋の色彩。桜色、茜色、若葉色……数えきれない愛の断片が奔流となって溢れ出し、俺とユキを純白の光で包み込んだ。
光の中で、俺は理解した。この写真立ては、単なる形見ではなかった。『魂のペア』ではない愛を選び、世界の記憶から消滅していった者たちの、最後の『記憶の光』を集積する装置。そして今、蓄えられた光が臨界点に達し、世界の法則を一時的に揺るがす、奇跡の扉を開いたのだ。
第五章 魂の交換
光の奔流の中で、俺の脳裏に、世界の真の姿が流れ込んできた。
『消滅の法則』は、罰ではなかった。それは、規定の運命から外れた愛のエネルギーを世界から隔離し、回収するためのシステム。そして、その法則にはたった一つだけ、例外が存在した。『魂の交換』。一方の存在を世界に定着させるため、もう一方がその存在の希薄さを、そして全ての記憶を受け継ぐ、究極の自己犠牲。
ユキを救う、唯一の方法。
俺が、彼女の代わりに消えるのだ。いや、違う。俺が彼女の『希薄さ』を引き受け、代わりに俺の『色彩』を彼女に与える。
光が収まりかけた時、俺は確かな輪郭を取り戻したユキの瞳を見つめて言った。
「ユキ。君が見てきた鮮やかな世界を、俺にくれないか」
彼女は戸惑い、首を横に振る。「そんなこと……そしたら、アキトさんが……」
「俺の世界と、交換しよう」
俺は、震える彼女の手を取った。「俺は、君のいない色鮮やかな世界なんていらない。君さえいてくれるなら、俺の世界が再びモノクロームに戻ったって構わない。君の記憶の重みを、俺に背負わせてくれ」
それは、俺のエゴだ。それでも、彼女に生きてほしかった。俺が愛したこの美しい色彩を、彼女に見てほしかった。
ユキの瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。それは、透き通ったダイヤモンドのように輝いていた。
「……あなたの色を、私がもらってしまうのね」
彼女は、静かに頷いた。俺の覚悟を受け入れる、決意の表情だった。
第六章 新しい世界の輪郭
俺たちは、光を放ち続ける写真立てを間に挟み、固く手を握り合った。
交換が始まる。
俺の視界から、色が津波のように引いていくのがわかった。壁紙のクリーム色、カーテンの青、そして目の前のユキの唇の赤。全ての色が、粒子となって彼女の中へと吸い込まれていく。あっという間に、世界はかつてのモノクロームへと戻っていく。
だが、ただ失うだけではなかった。流れ込んでくる。ユキの記憶が。彼女が愛した誰かの横顔、彼女が歩いたであろう知らない街並み、彼女が流した涙の味。色はない。だが、確かな重みと手触りのある、膨大な記憶の断片が、俺という器を満たしていく。空っぽだった俺のモノクロの世界に、初めて『陰影』が生まれた。
ふと気づくと、ユキの体は確かな実体を取り戻していた。彼女の瞳には、俺が焦がれた世界中の色彩が、星々のように宿っていた。
「……見えるわ」
ユキが、震える声で呟いた。
「あなたが愛した世界の色が……全部、ここに……」
彼女は自分の手を見つめ、泣きながら微笑んだ。
第七章 名もなき愛の色
俺の世界は、再び色を失った。しかし、以前の空虚な灰色とは全く違う。ユキから受け取った無数の記憶が、このモノクロの世界に無限の奥行きを与えてくれていた。
目の前に立つユキの姿だけが、なぜか淡い光の輪郭を帯びて見えた。それは赤でも青でもない、どんな言葉でも定義できない、名もなき『色』だった。俺たちが選び取った、運命に抗う愛の証明そのものなのかもしれない。
役目を終えた写真立ては、光を失い、ただの古い木枠に戻っていた。その中は相変わらず空っぽだ。だが、俺たちの間には、もはや形あるものなど必要なかった。
「君の世界は、綺麗かい?」
俺は、光の輪郭を帯びた彼女に尋ねた。
ユキは、俺が与えた色彩に満ちた瞳で、真っ直ぐに俺を見つめ返した。
「ええ、とても。あなたが愛した全ての色で、今、私の世界は満ちているわ」
その笑顔は、俺が今まで見たどんな色よりも、鮮やかだった。
俺たちはどちらも、もはや元の自分自身ではないのかもしれない。互いの魂の一部を交換し、新しい存在として生まれ変わったのだ。だが、それでいい。これが、俺たちが選んだ愛の形なのだから。
俺たちはどちらからともなく手を取り合い、新しい世界へと、静かに歩き出した。