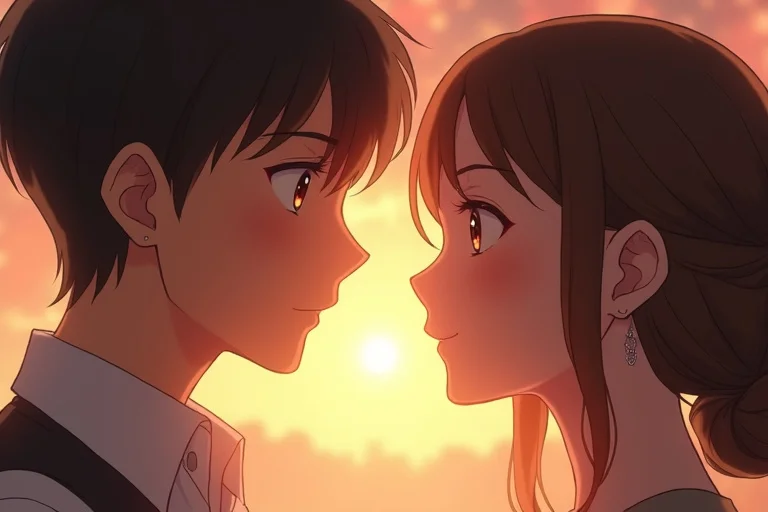第一章 完璧な未来のための契約
僕の人生は、ずっと耳鳴りのようなノイズに満ちていた。音響デザイナーとして、微細な音の差異を聞き分けることを生業にしながら、僕自身の内側で鳴り響く不協和音からは、決して逃れられなかった。そのノイズの正体は、十年前の記憶。ピアニストの夢を乗せたコンクールで、満場の聴衆の前で指が凍りつき、音楽を殺してしまった、あの日の記憶だ。
恋人の灯(あかり)と出会って、そのノイズは少しだけ遠のいた。古書店の店主である彼女は、古い紙の匂いと、陽だまりのような微笑みで、僕のささくれた心をそっと包んでくれた。彼女との未来を思った時、初めて人生のボリュームを上げたいと感じた。だからこそ、僕は恐れていた。この耳鳴りが、いつか僕たちの静かな幸福を掻き乱してしまうのではないかと。
「律(りつ)、これ、見て」
ある雨の午後、灯がタブレットの画面を僕に向けた。そこに表示されていたのは、『メモリー・エクスチェンジ』というサービスの広告だった。最先端の脳科学技術を用い、パートナー間で「最も忘れたい記憶」を一つだけ交換する。施術後、相手から受け取った記憶は、夢の断片のような曖昧なイメージとして残るだけで、苦痛は伴わない。そして、自分が手放した記憶は、完全に忘却の彼方へ消え去るのだという。
「完璧な未来のために、過去の荷物を一つだけ、預け合いませんか」
広告のキャッチコピーが、僕の心の最も柔らかい部分を的確に抉った。灯の横顔を盗み見る。彼女はいつも明るく笑っているが、時折、その瞳の奥に、僕の知らない深い影がよぎることがあった。彼女にも、僕に打ち明けられない過去があるのだと、直感的にわかった。
「やってみないか」僕の口から、思ったよりも乾いた声が出た。
灯は、僕の目をじっと見つめた後、静かに頷いた。「うん。律が、そうしたいなら」
僕が忘れたいのは、もちろんコンクールの記憶だ。彼女にそれを伝えると、「私は、家族との辛い思い出かな」と、少しだけ俯いて言った。それ以上、僕たちは互いの過去に踏み込まなかった。忘れてしまう記憶なのだから、詳細を語る必要はない。僕たちは、互いの痛みを消し去ることで、愛を証明しようとしていた。それが、この上なく純粋で、正しいことだと信じて疑わなかった。予約の日、僕たちは固く手を繋ぎ、白を基調とした無機質なクリニックの扉をくぐったのだった。
第二章 空白のコンチェルト
施術は、冷たいジェルをこめかみに塗られ、柔らかなリクライニングチェアで眠りに落ちるだけ、という驚くほどあっけないものだった。目覚めた時、世界はまるでノイズキャンセリングを施したヘッドフォンを通したように、クリアに感じられた。あの忌まわしいコンクールの記憶は、確かに消えていた。ピアノ、ステージ、聴衆。単語は思い出せるが、それに付随する屈辱や絶望といった感情の棘が、綺麗に抜き去られていた。
代わりに僕の心に残ったのは、灯がくれたという「記憶の残響」。それは、冷たい雨の匂いと、誰かの小さな背中、そして言いようのない喪失感。それだけだった。しかし、痛みはない。ただ、静かな映画のワンシーンのように、心の片隅に存在するだけだ。
「どう?」隣のチェアから起き上がった灯が、不安げに僕の顔を覗き込む。
「……消えたよ。本当に」
僕がそう言うと、彼女は心の底から安堵したように微笑んだ。「よかった」
その日を境に、僕たちの関係はより一層、輝きを増した。僕は長年の呪縛から解き放たれ、仕事にも集中できるようになった。何より、灯と笑い合う時間に、罪悪感を感じなくなったことが大きかった。彼女もまた、以前よりずっと表情が柔らかくなったように見えた。僕たちは結婚式の準備を始め、式場のパンフレットを広げては、未来の計画を語り合った。空白になった過去の上に、新しい音を重ねていく。僕たちの人生は、完璧なハーモニーを奏で始めたように思えた。
だが、時折、奇妙な感覚に襲われた。灯がくれたはずの「冷たい雨の記憶」が、ふとした瞬間に僕自身のものだったかのような錯覚を覚えるのだ。雨音を聞くと胸が締め付けられ、誰かの後ろ姿を街で見かけると、守れなかったという罪悪感に似た感情が胸をよぎる。
「僕が忘れた記憶って、どんな感じだった?」ある夜、僕は灯に尋ねた。
彼女は一瞬、言葉に詰まった後、こう答えた。「すごく静かで、でも、とても重たい音だった。でも、大丈夫。私がちゃんと持っておくから」
その言葉に安堵しながらも、僕は心のどこかで、自分の大切な一部分がくり抜かれてしまったような、巨大な空虚さを感じ始めていた。僕が捨てた記憶は、本当に僕だけを苦しめる、不要なノイズだったのだろうか。
第三章 君が忘れた、僕の記憶
結婚式を二週間後に控えた週末、僕たちは新居に運び込む荷物の整理をしていた。実家から持ってきた段ボールの底から、古いアルバムが出てきた。懐かしさにページをめくっていると、一枚の写真に目が釘付けになった。
十年前の、あのコンクールの日。ステージ袖で呆然と立ち尽くす僕を、遠くから撮った一枚だ。撮った覚えのないその写真に、なぜ、と首を傾げた時、その隅に写り込んでいるものに気づいて、息が止まった。
客席の片隅で、俯いて、肩を震わせている少女。その顔には見覚えがあった。頬を伝う涙、固く結ばれた唇。それは間違いなく、高校生の頃の灯だった。
全身の血が逆流するような感覚に襲われた。震える手で写真を持ち、リビングで紅茶を飲んでいた灯の元へ向かった。
「灯……これ、どういうことだ?」
僕の声は、自分でも驚くほど低く、冷たかった。写真を見た灯の顔から、さっと血の気が引いていく。彼女の瞳が大きく揺れ、やがて観念したように、ゆっくりと視線を落とした。
「……ごめんなさい」
長い沈黙の後、彼女は絞り出すように言った。そして、静かに全てを語り始めた。
灯は高校時代、僕のピアノの熱烈なファンだったのだという。僕が地元のホールで弾くたびに、彼女は客席の隅で、僕の音楽に救われていたのだと。僕の存在は、彼女の世界そのものだったのだと。
だから、あのコンクールの日、僕が演奏を止めてしまった時、彼女の世界もまた、音を立てて崩れ落ちた。
「私が忘れたかった記憶はね、家族とのことなんかじゃないの」灯は涙を堪えながら、言葉を続けた。「私が本当に忘れたかったのは……あの日、律が舞台の上で壊れていくのを見ていることしかできなかった、自分の無力さ。あなたを支える言葉一つ、見つけられなかった罪悪感。その記憶よ」
僕の頭を、鈍器で殴られたような衝撃が襲った。
「君は、じゃあ……」
「そう。私があなたにあげた記憶は、『あなたを救えなかった私の記憶』。そして、私があなたからもらった記憶は……私がずっと、一緒に背負ってあげたいと願っていた、『あなたの挫折の記憶』だったの」
彼女は、僕を過去から解放するために、この交換を選んだのだ。僕の最も深い痛みを、自ら引き受けるために。僕が感じていたあの奇妙な罪悪感や喪失感は、灯が僕に渡した彼女自身の苦悩の残響だった。僕は、自分の過去を捨てたつもりで、彼女の最も深い愛と痛みを受け取っていたのだ。
第四章 追憶のフーガ
僕は呆然と立ち尽くしていた。自分がどれほど愚かで、自己中心的だったかを思い知らされた。僕がゴミのように捨て去ろうとした過去は、灯にとっては、僕という人間を形作る、かけがえのない一部だったのだ。彼女は、僕の光だけでなく、その影までも、丸ごと愛してくれていた。
「どうして……」
「だって、あの日の律がいたから、今の律がいるんでしょう? 私は、あなたの全部が好きだから。あなたの痛みが、私をあなたに出会わせてくれたんだから」
涙でぐしゃぐしゃの顔のまま、彼女はそう言って微笑んだ。その笑顔は、僕が今まで見たどんな彼女よりも、痛々しく、そして美しかった。
その夜、僕は久しぶりに実家のピアノの前に座った。蓋を開けると、埃の匂いと共に、鍵盤の冷たさが指先に伝わる。コンクールの記憶は、感情を伴わない事実としてしか思い出せない。だが、灯が引き受けてくれたその痛みを、僕は今、確かに感じることができた。
ゆっくりと指を鍵盤に置く。そして、あの日、弾けなかった曲……ショパンの『別れの曲』を弾き始めた。
音は拙く、何度もつっかえた。指は震え、思うように動かない。しかし、一音一音に、灯への感謝と、過去の自分への赦しを込めた。これは忘却のレゾナンス(共鳴)だ。僕が捨てた痛みを彼女が奏で、彼女が抱えていた痛みを僕が奏でる。僕たちは、記憶を交換したのではない。互いの魂の、最も柔らかな部分を交換したのだ。
弾き終えた時、背後に灯の気配を感じた。振り返ると、彼女が静かに涙を流しながら立っていた。
「……おかえりなさい、律の音」
僕は立ち上がり、彼女を強く抱きしめた。もう、耳鳴りは聞こえなかった。僕たちの間にあるのは、不協和音ではない。互いの痛みを理解し、受け入れ合うことで生まれる、深く、豊かなハーモニーだった。
記憶を消し去ることで、完璧な未来は手に入らない。本当の愛とは、相手の傷跡にそっと触れ、その痛みを分かち合い、共に未来へと歩いていくことなのだ。僕たちのコンチェルトは、まだ始まったばかりだ。たとえ完璧な演奏にはならなくても、世界で最も優しい響きを持つ、二人だけの旋律を奏でていこう。窓の外では、僕たちの未来を祝福するように、静かな雨が降り始めていた。