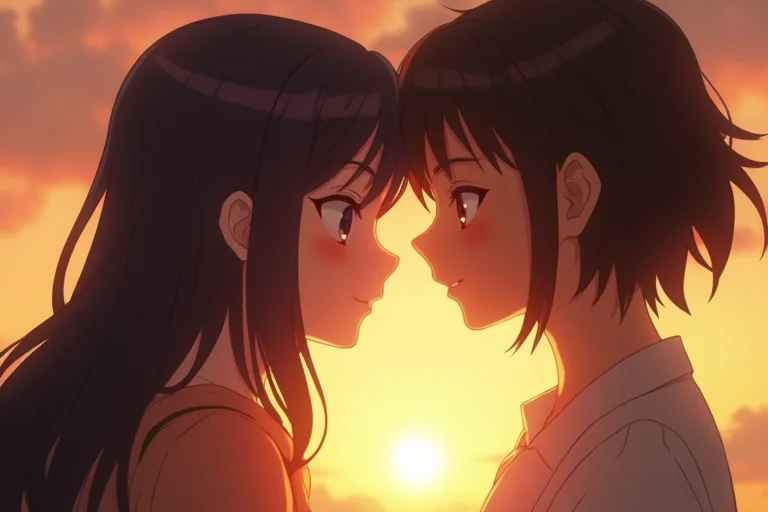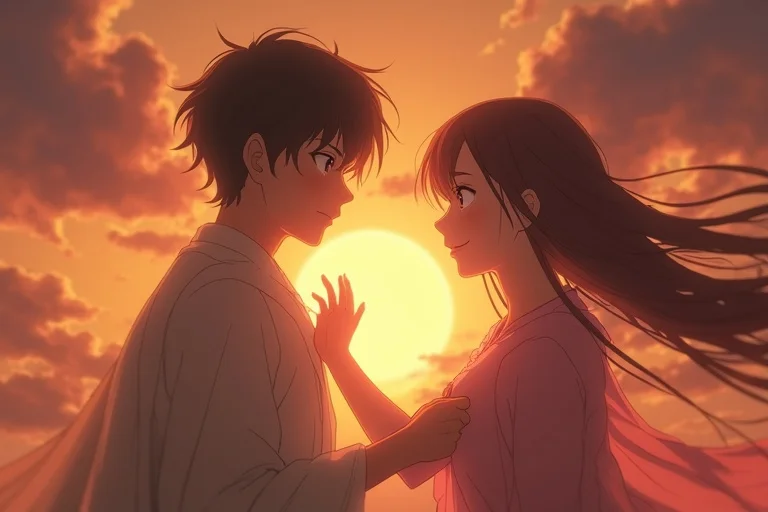第一章 ささやきは、あなただけに
水瀬音葉(みなせおとは)の人生は、声でできていた。目覚ましを止める「おはよう」から、カフェでのアルバイトで響かせる「いらっしゃいませ」、そして夜ごと繰り返す発声練習まで。彼女の世界は、声帯の震えが生み出す音の波で彩られていた。声優になるという夢は、彼女の存在そのものだった。
その日、彼女の世界に、異質な静寂が紛れ込んだ。
きっかけは、古びたレンガ造りの建物の二階にある、隠れ家のようなカフェでの出会いだった。窓際の席で、一人の男性が文庫本を読んでいた。射し込む午後の光が、彼の黒曜石のような髪を柔らかく照らし、その静謐な横顔は、まるで一枚の絵画のようだった。音葉は、心臓が不意に、しかし確かに、一つの音を立てたのを感じた。
注文を取りに行った時、彼の名前が月島響(つきしまひびき)だと知った。彼が顔を上げ、澄んだ瞳で音葉を見つめた瞬間、世界から音が消えた。いや、正確には、音葉が発するはずだった声が、喉の奥で形にならなかった。
「あ……あの、ご注文は」
声は出た。しかし、それは自分の鼓膜を震わせるだけで、彼以外の空間に溶けて消えてしまったようだった。カウンターにいる同僚も、隣の席の客も、誰一人として彼女の方を向かない。まるで、音葉が透明な膜に覆われ、彼女の声だけが外界から遮断されてしまったかのように。
パニックに陥りかけた音葉の耳に、彼の穏やかな声が届いた。
「ブレンドコーヒーを一つ。あなたの声、とても綺麗ですね」
音葉は目を見開いた。聞こえている。彼にだけは。
「え……?」
戸惑いながらも、もう一度声を出す。
「ありがとうございます……」
やはり、その声はカフェの喧騒にかき消されることなく、真っ直ぐに彼にだけ届いているようだった。響は小さく微笑むと、再び本に視線を落とした。
これが、音葉が体験した最初の「奇跡」、あるいは「呪い」の始まりだった。彼、月島響を前にした時だけ、彼女の声は、他の誰にも聞こえない、二人だけの秘密のささやきになるのだ。声優を目指す彼女にとって、それはあまりにも致命的で、そしてあまりにも甘美な現象だった。
第二章 ふたりだけの周波数
響との出会いから数週間、音葉は混乱と、抗いがたい引力との間で揺れていた。彼が経営する古書店「月読堂(つくよみどう)」に通うのが、いつしか彼女の日課になっていた。インクと古い紙の匂いが満ちるその場所で、響と話す時だけ、彼女の声は「特別」になった。
「この作家、好きなんですか?」
音葉が手に取った本を見て、響がカウンターの奥から静かに尋ねる。彼女が「はい、言葉の選び方が……」と答える声は、他の客の耳には届かない。まるで、二人の間にだけ存在する、見えない周波数があるかのようだ。
最初は恐怖だった。声優のオーディションの前日に響に会ってしまい、声が出ているのか不安でたまらなくなったこともあった。友人との電話中に彼のことを考えただけで、相手に「もしもし? 聞こえてる?」と何度も聞き返されたこともある。この現象は、彼女の夢を根底から脅かすものだった。
しかし、恐怖と同時に、奇妙な安らぎが心を占めていくのを、音葉は否定できなかった。
世界中の雑音から切り離され、ただ一人、響にだけ届く自分の声。それは、誰にも邪魔されない、純粋なコミュニケーションの形だった。普段は意識してしまう発声や滑舌も、彼の前ではどうでもよくなった。ただ、心を乗せて言葉を紡げば、彼は静かに耳を傾け、その深い瞳で受け止めてくれる。
「音葉さんの声は、雨の日の土の匂いに似てる」
ある日、響が唐突に言った。
「乾いた心に、静かに染み込んでくる感じがする」
その言葉に、音葉の胸は熱くなった。声優として「良い声だ」と言われるのとは違う、もっと根源的な部分を肯定された気がした。彼を想う気持ちが強くなるほど、彼女の声は彼だけのものになっていく。それは、世界との断絶を意味すると同時に、響との絶対的な繋がりを意味していた。
内面的な変化は、彼女の演技にも影響を与えた。次のオーディションで、音葉はこれまでになく高い評価を得た。「君のセリフには、静かなのに、確かな熱量がある。誰かたった一人に届けたい、というような……」審査員の言葉は、的を射ていた。皮肉なことに、世界から声を奪いかねないこの現象が、彼女の声に、本物の感情を与え始めていたのだ。
夢と恋。天秤は激しく揺れ動く。このまま彼を愛し続ければ、いつか本当に、世界に対して沈黙してしまうかもしれない。それでも、音葉は響に会うのをやめられなかった。彼にだけ届く声で、もっとたくさんのことを話したい。彼が奏でる沈黙を、もっと深く知りたい。その想いは、日増しに強くなるばかりだった。
第三章 沈黙の告白
季節が移ろい、街路樹の葉が赤や黄色に染まる頃、ついに恐れていた事態が訪れた。
その日、音葉は、最終審査まで残った大きな役のオーディションに臨んでいた。しかし、マイクの前に立った瞬間、彼女の喉から音は生まれなかった。頭の中に響の顔が浮かんだからだ。昨日、彼と交わした他愛ない会話、その時の優しい眼差し。彼への愛しさが胸を満たした瞬間、彼女の声は完全に世界から消え失せた。
唇は動くのに、音が出ない。ブースの向こうで、審査員たちが怪訝な顔でこちらを見ている。焦れば焦るほど、喉は固く閉ざされていく。結果は言うまでもない。夢への扉が、音もなく目の前で閉ざされた。
帰り道、冷たい雨が音葉の体を打ちつけた。悔しさと絶望で、涙が溢れて止まらなかった。すべて、響のせいだ。彼に出会わなければ。彼を愛してしまわなければ。そんな黒い感情が心をよぎる。もう、彼には会えない。会ってはいけない。愛せば愛すほど、私は私でなくなっていく。
その足で、音葉は「月読堂」に向かった。別れを告げるために。
店に入ると、響はカウンターで何かを書いていた。顔を上げた彼に、音葉は筆談用のメモ帳を突き出した。
『もう、会えません』
響は驚いたように目を見開いた。そして、音葉の濡れた髪と、泣き腫らした目元を見て、全てを察したようだった。彼は何も言わず、ただ静かに立ち上がると、店の奥から一枚の古い楽譜を持ってきた。そして、それを音葉の前に置いた。
『Silent Duet』
そう題された楽譜は、ピアノの連弾用だった。しかし、片方のパートには、音符が一つも書かれていなかった。ただ、休符だけが延々と続いている。
「僕も、同じなんだ」
響の声は、雨音に混じって、不思議なほどはっきりと音葉の耳に届いた。
「かつて、僕はピアニストだった。将来を嘱望されてもいた。でも、ある女性を愛したんだ。心から。すると、僕の弾くピアノの音が、少しずつ、他の誰にも聞こえなくなっていった。最初は気のせいだと思った。でも、コンクールの本番、満員のホールで、僕のピアノは完全な沈黙を奏でた。僕の耳と、そして、客席にいた彼女の耳にだけ、旋律は響いていたけれど」
彼の告白は、衝撃的だった。音葉が体験している現象と、全く同じ。
「彼女は僕を恐れて去っていった。僕は音を失い、夢を失った。だから、もう二度と誰も愛さないと決めたんだ。人と深く関わることを避けて、この静かな場所で生きていこうと」
響は、震える手で音葉の頬に触れた。
「君の声が僕にだけ聞こえるのは、君が僕を想ってくれているからだと思っていた。でも、違った。僕の声も……もう、君にしか聞こえていないんだよ。さっき、店の前を通りかかった常連客に挨拶をしたが、彼は気づかずに通り過ぎていった」
予想だにしなかった事実。彼は、彼女を愛したことで、残されていた「声」という最後の音さえも、世界から失おうとしていたのだ。二人は同じ呪いを、あるいは同じ祝福を、知らず知らずのうちに共有していた。沈黙の中で、二人の視線が絡み合う。それは、どんな言葉よりも雄弁な告白だった。
第四章 世界でいちばん、豊かな音
世界から隔絶された二人の、静かな日々が始まった。
音葉は声優の夢をきっぱりと諦めた。響もまた、人と関わることを最小限にした。二人の声は、互いにしか届かない。彼らが交わす言葉は、他の誰にも認識されない空虚な音波となった。筆談や手話を使うこともできたはずだ。しかし、二人はそうしなかった。
「おはよう、響さん」
朝、音葉がささやくと、響は微笑んで「おはよう」と返す。その声は、他の誰にも聞こえない。だが、互いの鼓膜を震わせ、心を温めるには十分すぎるほどの響きを持っていた。
彼らは、失ったものの大きさを嘆く代わりに、手に入れたものの尊さを見つめることにした。
世界中の誰にも聞かせられない、たった一人にだけ届く声。それは、究極の秘密の共有であり、絶対的な信頼の証だった。音葉は、不特定多数の誰かを喜ばせるための声を失った。その代わりに、響という、たった一人の心を震わせるための声を手に入れた。
ある晴れた午後、二人は海辺の公園を訪れた。潮風が頬を撫で、カモメの鳴き声が遠くに聞こえる。ベンチに座り、音葉は響の肩にそっと頭をもたせかけた。
「ねえ、私の声、まだ綺麗に聞こえる?」
世界にとっては無音の問いかけ。しかし、響にとっては、どんな音楽よりも美しい旋律だった。
「ああ。世界でいちばん、豊かな音がする」
響はそう答えると、おもむろに歌い始めた。それは、彼がピアニストだった頃に作ったという、誰にも披露したことのない歌だった。その拙く、しかし愛情に満ちた歌声は、もちろん音葉にしか聞こえない。
音葉も、それに合わせて小さな声でハミングを重ねた。声優を目指していた頃に培った、美しいソプラノ。二人の声が重なり合い、世界中の誰にも知られることのない、ささやかなデュエットが生まれる。
周りから見れば、彼らはただ黙って海を眺めている、奇妙な二人組に過ぎないだろう。しかし、彼らの内なる世界では、壮大な交響曲が奏でられていた。愛を語り、笑い合い、歌を歌う。そのすべてが、二人だけの宇宙で完結していた。
音葉はもう、世界からの沈黙を恐れていなかった。一つの扉が閉じる時、別の扉が開く。彼女は声で世界と繋がる道を失った代わりに、魂で響と繋がる道を見つけたのだ。
彼女は目を閉じ、響の声と、自分の声が織りなすハーモニーに耳を澄ませた。それは、拍手喝采も、富や名声ももたらさない。けれど、確かな温もりと、揺るぎない愛に満ちていた。世界でいちばん静かで、世界でいちばん、豊かな音。その音に包まれて、音葉は心の底から微笑んだ。二人の物語は、ここから静かに始まっていく。