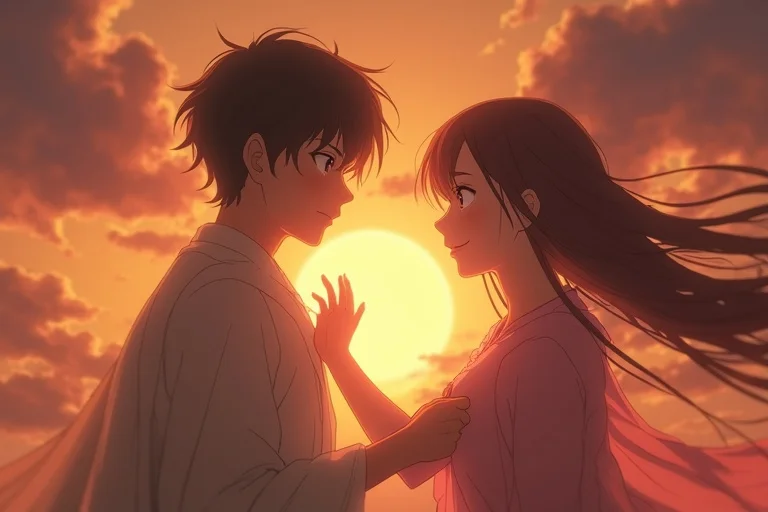第一章 触れられない境界線
神保町の裏路地に佇む古書店『時紡ぎ堂』の空気は、いつもインクと古い紙の匂いがした。埃を吸い込んだ陽光が、書架の隙間を金色に染め上げ、時間の流れを緩やかにしている。水瀬櫂は、その静寂の番人だった。彼はカウンターの奥で、革の表紙が擦り切れた本を、まるで壊れ物を扱うかのように修繕していた。
その日、店のドアベルがちりん、と乾いた音を立てた。入ってきたのは、今までこの店では見かけないタイプの女性だった。陽光をそのまま纏ったような、快活な雰囲気をした彼女は、興味深そうに店内を見回している。
「こんにちは」
彼女の声は、静寂に慣れた櫂の耳には少しだけ大きく響いた。櫂は顔を上げ、会釈を返す。言葉を発するのが、少し億劫だった。
彼女――月島栞が、この店に足を踏み入れたのは偶然だった。だが、彼女は櫂がカウンターに飾っていた小さなガラスのインク壺に、運命的な何かを感じたという。
「これ、すごく綺麗…。吹きガラスかしら。少し歪んでいるところが、呼吸しているみたい」
栞はそう言って、細く白い指をインク壺に伸ばした。その瞬間、櫂は自分でも驚くほどの速さで身を乗り出していた。
「さ、触らないでください!」
声が裏返る。栞の指は、インク壺の数ミリ手前で凍りついた。彼女の大きな瞳が、驚きに見開かれる。櫂の心臓が、警鐘のように激しく鳴り響いていた。やってしまった、と唇を噛む。過剰な反応だ。だが、彼にとって「触れる」という行為は、引き金を引くことに等しかった。
櫂には、生まれついての特異な体質があった。他人の肌に触れると、自分の記憶が一つ、ランダムに相手へ転送されてしまうのだ。それはまるで、魂の一部を削り取られるような感覚だった。失った記憶は、櫂の中から完全に消え去る。写真を見ても、人から話を聞いても、そこに感情的な繋がりを見出すことは二度とできない。ただの記録として頭に残るだけだ。だから櫂は、人との物理的な接触を極端に避けて生きてきた。握手も、肩を叩かれることも、彼にとっては恐怖だった。
栞は気まずそうに手を引っ込め、それでも笑顔を崩さなかった。
「ごめんなさい。大切なものだったんですね」
その屈託のなさが、逆に櫂の胸を締め付けた。それからというもの、栞は頻繁に店を訪れるようになった。彼女はガラス工芸家で、古いものに新しい命を吹き込むことにインスピレーションを感じるのだと言った。彼女は櫂にたくさんの話をした。ガラスの熱さ、形を変える瞬間の美しさ、失敗した作品の儚さ。櫂は聞き役に徹しながらも、彼女の言葉が作る鮮やかな世界に、少しずつ引き込まれていくのを感じていた。
彼女の存在は、櫂のモノクロームだった日常に、ステンドグラスのような光を差し込んだ。気づけば、彼は彼女が来るのを心待ちにするようになっていた。彼女の笑い声を聞きたい。彼女の話をもっと聞きたい。そして――触れたい。その抗いがたい衝動が、恐怖と同じだけの強さで、彼の内側から湧き上がってくるのだった。
第二章 ガラス越しの告白
季節が巡り、店先の紫陽花が雨に濡れる頃になっても、二人の間には見えないガラスの壁が存在し続けていた。一緒に映画を観に行っても、隣の席で感じる彼女の気配に緊張するばかりで、ストーリーは頭に入らない。食事をすれば、テーブルの下で足が触れ合わないように、不自然なほど身を固くした。
栞は、櫂の不自然な距離感に気づかないふりをしていた。だが、その壁が最も厚く感じられたのは、ある雨の日のことだった。
その日、栞は自作のガラスの風鈴を携えて店にやってきた。澄んだ青色の短冊が揺れる、美しい風鈴だった。
「これ、櫂さんに。お店の雰囲気に合うかと思って」
彼女が差し出した風鈴を受け取ろうとした瞬間、櫂の指が、彼女の温かい指先に触れそうになった。びくり、と電気が走ったような衝撃に、櫂は思わず手を引っ込める。風鈴が宙で揺れ、危うく落ちそうになったのを、栞が慌てて掴んだ。
カシャン、とガラス同士がぶつかる、悲しい音がした。
沈黙が落ちる。栞は俯いたまま、風鈴を握りしめていた。その表情は、長い前髪に隠れて見えない。
「……どうして?」
絞り出すような声だった。
「どうして、私に触れてくれないの? 私、何かしましたか?」
違う。そうじゃない。櫂は喉まで出かかった言葉を飲み込んだ。彼女を傷つけたくない。だが、このままでは、彼女をもっと深く傷つけてしまうだろう。降りしきる雨音が、責め立てるように店の屋根を叩いていた。
櫂は観念したように、深く息を吸った。そして、震える声で、全てを打ち明けた。自分の特異な体質のこと。人に触れると、大切な記憶が奪われてしまうこと。幼い頃、大好きだった飼い犬との最後の散歩の記憶を、通りすがりの人にぶつかった拍子に失ってしまったこと。その記憶は写真として残っているが、温もりも、匂いも、悲しみも、何一つ感じられないのだと。
「だから、君に触れるのが怖いんだ。もし君に触れて、君と出会った日の記憶が消えてしまったら…僕は、君という光が僕の人生に差し込んだ、あの最初の瞬間を、永遠に失ってしまう」
それは、櫂にとって初めての、魂からの告白だった。
話し終えた櫂の前で、栞はゆっくりと顔を上げた。その瞳は涙で潤んでいたが、そこに浮かんでいたのは軽蔑や恐怖ではなかった。驚きと、そして深い、深い慈しみのような色だった。
彼女はしばらく黙って櫂を見つめた後、そっと風鈴をカウンターに置いた。
「……なら」
彼女は震える唇で、信じられない言葉を紡いだ。
「なら、私にくれてもいい記憶を、触れて教えてよ。櫂さんのこと、もっと知りたいから」
第三章 最初の追憶、二つの真実
栞の提案は、櫂にとって世界の理を覆すような一撃だった。失うことを前提とした接触。それは、彼がこれまで最も忌み嫌い、避けてきた行為のはずだった。だが、彼女の真摯な瞳に見つめられると、彼の心の頑なな壁が、音を立てて崩れていくのが分かった。このまま彼女を失うくらいなら、記憶の一つや二つ、くれてやろう。そんな、やけっぱちに近い覚悟が芽生えていた。
数日後、二人は井の頭公園のベンチに座っていた。櫂は、どの記憶を差し出すか、ずっと考えていた。そして、一つの些細な、けれど彼にとっては輝かしい記憶を選び出した。初めて補助輪なしで自転車に乗れた日の記憶だ。夕暮れの公園、父の大きな背中、ペダルを踏み込む足の感触、風を切る音、そして世界が自分の力で広がっていく万能感。失うのは惜しい。だが、この記憶なら、彼女を傷つけることはないだろう。
「準備、できたよ」
櫂の声は、自分でも分かるほど上ずっていた。栞は何も言わず、静かに右手を差し出す。櫂は深呼吸を一つすると、震える指先を、ゆっくりと彼女の掌に近づけていった。
指が触れた瞬間だった。
世界から、音が消えた。櫂の脳裏に、あの日の公園の風景がフラッシュバックする。夕日が地面に長い影を落とし、父の「漕げ、前を見ろ!」という声が響く。だが、その映像は砂絵のようにサラサラと崩れ、色が褪せ、やがて完全な白に変わった。
喪失感。いつもの、胸にぽっかりと穴が開く感覚。しかし、今回は違った。穴が開いたその場所から、温かい何かが流れ込んでくる。それは、栞の指先の、信じられないほどの温もりだった。
櫂がはっと目を開けると、目の前の栞が、大粒の涙をぽろぽろと零していた。
「……見えた」
彼女は嗚咽混じりに言った。
「公園の坂道…錆びた補助輪…夕日…。櫂くん、すごく嬉しそうだった。風になったみたいに、笑ってた…」
彼女が、自分の記憶を追体験している。その事実に、櫂は言葉を失った。だが、驚きはそれだけでは終わらなかった。
彼の頭の中に、全く別の、しかし同じくらい鮮やかな光景が流れ込んできたのだ。
薄暗い工房。汗ばむ額。熱く燃える溶解炉のオレンジ色の光。吹き竿の先に、飴のように溶けたガラスが丸く膨らみ、震えながら形を成していく。初めて、自分の息吹が、無機質な塊に命を与えることに成功した瞬間の、焼け付くような歓喜。
それは、櫂の記憶ではなかった。
「栞さん、君は…」
櫂が呆然と呟くと、栞は涙を拭い、そして、初めて見せるような、少し寂しげな笑顔で頷いた。
「……私も、同じなの」
彼女もまた、触れた相手と記憶を交換してしまう体質だったのだ。櫂が自転車の記憶を失ったのと同時に、彼女は初めてガラスを吹いた日の記憶を失い、それを櫂に与えていた。
「ずっと、怖かった。誰かに触れるのが。私のせいで、相手の大切なものを奪ってしまうんじゃないかって。私の記憶が、相手を汚してしまうんじゃないかって。だから、人と深く関わるのを避けてきた」
彼女は、古書店で櫂が過剰に反応したのを見て、すぐに気づいたのだという。自分と同じ、孤独の匂いを。だから、彼女は彼に近づいた。確かめたかった。この世界に、たった一人でも同じ痛みを分かち合える人がいるかもしれない、という僅かな希望に賭けて。
「櫂さんに出会えて、よかった」
二つの孤独な魂が、初めて互いの真実に触れた瞬間だった。それは喪失ではなく、奇跡的な邂逅だった。
第四章 指先のテラリウム
その日を境に、二人の世界は完全に変わった。これまで二人を隔てていた透明な壁は砕け散り、彼らの恋愛は、世界で最もユニークな形を取り始めた。
彼らのデートは、記憶の交換会になった。
初めて訪れた水族館で、ジンベイザメの雄大な姿に感動しながら、そっと手をつなぐ。すると、櫂が子供の頃に初めて海を見て水平線の広さに圧倒された記憶が栞に流れ込み、代わりに栞が祖母の家で食べたスイカの甘い記憶が櫂の中に宿る。
触れ合うたびに、彼らは互いの一部を失い、互いの一部を得た。それは、パズルのピースを交換し合い、二人で一つの新しい絵を完成させていくような、神聖な儀式だった。櫂の失った記憶は栞の中で生き続け、栞が手放した記憶は櫂の中で新たな根を下ろす。それは喪失ではなく、共有であり、魂の融合だった。
櫂の中に、栞が幼い頃に転んで泣いた時の膝の痛みや、コンクールで入選した時の誇らしい気持ちが同居するようになった。栞の中には、櫂が浪人時代に感じた焦燥感や、初めて『時紡ぎ堂』の鍵を預かった日の責任感が芽生えた。彼らは互いの過去を生きることで、誰よりも深く相手を理解し、愛することができるようになっていった。
櫂は、もう人との接触を恐れなかった。彼は、記憶とは個人の書庫にしまい込むものではなく、大切な誰かと分かち合うことで輝きを増す、流動的な光のようなものだと知った。彼の内向的な世界は、栞という存在によって無限に拡張されたのだ。
一年が過ぎた。二人は夕暮れの海岸を、しっかりと手をつないで歩いていた。寄せては返す波の音が、心地よいリズムを刻んでいる。
「ねえ、櫂さん」
栞が、悪戯っぽく笑いながら尋ねた。
「次は、何の記憶を交換する?」
櫂は愛おしげに彼女を見つめ、少し考えてから、穏やかに微笑んだ。
「君と出会った、あの日の記憶はどうかな」
栞が、息を呑むのが分かった。それは、二人の始まりの記憶。二人にとって、何物にも代えがたい、最も大切な宝物だ。それを手放すことは、これまでのどんな記憶とも違う、大きな覚悟を必要とする。
だが、彼らはもう恐れていなかった。
その記憶を交換し、互いの中に相手との出会いを刻み込む。そうすれば、たとえ自分の頭の中から出会いの瞬間が消え去ったとしても、愛する人の中に、その輝きは永遠に生き続けるのだから。
「いいね」
栞は、幸せそうに微笑んで頷いた。
「私の人生で、最高の一日だったから。櫂さんにあげる」
二人は立ち止まり、額を寄せ合う。彼らの指先が、まるで小さなガラスのテラリウムを作るかのように、そっと触れ合った。そこには、二人の過去と未来、全ての愛が閉じ込められ、永遠の光を放ち始めるのだった。愛とは、自己を失うことではない。愛とは、相手と溶け合い、一つになって、より大きな世界を築いていく、果てしない旅路そのものなのかもしれない。