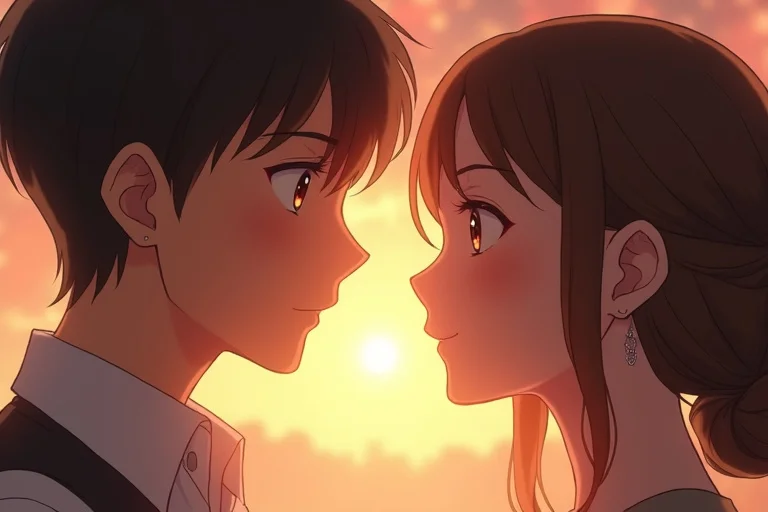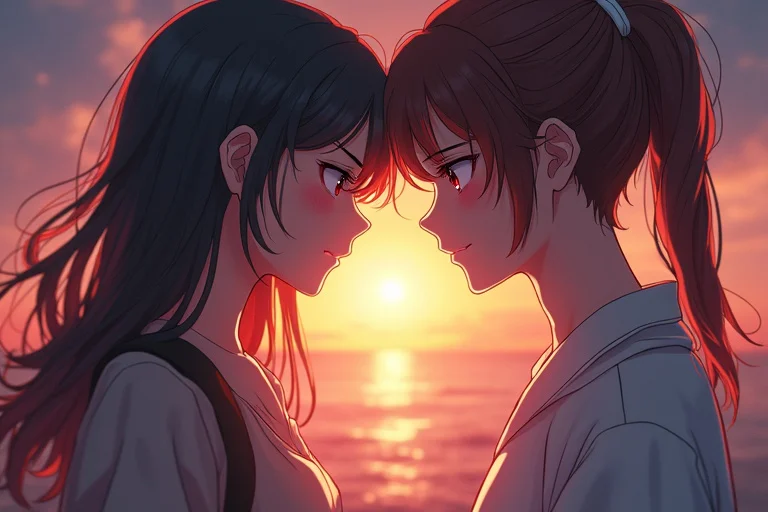第一章 はじめまして、を三十回
朝の光が、カーテンの隙間から細い刃のように差し込み、部屋の埃をきらきらと照らし出す頃、僕、水野蒼の一日は始まる。隣のベッドで眠る彼女、日向陽菜の穏やかな寝息を確認し、そっと寝室を出る。キッチンで湯を沸かしながら、昨日と同じ言葉を、新品のカードに書き記す。
『はじめまして、僕は水野蒼。君の恋人です』
陽菜は、一年前に遭った事故の後遺症で、眠るとその日の記憶をすべて失ってしまう。前向性健忘症、と医者は言った。だから僕たちの毎日は、常に「はじめまして」から始まるのだ。
カードを彼女の枕元に置き、僕はリビングで息を潜める。やがて、寝室から戸惑いの声が聞こえる。ドアがゆっくりと開き、警戒心に満ちた瞳が僕を捉えた。肩まで伸びた栗色の髪を揺らし、僕が昨日買ってあげたばかりのパジャマの袖を固く握りしめている。
「あの……どちら様、ですか?」
「おはよう、陽菜。僕は水野蒼。君の恋人だよ」
いつもの台詞だ。僕は作り笑顔を貼り付け、壁一面に飾られた写真や、机に置かれた分厚いアルバムを指さす。そこには、水族館ではしゃぐ彼女、公園で僕に寄り添う彼女、誕生日ケーキを前に満面の笑みを浮かべる彼女の姿がある。どれも、彼女にとっては見覚えのない、しかし紛れもない「昨日までの彼女」の記録だ。
陽菜は半信半疑のまま、アルバムを手に取る。ページをめくる指先が微かに震えている。僕は彼女が好きだったアールグレイの紅茶を淹れ、静かに向かいに座る。湯気の向こうで、彼女の瞳が揺れる。混乱、恐怖、そしてほんの少しの好奇心。僕はその感情の機微を、もう三百回以上見てきた。
「本当に……あなたが、私の?」
「うん。信じられないかもしれないけど、少しずつでいいから。思い出せなくても、また今日、僕を好きになってくれれば、それでいい」
僕の言葉に、彼女の肩からふっと力が抜ける。紅茶のカップを両手で包み込み、こくりと一口飲む。その仕草が、僕の知っている陽菜そのものであることに、胸の奥がきゅっと痛んだ。
「……変な感じ。でも、あなたの声、なんだか安心します」
そう言って、彼女ははにかんだ。その笑顔を見るために、僕は毎日、嘘とは言えないまでも、真実の一部を隠しながら、この奇妙な儀式を繰り返している。失われた記憶の代わりに、僕が彼女の世界のすべてにならなければならない。それが僕に課せられた、愛の形だと信じて。
第二章 一日限りの永遠
「わあ、すごい! まるで宇宙みたい!」
青い光に満たされた巨大な水槽の前で、陽菜は子供のように歓声を上げた。ジンベエザメが悠然と頭上を通り過ぎていく。その影が、陽菜の顔に落ちては消える。彼女の瞳は、初めて見る世界への驚きと喜びに、宝石のように輝いていた。
陽菜が僕を「恋人」として受け入れた後、僕たちは決まって「初めてのデート」に出かける。公園、映画館、そして彼女が一番好きな水族館。何度来ても、彼女にとっては初めての場所だ。
「見て、蒼さん! あの魚、虹色だよ!」
僕の袖を掴んで、無邪気に笑う。その笑顔は、僕が恋に落ちた頃と何も変わらない。事故の前、彼女は新進気লাইনেのイラストレーターで、その繊細な色彩感覚で世界を切り取る人だった。記憶は失っても、その感性だけは、彼女の中に深く根付いているようだった。
僕たちは、ペンギンのコーナーで笑い、イルカのショーに拍手を送り、クラゲが漂う暗い部屋で、寄り添ってその幻想的な光を眺めた。陽菜は僕の肩にこてんと頭を乗せる。シャンプーの甘い香りが鼻を掠めた。
「蒼さんの隣にいると、ずっと前からこうしていたような気がする。不思議だね」
「……そうだと、嬉しいな」
嘘だ。君は覚えていない。そう喉まで出かかった言葉を、僕は飲み込む。この穏やかな時間を壊したくない。この一日限りの永遠を、少しでも長く味わっていたい。
帰り道、夕日が街を茜色に染めていた。公園のベンチに座り、二人で自動販売機のアイスを食べる。陽菜は、幸せそうに目を細めた。
「楽しかった。すごく、すごく楽しかった。明日も、また一緒に来たいな」
その言葉は、純粋で、残酷な刃だ。僕の心臓を真っ直ぐに貫く。明日になれば、陽菜はこの日の楽しさも、僕と交わした言葉も、何もかも忘れてしまう。そして僕はまた、枕元にカードを置くのだ。
「……ああ、もちろん。明日も、その次も、ずっと一緒に来よう」
僕は微笑んで答える。この笑顔の裏で、心がどれだけ悲鳴をあげているか、彼女は知らない。それでいい。彼女が笑ってくれるなら、僕は何度でも道化になろう。それが、僕の愛なのだから。夜の帳が下りる頃、僕たちは手を繋いで、明日にはまた他人同士に戻る「我が家」へと帰った。
第三章 嵐の夜の告白
その夜は、激しい嵐だった。窓ガラスを叩きつける雨音と、時折空を引き裂く雷鳴が、部屋の中にまで響き渡る。陽菜は少し怯えた様子で、僕の腕にしがみついていた。その時だった。けたたましい音と共に、部屋の明かりがすべて消えた。
「停電……!」
突然の闇に、陽菜が息を呑む。僕は手探りで棚からロウソクを探し出し、火を灯した。ゆらゆらと揺れる小さな炎が、二人の顔をぼんやりと照らし出す。不安げな陽菜の瞳が、炎の光を映して潤んでいた。
沈黙が部屋を支配する。雨音と、ロウソクの芯が爆ぜる音だけが聞こえる。僕は何か明るい話題を探そうと口を開きかけた。だが、それよりも先に、陽菜が静かに口火を切った。その声は、今まで聞いたこともないほど低く、震えていた。
「ねえ、蒼さん」
「……どうしたの?」
「もし……もし私が、本当は全部覚えてるって言ったら、どうする?」
時間が、止まった。
雨音も、風の音も、自分の心臓の音さえも聞こえなくなった。目の前の陽菜が、まるで知らない誰かのように見える。彼女の瞳の奥に、僕の知らない深い、深い闇が広がっていた。
「……どういう、こと?」
絞り出した声は、自分でも驚くほどにかすれていた。
陽菜は俯き、長い沈黙の後、ぽつり、ぽつりと語り始めた。事故の後、記憶障害は確かにあったこと。しかし、それは最初の数週間だけで、ある朝、目覚めた時には、すべての記憶が繋がっていたこと。
「怖かったの」と彼女は言った。涙が、ロウソクの光を受けてきらりと光った。「記憶は戻ったのに、事故のせいで、私の右手は前みたいに絵を描けなくなってた。大好きだったことが、できなくなった。絶望だった。そんな私を、あなたは毎日、毎日、献身的に支えてくれた。記憶のない、無垢な私を……愛してくれた」
彼女の告白は、僕の頭を鈍器で殴りつけるような衝撃だった。
「だから、言えなかった。本当のことを言ったら、蒼さんはいなくなってしまうんじゃないかって。絵も描けない、ただの役立たずの私を、あなたは愛してくれないんじゃないかって。だから……私は、記憶喪失のフリを続けたの。毎日、初めて会うあなたに恋をするフリをした。そうすれば、あなたはずっと私のそばにいてくれると思ったから」
僕が愛していたのは、何だったのだろう。彼女の笑顔か。彼女の無垢さか。いや、違う。僕が愛していたのは、「彼女を支える自分」ではなかったのか。僕の献身は、彼女を救うどころか、偽りの仮面を被せ、苦しみの檻に閉じ込めるためのものだったのか。
壁一面の写真が、アルバムの笑顔が、すべて色褪せて見えた。僕が積み上げてきたと思っていた愛は、脆く、空虚な砂の城だった。嵐の音に紛れて、僕の世界がガラガラと崩れ落ちていく音がした。
第四章 朝凪に漕ぎ出す二人
嵐が過ぎ去り、嘘のように静かな夜が明けていった。僕は一睡もできなかった。リビングのソファに座り、白んでいく空をただ眺めていた。隣の部屋では、陽菜がどんな思いで夜を明かしたのだろう。
僕の心は、後悔と自己嫌悪でぐちゃぐちゃだった。彼女の嘘を責める気にはなれなかった。彼女をそこまで追い詰めたのは、紛れもなく僕自身だ。僕の独りよがりな「愛」が、彼女から真実を語る勇気を奪ったのだ。
愛とは何だ。信じるとは何だ。答えの出ない問いが、頭の中を巡る。
やがて、窓から差し込む朝の光が、部屋を優しく満たし始めた。それは、昨日までの光とは全く違う、新しい世界の始まりを告げる光のように感じられた。僕はゆっくりと立ち上がり、寝室のドアをノックした。
返事はない。そっとドアを開けると、陽菜はベッドの縁に座り、膝を抱えていた。泣き腫らした目が、僕を不安そうに見つめる。僕は彼女の前に進み、その場に膝をついた。彼女の視線と、同じ高さになるように。
「陽菜」
僕は、震える声で彼女の名前を呼んだ。
「ごめん。気づいてやれなくて、ごめん。君をずっと、苦しめてたんだな」
陽菜の瞳から、再び涙が零れ落ちた。彼女は首を横に振る。
「違う、私が……私が、弱かったから」
「弱くていいんだよ」と僕は言った。「僕だって弱い。君を失うのが怖くて、本当の君を見ようとしていなかった。でも、もうやめにしよう。こんな、悲しい芝居は」
僕は彼女の冷たい手を取った。その手は、かつて美しい絵を生み出した手だ。
「記憶があってもなくても、絵が描けても描けなくても、君は君だ。僕は、嘘をついてまで僕のそばにいたかった君の弱さも、君が一人で抱えてきた痛みも、全部まとめて愛したい。だから……もう一度、本当の君と、はじめましてをさせてくれないか?」
僕の言葉に、陽菜は顔を覆って泣きじゃくった。それは、長い間堰き止められていた感情の奔流だった。僕はただ、彼女の背中を優しくさすり続けた。
どれくらいの時間が経っただろう。陽菜が顔を上げた時、その瞳には、涙の向こうに、確かな光が宿っていた。彼女は、こくりと小さく頷いた。
僕たちは、どちらからともなく微笑んだ。それは、昨日までの笑顔とは違う、痛みと赦しを知った、大人の笑顔だった。
手を繋いで、リビングへ出る。壁の写真も、アルバムも、もう偽物には見えなかった。それらは、僕たちが必死に生きてきた、紛れもない愛の軌跡なのだ。
窓の外は、嵐が洗い流した空気が澄み渡り、穏やかな朝凪が広がっていた。
「おはよう、陽菜」
「……おはよう、蒼」
それは、僕たちが初めて交わす、本当の朝の挨拶だった。昨日までのすべてが溶けていくような、新しい一日が、今、静かに始まろうとしていた。