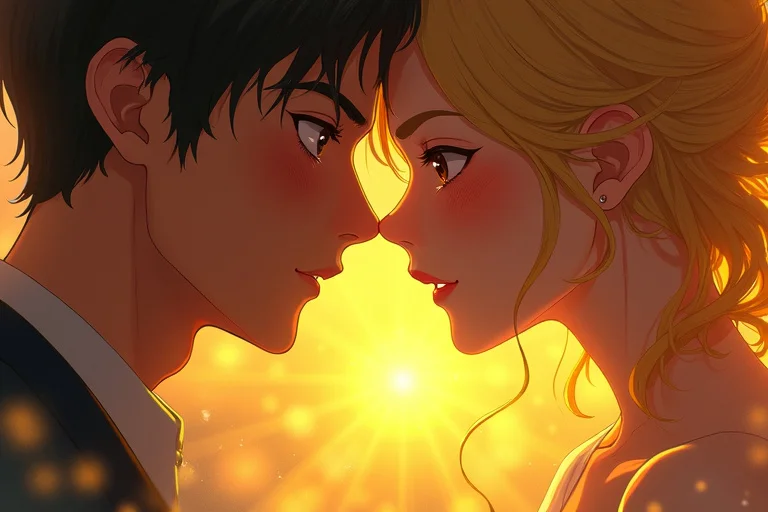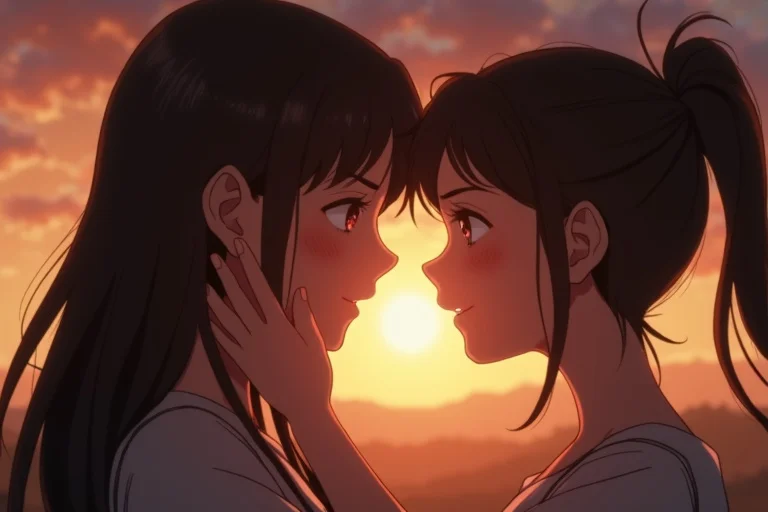第一章 触れられぬ心と愛の残像
カイの世界は、触れることで侵食される。古物商を営む彼の指先が、錆びたブリキの玩具や、ひび割れた陶器に触れるたび、奔流のように他人の過去が流れ込んでくるのだ。それは、持ち主がかつて最も深く愛した人物の『愛の残像(ヴィジョン)』。陽だまりの中で笑う少女、駅のホームで手を振る青年、皺の刻まれた手で赤子を抱く老婆。カイは彼らの愛の記憶を追体験するが、その温もりは決して彼自身のものにはならなかった。
能力は呪いだった。人と肌が触れ合うことを極端に避けるようになったのは、いつからだったか。握手も、肩が触れ合うほどの雑踏も、彼にとっては心を乱す激流でしかない。だからカイは、物言わぬ古物たちに囲まれたこの店の薄闇に安らぎを見出していた。窓から差し込む光が埃を金色に照らす中、彼はカウンターの隅に置かれたアンティークの砂時計を眺める。くびれたガラスの中で、銀色の砂が静かに時を刻んでいた。祖母の形見である『共鳴の砂時計』。それが彼の孤独な運命と分かちがたく結びついていることを、彼はまだ知らない。
誰もが、この世界とは別の次元に存在する『ソウルメイト』の存在を信じていた。時折見る不思議な夢、ふと心をよぎるデジャヴュ。それが、魂の片割れからの微かな信号だと人々は語り合う。カイもまた、その漠然とした信仰の中で、届かぬはずの温もりを、人知れず求め続けていた。
第二章 雨の日の訪問者と失われた紋様
冷たい雨が石畳を叩く午後だった。店のドアベルが、ちりん、と寂しげな音を立てた。濡れたコートの裾から雫を落としながら入ってきたのは、エラと名乗る女性だった。彼女の瞳には、洗い流された空のような、どこか物悲しい青が宿っていた。
「これを、お願いできますか」
彼女がカウンターに置いたのは、銀細工の小さなペンダントだった。月長石が埋め込まれ、使い込まれて角が丸くなっている。カイはためらった。これに触れれば、また見てしまう。だが、彼女の懇願するような眼差しを前に、断ることはできなかった。
指先が冷たい銀に触れた瞬間、世界が色を変えた。
夏の陽光が降り注ぐ、向日葵畑。風に揺れる麦わら帽子の下で、快活に笑う青年の顔。彼の隣には、幸せそうに目を細める、今より少し若いエラの姿があった。二人の笑い声が、夏の匂いと共にカイの鼓膜を満たす。それはあまりに鮮烈で、幸福な残像だった。そして、カイは見た。青年の腕に、そしてエラが見つめる向日葵の花の中心に、奇妙な紋様が陽炎のように揺らめいているのを。それは、彼がこれまで見てきた全ての『愛の残像』に共通して現れる、『失われた紋様』だった。
「……ありがとう」
残像から引き戻されたカイに、エラが静かに告げた。
「彼が、一番大切にしていたものなんです」
その声の震えに、カイは自分の能力が初めて、誰かの悲しみの深さに触れたのだと理解した。
第三章 砂時計の微光
エラが店を去った後、カイは一人、カウンターに凭れていた。向日葵畑の記憶が、網膜に焼き付いて離れない。あの幸福の残像は、同時にエラの喪失の深さを物語っていた。他人の心を覗く行為への罪悪感と、彼女の悲しみへの共感が、彼の胸を締め付けた。
その時だった。
ふと、視界の隅で何かが瞬いた。目を向けると、机の上の『共鳴の砂時計』だった。いつもは静かに時を落とすだけの銀色の砂が、まるで蛍のように、淡い青白い光を放っている。光は瞬き、呼吸するように明滅を繰り返し、やがて静かに消えていった。
初めて見る現象だった。祖母は言っていた。「この砂時計はね、本当の愛に触れた時、道を示してくれるのさ」。カイはハッとして、エラのペンダントに触れた時のことを思い返す。あの鮮烈な愛の残像。そして、『失われた紋様』。まさか。
彼は急いで引き出しからスケッチブックを取り出した。そこには、彼がこれまで見てきた残像から記憶を頼りに描き留めてきた、紋様の断片が無数に記されている。ある時は恋人たちの背景の雲の形に、ある時は親子の影が作る模様に。断片はどれも不完全で、意味をなさなかった。だが、エラの残像で見た紋様は、これまでで最も完全な形に近かった。砂時計は、この紋様のエネルギーに共鳴したのだ。カイの心に、確信めいた予感が芽生えた。この紋様を完成させれば、ソウルメイトへと繋がる道が開かれるのかもしれない。
第四章 紋様の断片を追って
その日から、カイの日常は一変した。彼は呪いとさえ思っていた能力を、自らの意志で使うようになった。古物を買い付けに訪れた市場では、露店の老夫婦の手を取り、彼らが若い頃に交わした誓いの残像を見た。図書館では、古書の貸し出し記録を調べて持ち主を訪ね、本に込められた父から娘への愛情の残像に触れた。
「ありがとう、お嬢さん」
「……え?」
パン屋で小銭を受け取った拍子に、店員の少女の手と触れ合う。彼女が亡くした愛犬と野原を駆け回る、無邪気な愛の残像。その温かさに思わず礼を言うと、少女はきょとんとした顔で彼を見つめた。
触れるたびに、様々な愛の形がカイの中に流れ込む。歓喜、慈愛、そして時には嫉妬や後悔を伴う歪んだ愛さえも。その全てに、『失われた紋様』は形を変えて潜んでいた。一つ残像を見るたびに、共鳴の砂時計は光を増し、その輝きは次第に持続するようになっていく。スケッチブックの紋様は、複雑で美しい幾何学模様として、その全貌を現しつつあった。しかし、他人の強烈な感情の奔流を受け止め続けることは、カイの精神を確実に摩耗させていた。夜ごと、他人の夢にうなされ、自分の記憶と他人の記憶の境界が曖昧になっていくような感覚に苛まれた。
第五章 完成された紋様と砂時計の導き
疲れ果てたカイが、公園のベンチで休んでいた時だった。小さな泣き声が聞こえた。見ると、母親とはぐれたらしい幼い少年が、大きな瞳に涙を溜めて立ち尽くしている。カイは無意識に立ち上がり、少年の前に屈み込んだ。
「どうしたんだい? ママは?」
「……わからない」
おずおずと差し出された小さな手を、カイはそっと握った。その瞬間、流れ込んできたのは、悲しみや不安ではなかった。それは、ほんの数分前、母親に高く抱き上げられた時の、純粋で絶対的な幸福感。世界が母親の笑顔だけで満たされているかのような、混じり気のない無垢な愛の残像だった。そして、その母親の微笑みの口元に、カイは最後のピースを見た。探していた、紋様を完成させる最後の一片。
スケッチブックのページが、ついに埋まった。
完成した紋様は、螺旋が複雑に絡み合い、中心に一つの点を抱く、宇宙の星図にも似た壮麗な図形だった。
その瞬間、懐に忍ばせていた『共鳴の砂時計』が、これまでとは比較にならないほどの強い光を放った。ガラスの中で輝く銀の砂が、重力に逆らうように一斉に上へと舞い上がり、砂時計の上部に集まっていく。そして、凝縮された光は、一本の鋭い光線となって、カイの胸元から北西の空を指し示した。その方角にあるのは、街を見下ろす丘の上に立つ、古びた天文台だった。
第六章 星降る丘の扉
息を切らして丘を駆け上がると、廃墟となった天文台が静かに彼を待っていた。錆びついた扉を押し開け、螺旋階段を上る。ドーム型の観測室の床には、月の光が差し込み、埃を銀色に染め上げていた。
床の中央。そこに、スケッチブックに描いたものと寸分違わぬ『失われた紋様』が、巨大なモザイク画として描かれていた。永い年月、誰にも知られずに、この場所で待っていたかのように。
カイは導かれるように紋様の中央に進み、光を放ち続ける『共鳴の砂時計』をそっと置いた。砂時計が台座に触れた瞬間、紋様全体が眩い光を放ち始めた。足元の床が震え、空間そのものが軋むような音が響き渡る。目の前の空間が水面のように揺らぎ、やがて星屑を散りばめたような、美しい光の扉が現れた。
扉の向こう側から、懐かしいような、それでいて未知の感覚がカイを誘う。これが、ソウルメイトのいる次元への入り口。カイは深呼吸を一つすると、期待と少しの恐れを胸に、光の中へと足を踏み入れた。
第七章 鏡像のソウルメイト
扉の向こうは、音のない、柔らかな光に満たされた無限の空間だった。そこに、一人の人物が立っていた。しかし、それはカイが想像していたような、見知らぬ魂の片割れではなかった。
そこに立っていたのは、カイ自身だった。
鏡に映したように瓜二つの姿。だが、その表情は決定的に違っていた。目の前の『彼』は、カイが今まで出会った誰の残像よりも深く、穏やかで、全てを受け入れるような慈愛に満ちた瞳で、静かにカイを見つめていた。それは、数えきれないほどの他人の愛に触れ、痛みと喜びを知り、彷徨の果てに真実を見つけた者の顔だった。
未来の自分の姿なのか。あるいは、別の次元で同じようにソウルメイトを探し求めた、もう一人の自分なのか。
『彼』は何も語らない。ただ、微笑みかけるだけだ。その微笑みが、カイの魂に直接語りかけてくる。――探していた相手は、外の世界にはいない。ずっと、君の中にいたのだ、と。
カイは悟った。『失われた紋様』は、ソウルメイトの次元への地図などではなかった。それは、他者の愛という鏡を通して、自分自身の魂の形を学び、自己の深淵へと至るための道標だったのだ。人々が夢やデジャヴュで感じていたソウルメイトの気配とは、まだ見ぬ自身の可能性、成長した未来の自分からの呼び声だったのだ。
真のソウルメイトとは、自己の最も深い場所で共鳴する、もう一人の自分。自己を完全に愛し、受け入れた先に存在する、究極の自我そのもの。
カイは光の扉を抜け、天文台へと戻った。砂時計の光は消え、紋様もただのモザイク画に戻っている。世界は何一つ変わっていない。だが、カイの世界は、もはや以前と同じではなかった。指先に宿る能力は、もはや呪いではない。それは、愛という普遍的な感情を学び、他者を、そして何より自分自身を深く愛するための、かけがえのない祝福だった。
古物店に戻ったカイは、雨上がりの街を濡らす夕陽を、穏やかな気持ちで眺めていた。もう、人に触れることを恐れない。これから出会うであろう、数多の愛の残像。その一つ一つが、彼自身をより深く形作っていくだろう。彼は、ようやく自分の人生を、その手で愛することができると知ったのだ。