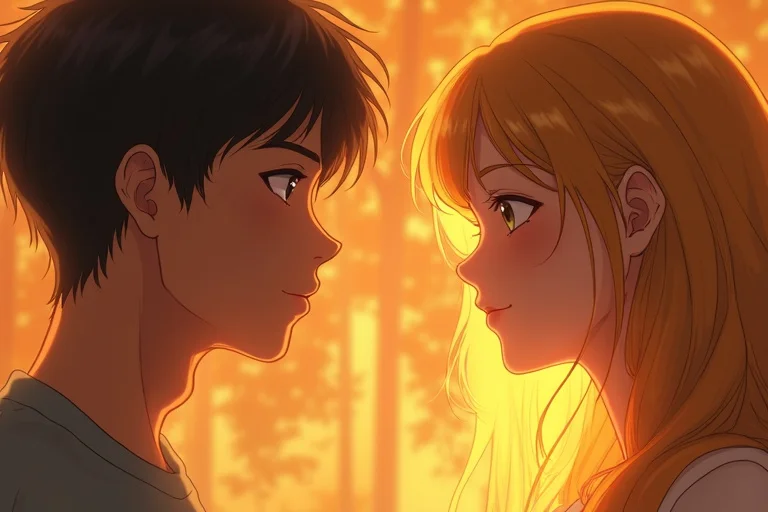第一章 琥珀の胸と薄暮の空
カイが淹れるコーヒーの香りは、いつだって街の感情の匂いよりも強かった。彼が働くカフェ『薄明』の窓から見える空は、今日もまた色褪せていた。かつてアウロラの街を彩った『エモーション・ダスト』の光は、年々その輝きを失い、今はただ、くすんだセピア色の帯が空に寂しく横たわるだけだ。人々は空を見上げるのをやめ、自分の靴先とスマートフォンの画面ばかりを見つめて歩くようになった。
「カイさん、また空を見てる」
カウンターの向こうから、リナの声がした。彼女はこのカフェの常連で、スケッチブックを片時も離さない画家だった。彼女の瞳だけが、この色褪せた街で鮮やかな光を失っていないようにカイには思えた。
「昔はもっと、すごかったんだ。喜びは黄金に、悲しみは深い藍色に空を染め上げていた」
カイは窓から目を離さずに呟いた。その声には、彼自身も気づかないほどの郷愁が滲んでいた。
「見てみたい。カイさんが見ていた空を」
リナは屈託なく笑う。その笑顔が、カイの胸を締め付けた。彼女に惹かれている。その自覚が、冷たい恐怖となって背筋を駆け上る。愛してはいけない。深く関わってはいけない。誰かを強く想うたび、自分の中から何よりも大切なものが零れ落ちていくのだから。
彼は無意識にシャツの胸元を抑えた。そこには硬い感触がある。誰にも見せたことのない、秘密の傷痕。
第二章 色褪せたワルツ
リナはカイをスケッチしたいと言い出した。断る理由を探しながらも、カイは結局、休日に彼女と公園で会う約束をしてしまった。彼女の情熱的な眼差しに、抗うことができなかったのだ。
その日は、奇跡のように空が淡い桜色の光で満たされていた。街中の恋人たちが囁き合う愛の言葉が、束の間の輝きを生んだのだろう。木漏れ日の下、リナは夢中で鉛筆を走らせ、カイはただ黙って彼女を見ていた。風が彼女の髪を揺らし、光の粒子がキラキラと舞う。時間が止まってしまえばいいと、本気で思った。
「できた」
リナが差し出したスケッチブックには、カイが見たこともないほど穏やかな顔をした自分が描かれていた。
「これが、本当のカイさんだよ」
彼女の言葉が、心の奥深くに仕舞い込んだ鍵を、いとも容易くこじ開けていく。ダメだ、と思うのに、心が彼女を求めて叫んでいた。その日、彼は生まれて初めて、自分の意志で誰かの手を握った。リナの驚いた顔と、すぐに赤らんだ頬。その全てが愛おしかった。
翌朝、カイは激しい喪失感とともに目を覚ました。昨日、何をしていた? リナと公園に行ったはずだ。だが、彼女とどんな話をしたのか、どんな表情をしていたのか、手を握った温かい感触さえも、霞がかかったように思い出せない。
震える手で胸元を探る。シャツの下、心臓のすぐそばに、また一つ。
蜂蜜色の、微かに光る小さな結晶が生まれていた。
『記憶の琥珀』。愛した記憶の墓標だ。
第三章 触れられない真実
カイはリナを避けるようになった。カフェで顔を合わせても、目を伏せ、短い言葉しか交わさない。リナは傷ついた顔をしたが、それでも毎日店にやって来た。
ある雨の日、客はリナ一人だった。彼女はカウンターに座るカイの前に、そっとスケッチブックを置いた。あの日、公園で描いた彼の肖像画だ。
「どうして、避けるの?」
「……君とは、もう会えない」
「理由を教えて。私、何かした?」
カイは言葉に詰まった。本当のことなど言えるはずがない。「君を愛するほど、君との思い出を失ってしまうんだ」なんて、狂人の戯言にしか聞こえないだろう。
彼が俯いた瞬間、リナが不意に身を乗り出し、彼の胸元にそっと触れた。シャツ越しに硬い琥珀の感触が伝わる。
「これ、なあに? 前から気になってた。たくさんある……」
その時だった。リナの指先が、一つの琥珀に強く触れた。
彼女の目が大きく見開かれる。
「え……?」
リナの瞳に、映像が流れ込んでいた。公園の木漏れ日。穏やかに笑うカイ。繋がれた手と手の温もり。それは、カイが失ったはずの、あの日の一番大切な記憶だった。
「これ……私の記憶? いいや、あなたの……?」
混乱するリナを前に、カイは血の気が引いていくのを感じた。秘密が、暴かれてしまった。
第四章 砕け散る世界の心臓
リナは逃げ出さなかった。むしろ、彼女は大学の図書館に籠り、古い文献を漁り始めた。アウロラの『エモーション・ダスト』に関する、お伽話のような伝承を。そして、一つの記述を見つけ出す。
『世界の感情は、ひとりの器に注がれ、その心臓を通して空へ還る。器が個人の愛に心を奪われる時、その愛の記憶は琥珀に封じられ、世界に還るべき光は失われる』
リナは震える手でカイにその文献を見せた。
「あなたが……『器』なの? あなたが記憶を失うのは、その愛を世界から奪っているから……? だから、光が消えていくの?」
全てが繋がった。カイが人を愛することをやめ、心を閉ざしたからではない。逆だ。彼が誰かを愛し、その記憶を琥珀として封じ込めてしまうたびに、世界の感情の総量が減っていたのだ。彼の喪失は、世界の喪失そのものだった。
カイの胸にある無数の琥珀。それは、彼がこれまでに出会い、愛し、そして忘れていった人々との記憶の結晶。その数だけ、世界は輝きを失ってきた。
その夜、アウロラの空から完全に光が消えた。エモーション・ダストの減衰は臨界点を超え、街は完全な沈黙と無感情の闇に包まれた。人々はただ虚ろに歩き、笑うことも、怒ることも忘れてしまったかのようだった。世界の心臓が、止まろうとしていた。
第五章 きみへの最後の言葉
「僕が、終わらせなければならない」
カイの瞳には、かつてないほど強い光が宿っていた。それは覚悟の光だった。
彼はリナを連れて、街で一番高い時計塔の頂上に登った。冷たい風が二人の間を吹き抜ける。眼下には、光を失い死んだように静まり返ったアウロラの街が広がっていた。
「方法があるんだ」
カイは胸元のシャツをはだけた。心臓の周りにびっしりと生まれた琥珀が、最後の力を振り絞るように微かに明滅している。
「この琥珀を、僕の全ての記憶を、解放する。そうすれば、光は戻るはずだ」
「全ての記憶って……そしたら、あなたはどうなるの!?」
リナが叫ぶ。
「僕のことも、忘れてしまうの!?」
「忘れるだろうね」
カイは静かに微笑んだ。それは、リナがスケッチブックに描いた、あの穏やかな笑顔だった。
「でも、君を愛したこの気持ちだけは、僕の中から消えない。この気持ちを、世界の光に変えるんだ。僕という個人の記憶じゃなく、誰をも照らす普遍的な愛の光に」
彼はリナの肩にそっと手を置いた。
「最後に、君の名前を呼ばせてくれ」
「リナ」
その声は、愛おしさに満ちていた。リナの頬を涙が伝う。彼女は知っていた。これが、彼が彼女を『リナ』として認識する、最後の瞬間になることを。
第六章 見知らぬ救世主
カイはリナから一歩下がり、塔の縁に立った。彼は両手を広げ、夜空を仰ぐ。そして、心の奥底から、リナへの愛を、これまで出会った全ての人への感謝を、失った記憶の奥底にある温もりを、一つ残らず呼び覚ました。
「ありがとう」
彼がそう呟いた瞬間、胸元の全ての琥珀が一斉に砕け散った。
眩いばかりの黄金の光が、カイの身体から奔流となって溢れ出す。それは一つの巨大な光の塊となり、空高く昇っていく。光はアウロラの空全体に広がり、闇を優しく払拭していった。
それは、かつてのエモーション・ダストではなかった。個人の感情が入り乱れる、喧騒で色とりどりの光ではない。ただ一つ、どこまでも静かで、温かく、全てを等しく包み込むような、白金の光。それは『愛』という概念そのものが、空に現れたかのようだった。
光が収まった時、塔の上には一人の青年が静かに佇んでいた。
彼はただ、自分がなぜここにいるのか分からない、という顔で、眼下に広がる美しい光の街を不思議そうに見つめていた。
第七章 愛だけが残る場所
数日後、リナは光を取り戻した街を歩いていた。人々は穏やかな笑顔を浮かべ、互いに親切にし、静かな幸福を享受していた。空に輝く普遍的な愛の光が、人々の心を常に温めていた。
カフェ『薄明』の前を通りかかった時、見慣れた姿が目に入った。記憶を失ったカイが、新しいオーナーに雇われ、戸惑いながらもコーヒーを淹れていた。
リナは店に入り、カウンターに座る。
「……コーヒーを、一杯」
「はい、かしこまりました」
彼は、リナを完全に見知らぬ客として扱った。その瞳には、かつての苦悩も、愛の記憶も、何も映っていない。ただ、空っぽの優しさだけがそこにあった。
コーヒーを受け取る時、リナの指先が彼の指に偶然触れた。
カイは少し驚いたように目を見開く。
「……あれ?」
彼は自分の胸をそっと押さえた。
「なんだろう。今、すごく……温かい気持ちに」
リナの目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。彼の心臓があった場所には、もう琥珀はない。けれど、彼が世界に与えた愛の痕跡は、彼の魂の最も深い場所に、温もりとして残っているのだ。
彼女は微笑んで、心の内でだけ呟いた。
(あなたのことは、私が永遠に覚えているから)
見知らぬ救世主は、今日も誰かのために、優しい香りのコーヒーを淹れている。世界は記憶を失っても、愛だけは決して忘れなかった。その愛の光の下で、リナは一人、彼との永遠の記憶を抱きしめて生きていく。