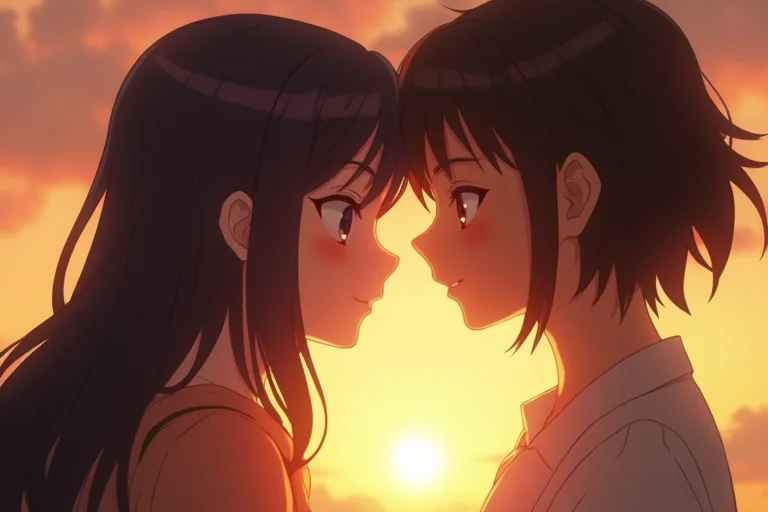第一章 甘い侵食
人混みは、情報の洪水だ。他人と肩が触れ合うだけで、その人物が今朝食べたトーストの香ばしさや、昨夜見た悪夢の残滓が、自分の感覚としてなだれ込んでくる。だから、神崎涼介は世界から身を引くようにして生きてきた。ヘッドフォンで耳を塞ぎ、常に俯き加減で歩く。それは、彼が生まれつき持つ呪いのような体質――強く心を動かされた相手と、五感を共有してしまう『感覚接続』から身を守るための、唯一の術だった。
接続は、恋に落ちた時に最も強く、永続的に発動する。一度繋がってしまえば、相手が感じる喜びも、痛みも、悲しみも、すべてがリアルタイムで涼介の心身を侵食する。それは共感などという生易しいものではない。文字通りの感覚の乗っ取りだ。過去に一度だけ経験した初恋は、相手の失恋の痛みに耐えきれず、自ら関係を断つという苦い結末に終わった。それ以来、涼介の心は固く閉ざされていた。
その日も、涼介はカフェの隅で、分厚い文庫本の世界に逃げ込んでいた。窓の外の喧騒を遮断し、物語のインクの匂いだけを静かに吸い込む。それが彼の安息だった。しかし、その平穏は唐突に破られる。トイレに立とうとした瞬間、横から飛び出してきた誰かと、鈍い音を立ててぶつかった。
「あっ、ごめんなさい!」
快活な、鈴が鳴るような声。顔を上げると、大きな瞳を驚きに見開いた女性が立っていた。彼女の手から滑り落ちたプラスチックカップが床を転がり、甘ったるい香りがふわりと立ち上る。
その瞬間だった。涼介の口内に、濃厚なキャラメルの甘さと、エスプレッソのほろ苦さが、まるで自分が飲んだかのように鮮明に広がった。全身の血が逆流するような感覚。嘘だ、と心が叫ぶ。だが、鼻腔をくすぐるホイップクリームの乳製品の匂いと、後味に残る微かなシナモンの風味は、紛れもない現実だった。
「大丈夫ですか? お怪我は…」
心配そうにこちらを覗き込む彼女の瞳。その奥に灯る、純粋な光に射抜かれた瞬間、涼介は悟った。最悪だ。また、誰かと接続してしまった。この、目の前の女性に、恋をしてしまったのだ。
彼女――後に陽菜と名乗った――が屈託なく笑うたび、涼介の胸には春の日だまりのような温かさが広がった。彼女が慌てて新しいコーヒーを買いに走る背中を見送りながら、涼介は口の中に残るキャラメルマキアートの甘い味に、これから始まるであろう地獄を予感し、静かに唇を噛み締めた。
第二章 共有された色彩
陽菜との接続は、涼介の孤独な日常を根底から揺さぶった。彼は陽菜から逃げようとした。カフェで会ったきり、二度と関わるまいと決めた。しかし、感覚のリンクは無慈悲なほど強固だった。
ある日の午後、自室で本を読んでいた涼介は、突然、指先に鋭い痛みを感じて飛び上がった。見れば自分の指は何ともない。だが、痛みは本物だ。心臓が跳ね、まさかと思う。数秒後、痛みに混じって、微かな消毒液の匂いと、絆創膏の粘着テープが肌に触れる感触が伝わってきた。陽菜がどこかで指を切ったのだ。涼介は自分の指をさすりながら、見えぬ彼女の安否を気遣うしかなかった。
しかし、伝わってくるのは痛みだけではない。晴れた日に公園のベンチに座っている時の、頬を撫でる風の心地よさ。画材店で新しい絵筆を手にした時の、高揚感と木の香り。彼女は絵を描くのが趣味らしく、涼介はしばしば、キャンバスに油絵の具が塗り込められていく重厚な感触や、テレピン油のツンとした刺激臭を体験した。
それは、涼介にとって未知の世界だった。灰色だった彼の日常は、陽菜の感覚を通して、鮮やかな色彩を帯び始めた。彼女が見る夕焼けの燃えるような赤、彼女が聴く雨音の優しいリズム、彼女が味わう手作りクッキーの素朴な甘さ。それらはすべて、涼介自身の体験となった。彼はいつしか、この感覚共有を罰ではなく、贈り物のように感じ始めていた。
意を決して、涼介は陽菜がよく利用するという画材店で「偶然」を装って再会した。
「あ、この間の!」
陽菜は涼介を覚えていて、人懐っこく笑った。涼介は、自分の心臓の鼓動が、彼女にも伝わってしまうのではないかと錯覚するほど高鳴るのを感じた。
二人は少しずつ言葉を交わすようになった。涼介は自分の体質のことをひた隠しにしながら、彼女の心の機微を驚くほど正確に読み取ることができた。彼女が口に出せないでいる迷いや、隠している小さな喜びを、まるで自分のことのように感じ取れたからだ。
「どうしてそんなに分かるの?」
陽菜は不思議そうに首を傾げる。涼介はただ、「君を見ていれば、なんとなく」と曖昧に笑うだけだった。
陽菜の隣にいる時間は、奇跡のようだった。共有される感覚は、二人の間に言葉以上の親密さを生んだ。彼女が笑えば、涼介も心から楽しくなった。彼女が悲しい映画を観て泣けば、彼の頬にも理由の分からない涙が伝った。自己と他者の境界線が溶けていくような、甘美で危険な一体感。涼介は、このまま陽菜という存在に溺れてしまってもいいとさえ思い始めていた。
第三章 不在の共鳴者
季節は巡り、二人は初めてのデートの約束をした。海が見える美術館。それは、涼介が提案し、陽菜が心から喜んだ場所だった。その日、涼介が感じたのは、純粋な幸福感だけだった。陽菜が隣で作品に見入る横顔。潮風に揺れる彼女の髪の匂い。二人で食べたジェラートのピスタチオの味。すべてが輝いていて、完璧だった。涼介は、この感覚共有という体質に、初めて心から感謝した。
その夜、自室のベッドで幸福の余韻に浸っていた涼介を、凄まじい苦痛が襲った。
「ぐっ…ぁ…!」
まるで全身の骨が軋むような、内側から引き裂かれるような激痛。呼吸ができない。これは陽菜の痛みじゃない。今日の彼女は、あんなにも幸せそうだった。それに、この痛みには覚えがない。それは絶望の色をしていた。光の一切ない、暗く冷たい、底なしの苦しみ。
涼介はパニックに陥った。これは誰の感覚だ? 接続が混線しているのか? それとも、自分の知らないところで、陽菜がとんでもない事故にでも遭ったのか? 彼は震える手でスマートフォンを掴み、陽菜に電話をかけた。
数コールの後、彼女は眠そうな声で電話に出た。
「もしもし、涼介くん? どうかしたの?」
その声は、平穏そのものだった。涼介は混乱しながらも、彼女が無事であることに安堵する。だが、それならこの痛みは一体何なのだ。
翌日、涼介は真実を探るために動き出した。昨夜の痛みの質感を頼りに、彼は一つの可能性に行き着く。長期入院患者、特に意識のない患者が抱える苦痛に似ているのではないか。彼は、陽菜のSNSや過去の会話の断片を必死で繋ぎ合わせ、一つの名前を見つけ出した。―――『高槻 湊(たかつき みなと)』。
湊は、陽菜の幼馴染だった。そして、彼は二年前に交通事故に遭い、以来、意識不明のまま病院のベッドで眠り続けている。
涼介は、湊が入院している病院を突き止め、病室の前に立った。ガラス窓の向こう、生命維持装置に繋がれた青年が静かに横たわっている。その姿を見た瞬間、涼介はすべてを理解した。昨夜の絶望的な痛みは、彼、湊のものだったのだ。
涼介が接続したのは、陽菜ではなかった。
正確に言えば、陽菜もまた、涼介と同じ『感覚接続』の体質者だったのだ。彼女は、意識不明の幼馴染、湊とずっと接続していた。彼の痛みや孤独を、二年もの間、たった一人で受け止め続けていた。
そして、涼介が陽菜に恋をしたあの日。涼介の恋心は、陽菜というフィルターを通して、ベッドの上で意識なく眠る湊の魂に届いた。涼介が感じていた陽菜との一体感、彼女の豊かな感受性、絵を描く喜び――それらは、湊が陽菜の身体を通して感じた、外部世界との久しぶりの繋がりに対する歓喜だったのだ。涼介が恋に落ちた相手は、陽菜の瞳を通してこちらを見ていた、不在の共鳴者、湊だった。
涼介は病室のガラスに額をつけ、その場に崩れ落ちた。自分が愛した感情は、一体誰のものだったのか。口の中に、あの日のキャラメルマキアートの味が、今はただ苦く、空虚に広がった。
第四章 三つの孤独、一つの和音
茫然自失のまま、涼介は陽菜に会った。いつもの公園のベンチで、彼は自分の体質のこと、そして湊の病室へ行ったことを、途切れ途切れに告白した。
陽菜は驚きもせず、ただ静かに聞いていた。やがて彼女の大きな瞳から、ぽろぽろと涙がこぼれ落ちた。涼介の舌に、その涙のしょっぱい味がじわりと染みる。
「気づいてたんだね」
陽菜は、自分が湊と接続していることを打ち明けた。彼女にとって湊は、恋愛対象ではなく、守るべき家族であり、半身だった。湊の意識が失われてから、彼女の世界もまた半分、色を失っていた。彼の孤独を共有し続けることは、彼女にとって贖罪にも似た行為だった。
「涼介くんと会って、湊が、喜んでいるのが分かったの」
陽菜は言った。
「あなたの感じること、考えていることが、私を通して湊に伝わって、彼の世界に光が差したみたいだった。絵を描くのがあんなに楽しくなったのも、湊があなたの感性を通して、もう一度世界を見ていたからなんだと思う」
涼介が恋したのは、陽菜の肉体と、湊の魂が織りなす、奇跡のようなキメラだったのだ。それは残酷な真実であると同時に、不思議な救いでもあった。自分は、誰からも理解されない孤独を抱えて生きてきた。陽菜も、湊も同じだった。三つの孤独な魂が、図らずも互いを見つけ、共鳴し合っていた。
「俺は、どうすればいい?」
涼介の声は震えていた。
陽菜は、そっと涼介の手に自分の手を重ねた。その瞬間、三人の感覚が、奔流のように涼介の中に流れ込んできた。
陽菜の、安堵と切なさが入り混じった温もり。
湊の、暗闇の中に灯った小さな蝋燭のような、微かで、しかし確かな喜びの感情。
そして、涼介自身の、戸惑いながらも、そのすべてを受け入れようとする、静かな決意。
それは、もはや単なる感覚共有ではなかった。それは、言葉になる前の感情が溶け合い、響き合う、美しい和音のようだった。
それから、涼介の日常は変わった。彼はもう、人との接触を闇雲に恐れたりはしない。週に数度、陽菜と共に湊の病室を訪れる。陽菜が湊の手に触れると、涼介は三人分の体温を感じる。涼介が窓の外の景色を陽菜に語って聞かせると、湊の側から、穏やかな満足感が伝わってくる。
愛とは、誰か一人を独占することではないのかもしれない。それは、対象が誰であれ、その魂の在り方を、痛みも、過去も、不在さえも丸ごと受け入れることではないか。涼介はそう思うようになった。
ある晴れた日の午後、涼介は病室の窓辺に立ち、目を閉じた。鼻腔に、陽菜が病室に飾ったフリージアの甘い香りが満ちる。指先には、陽菜がスケッチブックをめくる紙の乾いた感触。そして、その奥にかすかに、湊の指がほんの少しだけ動いたような、気のせいかもしれない微かな感覚。
三つの孤独が寄り添って生まれた、一つの静かな世界。涼介は、その複雑で、切なくて、どうしようもなく愛おしいハーモニーを、ただ静かに味わっていた。口の中に広がるのは、キャラメルマキアートの甘さではなく、もっと深く、名付けようのない、優しい味だった。