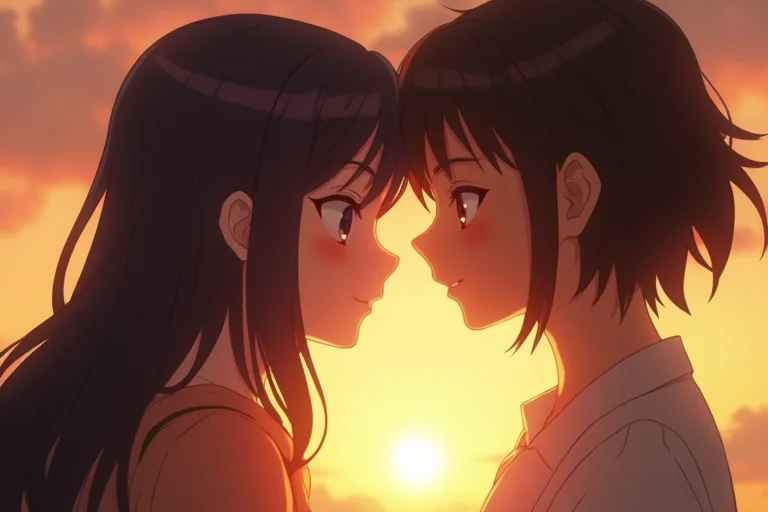第一章 透ける指先
この世界で恋に落ちることは、緩やかな自殺に他ならない。そんな冷笑が、いつからか人々の心の通奏低音になっていた。愛は寿命を交換する。その均衡が崩れれば、どちらかが一方的に命を吸われ、あるいは二人ともが急速に枯渇する「愛枯病」という名の呪いが待っている。だからこそ、人々は心を覆い、形式的な関係に安住した。
僕、カイにとって、そんな世界の法則はどうでもよかった。リヒトという、ただ一人の存在が僕の世界のすべてだったからだ。彼が笑えば、灰色の街にさえ淡い色彩が宿る。彼が僕の名を呼べば、凍てついた心臓が微かに熱を帯びる。
カフェの窓辺、午後の柔らかな光がリヒトの亜麻色の髪を透かしていた。彼が話す他愛もない冗談に相槌を打ちながら、僕は自分の右手をそっとテーブルの下に隠した。指先が、まるで薄い氷砂糖のように、向こう側の景色をぼんやりと映していたからだ。
誰かに心から恋をすると、己の寿命が物理的に相手へと流れ込む。僕の体に起きたこの現象は、その証だった。周囲の人間には、僕の存在が徐々に希薄になっていくのが見えるらしい。カフェの店員が僕を見る目に浮かぶ、憐れみと恐れの混じった感情がそれを物語っていた。けれど、不思議なことに僕自身には、その変化をはっきりと自覚できなかった。ただ、リヒトの隣にいる幸福感だけが、現実のすべてだった。
「どうした、カイ? 顔色が悪いぞ」
リヒトが心配そうに僕の顔を覗き込む。彼の瞳には、僕の知らない深い影が揺れていた。彼の体もまた、ところどころが薄く透けている。僕の愛が、彼の失われた寿命を補い始めているのだ。そう信じていた。この透ける指先は、彼を救うための尊い代償なのだと。
「なんでもない。君がここにいるだけで、僕は満たされるから」
そう言って微笑むと、リヒトは一瞬だけ、痛みに耐えるように顔を歪めた。
第二章 不協和の腕輪
生まれた時に誰もが与えられる『共鳴の腕輪』。そこには、個人の余命が結晶化した複雑な紋様が刻まれている。僕の左手首にはめられた銀の腕輪は、リヒトへの恋心を自覚して以来、その繊細な紋様を日々薄れさせていた。まるで、降り積もった雪が陽光に溶かされていくように、静かに、しかし確実に。
それは、僕の命がリヒトに捧げられている証。僕はその事実を受け入れていた。だが、不可解なのはリヒトの腕輪だった。
ある日、彼の部屋で画材の準備をしていると、机の上に無造備に置かれた彼の腕輪が目に入った。透けた体を持つ彼の腕輪は、僕と同じように紋様が薄れているはずだった。しかし、そこに刻まれた紋様は、奇妙なことに濃淡を不規則に繰り返していた。ある部分は深く、鮮やかに。ある部分は掠れて、消え入りそうに。まるで、満ち引きを繰り返す不安定な潮のようだ。
「…なぜ、君は癒されないんだ?」
僕の愛は、確かに彼に注がれているはずなのに。彼の体の透け具合は一向に改善されず、むしろその顔には深い疲労の色が刻まれていく。僕の命は、どこか別の場所へ流れてしまっているのだろうか。
街角で囁かれる「愛枯病」の噂が、冷たい霧のように心を覆い始める。愛し合う二人の寿命を、互いに喰らい尽くすという呪われた病。まさか、僕たちの愛が、その呪いに蝕まれているというのか? 僕の愛が、リヒトを苦しめているというのか?
疑念が黒い染みとなって、純粋だったはずの想いを汚していく。
第三章 朽ちる肖像
僕は画家だ。僕にとって描くことは、祈りに近い行為だった。アトリエのイーゼルには、描きかけのリヒトの肖像画が立てかけてある。カンバスの中の彼は、僕が焦がれる、生命力に満ちた姿で微笑んでいた。一筆ごとに愛を込める。僕の命を、絵の具に溶かして塗り重ねていく。
しかし、皮肉なことに、肖像画の彼の頬に血色が戻るたび、現実のリヒトはますます生気を失っていった。彼の咳は深くなり、歩く姿は老人のように覚束ない。
その夜、アトリエを訪れたリヒトが、僕に背を向けて何か小さな包みを呷るのを見てしまった。床に転がったのは、特殊な薬の空き瓶。寿命の急激な消耗を、一時的に緩和するための高価な薬だ。
僕は、彼の肩を掴んで問い詰めた。
「どうしてだ! なぜなんだ、リヒト!」
「僕の愛は、君を蝕んでいるのか? これは『愛枯病』なのか!」
振り向いたリヒトの顔は、僕の知らない男の顔だった。頬はこけ、目元には深い皺が刻まれている。彼は、僕の手をそっと振り払うと、力なく笑った。
「お前の愛は温かいよ、カイ。太陽みたいに…。ただ、少しだけ、強すぎるだけさ」
その答えは、答えになっていなかった。彼の瞳の奥に広がる闇は、僕の愛ですら照らせないほど、深く、昏かった。
第四章 秘められた温室
リヒトの言葉を信じることはできなかった。彼の嘘を見抜けないほど、僕は愚かではない。翌日、僕はアトリエを抜け出し、彼の後を追った。僕の胸を締め付ける、この得体の知れない不安の正体を突き止めるために。
リヒトが向かったのは、街の外れにある古びた療養施設だった。かつては富裕層が静養に使っていたというその場所は、今は訪れる者も少なく、静寂に包まれている。彼が建物の裏手へ回り込むのを、僕は息を殺して見守った。
その先にあったのは、忘れ去られたように佇むガラス張りの温室だった。蔦の絡まる鉄の扉を開け、リヒトは中へ消えていく。僕は数分待ってから、そっとその後を追った。
温室の中は、甘い花の香りと湿った土の匂いで満ちていた。色とりどりの花々が咲き乱れ、天井のガラスからは柔らかな陽光が降り注いでいる。その中央に置かれたベッドに、一人の少女が眠っていた。
純白のドレスを纏い、穏やかな寝息を立てる少女。その体は、僕やリヒトとは対照的に、一点の曇りもなく、生命の輝きに満ちている。
そして、僕は息を呑んだ。
その顔に見覚えがあった。何年も前、まだ幼かった頃、祭りの日に一度だけすれ違い、その可憐さに一瞬で心を奪われた少女。僕の、淡く儚い『初恋の相手』。
その瞬間、僕の足元から世界が崩れ落ちていくような感覚に襲われた。僕が捧げ続けてきた寿命は、リヒトを通り抜け、この少女へと流れ込んでいたのだ。リヒトの腕輪の紋様が不規則に濃淡を繰り返していたのは、僕からの寿命が流れ込む一方で、この少女からの微弱な感謝の念――それもまた愛の一種だ――が還流していたからに他ならない。
僕の愛は、リヒトを救ってはいなかった。彼を、ただの管(くだ)にしていただけだったのだ。
第五章 愛枯の代償
「…エルマ。僕の、たった一人の妹だ」
僕の背後に、いつの間にかリヒトが立っていた。彼の声は、枯れ葉が擦れるようにかさついていた。
彼は全てを語り始めた。数年前、エルマには恋人がいたこと。二人は深く愛し合ったがゆえに、最も残酷な病である「愛枯病」に罹患したこと。恋人は先に命尽き、エルマもまた死の淵を彷徨ったこと。
「僕は、エルマに生きてほしかった。そのためなら、何でもするつもりだった」
リヒトは、禁じられた古の秘術に手を出した。愛の呪いを、自らの身に引き受ける儀式。彼はエルマの代わりに「愛枯病」の進行を引き受け、彼女の命を繋ぎ止めた。だが、それは彼の寿命を猛烈な速さで削り取る、悪魔との契約にも等しかった。
そこへ現れたのが、僕だった。リヒトに向けられた、僕の純粋で、強大で、一方的な愛。リヒトは、その愛を利用した。僕の寿命を、自らをフィルターとしてエルマへと流し、彼女の命を養うための「燃料」としたのだ。彼が急速に老いていったのは、そのフィルターとなる代償だった。
「お前の愛に救われたのは、エルマだ。僕は、お前を騙した…利用したんだ。許してくれとは、言わない」
彼の髪はほとんど白くなり、かつての面影はどこにもなかった。罪悪感と、妹への愛と、そして僕への僅かな友情が、その深い皺に刻まれている。
残酷な真実だった。僕は親友に裏切られた。だがそれ以上に、僕が無意識のうちに、初恋の相手の命を救い続けていたという事実が、心を締め付けた。この愛の連鎖は、あまりにも歪で、そしてあまりにも、純粋だった。
第六章 最後の色彩
アトリエに戻った僕は、イーゼルの前に立った。描きかけのリヒトの肖像画。そこにはまだ、僕が愛した彼の姿が残っている。
僕は、パレットに新しい絵の具を絞り出した。赤、青、黄。命の色。
決意は、とうに固まっていた。
リヒトの犠牲も、エルマへの想いも、僕の初恋も、そしてこの裏切りさえも。すべてを僕が引き受ける。この歪な愛の鎖を完成させるのが、僕の役目なのだ。
筆を握る。僕の指先は、もうほとんど見えなかった。右腕が、胸が、足が、次々と透明になっていく。体の芯から熱が奪われ、存在そのものが希薄になっていく感覚。それでも、僕は笑っていた。初めて、自分の愛の行き着く先を、その意味を、はっきりと理解できたからだ。
「リヒト、君は間違ってなんかいなかったよ」
最後の一筆を、カンバスに置く。それは、肖像画のリヒトの瞳に、生命の輝きを灯すための、光の一点だった。
その瞬間、僕の体は無数の光の粒子となって、アトリエの空間に溶けていった。左手首から滑り落ちた『共鳴の腕輪』が、カラン、と乾いた音を立てる。その紋様は、完全に消え失せていた。
――遠く離れた温室で、エルマが長い眠りから静かに目を覚ます。傍らには、急速な老化が嘘のように止まり、穏やかな寝顔になったリヒトが眠っていた。
目覚めた少女の瞳に映る世界は、どんな色をしているのだろう。誰かの命を糧に得た未来を、彼女はどう生きていくのだろう。究極の愛の果てにあるのは、救済か、それとも新たな悲劇の始まりか。
その答えは、もう誰にも分からない。ただ、アトリエには一枚の肖像画だけが、永遠の愛の証として、静かに残されていた。