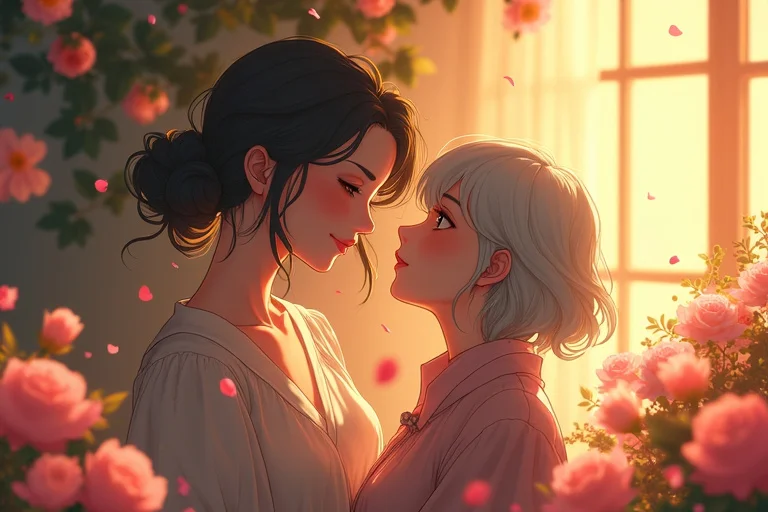第一章 透ける小指と彼女の栞
僕、水野蒼(みずの あお)には秘密がある。それは、僕の左手の小指が、時折、光にかざしたガラス細工のように透けることだ。世界で稀に報告される奇病、「進行性自我希薄化症候群」――通称「透光症候群」。強い情動、特に恋愛感情を抱くと、身体が分子レベルで崩壊し、徐々に透明になって存在が消滅していくという、まるで出来の悪いSF小説のような病。治療法はない。
だから僕は、心を波立たせるものすべてから距離を置いて生きてきた。図書館の司書という仕事は、そんな僕にうってつけだった。静寂と古書の匂いに満たされたこの場所では、感情は緩やかに流れ、世界との間に心地よい一枚の膜を隔ててくれる。僕は本を修復し、分類し、貸し出す。物語の世界に没入することはあっても、現実の誰かに心を揺さぶられることはない。そう、彼女に出会うまでは。
彼女――陽菜(ひな)は、週に二、三度、閉館間際にやってくる。いつも植物図鑑や園芸の本が並ぶ棚へ直行し、真剣な眼差しで数冊を選んでは、カウンターに持ってくるのだ。陽の光を吸い込んだような明るい髪、笑うと少しだけ下がる眉、そして何より、植物について語るときの、きらきらと輝く瞳。僕は、彼女がカウンターに来るたびに、心臓のあたりが不自然に熱を帯びるのを感じていた。そしてその夜には決まって、左手の小指の透明度が増すのだった。
危険信号だ。このままではいけない。僕は彼女に対して意識的に壁を作り、業務的な対応に徹した。しかし、運命とは意地の悪い脚本家らしい。
ある雨の日、彼女が借りた本の間から、一枚の栞がはらりと落ちた。押し花であしらわれた、可憐な忘れな草の栞だった。
「あ……」
僕が拾い上げようとするより先に、彼女が手を伸ばした。その瞬間、僕らの指先が、ほんのわずかに触れ合った。温かかった。まるで、小さな太陽に触れたような熱が、指先から全身へと駆け巡る。僕は慌てて手を引いた。
「すみません」
「ううん、ありがとう」
彼女は屈託なく笑い、栞を受け取った。「この花、好きなの。花言葉、知ってる?」
僕は首を横に振る。
「『私を忘れないで』。それと、『真実の愛』」
彼女はそう言って、悪戯っぽく片目をつむいだ。その瞬間、僕の視界の端で、左手の小指が、今までで最も鮮明に、向こう側の景色を映し出した。僕は恐怖に駆られ、血の気が引くのを感じながら、彼女の顔をまともに見ることができなかった。この感情は、僕の存在を蝕む毒なのだ。
第二章 ガラス越しの植物園
陽菜を避け始めて一週間が経った。彼女が図書館に来る時間になると、僕はわざと書庫整理に没頭し、他の職員にカウンターを任せた。自己嫌悪と安堵が入り混じった奇妙な感情に、胸が締め付けられる。僕の小指は、幸いにも元の不透明さを取り戻しつつあった。このまま、また静かな日常に戻ればいい。そう願っていた。
しかし、その願いは脆くも崩れ去った。閉館作業を終えて図書館の裏口から出ると、彼女が立っていたのだ。夕暮れの淡い光の中で、少し心細そうに。
「水野さん」
僕の名前を呼ぶ声に、心臓が跳ねる。無視して通り過ぎることもできたはずなのに、僕の足はコンクリートに縫い付けられたように動かなかった。
「どうして、避けるの?」
まっすぐな瞳が僕を射抜く。僕は言葉に詰まった。本当のことなど、言えるはずがない。
「……忙しかっただけです」
我ながら、ひどく冷たい声が出たと思う。彼女は悲しそうに眉を寄せたが、すぐにふっと微笑んだ。「そっか。よかった」
そして、一枚のチケットを僕に差し出した。「よかったら、これ。私が働いてる植物園の招待券。今、夜間開園してて、すごく綺麗なの。……忙しくない日に、来てくれたら嬉しいな」
断るべきだった。僕の理性はそう叫んでいた。だが、彼女の寂しげな笑顔を前にして、僕の口が発したのは、自分でも信じられない言葉だった。
「……いつ、行けばいいですか」
週末、僕は陽菜と植物園のガラス張りの大温室にいた。むっとするほど湿った空気、青々とした葉の匂い、そして見たこともないような極彩色の花々。天井から吊るされたランが優雅に揺れ、夜の闇を背景にライトアップされた熱帯植物は、まるで異世界の生き物のように妖しく輝いていた。
「この『月下美人』、一晩しか咲かないの。見られてラッキーだよ」
陽菜は僕の手を引き、白い大輪の花の前まで導いた。甘く、それでいてどこか儚い香りが僕らを包む。彼女は本当に楽しそうに、一つ一つの植物の物語を語ってくれた。その横顔を見ていると、僕の胸を満たしていた恐怖や警戒心が、温かい湯に溶けていくようだった。
「水野さんは、どうして図書館の司書になったの?」
帰り道、並んで歩きながら彼女が尋ねた。
「……静かな場所が好きだから」
「そっか。私は逆だな。植物って静かに見えるけど、本当はすごく賑やかなの。水を吸い上げる音、葉が光を求めるざわめき、花が開く瞬間の息遣い。そういう声を聞いてるのが好き」
彼女の言葉は、僕が知らなかった世界の扉を開けてくれるようだった。もっと彼女の話が聞きたい。もっと、彼女のことを知りたい。その思いが、堰を切ったように溢れ出してくる。
その夜、自室の鏡に映った自分の姿に、僕は息を呑んだ。左手は、手首の近くまでが淡く透き通り、まるで幽霊のようになっていた。心臓を鷲掴みにされるような恐怖。陽菜と過ごした幸福な時間の代償は、あまりにも大きかった。愛してはいけない。この想いは、僕自身を消滅させる呪いだ。僕は震える手で携帯電話を握りしめ、彼女からの「今日はありがとう。また会いたいな」というメッセージを、ただ見つめることしかできなかった。
第三章 二つの透明な手
それから、僕は再び陽菜を徹底的に避けるようになった。図書館では視線を合わせず、彼女からの連絡には一切応じなかった。僕の心は罪悪感で張り裂けそうだったが、これ以上自分の身体が透けていく恐怖には耐えられなかった。存在が消えることは、死ぬことよりも恐ろしい。陽菜という光が強ければ強いほど、僕という影は薄れていくのだ。
そんなある嵐の夜、アパートのドアを激しく叩く音が響いた。びしょ濡れになった陽菜が、そこに立っていた。
「どうして! どうして何も言ってくれないの! 私、何か悪いことした?」
彼女の瞳からは、大粒の涙が雨粒と一緒になって頬を伝っていた。その悲痛な表情に、僕の心の壁は粉々に砕け散った。
「中に入って……風邪をひく」
部屋に入れたものの、かける言葉が見つからない。タオルを渡す僕の手が、自分でも分かるほど震えていた。
「ごめん……。僕のせいだ」
僕はもう、隠し通すことなどできないと悟った。観念して、照明の光に自分の左手をかざしてみせた。透けた指先が、壁紙の模様をぼんやりと映している。
「僕は、病気なんだ。『透光症候群』っていう……。誰かを、特に君のような人を強く想うと、身体がこうやって消えていってしまう。だから、君とは一緒にいられないんだ。君を愛せば愛するほど、僕は……僕でなくなってしまう」
嗚咽が漏れた。情けなくて、惨めで、どうしようもなかった。これで終わりだ。彼女は僕を化け物だと思って、逃げていくだろう。それでいい。それが正しいのだ。
沈黙が部屋を支配する。陽菜は驚いたように目を見開いたまま、僕の透けた手を見つめていた。やがて、彼女はゆっくりと顔を上げた。その表情に、僕が予想した恐怖や嫌悪の色はなかった。むしろ、それは深い、深い哀れみと、そしてどこか安堵したような、不思議な色を湛えていた。
彼女は何も言わずに、濡れたカーディガンの右腕の袖を、静かにまくり上げた。
そして、僕は信じられない光景を目の当たりにした。
彼女の右腕は、手首から先が、存在しなかった。いや、違う。存在しないのではない。そこは、僕の左手よりもさらに透明度を増し、まるでクリスタルのように、向こう側の景色を完全に映し出していたのだ。
「……私も、同じなの」
陽菜は、泣き笑いのような、美しい笑顔で言った。
「ずっと一人だと思ってた。この苦しみを分かってくれる人なんて、どこにもいないって。……水野さんに出会う前ね、私にも、すごく好きな人がいたの。その人を想うたびに、私の手は少しずつ透明になって……最後には、こうなった。彼は、私のこの手を怖がって、去っていったわ」
衝撃で、頭が真っ白になった。彼女も? この太陽のような女性が、僕と同じ闇を、孤独を抱えて生きてきたというのか。彼女が植物の静かな賑わいを愛するのは、命の儚さと、それでも懸命に生きようとする力強さに、自分を重ねていたからなのかもしれない。
僕の胸に、嫉妬と、そしてそれ以上に強烈な愛しさが、嵐のように吹き荒れた。僕らは同じ痛みを抱えた、世界のたった二人の共犯者だったのだ。
僕は無意識のうちに、彼女の透明な右手を取っていた。触れているはずなのに、そこには確かな感触がない。ただ、心の奥深くで、彼女の魂の温かさが伝わってくるような気がした。
第四章 夕映えに溶ける影
僕たちは、残された時間を共に生きることを選んだ。互いの身体が日に日に透けていくことを、恐怖ではなく、愛の証として受け入れることにしたのだ。それは、終わりに向かって加速していく、切なくも輝かしい日々だった。
「消えるまでにしておきたいことリスト」を、二人で作った。拙い文字で書き連ねたささやかな願い。海を見に行く、一緒に料理をする、夜通し語り合う、日の出を見る。僕たちは、その一つ一つを、まるで宝物のように慈しみながら実行していった。
僕の身体は、もう胸のあたりまでが光の輪郭だけになっていた。食事をしても、味はほとんど感じない。けれど、陽菜が「おいしいね」と笑う顔を見るだけで、心が満たされた。僕の存在は希薄になっていくのに、僕の世界は、かつてないほど色鮮やかで、意味に満ちていた。消えることは、もう怖くなかった。陽菜と出会えなかった人生を、空っぽのまま生き永らえることの方が、よほど恐ろしい。
リストの最後の一つ、「一緒に夕日を見る」を叶えるために、僕たちは海辺に来ていた。砂浜に座り、寄り添う。陽菜の身体も、足元から淡く透け始めている。空と海を茜色に染めながら、巨大な太陽がゆっくりと水平線に沈んでいく。潮風が、僕らの実体のない身体を通り抜けていくようだった。
「ねえ、蒼くん」陽菜が僕の肩に頭を預けて囁く。「怖くない?」
「怖くないよ」僕は、ほとんど輪郭だけになった腕で、彼女をそっと抱きしめた。「君といれば、何も」
真実だった。この腕に陽菜の温もりを感じることはもうできなくても、僕の魂は、確かに彼女の魂に触れていた。
「見て」彼女が、僕たちの足元を指さした。「私たちの影、一つになってる」
夕日に長く伸びた影は、砂の上で、くっきりと一つに重なっていた。僕らの身体が光に溶けていくとしても、僕らがここにいたという証は、この世界に確かに刻まれている。愛とは、存在を賭してでも求める価値のある、唯一の光なのだと知った。
「陽菜……愛してる」
言葉が、音になったかどうかは分からない。けれど、彼女には伝わったはずだ。彼女の笑顔が、夕日の中で淡く滲む。
僕の意識が、ゆっくりと光の中に拡散していく。最後に感じたのは、絶望的な喪失感ではなく、すべてを包み込むような、穏やかで満ち足りた幸福感だった。僕らは、世界で最も美しい光になるために、溶けていくのだ。僕と彼女の愛という、ただ一つの光に。