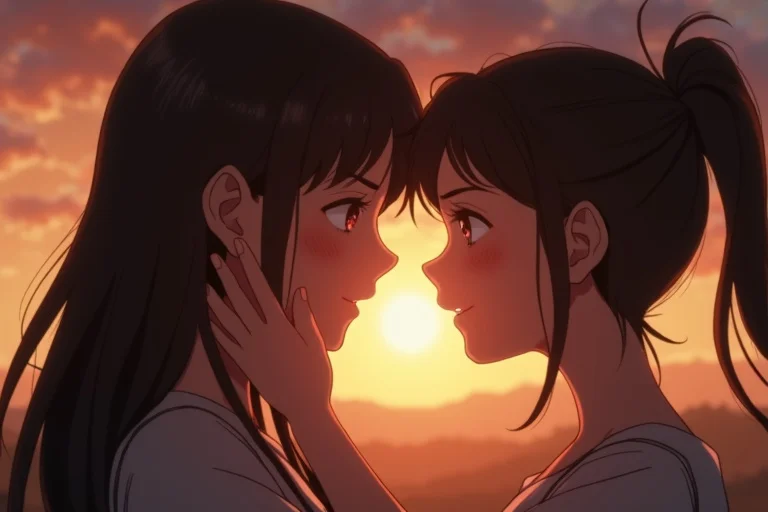第一章 無色の男
私の世界は、常に色彩で飽和している。それは絵の具をぶちまけたパレットのように、猥雑で、時に美しく、そして絶え間なく感情の色が渦巻いている。幼い頃から私、水野楓には、人の「恋心」が色として見えた。カフェのカウンターに立つ私の目には、向かい合って微笑むカップルの周りに浮かぶ、熟した果実のような情熱的な赤色や、注文を待つ列で、そっと憧れの先輩を見つめる大学生の淡い桜色が見える。失恋したばかりの友人を慰める女性の肩には、寄り添うようにして滲む、悲しみを帯びた空色の光。
この能力は、祝福であると同時に呪いでもあった。他人の秘めた想いが手に取るようにわかるせいで、私は人間関係に臆病になった。言葉の裏にある鮮烈な色に気疲れし、いつしか自分の感情に蓋をするようになった。自分の心だけは、なぜかいつも無色透明だったからだ。まるで、私自身には感情という絵の具が与えられていないかのように。
そんな私の灰色の日常に、唯一、安らぎを与えてくれる存在がいた。週に三度、決まって午後二時にやってくる、桐谷陽という男性。彼はいつも窓際の一番奥の席に座り、文庫本を広げて静かにコーヒーを飲む。彼が特別なのは、その周囲に一切の「色」が見えないことだった。誰かに恋をしているわけでも、誰かから想いを寄せられているわけでもない。彼の周りだけ、世界の色彩がふっと途切れているかのように、穏やかな無色が広がっている。
その透明感は、私にとって救いだった。感情の洪水から身を守るための、小さな避難所。だから私は、彼が店に入ってくるときのドアベルの音を、いつも心待ちにしていた。
「いつものブレンドでよろしいですか?」
「はい、お願いします」
彼の声は、彼の佇まいと同じく、静かで落ち着いていた。私は手際よくコーヒーを淹れながら、横目で彼の姿を盗み見る。陽の光が彼の黒髪を柔らかく照らし、真剣な眼差しが本のページを滑っていく。その無色透明な世界に、私は知らず知らずのうちに惹きつけられていた。この人となら、色のない、ただの言葉と心だけで繋がれるのかもしれない。そんな淡い期待が、モノクロームだった私の心に、ほんのりと熱を灯し始めていた。だが、その熱が何色なのか、私自身には知る術がなかった。
第二章 色彩の欠片
桐谷さんと話すようになって、数ヶ月が経った。きっかけは、彼が読んでいた本だった。私が好きな作家の、あまり知られていない初期の作品。思わず「その本、面白いですよね」と声をかけると、彼は少し驚いたように顔を上げ、そして穏やかに微笑んだ。
「ご存知なんですか。嬉しいな」
それから、私たちは少しずつ言葉を交わすようになった。好きな本のジャンル、コーヒーの好み、休日の過ごし方。彼の言葉はいつも誠実で、私の言葉にじっと耳を傾けてくれる。彼の周りには相変わらず色は見えない。だからこそ、私は安心して心を開くことができた。彼の前では、私はただの「水野楓」でいられた。人の感情の色を読み解く能力者ではなく、一人の人間として。
店が混み合っている日、カウンターで作業をする私の耳に、すぐ近くの席の会話が飛び込んできた。
「……だから、もう無理だって言ってるの!」
ヒステリックな女性の声と共に、目の覚めるような、怒りと悲しみが混じった紫色のオーラが立ち上る。対する男性の周りには、困惑と未練を示す濁った緑色が揺らめいていた。私は思わず眉をひそめ、気分が悪くなるのを感じた。
その時、ふと視線を感じて顔を上げると、奥の席の桐谷さんが私を見ていた。彼は心配そうな顔で、静かに頷いた。まるで、「大丈夫?」とでも言うように。その瞬間、私の胸を苛んでいた不快感が、すっと和らぐのを感じた。彼は私の能力を知らない。ただ、私が何かを感じ取って辛そうにしていることに気づいてくれただけだ。それでも、そのささやかな共感が、何よりも嬉しかった。
この感情は何だろう。桐谷さんといる時の、この胸の奥がじんわりと温かくなる感覚。それは、他の客たちが見せる鮮やかな恋心の色とは違う、もっと静かで、それでいて確かな何かだった。
ある雨の日、私は勇気を出して言った。
「あの、桐谷さん。もしよかったら、今度……一緒に映画でも見に行きませんか」
言い終えた瞬間、心臓が大きく跳ねた。断られたらどうしよう。彼の無色の世界を、私の存在でかき乱してしまうのではないか。そんな不安が渦巻く。
桐谷さんは数秒間、黙って私を見つめた。そして、雨粒が窓を叩く音に混じって、彼の静かな声が響いた。
「ええ、ぜひ。楽しみにしています」
彼の返事を聞いた私の世界は、ほんの少しだけ、明るくなった気がした。それでもまだ、そこに色がついているのかどうかは、分からなかった。ただ、今まで感じたことのない期待という名の柔らかな光が、心の奥底から差し込んできたことだけは確かだった。
第三章 純白の告白
映画館の暗闇、隣に座る桐谷さんの気配。スクリーンが放つ光が、彼の真剣な横顔を時折照らし出す。物語よりも、彼のわずかな息遣いや、ポップコーンに伸びる指先に、私の意識は奪われていた。映画が終わって外に出ると、夕暮れの空が街を茜色に染めていた。街ゆく人々からは、相変わらず様々な色の感情が立ち上っている。でも、不思議と気にならなかった。私の世界の中心は、今、隣を歩くこの人だったから。
「面白かったですね」
「はい。水野さんが好きそうだと思っていました」
そんな何気ない会話が、宝石のようにきらめいて感じられる。私たちは夕食を共にし、その後、近くの公園のベンチに腰を下ろした。夜の帳が下り、街灯がぼんやりと足元を照らしている。沈黙が心地よかった。この時間が永遠に続けばいいのに、と柄にもなく願ってしまう。
不意に、桐谷さんが口を開いた。
「水野さん」
彼の声は、いつもより少しだけ緊張しているように聞こえた。私は彼の顔を見つめる。彼の瞳の奥に、何か強い意志のような光が宿っているのが見えた。
「あなたのことが、好きです。初めて会った時から、ずっと」
その言葉が私の耳に届いた瞬間、世界が一変した。
桐谷さんの全身から、突如として、眩い光が放たれたのだ。それは、私がこれまで見てきたどんな恋心の色とも違った。赤でもなく、青でもなく、ピンクでもない。すべての色を内包し、すべてを超越したかのような、清らかで、神々しいほどの「純白」の光。あまりの輝きに、私は思わず目を細めた。
「……え?」
何が起きているのか理解できず、混乱する私に、桐谷さんは静かに続けた。
「驚きましたか。……僕も、あなたと同じものが見えるんです。人の恋心の色が」
彼の告白は、私の頭を鈍器で殴られたかのような衝撃を与えた。彼も、同じ能力を?
「じゃあ、今まで色が見えなかったのは……」
「ええ。僕は誰にも恋をしていなかったから。あなたに出会うまでは」
彼は私の手をそっと取った。彼の掌は温かかった。
「僕たちの世界では、ごく稀に、同じ力を持つ者同士が強く惹かれ合うことがあるそうです。その時、二人の間に生まれる想いは、他の誰にも見えない特別な色になる。……純粋な、白に」
純白。その言葉が、私の心に深く染み渡る。彼に色が見えなかったのは、彼が空っぽだったからじゃない。私と同じように、誰にも見つけられない特別な色を、心の内に秘めていたから。
そして、私は気づいてしまった。私の心の中にずっとあった、あの温かくて、穏やかで、でも確かな感情の正体に。私自身の恋心が色として見えなかったのは、それが不確かなものだったからではない。それは最初から、彼にしか見つけられない「純白」の輝きを放っていたのだ。
今までずっとモノクロームだと思っていた自分の心が、実は世界で最も眩しい光で満たされていたことを、私はその時、初めて知った。
第四章 私たちの色
「私も……私も、桐谷さんのことが好きです」
震える声でそう告げた瞬間、信じられないことが起きた。自分の身体の内側から、温かい光が奔流のように溢れ出し、視界が真っ白に染まったのだ。それはまるで、長い間閉ざされていた扉が開かれ、蓄えられていた光が一斉に解き放たれたかのような感覚だった。これが、私の色。これが、私の恋心。桐谷さんと同じ、純白の輝き。
私たちは、どちらからともなく互いを抱きしめていた。彼の胸の中で、私は初めて自分の能力を、そして自分自身を、心から受け入れることができた。この力は呪いなんかじゃなかった。世界でたった一人の、運命の人と出会うための道標だったのだ。
それからの日々は、まるで生まれ変わったかのようだった。私の働くカフェの店内は、今も様々な恋の色で溢れている。けれど、もうその他人の色に惑わされることはない。私の隣には、いつも穏やかな純白の光を放つ桐谷さんがいてくれるから。そして、私自身もまた、彼に応えるように白い光を輝かせているのが、今はっきりと感じられる。
時々、私たちは二人で手を繋ぎ、街を歩く。すれ違う人々が放つ色とりどりの光を眺めながら、その一つ一つの恋の物語に、心の中でエールを送る。かつては私を苛んだその色彩が、今では愛おしく思えた。世界はこんなにもたくさんの愛で満ちている。
ある晴れた午後、いつものようにカフェのカウンターに立っていると、桐谷さんが窓際の席から私にそっと手を振った。彼の周りには、柔らかな陽光と溶け合うようにして、優しい白色のオーラが漂っている。私は微笑み返し、自分の胸からも温かい光が溢れ出すのを感じた。
他の誰にも見えない、私たちだけの秘密の色。
それはどんな鮮やかな色彩よりも強く、深く、そして永遠に私たちの世界を照らし続けるだろう。
私の世界は、色に満ちている。
そして、その中心で最も強く輝いているのは、あなたという名の、純白の光だ。