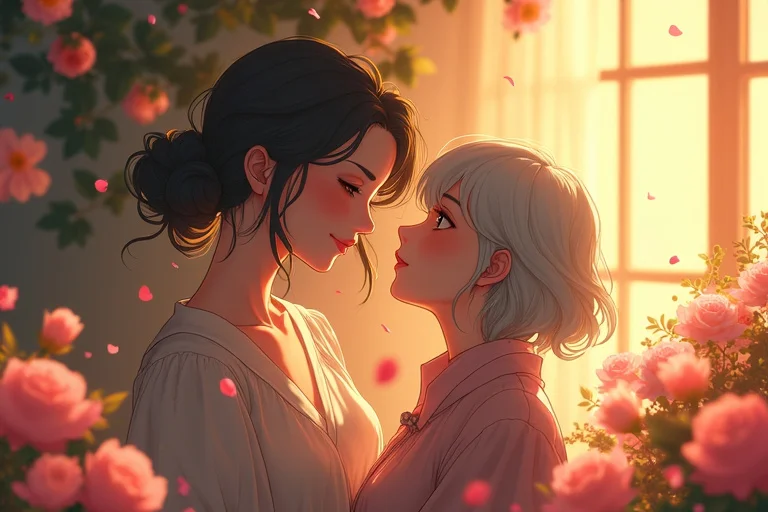第一章 触れられぬ手のひら
古書のインクと埃の匂いが満ちる静寂の中、僕はカウンターの奥で指先を組んでいた。人と触れることを極端に避ける僕にとって、この「時雨堂古書店」は完璧な隠れ処だった。客のまばらな昼下がり、僕は店の奥にある自室に戻り、桐の小箱を開ける。中には、僕がこれまでに盗んできた、色とりどりのガラス片――人々の「愛の記憶」が詰まっていた。
ルビーのように燃える情熱。サファイアのように澄んだ思慕。トパーズのように温かい慈愛。それぞれが、かつての持ち主の人生で最も輝いた瞬間を宿し、僕の手のひらの上で静かに呼吸している。僕はその中の一つ、ひときわ深く、穏やかな光を放つ翠玉のクリスタルをそっとつまみ上げた。ひんやりとした感触が、指先から罪悪感と共に胸に広がる。これは、僕の初恋の、そして唯一の友である陽菜(ひな)の記憶だった。
第二章 色褪せた世界
異変は、霧のように静かに、しかし確実に世界を覆い始めていた。テレビのニュースキャスターが、感情の乏しい声で「無気力症候群」と呼ばれる原因不明の症状が世界的に蔓延していると告げる。人々が愛する能力を失い、それに伴い平均寿命が急速に縮んでいる、と。その日、古書を探しに来た老婦人が、書棚の前でふらりと僕の腕に寄りかかった。
しまった、と思った瞬間、彼女の手のひらから零れ落ちたのは、いつものような輝くクリスタルではなかった。
無色透明の、乾いた砂。
それは僕の指の間をすり抜け、床の木目に吸い込まれるように消えた。熱も、色も、形もない。ただの虚無。僕は凍り付いた。僕の力が、壊れた。いや、世界が、壊れ始めているのだ。指先に残るざらりとした感触だけが、悪夢ではないことを告げていた。
第三章 翠玉の記憶
「奏(かなで)、いる?」
ベルの音と共に、陽菜が太陽の匂いを連れて店に入ってきた。彼女の笑顔は、色褪せ始めたこの世界で唯一、鮮やかなままだった。
「最近、なんだか変だよ。街ゆく人も、テレビの中の人も、みんな大切な何かを忘れてしまったみたいで」
心配そうに僕の顔を覗き込む彼女。その手が、僕の手に伸びてくる。
僕は咄嗟に、火傷でもしたかのように手を引いた。
陽菜の顔に、一瞬だけ寂しげな影が落ちる。
「ごめん……」
僕がそう言うのが精一杯だった。彼女は知らない。十年も前、僕がこの呪われた力に目覚めた日、初めて彼女に触れてしまったこと。そして、彼女が僕に向けていた淡い初恋の想いを、この翠玉のクリスタルとして奪い去ってしまったことを。君は、僕を好きだった記憶さえ、もう持ってはいないんだ。その事実が、鉛のように僕の胸に沈んでいた。
第四章 世界の渇き
世界から、急速に色彩が失われていった。恋人たちは互いの名前を忘れ、親子は温かい眼差しを交わさなくなり、芸術家はキャンバスの前で筆を止めた。愛という概念そのものが、人々の理解を超えた古代の言語のように風化していく。それに呼応するように、街には救急車のサイレンが頻繁に響き渡るようになった。人々は、まるで内側から生命のロウソクが消えていくかのように、次々と倒れていった。
僕は自室の桐箱を開け、愕然とする。かつて宝石のように輝いていたクリスタルたちが、その光をほとんど失い、くすんだ石ころに成り果てていた。まるで、この世界そのものの生命力と繋がっているかのように。僕が触れる人々から零れ落ちる無色の砂。輝きを失っていくクリスタル。急速に縮んでいく人々の寿命。
全ての線が、僕という一点で交わった。
この世界の渇きは、僕が原因だ。
認めがたいその真実が、僕の喉を締め付けた。
第五章 原初の祭壇
突き動かされるように、僕は店を飛び出した。向かう先は、陽菜から翠玉のクリスタルを奪ってしまった場所。街外れにある、廃教会。蔦の絡まる石の扉を押し開けると、ステンドグラスの砕けた窓から、灰色の光が差し込んでいた。祭壇の前へ、まるで何かに導かれるように歩みを進める。
そこに立った瞬間、脳内に直接、声ではない声が響き渡った。
それは、世界の記憶だった。
この世界は、かつて存在した巨大な「原初の愛」の結晶体そのもの。そして、人々が交わす愛は、その結晶体を維持するためのエネルギー。捧げられた愛は相手の命となり、捧げた者の命は世界へと還る。美しい「命の等価交換」。僕の能力は、そのサイクルから溢れ出た過剰な愛のエネルギーを一時的に保管し、調和を保つための安全装置だったのだ。
しかし、あの日。トラックに轢かれそうになった陽菜を突き飛ばした時、僕は彼女を失う恐怖から、無意識に能力を暴走させた。彼女を守りたいという強すぎる想いが、安全装置を破壊した。僕の手は、世界中の愛を際限なく吸収し続ける「渇きの渦」へと変貌してしまったのだ。僕が集めたクリスタルは、本来世界に還るべきだった愛のエネルギーそのものだった。
第六章 愛を還す者
世界を救う方法は、一つしかなかった。僕が盗んできた全ての愛を、この祭壇を通じて「原初の愛」へと還すこと。
僕は懐から、最後の輝きを保つ翠玉のクリスタルを取り出した。陽菜の、純粋な初恋の記憶。それを祭壇にそっと置くと、クリスタルはまばゆい翠の光を放ち、祭壇の上に光の道筋を描き出した。
僕は、桐箱から一つ、また一つとクリスタルを取り出し、光の中へと置いていく。
燃えるような恋。穏やかな夫婦の愛。報われなかった片想い。その全てが、誰かの人生の断片であり、世界の礎だった。涙が頬を伝う。ごめんなさい、ごめんなさい。心の中で繰り返しながら、僕は全ての愛を還していく。
そして、最後の一つを還し終えた時、世界の声が再び響いた。
『代償を』
光の道筋を完全に開くには、鍵が必要だという。僕自身の、「愛」という概念そのものを。
僕は静かに頷いた。
陽菜の笑顔が脳裏に浮かぶ。これで君が、君の世界が救われるのなら。
僕は祭壇に手を置いた。僕の中から、何かが決定的に抜き取られていく感覚。陽菜への想い。家族への情。美しいものへの感動。それらが全て、色を失い、意味を失い、ただの記号になっていく。心が、空っぽになった。
刹那、祭壇から放たれた光が、廃教会を突き抜け、天へと昇っていく。世界中に、失われた色彩と温もりが還っていくのが分かった。
気づけば、僕は教会の前に佇んでいた。背後で、僕を呼ぶ声がする。
「奏!」
陽菜が駆け寄ってくる。彼女は僕の手を、ためらいなく、強く握った。
「よかった…! 無事だったんだね!」
その手の温かさに、僕は何も感じなかった。ただ、彼女の向こうに広がる空を見つめる。
空は、忘れていたほど、青かった。
第七章 愛のない世界で
世界はゆっくりと、だが確実に癒えていった。人々は再び愛を語り、恋をし、新しい命が芽生え始めた。街には活気が戻り、ニュースは明るい話題を報じるようになった。まるで悪夢から覚めたかのように、世界は日常を取り戻した。
僕だけが、その輪の外にいた。
陽菜は、以前にも増して僕のそばにいてくれるようになった。彼女は僕に笑いかけ、触れ、その温かい眼差しで僕を見つめ続ける。彼女の愛は、きっと僕の寿命をわずかに伸ばしてくれているのだろう。そして、その分だけ、彼女自身の命が削られていることも、理屈としては理解できた。
でも、僕の心は凪いだ水面のように、何も映さない。感謝も、喜びも、罪悪感さえも。
ある晴れた日、陽菜が小さな花束を手に店を訪れた。
「これ、奏の好きだったフリージアだよ。覚えてる?」
僕はその花束を受け取った。鼻を近づけると、甘い香りがした。かつての僕なら、この香りに陽菜との思い出を重ね、胸をときめかせたのかもしれない。
だが、今の僕には、それがただの「甘い匂いのする植物」でしかなかった。
「……ありがとう」
僕は、感情のない声でそう言った。陽菜は一瞬だけ寂しそうに微笑んだが、すぐにいつもの笑顔に戻った。
僕は愛を還し、世界を救った。その代償に、僕は世界でただ一人、愛のない場所に永遠に取り残された。陽菜が捧げてくれる愛を感じることもできず、ただその命の輝きを一方的に受け取り続けるだけの、空っぽの器として。
それでも世界は美しく、陽菜は僕の隣で笑っている。
それが僕の得た結末であり、僕がこれから生きていく、世界の全てだった。