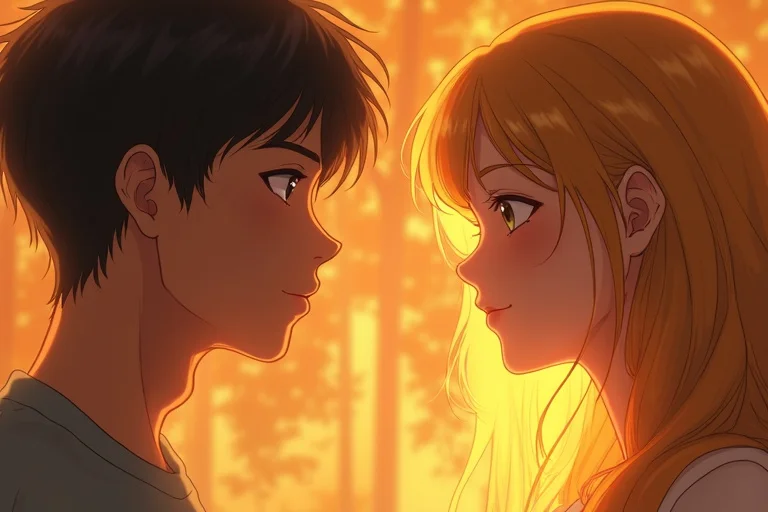第一章 心に響くアリア
僕、相沢律(あいざわりつ)の心には、いつも歌が流れている。それは愛する人、陽菜(ひな)の歌だ。彼女の魂が奏でる、僕だけに聴こえるアリア。陽菜が笑うと、歌は陽だまりのように温かいメロディを紡ぎ、彼女が少しでも悲しむと、マイナーコードの切ないフレーズが心を締め付けた。
僕たちが付き合い始めた日、心に響いたのは高らかなファンファーレだった。そしてその夜、空を見上げると、まるで祝福するかのように、ひときわ明るい新しい星が一つ、瞬いていた。この世界では、人々が『真実の愛』を抱くたびに、空に星が生まれるという。僕たちの星は、他のどの星よりも誇らしげに輝いて見えた。
陽菜は駅前の小さな花屋で働いている。店先に並ぶ色とりどりの花々のように、彼女の存在そのものが世界を鮮やかに彩っていた。僕が営む古書店の、インクと古い紙の匂いが染みついた空間に、彼女が持ち込むフリージアの甘い香りは、まるで異世界の風のようだった。
「律くん、この本、面白そう」
彼女が指差すのは、少し色褪せた装丁の詩集。その時、僕の心に流れるのは、小鳥のさえずりのような軽やかなワルツだ。歌詞はいつも、僕への素直な想いを語ってくれる。
『あなたのいる場所が、私の帰る場所』
その歌を聴くたび、僕は幸福の頂点にいるような気持ちになった。書斎の机の引き出しには、祖父から譲り受けた古びた五線譜がある。誰にも読めない奇妙な記号で埋め尽くされているが、僕にはそれが、過去から未来へと連なる愛の歌の記憶のように感じられた。陽菜の歌を聴きながら、時折その五線譜を眺めるのが、僕の密やかな習慣だった。
第二章 不協和音の予兆
変化は、夏の終わりの雨の日に訪れた。湿った空気が街を覆い、僕の心にもじっとりとした影を落としていた。その日、陽菜の歌に、初めて不協和音が混じったのだ。
それは、ピアノの鍵盤を一つだけ間違えて叩いたような、ほんの僅かなズレ。しかし、彼女の魂と完璧に調和していた僕の聴覚にとって、その違和感は無視できるものではなかった。軽やかだったワルツの旋律が、ふとした瞬間に揺らぎ、歌詞の隙間に、言葉にならないため息のようなものが混じる。
「どうしたの? 何かあった?」
「ううん、何でもないよ」
彼女は笑う。その笑顔はいつも通り太陽のようだったが、僕の耳に届く歌は、その裏側で微かに震えていた。不安が胸の奥で小さな棘のように刺さる。気のせいだ、きっと疲れているだけだ。そう自分に言い聞かせても、一度生まれてしまった不協和音は、日を追うごとに存在感を増していった。
夜空を見上げると、僕たちの星の輝きが、心なしか翳っているように見えた。まるで薄い雲のベールを被ったかのように、その光は頼りなく瞬いている。世界が、少しずつ彩度を失っていくような、そんな静かな恐怖が僕を包み込み始めていた。
第三章 知らない誰かのバラード
決定的な断絶は、秋風が街路樹の葉をさらい始めた頃にやってきた。陽菜とカフェで向かい合っていた、その瞬間。
突然、僕の心の中で鳴り響いていた彼女のワルツが、ぷつりと途切れた。静寂。そして、全く別の歌が流れ始めたのだ。
それは、僕の知らない誰かの歌だった。低く、甘く、そしてどうしようもなく切ない男性ボーカルのバラード。ピアノのアルペジオが静かに始まり、チェロのむせび泣くような旋律が絡みつく。歌詞は、遠い昔に交わした約束と、再会を願う焦がれるような想いを歌っていた。
『君という名の光を、もう一度この腕に』
目の前の陽菜は、何も変わらず僕に微笑みかけている。だが、僕の心に響くのは、彼女が別の誰かを想う、情熱的な愛の歌だった。混乱が頭を殴りつける。僕は陽菜を愛している。彼女も僕を愛してくれているはずだ。それなのに、なぜ。この歌は、誰の歌なんだ?
その日から、僕の世界は灰色になった。陽菜の笑顔を見るたびに、その裏で流れるバラードが僕の心をえぐる。夜空を見上げても、新しい星が生まれる気配はない。それどころか、空に浮かぶ星々は皆、病を得たかのように輝きを失い、僕たちの星に至っては、今にも燃え尽きてしまいそうなほど弱々しい光を放つだけだった。愛が終われば、星は消える。僕たちの愛は、終わってしまうのか?
第四章 五線譜が語る真実
絶望の淵で、僕は書斎の引き出しに仕舞い込んだ、あの古びた五線譜に手を伸ばした。インクのかすれた奇妙な記号たち。これまでただ眺めるだけだったそれに、僕は藁にもすがる思いで向き合った。
ページをめくる指が震える。何時間も、何日も、僕はその記号と格闘した。そして、ある事実に気づいた時、全身の血が凍りつくような感覚に襲われた。
五線譜に描かれた記号の連なりは、僕が心の中で聴いてきた『歌』の旋律と、完璧に一致していたのだ。陽菜と出会った日の高揚、愛を育んだ日々のワルツ、そして、あの不協和音。全てが、この五線譜に記されていた。これは単なる楽譜ではない。魂の『願い』そのものを書き記した、世界の設計図なのだ。
最後のページには、こう走り書きされていた。
『魂の歌は、感情の模倣にあらず。その者が真に望む幸福への道標なり』
雷に打たれたような衝撃。僕が『陽菜の僕への愛の歌』だと思っていたものは、違ったのだ。それは、陽菜の魂が『本当に望む幸福』を歌にしたものだった。僕との日々が彼女の幸福であった時、歌は僕への愛を歌った。だが、彼女の魂が求める真の幸福が別の場所にあるのなら、歌は変わる。
今、僕の心で鳴り響くバラード。それは、陽菜が心の奥底で焦がれる相手――最近海外から帰国したという幼馴染の音楽家、海斗という男の歌なのだと、僕は直感的に理解した。空の星が輝きを失っていくのは、愛が偽りになったからではない。人々が、魂の求める真の幸福から目を逸らし、その『願いの歌』を聴こうとしないからだ。
第五章 無償の愛への昇華
僕は陽菜を、僕たちが初めてデートした公園のベンチに呼び出した。落ち葉が風に舞い、カサカサと乾いた音を立てている。隣に座った陽菜の横顔は、どこか追いつめられたように儚げだった。
「律くん、ごめんなさい……」
彼女が切り出す前に、僕は静かに首を振った。
「聞かせてほしい。君の、本当の気持ちを」
陽菜は驚いたように僕を見つめ、やがてぽつりぽつりと語り始めた。幼馴染の海斗との再会。忘れたはずだった遠い日の約束。自分でも制御できない、奔流のような感情。
彼女の話を聞きながら、僕の心には、あの切ないバラードがこれまで以上に大きく響き渡っていた。嫉妬や悲しみがなかったわけではない。胸は張り裂けそうだった。しかし、それ以上に強く感じたのは、陽菜がようやく、自分の魂の歌に耳を傾けようとしていることへの、不思議な安堵感だった。
「陽菜」
僕は彼女の名前を呼んだ。
「僕は、君の幸せを心から願っている。君が、君の魂が歌う通りの道を歩むことが、僕にとっても一番の喜びだ」
その言葉が、僕自身の真実だと気づいた瞬間、奇跡が起きた。
心の中で鳴り響いていた海斗のバラードに、澄み切ったソプラノの旋律が、そっと寄り添うように重なったのだ。それは陽菜の魂の歌。二つの歌は互いに溶け合い、これまで聴いたどんな音楽よりも美しく、完璧なデュエットを奏で始めた。
涙が頬を伝う。これは失恋の涙ではない。僕の愛が、所有欲や執着から解き放たれ、ただひたすらに相手の幸福を願う『無償の愛』へと昇華された瞬間の、祝福の涙だった。
第六章 星が生まれる夜
その夜、僕は一人で思い出の丘に登った。街の灯りが遠くで瞬き、空には満月が浮かんでいる。
見上げると、輝きを失いかけていた星々が、再び生命力を取り戻したかのように力強く光っていた。世界が、もう一度その色彩を取り戻していく。
そして、空の一番高い場所で、一つの新しい星が、静かに、しかし何よりも強く、温かい光を放ち始めた。それは、僕の星だった。陽菜との愛の星ではない。彼女の幸福を心から願い、手放すことを選んだ僕の『無償の愛』が生み出した、真実の星だった。
僕の心には、今も陽菜と海斗の幸福なデュエットが響き続けている。それはもう僕を苦しめる不協和音ではなく、ただただ美しい、魂の協和音だった。
僕はその歌を聴きながら、夜空に生まれたばかりの自分の星を見つめた。愛する人を失い、僕は、真実の愛の形を知った。この静かな喜びと、優しい痛みを胸に抱きながら、僕はこれからもこの歌を聴き続けていくのだろう。空に、僕だけの星が輝く限り。