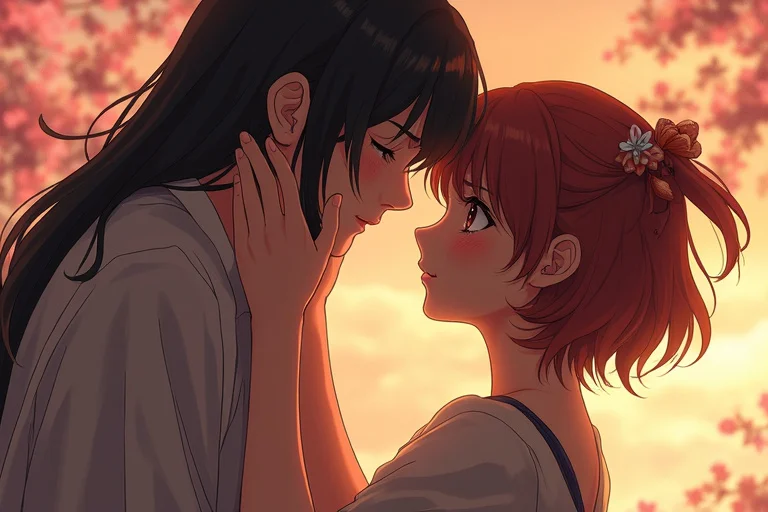第一章 硝子の恋心
私の恋は、いつも輪郭から溶けていく。
この世界では、人の寿命は生涯で受け取る「真実の愛の言葉」の総量で決まる。愛の言葉は生命の糧であり、その温かな響きが心臓を動かし、血を巡らせる。だから人々は愛を囁き、愛を求め、そうして生を繋いできた。
そんな世界で、私は呪われた体質を持って生まれた。誰かに恋をすると、その感情の強さに比例して、体が半透明になってしまうのだ。指先が、腕が、まるで薄い硝子のように向こう側を透かし始め、愛が深まるほどに存在そのものが希薄になっていく。唯一、その想い人から愛を返されたときだけ、私は失った実体を取り戻せる。
だから私は、恋を避けて生きてきた。図書館の片隅で、古い本のインクの匂いに包まれているときだけが、私の輪郭が最も確かな時間だった。
あの日、図書館の帰り道、私は偶然、路地裏に佇む古い時計店を見つけた。錆びた看板には「響時計店」とだけ。ガラス窓の向こうで、黙々と小さな歯車を磨く青年がいた。響一(ひびき はじめ)。それが、彼の名前だった。
彼がピンセットで操る銀色の部品が、窓から差し込む西日を浴びて、きらりと光を放つ。その一瞬の煌めきに、私の心臓が大きく音を立てた。その瞬間、私の左手の小指の先が、ふっと淡く透けたのを、私は見逃さなかった。
恋の始まりは、いつもこうだ。甘美な痛みと共に、私という存在を少しずつ世界から削り取っていく。それでも私は、彼の姿に目を奪われた。店から漏れる微かな油の匂い、規則正しく響く時計の秒針の音。そのすべてが、私の心をどうしようもなく惹きつけた。
帰り道、アスファルトの上にぽつりと、涙の雫のようなものが落ちた。拾い上げると、それは冷たくて硬い「透明な結晶」だった。私の体が透けるたびに、その残滓からこぼれ落ちる、私の恋心の化身。それはあまりに綺麗で、そして、ひどく哀しかった。
第二章 沈黙の旋律
私は、時計の修理を口実に、彼の店に通うようになった。
「この懐中時計、祖母の形見なんです」
嘘だった。古道具屋で埃をかぶっていた、ただの古い時計だ。一は無言でそれを受け取ると、ルーペを目に当て、静かに分解を始めた。店の中は、カチ、コチ、という無数の時計が刻む音だけが満ちていた。それはまるで、世界の喧騒から切り離された、穏やかな沈黙の旋律のようだった。
「……ネジが一つ、摩耗している」
しばらくして、彼がぽつりと呟いた。低く、落ち着いた声だった。その声が鼓膜を震わせるたびに、私の腕はまた少し透明度を増していく。
彼は言葉少なだったが、決して冷たいわけではなかった。私が本の話をすれば静かに耳を傾け、私が街で見つけた猫の話をすれば、その口元に微かな笑みを浮かべた。けれど、彼が私に「愛の言葉」をくれることは決してなかった。それどころか、「綺麗だ」とか「ありがとう」といった、当たり前の感情を示す言葉すら、彼の口から聞くことは稀だった。
世間では「言葉枯渇病」が静かに広まっていた。人々から愛の言葉が失われ、若くして命を落とす者が増えているという。カフェで交わされる会話も、どこか乾いていて、切実さに欠けていた。まるで世界の潤いが、少しずつ失われているようだった。
彼と会う時間は、私にとって至福だった。けれどその代償に、私の体は着実に世界との境界を失っていく。向かい合って座っていても、テーブルの木目が私の膝を透かして見える。このままでは、私は彼の前で完全に消えてしまうだろう。愛されているという確信がなければ生きられないこの世界で、愛の言葉をくれない人を愛し続けることは、緩やかな自殺に等しかった。
第三章 砕けた言葉
友人たちは、日に日に薄くなっていく私を見て、泣きそうな顔で言った。
「雫、もうあのお店に行くのはやめて。あなた、消えちゃうわ」
分かっていた。けれど、彼のいない世界で確かな輪郭を持って生きるより、彼に見つめられながら消えていく方が、ずっと幸せなのだとさえ思えた。
ある雨の日、私の体は、胴体までがぼんやりと透けるようになっていた。店のドアを開けると、一が驚いたように顔を上げた。雨に濡れた私の姿が、まるで水彩画のように滲んで見えたのだろう。
「どうしたんだ、その体……」
「これが、私の体質なの」
私は、すべてを打ち明けた。恋をすると体が消えてしまうこと。相手に愛されない限り、元には戻れないこと。そして、その相手が、あなたであること。
「だから……お願い。一言でいいの。『愛してる』って、言ってくれなくてもいい。『好きだ』でも、『大切だ』でも……何か、言葉をください。そうでないと、私は……」
声が震えた。懇願する私の目の前で、一は苦痛に顔を歪めた。彼は何かを言おうと唇を開き、けれどそこから漏れたのは、音にならない息だけだった。やがて、絞り出すように彼は言った。
「……すまない」
その一言が、私の最後の希望を打ち砕いた。砕けたガラスのように、私の心に鋭い痛みが走る。違う、私が欲しかったのは謝罪の言葉じゃない。どうして。どうして、あなたは私に愛をくれないの? 答えのない問いが、ますます透明になっていく体の中で空しく響いた。
第四章 世界の渇き
私は、一の店に行くのをやめた。
彼から離れれば、この恋心も薄れて、私の体も元に戻るかもしれない。そう信じたかった。だが、現実は違った。彼を想う気持ちは消えるどころか、会えない時間の中でますます募り、私の体は存在の縁から崩れ落ちていくようだった。
そして、異変は私だけにとどまらなかった。私が一から離れたのと時を同じくして、世界の「言葉枯渇」は急速に進行した。街行く人々の会話からは感情が消え、テレビのニュースキャスターは抑揚のない声で原稿を読み上げる。まるで世界全体が、愛という感情を忘れてしまったかのようだった。人々は次々と倒れ、世界の寿命が目に見えて縮んでいくのが分かった。
いてもたってもいられず、私は再びあの路地裏へと向かった。店のドアは固く閉ざされていた。窓から中を覗くと、彼は作業台に突っ伏していた。その姿は、ひどく小さく、孤独に見えた。
私は裏口からそっと店に入った。床に、古びた革張りの本が一冊、落ちている。手に取って開くと、そこには信じられない記述があった。
『世界に満ちる愛の言葉は、ただ一人の「調律者」の心から湧き出る泉に源を発する。調律者は、その声で世界に愛を供給する。もし調律者が愛を囁くことをやめ、その心を固く閉ざしてしまえば、泉は枯れ、世界は愛の渇きによって滅びるであろう』
その瞬間、すべてを理解した。一こそが、この世界の「調律者」なのだ。彼はきっと、自分の言葉が人々の命を左右するという、あまりに重すぎる宿命に耐えきれず、愛を語ることを自ら封じてしまったのだ。彼の沈黙は、世界を守るための、あまりに優しい自己犠牲だった。そして、私が彼に愛を求めたことは、彼の固く閉ざした心の扉を、さらに内側から固く閉ざさせてしまったのだ。
第五章 最後の結晶
真実を知った私は、彼のもとへ走った。もう、私の体に輪郭と呼べるものはほとんど残っていなかった。心臓のあたりが淡い光として明滅しているだけ。一歩進むたびに、体からキラキラと無数の「透明な結晶」がこぼれ落ち、私の通った跡に光の道筋を描いていく。
作業台に突っ伏していた一が、その光の音に気づいて顔を上げた。彼の目に映ったのは、ほとんど光の粒子と化した、私の姿だった。
「……雫」
彼の声が、か細く震える。
私は、消えゆく体で、彼に微笑みかけた。もう、言葉を求める気持ちはなかった。ただ、彼の苦しみを少しでも和らげたかった。
「あなたのせいじゃ、ないよ」
「……」
「私が、勝手にあなたを好きになっただけ。私が、あなたを愛したかっただけだから」
一の瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。彼は私に駆け寄り、その実体のない体を抱きしめようとするが、彼の腕は空しく私をすり抜ける。言葉を紡ごうと喘ぐ彼の唇から、声は出ない。
ああ、もうすぐ、私は完全に消える。
彼の涙が、私のこぼした結晶の上に落ちて、澄んだ音を立てた。それが、私がこの世界で聞いた、最後の音になるのだろうか。
第六章 内なる泉
意識が薄れ、光の粒子に分解されていく、その瞬間。私の心に、一つの澄み切った感情が満ちていくのを感じた。
それは、見返りを求める愛ではなかった。愛されることを期待する心でもなかった。ただ、目の前にいる彼の存在そのものが、どうしようもなく愛おしいという、純粋な想い。
(言葉なんて、いらなかったんだ)
彼に愛を囁いてもらえなくてもいい。彼に触れてもらえなくてもいい。私は、ただ、あなたが存在してくれる、この世界に生きていてくれる。それだけで、こんなにも満たされている。
そう心から決意した瞬間、私の内側から、まったく新しい光が溢れ出した。それは、誰かから与えられる光ではなく、私自身の魂の核から湧き出る、温かな黄金色の光だった。
消えかけていた私の体が、その光に包まれて、再び輪郭を取り戻し始める。透明な硝子ではなく、温かい血の通った、確かな実体を持って。
そして、奇跡が起こった。私の足元に散らばっていた無数の「透明な結晶」が、その黄金色の光に呼応するように一斉に輝きだしたのだ。結晶はふわりと宙に舞い上がり、光の雨となって世界中に降り注いでいく。それは、他者から与えられることを待つのではなく、自らの内側から湧き出る「無条件の愛」の源泉だった。
第七章 言葉のいらない朝
世界に、再び「愛の言葉」が戻ってきた。
しかし、その言葉の質は、以前とはまったく違うものに変わっていた。それはもはや、寿命を取引するための呪いのようなものではなく、人々が自らの内なる泉から汲み上げ、惜しみなく与え合う、温かい贈り物となっていた。
工房の中、私と一は、ただ黙って手を取り合っていた。彼の指先が、私の手の甲をそっと撫でる。その優しい感触だけで、彼のすべての想いが伝わってくるようだった。彼の瞳は、もう苦痛に歪んではいない。穏やかな光をたたえ、静かに私を見つめている。
彼は、もう二度と「愛してる」とは言わないだろう。彼が背負った宿命は消えない。けれど、それでよかった。私たち二人にはもう、愛を確かめ合うための言葉は必要なかった。
窓から差し込む朝の光が、工房の埃をキラキラと照らし出す。新しい世界の始まりを告げる光の中で、私たちは互いの存在そのものが、何よりも雄弁な愛の証明であることを知っていた。私たちの愛は、もう決して消えたりしない。言葉ではなく、ただ、そこにある。確かな輪郭を持って。