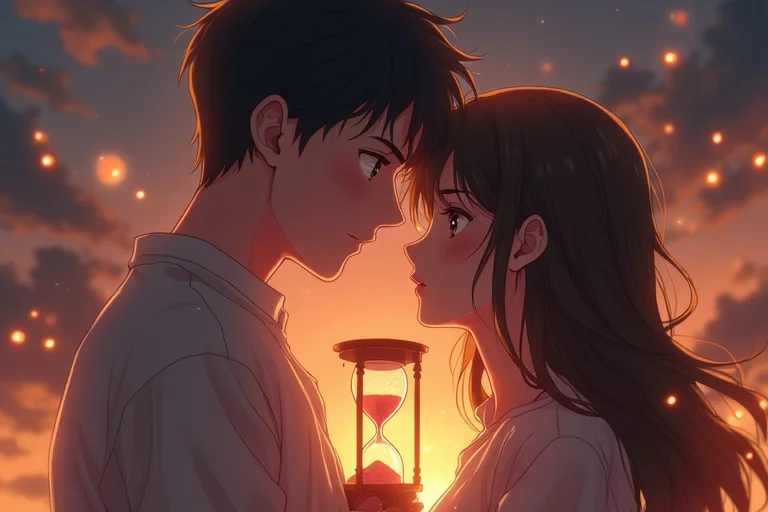第一章 触れられない贈り物
古書店の隅、午後の光が埃を金色に照らす場所が、水島湊の定位置だった。インクと古い紙の匂いに包まれ、彼は世界の喧騒から切り離された聖域にいる。だが、その平穏は、彼が持つ特異な能力によって、常に薄氷の上にあった。湊には、物に触れると、その最後の所有者が込めた強い感情を読み取ってしまう、サイコメトリーという呪いにも似た才能があった。だから彼は、古書を扱う時ですら、薄い手袋を外さない。他人の激情や絶望が、津波のように流れ込んでくるのを防ぐために。
そんな湊にとって、恋人である藤宮栞の存在は、唯一無二の光だった。彼女は、湊が人と距離を置く理由を知らない。ただ、彼の少しばかり壁のある性格を「思慮深いところが好き」と言って、ひまわりのような笑顔でその壁を照らしてくれる。彼女にだけは、素手で触れることができた。彼女から伝わってくるのは、いつだって陽だまりのように純粋で、温かい愛情だけだったからだ。
「湊、お誕生日おめでとう」
二十六歳になったその日、栞は少しはにかみながら、小さな包みを差し出した。丁寧にラッピングされたそれを開くと、中から現れたのは手作りの革のブックカバーだった。少し不揃いなステッチが、彼女が時間をかけて作ってくれた証のようで、湊の胸を熱くする。色は、湊が好きな深い森のような緑色。
「すごい……綺麗だ。ありがとう、栞」
感謝を込めて、彼はブックカバーにそっと指を伸ばした。栞が作ってくれたのだ。きっと、あの温かい感情で満たされているに違いない。そう信じて疑わなかった。
指先が、滑らかな革に触れた瞬間――湊は息を呑んだ。
流れ込んできたのは、栞の愛情だけではなかった。もちろん、彼女の「喜んでくれるかな」という期待と愛情の波動は感じる。だが、その奥に、もっと深く、もっと濃密な、別の誰かの感情が存在していた。それは、熟成されたワインのように芳醇で、夕暮れの空のように切ない、圧倒的なまでの愛情。知らない男の、深い、深い愛情だった。
湊の全身から血の気が引いていく。これは、誰だ? このブックカバーを作ったのは、栞だけではないのか? それとも、彼女はこのブックカバーを、この愛情の持ち主である男から貰い、それを俺に?
混乱する頭で栞の顔を見ると、彼女は期待に満ちた瞳でこちらを見つめている。「どうかな?」と無邪気に笑うその顔が、今は得体の知れない仮面のように見えた。湊は喉の奥で言葉を詰まらせ、ただ「……ありがとう。大切にするよ」と絞り出すのが精一杯だった。
その日から、湊の世界に、静かだが確実な亀裂が入り始めた。栞からの贈り物に触れるたび、彼は見知らぬ男の愛情に焼かれることになったのだ。
第二章 歪んだプリズム
疑念というプリズムは、湊の見る世界を歪ませていった。栞の何気ない仕草ひとつひとつが、棘となって心に突き刺さる。スマホを伏せて置くこと。時折、会話の途中で遠くを見るような目をすること。以前は気にも留めなかったそれらが、今ではすべて浮気の証拠のように思えてならなかった。
ブックカバーは、彼の書斎の机の上に置かれている。それに触れるのが怖かった。だが、確かめずにはいられなかった。夜、栞が眠りについた後、湊は書斎に籠もり、恐る恐るその革に触れる。流れ込んでくるのは、やはりあの感情だった。栞が自分を想う気持ちの層の下に、揺るぎなく存在する、父性にも似た、あるいはもっと純粋な伴侶への愛のような、巨大な愛情の塊。それは嫉妬を煽るというより、むしろ湊を無力感に苛んだ。こんなにも深い愛情を注ぐ男が、栞のそばにいるという事実。
「このブックカバー、本当に栞が作ったの?」
ある週末の昼下がり、耐えきれずに尋ねてみた。栞は一瞬、目を丸くしたが、すぐに嬉しそうに頷いた。
「うん、そうだよ。デザインから革の裁断、縫製まで、全部。……変だったかな?」
「いや、すごく上手だから……誰かに教わったりしたのかと思って」
「え? ああ、うん。まあ……ちょっとね」
栞はそう言って、言葉を濁した。その曖昧な態度が、湊の疑念にさらに油を注ぐ。彼女は嘘をついている。その確信が、冷たい水のように湊の心を浸していく。
二人の間の空気は、目に見えて重くなった。湊が栞に触れる回数が減った。彼女の手を握る時も、抱きしめる時も、心のどこかでブックカバーに宿っていた男の感情がちらつき、純粋な気持ちになれない。栞もその変化に気づいているようだった。彼女の笑顔には、時折、戸惑いと悲しみの色が滲むようになった。
「湊、最近、何かあった? 疲れてる?」
心配そうに尋ねる彼女に、湊は「仕事が忙しいだけだよ」と答えることしかできない。自分の能力のことも、抱えた疑いも、何も打ち明けられない。それを口にすれば、この脆い幸福が、ガラス細工のように粉々に砕け散ってしまう気がした。
湊は、自分の能力をこれほど呪ったことはなかった。人の感情が分かるはずの力が、愛する人の心を、誰よりも分からなくさせている。真実はどこにあるのか。彼は出口のない迷路を彷徨い、もがき苦しんでいた。ブックカバーの深い緑色は、もはや癒しの色ではなく、底なしの沼の色に見えていた。
第三章 空っぽの工房に響く声
決定的だったのは、ある雨の日の夕方だった。栞が「ちょっと友だちと会ってくるね」と言って家を出ていった。その声に微かな緊張を感じ取った湊は、衝動的に彼女の後を追う決心をした。黒い傘を差し、距離を保ちながら彼女の背中を追う。降りしきる雨が、湊の焦燥感を煽るようだった。
栞が向かったのは、繁華街でもお洒落なカフェでもなかった。古い商店が立ち並ぶ、寂れた一角。彼女は、一軒の古びた建物の前で足を止め、錆びついた扉に鍵を差し込んで中へと消えた。看板には掠れた文字で『藤宮革工芸』と書かれている。彼女の名字だ。
湊は建物の影に身を潜め、息を殺した。浮気相手の工房か? ここで二人は逢瀬を重ねているのか? どす黒い想像が頭を渦巻く。しばらくして、中から話し声が聞こえてきた。栞の声と、そして、低く、穏やかな男の声。ブックカバーから感じた愛情の持ち主の声に違いない。
湊は、真実を知る恐怖と、このままではいられないという衝動の狭間で葛藤した。そして、意を決して、工房の曇りガラスの窓に耳を寄せる。
「――お父さん、あのね、湊さん、すごく喜んでくれたよ。私が作ったブックカバー」
栞の弾んだ声が聞こえた。
お父さん? 湊の思考が停止する。栞の父親は、彼女が高校生の時に交通事故で亡くなったと聞いている。では、今、彼女が話している相手は一体誰なんだ。
「そうか、それは良かった。栞。ステッチの最後の処理、ちゃんとできたか?」
男の声が応える。その声は、どこか不自然にクリアで、僅かなデジタルノイズが混じっているように聞こえた。
湊は混乱しながら、窓の隙間から中を覗き込んだ。工房の中は、革の匂いとオイルの匂いが充満しているようだった。壁には使い込まれた道具が整然と並んでいる。しかし、そこにいたのは栞一人だけだった。彼女は作業台の前に座り、置かれたスピーカーに向かって話しかけている。男の姿はどこにもない。
「うん、お父さんが教えてくれた通りにやったら、綺麗にできた。……ねえ、お父さん。また新しいもの、作りたいな。今度は、湊さんの鞄とか」
「いいじゃないか。基本は同じだ。ゆっくり、焦らずにな」
湊は、その光景の意味を悟り、全身の力が抜けていくのを感じた。
栞が話していたのは、生身の人間ではなかった。彼女は、AIだったのだ。生前の父親が遺した膨大な音声データと日記を元に、ある企業が開発した対話型AI。栞は、亡き父の面影を宿したそのAIと対話するために、父が遺したこの工房に、一人で通っていたのだ。
ブックカバーは、栞が「AIの父」に教えを乞いながら、父が愛用していた革と道具を使って、たった一人で作り上げたものだった。そこに宿っていた、あの深く、切ないほどの愛情は、栞が亡き父を想う気持ちと、データの中に生きる父が娘を想う気持ち――その二つが奇跡のように重なり合って、革に染み込んだものだったのだ。
雨音だけが、やけに大きく聞こえた。湊は、自分の愚かさと、栞が一人で抱えてきた途方もない孤独と愛情の深さに、ただ立ち尽くすしかなかった。
第四章 愛のサイコメトリー
その夜、湊は帰宅した栞をまっすぐに見つめた。栞は湊のただならぬ様子に、不安げな表情を浮かべている。
「湊……どうしたの?」
「栞、話があるんだ」
湊は、栞を手招きして書斎に連れて行った。机の上に置かれた、あの緑色のブックカバーを手に取る。そして、深呼吸を一つすると、これまで誰にも明かしたことのない秘密を打ち明けた。
「俺には、物に触れると、最後の持ち主の感情が分かる力があるんだ」
栞は驚きに目を見開いている。湊は続けた。
「君からこのブックカバーを貰った時、触れたんだ。君の愛情と一緒に、別の……すごく大きくて、温かくて、少し切ない、知らない誰かの愛情を感じた。だから、怖かった。君に、他に大切な人がいるんじゃないかって。ずっと、苦しかった」
彼の告白に、栞の瞳からぽろぽろと涙がこぼれ落ちた。それは、責める涙ではなかった。安堵と、そして長年一人で抱えてきた想いが溢れ出したかのような、美しい涙だった。
「……そうだったんだ。ごめんね、湊。不安にさせて」
栞は、震える声で工房でのこと、AIの父親のことをすべて話してくれた。父親を亡くした悲しみ、その技術があることを知った時の喜び、そして、まるで父がまだ生きているかのように対話できる時間の愛おしさ。それは、誰にも理解されないだろうと、ずっと一人で胸に秘めてきた秘密だった。
「そのブックカバーはね、お父さんが昔、お母さんのために作るはずだった革の残りを使ったの。だから……お父さんの気持ちも、こもってたのかもしれない」
湊は、もう一度ブックカバーにそっと触れた。今度は、もう怖くなかった。流れ込んでくる感情の輪郭が、はっきりと分かる。栞が湊を想う、ひたむきな愛情。そして、その奥にある、娘の幸せを願う父親の、時を超えた優しい眼差し。二つの愛が、美しいグラデーションを描いて、湊の心を温かく満たしていく。
「そうか……そうだったんだな」
湊の目からも、一筋の涙が頬を伝った。彼は自分の能力を呪っていた。だが、違った。この力があったからこそ、彼は栞の、そして彼女の父親の、目には見えない愛の深さに触れることができたのだ。
「栞」
湊は栞を強く抱きしめた。もう、触れることを躊躇わない。彼女の温もり、微かなシャンプーの香り、背中に伝わる鼓動。そのすべてが愛おしい。
「言ってくれて、ありがとう」
「ううん。聞いてくれて、ありがとう、湊」
二人はしばらくの間、言葉もなく抱きしめ合っていた。窓の外では、雨が上がって静かな夜が広がっている。
湊は、自分のこの力を、これからは「愛のサイコメトリー」と呼ぼうと心に決めた。それは、愛する人の心の奥底にある、言葉にならない想いや、見えない絆の形を教えてくれる、祝福の力なのだ。
彼の掌の中にあるブックカバーは、ただの贈り物ではない。それは、過去と現在、そして未来を繋ぐ、いくつもの愛が宿った、かけがえのない宝物だった。湊は、これからこのぬくもりと共に、栞と歩んでいく。触れることを恐れずに、愛の輪郭を確かめながら。