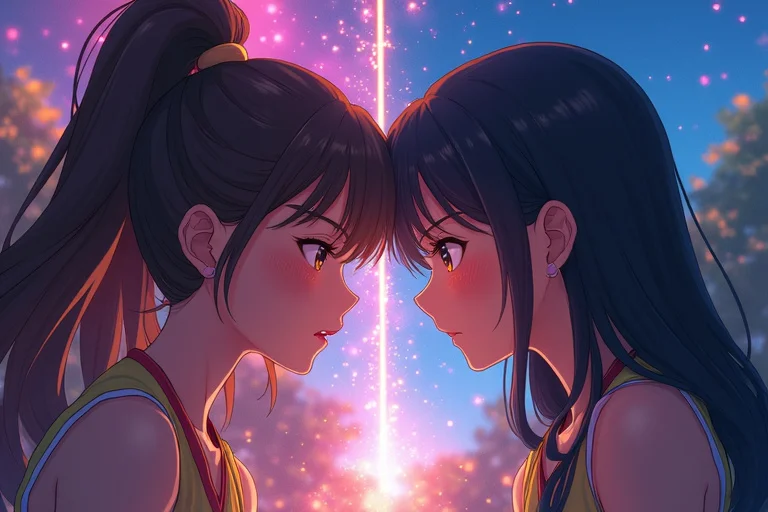第一章 共鳴する追憶
壁にもたれかかった僕、湊(みなと)の指先が、掌に収まるほどの滑らかな円盤状のデバイスに触れる。アコースティック・メモリー。それが、この世界のどんな楽器よりも僕の心を慰めてくれる、唯一無二の存在だった。ヘッドフォンを耳に当て、再生ボタンをそっと押す。
途端に、世界は色と音を取り戻す。
ザー、という柔らかなノイズの向こうから、夏の夕暮れの音が立ち昇ってきた。遠くで鳴くひぐらしの声が低音弦のように響き、僕らの足元の草が風に擦れる音は、繊細なパーカッションのようだ。そして、その中心で高らかに鳴り響く旋律。
「見てみろよ、湊!空が燃えてるみたいだ!」
陽(はる)の声だ。快活で、一点の曇りもない、真夏の太陽みたいな声。僕の記憶の中で、彼の声はいつもチェロのように豊かで温かい音色を奏でる。この音源は、三ヶ月前、陽が遠い街へ引っ越す直前に二人で見た丘の上の夕焼け。僕たちは、燃えるような空の下で、くだらない冗談を言い合って腹を抱えて笑った。その笑い声が、幾重にも重なるハーモニーとなって鼓膜を震わせる。
アコースティック・メモリーは、単なる録音機ではない。それは、僕と陽が共有した時間の「感情の響き」を記録する装置だ。楽しかった記憶は明るい長調のシンフォニーに、少しだけ切ない思い出は感傷的なピアノソナタに。二人で過ごした濃密な時間ほど、その音は深く、豊かになる。
陽がいなくなってから、僕の世界はひどく静かになった。内向的で、人と話すのが苦手な僕にとって、陽は唯一の「音」だった。彼がいれば、灰色の日常もフルカラーのミュージカルに変わった。しかし今、僕の周りには意味のない雑音しかない。だから僕は、こうして頻繁に過去の音に耳を澄ます。ヘッドフォンの中の完璧な世界に浸っている時だけ、僕は孤独を忘れられた。
最近、陽からの連絡は途絶えがちだった。新しい生活に忙しいのだろう。分かってはいても、胸に空いた穴は、日に日に大きく、深く、静かになっていく。僕はデバイスの再生を止め、訪れた完全な沈黙に耐えられず、再び別のトラックを選んだ。
『秘密基地の誓い』と名付けた音源。小学生の頃、神社の裏山に作った秘密基地で交わした約束の音だ。「僕たち、ずっと親友だからな」。幼い陽の声が、少しだけ上ずったヴァイオリンのように、純粋な響きで再生される。それに答える僕自身の声は、おぼつかなく震えるヴィオラのようだった。
この音を聞けば、大丈夫。僕たちの友情は、こんなにも美しい和音を奏でているのだから。距離なんて関係ない。そう自分に言い聞かせる。だが、その美しいハーモニーが、現実の静寂をより一層際立たせていることには、気づかないふりをしていた。僕の日常は、過去の共鳴にすがりつくことで、かろうじて成り立っていた。
第二章 沈黙のフーガ
最後に来た陽からのメッセージは、一週間前の『ごめん、今忙しい』という短いものだった。それきり、僕のスマートフォンが彼の名前を告げることはない。アコースティック・メモリーの中ではあんなに饒舌に語りかけてくる陽が、現実では遠い存在になっていく。その乖離が、僕の心を静かに蝕んでいった。
このままではダメだ。記憶の音に浸っているだけでは、いずれ僕たちの友情の弦は切れてしまうかもしれない。気づけば、僕は駅の券売機の前で、陽の住む街までの片道切符を握りしめていた。驚かせたい、という気持ちと、ただ彼の顔が見たいという純粋な衝動が、僕の足を動かしていた。
新幹線に揺られながら、僕は何度もアコースティック・メモリーを再生した。二人で徹夜してクリアしたゲームの、歓喜のファンファーレ。文化祭の準備中、ペンキまみれになって笑い転げた時の、不規則で陽気なリズム。それらの音は、これから始まる再会のプレリュード(前奏曲)のように聞こえた。僕たちの友情は、少しの休符を挟んだだけで、またすぐに力強いフォルテッシモを取り戻すはずだ。
陽の街は、僕の住む静かな地方都市とは違い、絶え間なく様々な音が溢れる場所だった。電車の往来、無数の人々の話し声、店のBGM。それは僕にとって不快なノイズの洪水でしかなく、早く陽という名の「調律された音楽」に会って、この不協和音から逃れたいと心から願った。
地図アプリを頼りに、陽が住むアパートにたどり着く。少し古びた、けれど清潔そうな建物だった。三階の一番奥の部屋。ドアの前に立ち、深呼吸を一つ。インターホンを押す指が、期待と不安でわずかに震えた。
数秒の沈黙の後、ドアがゆっくりと開いた。
「……湊?なんでここに?」
そこに立っていたのは、紛れもなく陽だった。けれど、僕の記憶の中の彼とは、どこか違っていた。彼の声は、僕が焦がれたチェロの温かい響きではなく、もっと乾いていて、平坦な音色をしていた。驚きよりも戸惑いの色が濃い表情に、僕の心臓が不自然なリズムを刻む。
「陽……会いに来ちゃった」
「ああ……まあ、入れよ」
通された部屋は、ダンボールが隅に寄せられたままで、まだ生活感がなかった。陽は僕に缶コーヒーを一つ渡すと、自分はベッドの端に腰掛け、気まずそうに床の一点を見つめている。僕たちの間に流れるのは、心地よい休符ではなく、息の詰まるような完全な沈黙だった。この沈黙は、アコースティック・メモリーには一度も記録されたことのない、冷たくて重い音だった。
第三章 不協和音の真実
「あのさ、覚えてるか?三ヶ月前の夕焼け。丘の上で見たやつ。すごかったよな」
耐え難い沈黙を破りたくて、僕は一番のお気に入りの記憶を口にした。アコースティック・メモリーの中で、最も輝かしいシンフォニーを奏でる思い出。陽もきっと笑顔で頷いてくれるはずだった。
しかし、陽は眉をひそめ、不思議そうな顔で僕を見た。
「夕焼け?ああ……そんなこと、あったっけな。ごめん、あんまり覚えてない。俺、そういうロマンチックなやつ、昔から興味ないだろ」
その言葉は、鋭いガラスの破片のように僕の鼓膜を突き刺した。興味がない?覚えていない?そんなはずはない。だって、あの時の君は、空が燃えていると、子供のようにはしゃいでいたじゃないか。僕の頭の中で鳴り響いていたはずの壮大なオーケストラが、突然プツリと途絶えた。
「う、嘘だろ?じゃあ、秘密基地の誓いは?ずっと親友だって……」
「秘密基地?ああ、あったな、そんなの。小学生の頃だろ?懐かしいな」
陽の反応は、まるで他人事だった。彼の声には、僕が大切に守ってきた記憶に対する熱量が、ひとかけらも含まれていない。僕が宝物のようにしてきた記憶の数々は、彼にとっては色褪せた過去の一コマに過ぎなかったのだ。
ショックで、言葉が出なかった。何かがおかしい。僕の知っている陽はどこにいるんだ?目の前にいるこの男は、一体誰なんだ?
僕は逃げるようにアパートを飛び出した。わけがわからないまま走り、近くの公園のベンチに倒れ込む。震える手でアコースティック・メモリーを取り出し、ヘッドフォンを装着した。確かめなければ。僕の記憶が、僕たちの友情が、本物だったという証拠を。
『丘の上の夕焼け』を再生する。
いつものように、ひぐらしの声と風の音が流れ、そして陽の快活な声が響き渡る。「見てみろよ、湊!空が燃えてるみたいだ!」
……そうだ、これだ。これが真実だ。
その時、ポケットのスマートフォンが震えた。画面には『陽』の文字。混乱しながらも通話ボタンを押すと、現実の陽の、あの乾いた声が耳に届いた。
『湊、ごめん。さっきは変な態度とって。でも、お前が話してる思い出、俺にはほとんどピンとこないんだ。お前の持ってるその機械、本当は何なんだ?』
ヘッドフォンの中の理想の陽の声と、電話越しの現実の陽の声が、頭の中で混ざり合い、耳障りな不協和音を生み出す。その瞬間、雷に打たれたように、僕の脳裏に封印されていた「本当の記憶」が蘇った。
あの夕焼けの日。僕たちは、些細なことで喧嘩していた。「お前はいつもそうだ」「お前に何がわかるんだ」。空の美しさなんて目に入らないまま、気まずい沈黙の中で丘を下りた。
秘密基地の誓いの日。僕は緊張して何も言えず、陽が一方的に「まあ、これからもよろしくな」とぶっきらぼうに言っただけだった。
笑い転げたはずの文化祭。僕は人混みが苦手で、ほとんど一人で隅にいただけだった。
アコースティック・メモリーは、単なる記録装置ではなかった。それは、僕の「こうであったらいいな」という願望を読み取り、現実の記憶を理想の形に「調律」し、美しい音楽として保存する装置だったのだ。
僕が今まで聞いてきた、僕たちの友情の証。あの美しいハーモニーは、すべて僕が作り上げた幻想。僕が一人で奏でていた、孤独なソロ演奏だったのだ。
デバイスが手から滑り落ち、地面に乾いた音を立てて転がった。僕の世界から、すべての音が消えた。
第四章 未完のソナタ
絶望とは、こういう音のない虚無のことを言うのだろうか。僕が信じ、支えられてきたものすべてが、砂の城のように崩れ去っていく。僕の友情は、僕が作り出した偽物だった。陽との関係も、僕が一方的に美化していただけの、独りよがりな幻想だったのだ。
公園のベンチでうずくまる僕の背後から、そっと声がした。
「湊」
顔を上げると、息を切らした陽が立っていた。その表情は、先ほどのアパートでの戸惑いとも、僕の記憶の中の快活さとも違う、不器用で、痛みを堪えるような顔だった。
「お前の気持ち、少しだけわかった気がする」
陽は僕の隣に静かに腰を下ろした。「俺は、お前が思うほど良い奴じゃない。不器用で、すぐ人を傷つけるし、自分のことで精一杯だ。だから……お前は、完璧な俺との思い出を作りたかったんじゃないか?」
涙が、堪えきれずに溢れ出した。
「でも、全部、偽物だったんだ……僕が聞いてた音は、僕が勝手に作った、嘘のハーモニーだったんだ」
「偽物か?」陽は静かに首を振った。「お前がそうやって、俺との関係を大事にしたいって必死に願ってくれたこと。その気持ちは、本物だろ?」
彼の言葉が、音を失った僕の世界に、小さな波紋を広げた。
「俺は、その気持ちに応えられてなかった。いつも自分のことばかりで、お前が何を感じてるかなんて、考えようともしなかった。ごめんな、湊」
陽は、落ちていたアコースティック・メモリーを拾い上げ、僕の手にそっと握らせた。
「なあ、湊。これからは、不協和音だらけかもしれない。喧嘩もするだろうし、気まずい沈黙だってあると思う。それでも……本当の音を、二人で作っていかないか?」
僕は、陽の顔を見つめた。彼の瞳には、僕が理想としていた輝きとは違う、頼りなく、けれどどこまでも誠実な光が宿っていた。それは、完璧な調律を施されたどんな音楽よりも、僕の心を強く揺さぶる響きを持っていた。
偽りの美しいハーモニーはもういらない。傷だらけで、ぎこちなくてもいい。僕は、目の前にいるこの不完全な陽と、本当の関係を築きたい。
僕は涙を拭い、アコースティック・メモリーの録音ボタンを押した。今まで一度も使ったことのない、赤いランプが小さく灯る。そして、陽に向かって、精一杯の力で微笑みかけた。
「……うん」
その一言は、装置の中で、これまで聞いたどんな美しい音色とも違う、少しだけ震えた、けれど温かい、新しい始まりの音として記録された。それは、まだメロディーもリズムも持たない、たった一つの単音。僕と陽の、これから始まる未完のソナタの、最初の音だった。