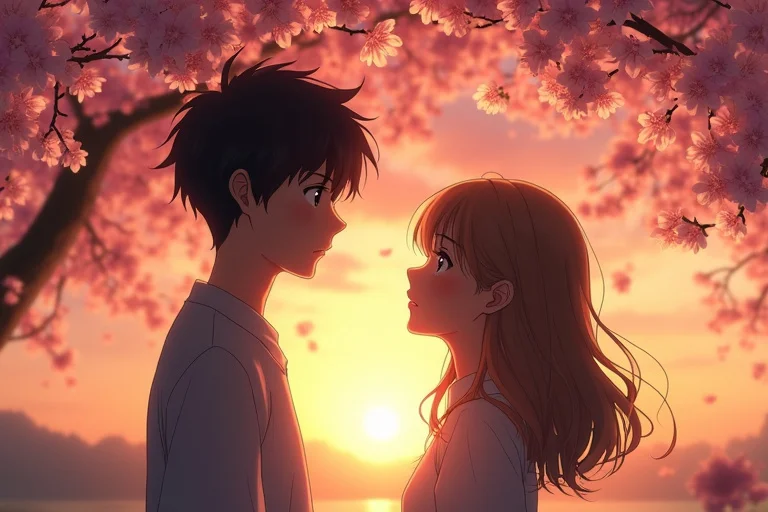第一章 凍てついたチューリップ
高槻湊の日常は、寸分の狂いもなく組み立てられた精密な模型のようだった。朝六時に起床し、きっかり七分間で身支度を整え、豆から挽いたコーヒーを飲み干す。七時半にアパートを出て、同じ歩幅で駅へ向かう。図書館司書という彼の職業は、この性格によく合っていた。分類され、整理され、静寂に満たされた世界。変化とは、そこに紛れ込むノイズでしかなかった。
その日、湊の完璧な日常に、ほんの僅かな不協和音が混じった。駅前のロータリーに設けられた小さな花壇。色とりどりのチューリップが、春の訪れを告げていた。昨日、赤いチューリップの一群の中に、一つだけ固く蕾を閉じたままの黄色い個体があったのを、彼は記憶していた。それが今朝、ほころび始めているはずだった。しかし、その黄色いチューリップは、昨日と全く同じ姿で、頑なに唇を結んでいた。
「……気のせいか」
湊は眉をひそめたが、すぐに思考を打ち切った。自分の記憶違いだろう。彼は人より少し、観察眼が鋭いだけだ。電車に乗り込み、いつもの車両のいつものドア横に立つ。窓の外を流れる景色は、昨日と何ら変わりない。それでよかった。彼は変化を好まない。
しかし、翌日も、黄色いチューリップは蕾のままだった。その翌日も。周囲の赤いチューリップが満開を迎え、少しずつ花びらの縁を茶色く変色させ始めているというのに、その一輪だけが、まるで琥珀の中に封じ込められたように、時間を拒絶していた。
異変は、それだけでは終わらなかった。
金曜日の午後、湊は図書館の窓から外を眺めていた。通りの向かいにある古い喫茶店『レンガ』。その窓には、一週間前から新しいブレンドコーヒーのポスターが貼られていた。セロハンテープで四隅を留められただけの、ありふれたポスター。しかし、左上のテープの端が、ほんの少しだけ、犬の耳のように折れ曲がっている。湊はその些細な特徴を覚えていた。先日の強風で、一度剥がれかかったからだ。
今日も、ポスターは全く同じ角度で折れ曲がったまま、窓に張り付いていた。風が吹いても、雨が降っても、ぴくりとも動かない。まるで、風景の一部として印刷された絵のように。
湊の胸に、冷たい染みがじわりと広がるのを感じた。世界が、彼の知らないうちに、少しずつ瞬きを忘れている。彼の愛した「変わらない日常」とは、静かに移ろい続ける時間の上に成り立つ、危うい均衡だった。今、彼が目にしているのは、それとは全く質の異なる、不気味な「停滞」だった。背筋を、ぞくりとした悪寒が駆け上った。
第二章 静止した風景のカタログ
停滞は伝染病のように、湊の視界を侵食し始めた。
彼は日記帳を一冊用意し、それを『停滞観察記録』と名付けた。几帳面な文字で、日付、場所、そして停滞している対象物を記録していく。それは、狂気に抗うための儀式であり、この世界で自分だけが正気であることの証明だった。
四月二十日、晴れ。近所の公園の砂場。昨日、子供たちが作ったであろう砂の城が、一粒の砂もこぼさずに同じ形を保っている。隣で揺れるブランコだけが、ぎい、ぎい、と時を刻んでいた。
四月二十二日、雨。アパートの隣の家の物干し竿。青いチェックのシャツが、雨に濡れることもなく、昨日と同じ皺の形でぶら下がっている。雨粒は、そのシャツだけを避けて落ちていくように見えた。
四月二十五日、曇り。商店街の八百屋の店先。木箱に山積みにされたトマトの一つが、不自然なまでに完璧な艶を放ち続けている。他のトマトが日に日に熟し、柔らかくなっていく中で、それだけが食品サンプルのような永遠性を宿していた。
湊は誰にも、この奇妙な発見を話すことができなかった。一度、同僚の司書に「駅前のチューリップ、一輪だけ咲かないんですよ」と漏らしたことがある。同僚は「へえ、そういう種類なんじゃない?」と興味なさそうに笑っただけだった。彼らにとって、それは世界のバグではなく、単なる日常の些事なのだ。孤独感が、じっとりとした湿気のように湊の心にまとわりついた。
変化を嫌っていたはずの自分が、今や必死で「変化」を探している。雲が流れること。木の葉が揺れること。道行く人の表情が変わること。それらが、まだ世界が生きている証のように思えた。停滞した物体は、まるで世界の写真に空いた小さな穴のようで、その向こうには底知れない虚無が広がっている気がした。
夜、自室の窓から外を眺めるのが、湊の新たな日課になった。彼の部屋は三階にあり、向かいのアパートの同じ階の部屋がよく見えた。そこに住んでいるのは、若い夫婦と、五歳くらいの女の子だった。湊は彼らと話したことはないが、その生活の断片を、窓越しに何度も見ていた。
母親がベランダで洗濯物を取り込む姿。父親が娘を肩車して帰ってくる姿。窓辺で絵本を読む娘の小さな横顔。それは湊にとって、彼の静かな日常を彩る、遠いけれど温かい風景の一部だった。
しかし、ある夜、湊はその窓に、新たな「停滞」を見つけてしまった。向かいの部屋のカーテンの隙間から、母親らしき女性の姿が見えた。彼女は窓辺に立ち、じっと外を眺めている。その表情までは窺えない。だが、問題は、彼女が昨日も、一昨日も、全く同じ時間に、全く同じ場所に、全く同じ格好で立っていたことだった。
湊は息を呑んだ。これまで停滞していたのは、無機物や植物だった。しかし、今、彼の目の前で、人間の時間が止まっている。これは、もはや世界のバグなどという生易しいものではない。何かが、根本的におかしくなっている。彼の整然とした世界は、音もなく崩壊を始めていた。
第三章 窓越しの永遠
恐怖が、湊の行動を後押しした。これはもう、観察しているだけでは済まされない。彼は日記帳を閉じ、コートを羽織ると、自分のアパートを飛び出した。冷たい夜気が肌を刺す。向かいのアパートのエントランスを抜け、エレベーターで三階へ向かう。心臓が、これまで感じたことのないほど激しく脈打っていた。
目的の部屋のドアの前で、湊は一度深呼吸をした。表札には『小野寺』と書かれている。震える指でインターホンを押すと、数秒の間をおいて、内側からドアが開いた。
現れたのは、憔悴しきった様子の若い男だった。目の下には深い隈が刻まれ、無精髭が伸びている。湊が窓から見ていた、娘を肩車していた父親だ。
「……どなたですか?」男は訝しげに湊を見た。
「突然申し訳ありません。向かいの……高槻と申します」湊は言葉を選びながら、慎重に切り出した。「少し、お伺いしたいことがありまして。その……奥様のことなんですが」
男の表情が、さっと曇った。「妻が、何か?」
「毎晩、窓辺に立っておられますよね。ここ数日、ずっと同じ時間に……。何か、ご事情でも?」
湊の言葉に、男はしばらく無言で立ち尽くしていた。その瞳が、絶望と諦念の入り混じった色に揺れる。やがて彼は、力なく微笑むと、湊を部屋の中に招き入れた。
「どうぞ。見ていってください」
部屋の中は、奇妙なほど生活感がなかった。家具は最小限で、壁には一枚の写真も飾られていない。男はリビングの中央、窓際に置かれた一台の大きな装置を指差した。それは湊が見たこともないような、複雑な配線とモニターを備えた機械だった。そして、その機械が、窓ガラスに向けて淡い光を投射していた。
湊が見ていた「窓辺の母親」は、そこにいなかった。
「あれは、妻ではありません」男――小野寺は、静かな声で語り始めた。「妻の……彩香と、娘の美咲は、一年前の春、交通事故で亡くなりました」
湊は息を呑んだ。言葉が出なかった。
「私は、耐えられなかった。あの二人がいない日常に。笑い声も、温もりも、何もかもが消えたこの部屋で、正気でいられる自信がなかった」
小野寺は装置に触れた。「これは、『メモリアル・シミュレーション』システムです。故人のSNS、写真、動画、日記……あらゆるデジタルデータをAIに学習させ、最も幸せだった一日を、ホログラムとして永遠に再現するんです」
彼はモニターの一つを操作した。すると、部屋の空間に、ふわりと映像が浮かび上がった。桜が舞う公園。楽しそうに笑う彩香さんと、その手を取って駆け出す美咲ちゃん。それは、あまりにも幸福で、胸が締め付けられるほど美しい光景だった。
「私が見ていたのは……」
「ええ。窓に投影された、ホログラムです。美咲が熱を出して、彩香が一日中、窓の外を眺めながら回復を祈っていた日。私にとっては、何でもない、でもかけがえのない一日でした」
湊は全身の力が抜けていくのを感じた。彼が追い続けてきた「停滞」の正体。世界の異常だと思っていた現象は、たった一人の男の、深すぎる愛と、癒えることのない悲しみの現れだったのだ。
「あなたの部屋から見える、あのチューリップや、公園の砂場……。おそらく、シミュレーションが外部の風景データを取り込む際に、何らかのエラーを起こしたんでしょう。投影範囲の境界で、時間の同期がズレてしまったのかもしれない。あなたの観察眼が鋭すぎたんですよ」小野寺は自嘲気味に笑った。
湊は、返す言葉が見つからなかった。変化のない日常を愛していた自分が、世界の「停滞」に恐怖を感じていた。その矛盾が、今、痛いほどによくわかった。日常とは、停滞ではない。昨日と今日が僅かに違うこと。花が咲き、そして萎れていくこと。そのささやかな変化の連なりこそが、「生きている」ということの証なのだ。
窓の外では、シミュレーションの彩香さんが、変わらない姿で、変わらない祈りを捧げている。永遠に終わらない一日の、優しい地獄の中で。
第四章 明日のための栞
湊は、小野寺に何も言わなかった。ただ深く、深く頭を下げて、彼の部屋を後にした。かけるべき言葉など、何一つ思いつかなかった。慰めも、同情も、彼の途方もない悲しみの前では、あまりに無力で、陳腐に思えた。
自分の部屋に戻り、ベッドに倒れ込む。天井の染みを見つめながら、湊は考えていた。自分は、小野寺を責めることができるだろうか。故人を偲び、その思い出の中に閉じこもる彼を、誰が非難できるというのか。自分だって、変化を恐れ、停滞した日常に安らぎを見出していたではないか。
夜が明けた。
湊は、いつもより少しだけ遅く家を出た。足取りは重かったが、不思議と心は静かだった。駅へ向かう道すがら、彼はあの花壇に目をやった。
昨日まで、頑なに蕾を閉じていた黄色いチューリップ。その花びらが、ほんの少しだけ、ほころんでいた。そして、隣で満開を誇っていた赤いチューリップの一輪が、力なく花びらを一枚、地面に落としていた。
小野寺が、シミュレーションを止めたのだろうか。それとも、湊自身の世界の見え方が、変わっただけなのだろうか。真実はわからない。だが、どちらでもよかった。
湊は、その萎れた花びらに、時の流れを見た。始まりがあれば、終わりがある。咲き誇る日があれば、散りゆく日もある。その止めどない移ろいの中にこそ、生命の輝きがある。彼は初めて、変化していく日常そのものを、心の底から愛おしいと感じた。
図書館に着くと、彼は自分の机に向かい、引き出しから『停滞観察記録』を取り出した。几帳面な文字で埋め尽くされたページを、彼はゆっくりと眺める。それは、世界の異常の記録であると同時に、変化から目を背けていた自分自身の記録でもあった。
湊は、最後のページを、力強く破り取った。そして、万年筆を手に取り、真っ白な新しいページに、静かにインクを走らせた。
『四月二十八日。今日、花が萎れた』
それは、世界の終わりではなく、彼の新しい日常の始まりを告げる、最初の言葉だった。窓の外では、街が動き、人が行き交い、雲が流れていく。当たり前で、そして奇跡のような風景。湊は、その全てを祝福するように、そっと目を閉じた。彼の心の中の景色もまた、ゆっくりと、しかし確かに、動き始めていた。