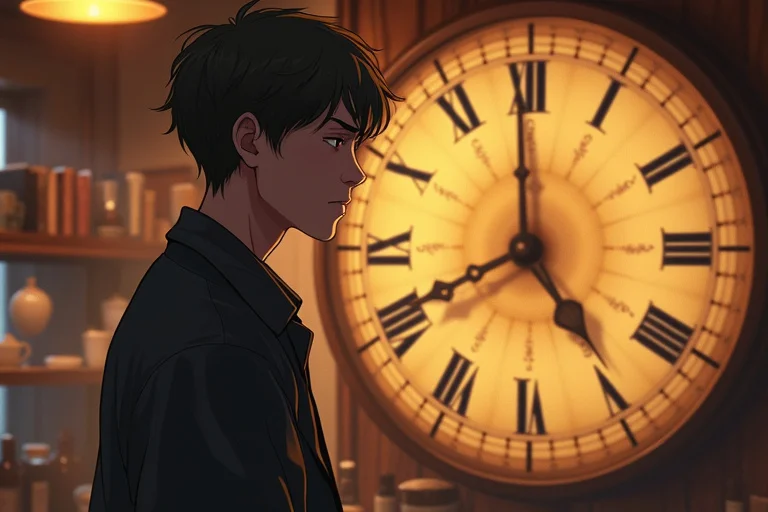第一章 色褪せたリスト
妻・美津子が死んで、一年が経った。四季が一巡りし、彼女のいない春が再び訪れたというのに、俺の心だけが凍てついた冬に取り残されたままだった。埃の積もったリビングの片隅で、段ボールに詰められたままの遺品を整理する気力も湧かない。それは、美津子との思い出を、そして彼女の「死」を、この手で完全に整理してしまう行為に思えたからだ。
しかし、娘の「お父さん、少しは前を向かなきゃ」という言葉に背中を押され、重い腰を上げたのが今日の昼過ぎのことだ。
段ボールの一つを開けると、樟脳の匂いと共に、美津子が大切にしていた小物が現れた。旅行先で集めたガラス細工、手触りの良いハンカチ、そして、年季の入った木製のオルゴール。蓋に施された薔薇の彫刻は、長年の月日で角が丸くなっている。俺がプロポーズの言葉と一緒に贈った、思い出の品だ。懐かしさで胸が詰まり、そっと蓋を開けた。
メロディーは鳴らない。とうの昔に壊れてしまったのだろう。だが、その空っぽのはずの箱の中に、一枚の折り畳まれた紙片が収まっていた。上質な和紙だ。日に焼けて、セピア色に染まっている。
広げてみると、そこには美津子のものだろう、丸みを帯びた優しい筆跡で、こう記されていた。
『私たちの思い出リスト』
その下に、箇条書きでいくつかの項目が並んでいる。
・雨の日の水族館、イルカのジャンプ
・真夜中のベランダ、二人だけの天体観測
・初めて喧嘩した後の、クリームソーダの味
・木漏れ日の公園で読んだ、詩集の言葉
読み進めるうちに、俺の眉間に深い皺が刻まれていくのが自分でも分かった。なんだ、これは。雨の日に水族館へ行った記憶など、俺にはない。そもそも俺は人混みが苦手で、水族館など何十年も足を運んでいない。ベランダでの天体観測? そんなロマンチックな真似をした覚えもない。クリームソーダも、公園での詩集も、全く身に覚えがなかった。
これは、誰との思い出だ?
心臓が、冷たい手で鷲掴みにされたような感覚に陥った。まさか。美津子に限って、そんなことがあるはずがない。四十年以上も連れ添ってきた妻だ。彼女が俺以外の誰かと、こんなにも親密な時間を共有していたというのか?
オルゴールは、空っぽではなかった。俺の知らない、そして知りたくもなかった「誰か」との思い出で、満たされていたのだ。俺は力なく紙片を握りしめた。カサリ、と乾いた音が、静まり返った部屋に虚しく響いた。それは、俺たちの結婚生活そのものが、音を立てて崩れていく前触れのようだった。
第二章 知らない妻の横顔
翌日から、俺の奇妙な巡礼が始まった。リストの謎を、この目で確かめずにはいられなかったのだ。疑念と、ほんのわずかな希望――何かの間違いであってほしいという願い――を胸に、俺はまず「雨の日の水族館」を目指した。
あいにく天気は快晴だったが、俺はわざわざ電車を乗り継いで、隣町の古びた水族館へ向かった。薄暗い館内は、平日の昼間だというのに、遠足の子供たちの歓声で満ちていた。俺は人波をかき分けるようにして、イルカショーのプールサイドにたどり着く。
ショーが始まると、軽快な音楽に合わせてイルカたちが見事なジャンプを繰り返した。水しぶきが太陽の光を浴びて、虹のように煌めく。子供たちが手を叩いて喜ぶ中、俺はただ呆然と立ち尽くしていた。もし、美津子がここにいたのなら。彼女はどんな顔で、この光景を見ていたのだろう。俺の知らない男の隣で、少女のように微笑んでいたのだろうか。想像するだけで、胃の腑がキリキリと痛んだ。
次に訪れたのは「木漏れ日の公園」だ。リストには公園の名前までは書かれていなかったが、近所で一番大きな、欅並木の美しい公園に違いないと見当をつけた。ベンチに腰掛け、美津子が好んで読んでいた詩集を開く。ページをめくる指が、微かに震えた。
『あなたのいない世界は、色のない絵のようだ』
そんな一節が目に留まる。まるで今の俺の心情を言い当てられたようで、息が詰まった。美津子も、この詩を読んだのだろうか。そして、隣にいる「誰か」に、その感動を伝えたのだろうか。
公園のベンチで、水族館のプールサイドで、俺が見つけたのは、妻との思い出ではなかった。そこにいたのは、俺が全く知らなかった「美津子」という一人の女性の姿だった。俺が知っている彼女は、いつも家庭を守り、少しおっちょこちょいで、花を愛する穏やかな妻だった。だが、リストの中の彼女は、もっと自由で、情熱的で、生き生きとしているように思えた。
もしかしたら、俺が彼女を、退屈な日常に縛り付けていたのではないか。夫という役割に胡坐をかき、彼女の心をちゃんと見ていなかったのではないか。
罪悪感と嫉妬が、黒い渦となって胸の中で膨れ上がっていく。リストの紙片は、今や俺の罪を告発する告発状のように思えた。俺は、妻の何を分かっていたというのだろう。帰りの電車の中、窓ガラスに映る自分の顔は、ひどく老け込んで見えた。
第三章 真実の在り処
巡礼は、俺の心を癒すどころか、ますます深い闇へと引きずり込んでいった。疑念は確信に変わりつつあり、美津子の思い出が詰まっているはずのこの家さえも、息苦しい場所に感じられた。もう、何もかも捨ててしまいたい。そんな衝動に駆られ、再び遺品の段ボールに手をかけた時だった。
箱の底から、一冊の分厚いノートが顔を出した。どこにでもある、大学ノートだ。表紙には何も書かれていない。何気なくページをめくった俺は、そこに並んだ文字を見て、息を呑んだ。それは、紛れもなく美津子の筆跡だった。
日記だ。
背徳感に苛まれながらも、俺は渇いた喉で唾を飲み込み、そのページを貪るように読み始めた。日付は、彼女が亡くなる五年前から始まっていた。
『今日、病院で先生からお話があった。若年性アルツハイマー型認知症、だそうだ。頭が真っ白になった。これから、少しずつ記憶が消えていくらしい。和彦さんとの大切な思い出も、いつか忘れてしまうのだろうか。それが、何よりも怖い』
心臓が、大きく跳ねた。アルツハイマー? 美津子が? 俺は全く知らなかった。彼女はそんな素振りを微塵も見せなかった。
ページをめくる手が、震えを抑えきれない。
『〇月×日。昨夜、和彦さんとベランダから流れ星を見た。ほんの数秒の出来事だったけど、すごく綺麗だった。忘れないように、すぐに書き留めておこう。「真夜中のベランダ、二人だけの天体観測」。うん、素敵な響きだ』
『〇月△日。テレビで水族館の特集をやっていた。イルカが空を飛んでいるみたいだった。昔、和彦さんといつか行こうねと話したのを思い出した。結局行けずじまいだったけど、テレビの前で二人で見たこの時間も、私にとっては宝物。「雨の日の水族館、イルカのジャンプ」。リストに加えよう』
『〇月□日。些細なことで和彦さんと喧嘩してしまった。私が悪いのに、素直に謝れなかった。気まずい空気の中、彼が黙ってクリームソーダを作ってくれた。昔、喫茶店で初めてデートした時に飲んだのと同じ味。緑色の炭酸が、心の棘を溶かしてくれた気がした。「初めて喧Kaした後の、クリームソーダの味」。ありがとう、和彦さん』
そこにあったのは、俺が「些細な日常」として記憶の隅にも留めていなかった、ささやかな出来事の記録だった。美津子は、それら一つ一つを、失われゆく記憶の海の中から必死に掬い上げ、宝物のように大切に書き留めていたのだ。
俺が浮気を疑った「誰か」は、どこにも存在しなかった。リストに書かれた思い出の相手は、紛れもなく、この俺だったのだ。美津子は、病の進行によって薄れていく「俺との思い出」を、忘れたくなかった。ただ、その一心で。
俺は、なんて愚かだったんだ。彼女の深い愛情にも、孤独な闘いにも気づかず、勝手に疑い、傷ついていた。日記の最後の方のページは、文字が乱れ、同じ言葉が何度も繰り返されていた。彼女が最後まで必死に繋ぎ止めようとしていた記憶の断片が、そこには痛々しく散らばっていた。
「美津子……ごめん……ごめんな」
声にならない嗚咽が、喉から漏れた。涙が次から次へと溢れ出し、日記のページに滲んで染みを作った。それは、まるで乾ききった俺の心に、ようやく降り注いだ慈雨のようだった。
第四章 二人分のオルゴール
俺は顔を上げ、もう一度、あの木製のオルゴールを手に取った。蓋に彫られた薔薇のレリーフを、震える指でそっと撫でる。このオルゴールは、空っぽなんかじゃなかった。壊れてもいなかった。ただ、俺がその鳴らし方を知らなかっただけだ。
美津子の日記と、色褪せたリスト。それらが、このオルゴールを再び鳴らすための、たった一つの鍵だった。
リストに書かれた思い出は、俺が忘れてしまっていた、あるいは日常に埋もれて気づきもしなかった、ささやかな幸福の記録だ。美津子にとっては、その一つ一つが、どんな宝石よりも価値のある輝きを放っていたのだろう。彼女は、俺が思っていた以上に、俺を、そして俺との生活を、深く、深く愛してくれていた。
俺はリストを丁寧に折り畳み、日記と一緒にオルゴールの中に戻した。そして、静かに蓋を閉じる。
これからは、俺がこの記憶を守っていこう。俺が、二人分の記憶を生きていこう。美津子が忘れることをあれほど恐れた思い出を、今度は俺が、一日たりとも忘れない。そう、心に誓った。
窓の外では、いつの間にか夕日が西の空を茜色に染めていた。部屋の中に差し込む光が、埃の中でキラキラと舞っている。それはまるで、祝福の紙吹雪のようにも見えた。
不思議なことに、あれほど重く感じていた部屋の空気が、今は澄み渡っているように感じられる。美津子のいない寂しさが消えたわけではない。だが、その寂しさの底に、温かく、確かな光が灯ったのだ。
ふと、オルゴールの巻き鍵に指が触れた。今まで壊れていると決めつけて、一度も回そうとしなかったネジだ。試しに、ゆっくりと回してみる。カチ、カチ、と微かな抵抗を感じながら、ネジが巻かれていく。
そして、蓋を開けた。
―――澄んだメロディーが、静寂を破って流れ出した。
それは、俺たちの結婚式で流した、懐かしいワルツの曲だった。途切れ途切れで、少し調子が外れているけれど、紛れもなく、あの日の音楽だ。
止まっていた時間が、再び動き出す。音色は、美津子の笑い声のように優しく、部屋の隅々まで満たしていく。俺は目を閉じ、そのメロディーに耳を澄ませた。
そこには、確かに美津子がいた。俺の隣で、はにかむように微笑んでいる。
オルゴールは、もう空っぽじゃない。俺と美津子、二人分の愛と記憶で、今、確かに満たされているのだ。俺は涙で滲む夕焼け空を見上げながら、そっと呟いた。
「ありがとう、美津子。これからも、ずっと一緒だな」
音の粒が、光の粒子となって溶けていく。俺の日常は、これからも続いていく。だが、それはもう、昨日までと同じ「日常」ではなかった。