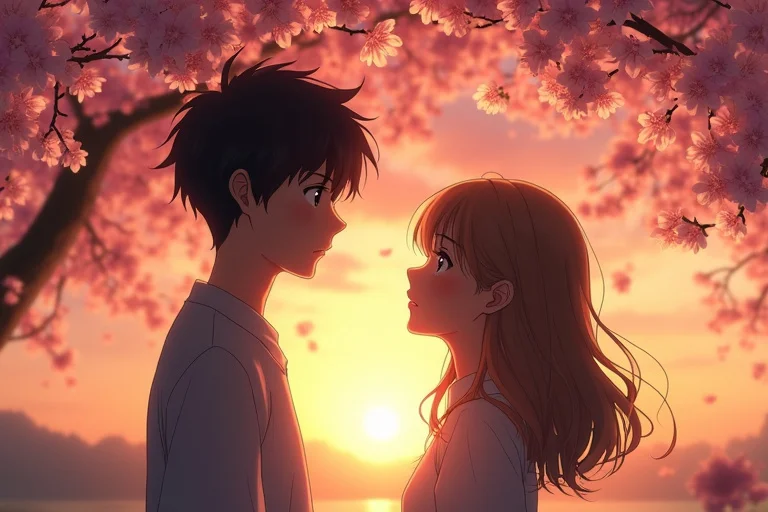第一章 影法師のスケッチ
望月健斗の日常は、寸分の狂いもない精緻な機械仕掛けのようだった。午前六時半に鳴るスマートフォンのアラーム。遮光カーテンの隙間から差し込む、計算された一筋の光。豆から挽いたコーヒーの、苦くも芳しい香りが、彼の覚醒の合図だった。システムエンジニアである彼の仕事場は、静まり返った自室のデスク。リモートワークという自由な環境下にありながら、彼は自らに厳格なルールを課していた。九時から十七時までは、私語ひとつなくコードの森を彷徨い、昼休憩はきっかり六十分。近所の公園のベンチで、コンビニのサンドイッチを齧るのが常だった。
変化は、退化だ。健斗はそう信じていた。予測不能な出来事はノイズであり、心の平穏を乱すバグに過ぎない。だから彼は、この完璧に制御された日常を愛していた。それは、誰にも侵されることのない、彼だけの聖域のはずだった。
異変が起きたのは、木犀の香りが街角に立ち始めた、ある火曜日のことだった。
仕事を終え、ポストを覗くと、見慣れない一通の封筒が入っていた。宛名も差出人もない、ただ真っ白な封筒。警戒しながら中身を滑り出させると、現れたのはスケッチブックを破り取ったような、ざらついた質感の一枚の紙片だった。
そこに描かれていたのは、鉛筆の濃淡だけで表現された、公園の古びた滑り台。
健斗は息を呑んだ。それは、彼がまさに今日の昼休憩に、サンドイッチを食べながらぼんやりと眺めていた、あの滑り台そのものだった。錆の浮いた手すり、子供たちの落書きがうっすらと残る側面。その描写は、写真かと見紛うほどに正確だった。
偶然か。いや、しかし。背筋を冷たいものが走り抜ける。誰かが、自分を見ている。その確信が、健斗の完璧な日常に、最初の亀裂を入れた。
その日から、差出人不明のスケッチは毎日届くようになった。彼が昼に立ち寄った書店の、平積みの新刊コーナー。夕暮れ時に見上げた、電線にとまる一羽の鴉。昨日、自販機で買った缶コーヒーの銘柄。健斗がその日に見た風景が、翌朝には必ずポストに投函されているのだ。
ストーカー。その悍ましい単語が頭をよぎる。健斗は犯人を特定しようと、わざと行動パターンを変えてみた。いつもと違う道を通ってスーパーへ向かい、普段は行かないカフェに入った。しかし、無駄だった。翌朝届けられたスケ-ッチには、そのカフェの窓辺に置かれた小さなサボテンが、克明に描かれていた。
まるで、影法師のように寄り添い、彼の視界を盗み見ている存在。その気配は、健斗の心をじわじわと蝕んでいった。彼の聖域は、静かに、しかし確実に侵食され始めていた。
第二章 色づく日々
不気味なスケッチが届き始めて二週間が経った。健斗の心は、恐怖と苛立ち、そして奇妙な好奇心の間で揺れ動いていた。警察に相談するにも、描かれているのは無害な風景画ばかりで、具体的な脅迫や要求があるわけではない。ただ、監視されているという事実だけが、鉛のように重くのしかかっていた。
変化は、スケッチそのものに現れ始めた。
ある朝、ポストから取り出した紙片を見て、健斗は僅かに目を見開いた。いつもモノクロだったはずの絵に、色がついていたのだ。それは、彼が昨日見上げた夕焼けの風景。空を染める茜色と、ビルの輪郭を溶かすような深い橙色が、淡い水彩絵の具で繊細に表現されていた。それは恐怖を煽るというより、むしろ息をのむほどに美しかった。
それからというもの、スケッチは日ごとに色彩を増していった。雨上がりのアスファルトに反射するネオンの滲んだ光、路傍に咲く紫陽花の露を含んだ青、神社の境内で見かけた三毛猫の柔らかな毛並み。犯人は、健斗の目を通して世界を見、それをキャンバスの上で再現しているかのようだった。
健斗は、いつしかそのスケッチを捨てるのをやめていた。最初は証拠として保管するつもりだったが、今は違う。彼は無機質だった自室の壁に、それらの紙片を一枚、また一枚と貼り付けていった。殺風景な白い壁は、いつしか様々な風景と色彩で埋め尽くされ、まるで世界の断片を集めたギャラリーのようになった。
彼は壁を眺めながら、自分が無意識のうちに通り過ぎていた日常の美しさに気づかされる。規則正しいだけの退屈な風景だと思っていた道端に、こんなにも豊かな表情があったとは。
皮肉なことに、ストーカーの存在が、健斗に世界の解像度を上げることを強いていた。彼は外出するたび、以前よりも注意深く周囲を観察するようになった。明日のスケッチには、何が描かれるだろうか。恐怖心は薄れ、それは次第に、未知の相手との静かな対話のような感覚に変わっていった。
壁に貼られたスケッチを見つめる。それは、健斗自身の生きた軌跡そのものだった。彼の平穏だが空虚だった日常は、名前も顔も知らぬ誰かによって、少しずつ、しかし確実に色づき始めていた。
第三章 聞こえる風景
決定的な転機は、突然訪れた。
その日届いたスケッチを見て、健斗は凍りついた。描かれていたのは、彼が幼い頃に住んでいた家の庭だ。夏の陽光を浴びて輝く向日葵と、今はもう撤去されてしまった古びた鉄のブランコ。それは、今日の風景ではない。二十年以上も前の、彼の記憶の底に眠っていた原風景だった。
どうして。ストーカーは、なぜ自分の過去を知っている?
健斗の頭は混乱した。これまで築き上げてきた「監視されている」という仮説が、ガラガラと音を立てて崩れていく。これは、単なるストーキングではない。もっと深く、不可解な何かが関わっている。
翌朝、ポストにはスケッチの代わりに、一枚のメモだけが入っていた。拙い、震えるような文字で、こう書かれていた。
『明日の午後三時、いつもの公園で』
いつもの公園。昼休憩を過ごす、あの場所だ。健斗は腹を決めた。この謎めいたゲームに、終止符を打つ時が来たのだ。
約束の日、健斗は心臓の音を背中に聞きながら、公園のベンチに座っていた。午後三時。きっかりその時間に、一人のヘルパーに付き添われた車椅子の老婦人が、ゆっくりとこちらに近づいてきた。健斗は彼女に見覚えがあった。隣のアパートに住む、高村さんだ。病気で寝たきりに近い状態で、ここ数年は姿をほとんど見ていなかった。
車椅子は、健斗の隣で止まった。高村さんは、陽光に目を細めながら、か細い、しかし澄んだ声で言った。
「望月さん。…ごめんなさいね、驚かせたでしょう」
健斗は言葉を失った。まさか、この弱々しい老婆が、あのスケッチの送り主だというのか。
「どうして…あなたが」
「ええ、私が描いていました」。高村さんは、静かに頷いた。「病気でね、もうずっと外には出られなかった。窓から見える景色を描くのが、唯一の楽しみだったの」
彼女は、ゆっくりと続けた。
「でも、最近、とうとう目もほとんど見えなくなってしまってね。もう何も描けないと、絶望していたんです」
では、なぜ。健斗の疑問を察したように、彼女は微笑んだ。
「あなたの『音』を、聴いていたのよ」
音? 健斗は眉をひそめた。
「毎朝、決まった時間に聞こえるあなたの足音。日中、壁の向こうから微かに響く、キーボードを打つ音。時々、ベランダでコーヒーを飲むんでしょう? マグカップを置く、カタン、という小さな音。あなたの生活音が、ベッドの上の私にとっての、時計であり、カレンダーだったんです。あなたの音が聞こえると、ああ、今日も一日が始まるんだ、世界はまだ動いているんだって、安心できたのよ」
高村さんの言葉は、健斗の胸に深く突き刺さった。
「視力を失って、何も見えなくなった日。いつものように、あなたが家を出ていく足音を聴いていたの。そうしたら、不思議なことが起きた。…あなたの見ている風景が、頭の中に流れ込んでくるように、見えたんです」
駅前のポスト、商店街の猫、カフェのサボテン。それは、共感覚の一種だったのか、あるいは孤独な魂が響き合わせた奇跡だったのか、誰にも分からない。
「あなたの目を通して、私はもう一度、世界を見ることができた。本当に、楽しかった…」
幼い頃の庭の絵は、と健斗が尋ねる前に、彼女は答えた。
「先日、お母様と電話で話していましたね。壁が薄いから、聞こえてしまって。あなたの楽しそうな声から、懐かしい風景が見えたのよ。本当に、綺麗だったわ」
そう言って、高村さんは震える手で、一枚の真っ白なスケッチブックの切れ端を健斗に差し出した。
「これが、今の私の世界。もう、何も見えない。でもね…」
彼女は健斗の方を向き、光を失った瞳で、確かに彼を捉えた。
「あなたの音は、ちゃんと聞こえているわ。ありがとう。私の退屈な日々に、彩りをくれて」
健斗は、自分が無価値だと思っていた日常が、隣で静かに生きる人の世界そのものを照らしていたという事実に、打ちのめされた。彼の価値観が、根底から覆った瞬間だった。
第四章 きみのための世界
あの日を境に、望月健斗の世界は変わった。いや、世界が変わったのではない。彼自身が変わったのだ。
彼が退屈なルーティンだと思っていた毎日は、誰かにとってのかけがえのない「物語」だった。彼が刻むキーボードの音は、誰かにとっての「今日」を知らせるチャイムだった。彼が淹れるコーヒーの香りは、壁を越えて届くことはなくとも、その気配は、誰かの孤独を温めていたのかもしれない。
自分の存在には、意味があった。そう知った瞬間から、彼の日常は、驚くほどの輝きを放ち始めた。
翌朝、健斗はいつものようにベランダに出て、コーヒーを淹れた。そして、隣のアパートの、高村さんのいるはずの窓に向かって、静かに語りかけた。
「高村さん、おはようございます。今朝の空は、鱗雲が広がって、秋らしいですよ」
返事はない。だが、聞こえているはずだ。健斗は、自分の五感を総動員して、世界を捉えようとした。高村さんのために。
「公園の金木犀が、満開です。風が吹くたびに、甘い香りがします」
「今日の昼は、トマトソースのパスタを食べました。酸味とニンニクの香りが、食欲をそそるんです」
彼は、自分の視覚、嗅覚、味覚を、言葉という音に変えて、高村さんに届け続けた。それは、日に日に彼の習慣になっていった。誰かのために世界を切り取るという行為は、皮肉にも、彼自身の人生を何倍も豊かにした。道端の雑草の生命力に、子供たちの屈託のない笑い声に、夕陽に染まる電車の窓の美しさに、彼は生まれて初めて心から感動するようになった。
ある週末、健斗は文房具店にいた。そして、一冊のスケッチブックと、水彩絵の具のセットを買った。
自室のベランダに出る。壁一枚を隔てた隣人に語りかけるように、彼は新しいスケッチブックの、真っ白なページを開いた。
「高村さん。今から、僕が絵を描いてみます。あなたが見せてくれたみたいに、うまくはないかもしれませんけど」
彼は、眼下に広がる、見慣れた、しかし今は愛おしい街の風景に筆を走らせた。不器用な線が、ぎこちない色彩が、紙の上に少しずつ世界を立ち上げていく。
それは、高村さんが描いてくれたような、神業じみた精密な絵ではなかった。だが、そこには確かな「意志」が込められていた。誰かと世界を分かち合いたいという、切実で温かい願い。
彼の日常は、もはや自己完結した無菌室ではない。隣人の気配を感じ、世界と繋がり、言葉と色彩を紡いでいく、かけがえのない舞台となった。
健斗は、描き上げたばかりの絵を太陽に透かす。淡い光が、彼の不器用な世界を優しく照らしていた。僕の音は、僕の言葉は、僕の絵は、きみの世界に届いているだろうか。
日常とは、それ自体が奇跡なのかもしれない。誰かにとっての光や音になっているとは知らずに、僕たちは、ただ懸命に今日という日を生きている。そして、時折、その響きは壁を越え、孤独な魂をそっと温めるのだ。
健斗は、もう一枚、新しいページをめくった。風が、次の物語の始まりを告げるように、優しく彼の頬を撫でていった。