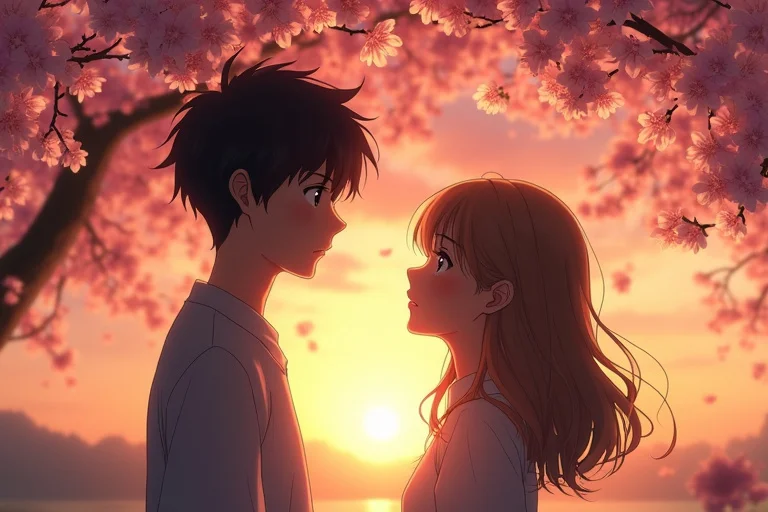佐藤健太の日常は、秒単位で組み立てられた精密機械のようだった。毎朝六時半に起床。七時十五分の電車に乗り、決まって後ろから三両目の右側のドア、そのすぐ横の席に座る。そこが彼の定位置だった。車窓から流れる灰色のビル群をBGMに、無心でスマホを眺める。それが、退屈で、しかし安心できる彼の世界の全てだった。
その月曜日の朝までは。
ふと顔を上げた健太は、目を疑った。いつもはただの雑居ビルが連なる風景の中に、違和感が鎮座していた。五階建ての古いビルの屋上に、巨大な三毛猫がいたのだ。全長五メートルはあろうかという、リアルな質感の置物。右手を挙げた、典型的な招き猫のポーズだ。
「……え?」
思わず声が漏れた。あんなもの、先週まであっただろうか。いや、あるはずがない。あんなに巨大なものが突如現れれば、ネットニュースくらいにはなるはずだ。だが、周囲の乗客は誰一人として気にも留めていない。
火曜日の朝。健太は昨日の幻覚を確かめるように、ビルの見える区間に差し掛かると窓に張り付いた。猫は、いた。だが、ポーズが違う。昨日挙げていたはずの右手の代わりに、今日は左手を優雅に掲げている。まるで「人もお金も、どんと来い」とでも言うように。
水曜日。猫は同じビルの屋上の隅に移動し、香箱座りをしていた。その姿は、街全体を見守る王様のように堂々としている。健太は確信した。これは、動いている。彼は急いでスマホを取り出し、証拠写真を撮った。
木曜日。いつものビルに猫の姿はなかった。健太の胸に、ちくりと小さな失望が刺さる。終わってしまったのか。だが、諦めきれずに視線を彷徨わせると、彼は見つけた。隣の、もっと背の高いビルの屋上で、気持ちよさそうにぐーっと伸びをしている猫の姿を。
その日から、健太の通勤時間は宝探しに変わった。
「今日はどこだ?」「どんなポーズだ?」
つり革広告やスマホのニュースよりも、窓の外の風景が何倍も面白くなった。ビルの影、クレーンの上、アンテナの横。まるでかくれんぼを楽しむように、猫は毎日違う場所に、違う姿で現れた。この壮大な秘密を、この車両で、いや、おそらくこの世界で知っているのは自分だけだ。その事実が、健太の灰色の日常に鮮やかなインクを垂らした。
そして、運命の金曜日がやってきた。
その日は朝から土砂降りで、強風が街路樹を揺らしていた。電車はノロノロと進み、車内には湿った空気が充満している。健太がいつものように猫を探すと、思わぬ場所にその姿を見つけた。建設中のビルの、巨大なクレーンの真下だ。猫は身を丸め、まるで何かからクレーンを守るようにうずくまっている。
健太は違和感を覚えた。よく見ると、クレーンのアームの一部が不自然に傾ぎ、強風に煽られて危険なほど揺れている。今にも外れて、真下の道路に落下しそうだ。
「まずい!」
健太は衝動的に立ち上がると、震える手で鉄道会社の緊急連絡先に電話をかけた。
「もしもし!今、電車から見えたんですが、○○駅手前の建設現場のクレーンが、すごく危ない状態で……!」
一気にまくしたて、彼は言葉を呑んだ。「その下に、巨大な猫が」という、最も重要な事実を伝えることはできなかった。
その日の夕方、テレビのニュースが、クレーンのアーム落下事故が未然に防がれたことを報じていた。匿名の一本の通報がきっかけだった、とアナウンサーは言った。
週が明けた月曜日。空は嘘のように晴れ渡っていた。
健太は、少しだけ高鳴る胸を押さえながら、いつもの定位置から窓の外を見つめた。
猫は、いた。
一番最初に見つけた、あの五階建てのビルの屋上の、ど真ん中に。誇らしげに胸を張り、右手を高く、高く掲げていた。その目はまっすぐにこちらを見つめ、まるで「よくやったな、相棒」と、ウインクしているように見えた。
健太は、窓ガラスに映る自分の顔が笑っているのに気づいた。彼は誰にも見えないように、そっと窓の向こうの守り神に向かって、親指を立てた。
午前七時三十二分。彼の退屈だった日常は、壮大な秘密を乗せて、今日もまた走り出す。明日、あの猫はどこにいるだろう。考えるだけで、胸が躍った。