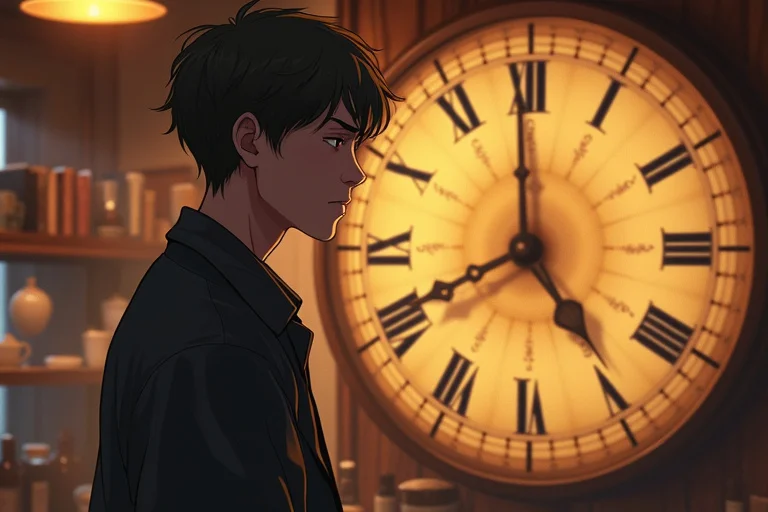デジタル時計の数字が17時59分から18時00分へと無機質に変わる瞬間、佐藤誠はいつも息を詰める。オフィスに充満するカフェインと焦燥の匂いの中で、その瞬間だけが彼にとっての聖域であり、同時に戦いのゴングだった。
「お先に失礼します」
誰に言うでもなく呟き、パソコンの電源を落とす。彼の声は、深夜残業へと向かう同僚たちのキーボードを叩く音の波間に、小石のように沈んでいった。コピー機の前で腕を組む後輩の田中が、聞こえよがしに「ミスター・シックスのお帰りだ」と囁くのが聞こえる。六時きっかりに帰る男。それが、この会社での佐藤の呼び名だった。部長の眉間に刻まれた深い谷を見ないようにして、佐藤は逃げるようにオフィスを後にする。エレベーターの扉が閉まる瞬間、ガラスに映った自分の顔は、罪悪感と安堵が混じり合った、ひどく情けない表情をしていた。
満員電車に揺られながら、彼はいつも窓の外の景色を追う。家々の灯りが、まるで遠い星のように瞬いては流れていく。どの窓の下にも、それぞれの日常があるのだろう。温かい食卓、子供の笑い声、穏やかな時間。自分は、そのどれからも遠い場所にいるような気がした。
会社では社運を賭けた大型コンペの準備が佳境を迎えていた。チーム全員が泊まり込みも辞さない覚悟で、モニターの光に顔を青く染めている。佐藤も日中は、誰よりも集中して資料を作り、分析を行った。だが、あのサイレンが鳴れば、彼はすべてを中断する。
「佐藤!今日くらいは残れ!チームの一員としての自覚はないのか!」
ついに部長の怒号が飛んだ。四方から突き刺さる非難の視線が、彼の背中を焼くようだった。
「申し訳ありません。ですが、帰らせていただきます」
深く頭を下げることしかできない。どうして帰るのか、そのたった一つの理由を、彼は誰にも言えなかった。言えばきっと、同情という名の気遣いが、彼が守りたいものを歪めてしまう気がしたのだ。申し訳ない。本当に。心の中で繰り返しながら、彼はまた独り、夜の街へと歩き出す。足が向かうのは、自宅ではなく、電車を乗り継いだ先にある郊外の総合病院だった。
プレゼンを明日に控えた夜、事態は起きた。クライアントから、企画の根幹を揺るがすコンセプトの修正依頼が舞い込んだのだ。時間は、夜の10時を回っていた。オフィスは絶望的な沈黙に包まれ、誰もが頭を抱えていた。
「くそっ、もう間に合わない…!」
苛立ちを隠せない田中が、何かヒントはないかと佐藤のデスクを半ば八つ当たりのように漁り始めた。その時、乱雑に積まれた書類の下から、一冊のくたびれた絵本が滑り落ちた。『星を釣るクマ』。何度も読み返されたのであろう、ページの角は丸く、表紙には小さな手の跡がいくつもついている。見返しには、たどたどしい文字で『パパへ ひかり』と書かれていた。
田中は、吸い寄せられるようにそのページをめくった。夜空の星を、長い釣り竿で一つずつ釣り上げる心優しいクマの物語。その素朴で、あまりに場違いな物語の中に、彼は稲妻のような閃きを感じた。点在する課題を、一つずつ丁寧に解決していく。派手さはないが、誠実なアプローチ。これだ。これこそ、今の自分たちに足りなかった視点じゃないか。
田中はいてもたってもいられず、緊急連絡先リストから佐藤の携帯を鳴らした。数回のコールの後、ようやく繋がった電話の向こうから、聞き慣れない電子音が微かに聞こえてくる。ピッ、ピッ、と静かに時を刻む音。
「佐藤さん、今どこですか?」
「……病院だ」
かすれた声だった。
「え……?」
「娘が、いるんだ。一年前から。毎晩、六時半に絵本を読んでやらないと、あいつ、眠れないんだよ」
それは、悲痛な告白だった。毎晩18時に鳴るサイレンは、彼にとって、娘との約束を守るためのスタートの合図だったのだ。チームへの裏切りではなく、たった一人の家族を守るための、孤独な戦いだった。
電話を切った田中は、立ち尽くすチームメンバーに、震える声で全てを話した。オフィスは水を打ったように静まり返り、誰もが自分たちの身勝手な言葉を恥じた。やがて、部長が「…そうか」とだけ呟き、田中の見つけた絵本を手に取った。
「やるぞ。ミスター・シックスの分までな」
その声は、もう怒りではなく、温かい決意に満ちていた。
翌朝、始発電車で駆けつけた佐藤が見たのは、完璧に仕上がったプレゼン資料と、彼のデスクに置かれた一本の栄養ドリンクだった。そして、田中の走り書きのメモ。「お疲れ様です。あとは任せてください」。
プレゼンは、奇跡的な大成功を収めた。
その日の帰り道、駅へと向かう佐藤の隣に、田中が追いついた。夕暮れの光が、二人の疲れたスーツを橙色に染めている。
「佐藤さん」
「……ああ」
「今度、その…ひかりちゃんに、俺も絵本、読んでやってもいいですかね?」
佐藤は少し驚いたように田中を見つめ、それから、ふっと息を吐くように笑った。この一年、彼の顔から消えていた本物の笑顔だった。
「ああ。ぜひ、頼むよ」
十八時のサイレンは、もう彼を孤独にするための音ではなかった。それは、守るべきものがある日常の、誇らしいファンファーレに変わっていた。街の灯りが、昨日よりもずっと近く、温かく感じられた。