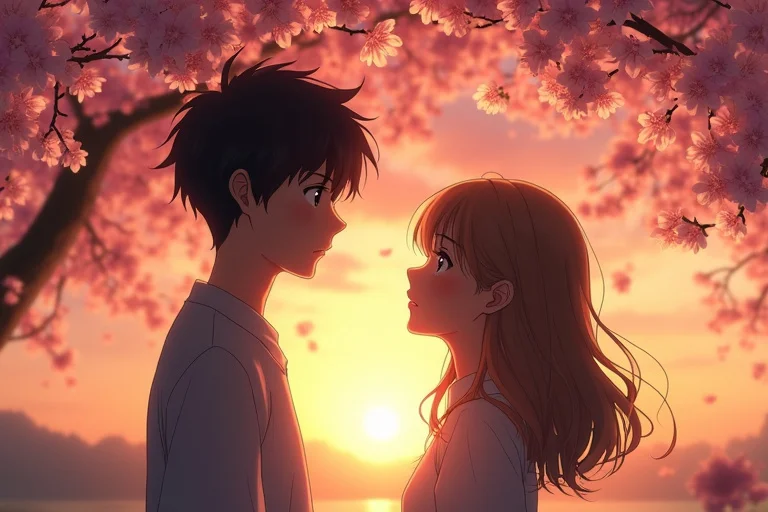月曜日の朝。僕、佐藤拓也の日常は、正確な歯車のように動き出す。午前六時半に起床、七時ちょうどに家を出て、七時十五分の電車に乗る。そして、会社の最寄り駅に着くのが七時三十二分。ここからが、僕だけの小さな儀式の時間だ。
改札を出てすぐの隅に、ぽつんと佇む古びた自動販売機。塗装は剥げかけ、商品サンプルは日に焼けて色褪せている。誰も見向きもしないようなその自販機で、百三十円の微糖缶コーヒーを買うのが僕の習慣だった。
その日もいつも通り、財布から取り出した百円玉と十円玉三枚を、ゆっくりと投入口に滑り込ませた。お目当ての商品のボタンを押す。ガコン、と重たい音を立てて、取り出し口に転がり落ちてきたのは、見慣れた缶コーヒーではなかった。
それは、つや消しの銀色をした、ラベルのない缶だった。中央にただ一言、『追い風』とだけ、明朝体で記されている。
「……なんだこれ?」
押し間違えたか? いや、ボタンは一つしかない。戸惑いながらも、僕はその奇妙な缶を手に取った。ひんやりとした金属の感触が、眠気を覚ます。とりあえず、プルタブを開けて一口。味は、ごく普通のスポーツドリンクのようだった。
その日の仕事は、驚くほど順調に進んだ。面倒なクライアントからの電話は鳴らず、昨日まで頭を悩ませていた企画書はすらすらと書けた。いつもは嫌味ばかりの鈴木部長が、「佐藤くん、これ面白いじゃないか」なんて褒めてくれる始末。まるで、見えない強い風が僕の背中を押し続けてくれているようだった。
翌朝、僕は期待に胸を膨らませて自販機の前に立った。しかし、出てきたのはいつもの微糖缶コーヒー。まあ、そんなにうまくはいかないか。
それからというもの、僕の朝の儀式は「日常」から「冒険」に変わった。三日に一度、あるいは一週間に一度、自販機は僕に不思議な缶を授けてくれるようになったのだ。
『猫の言葉がわかるスプレー』をこっそり使った日には、公園のボス猫から「そこの人間、俺様の昼寝の邪魔をするな」と凄まれ、『五分間だけ、誰よりも足が速くなるガム』を噛んだ日には、遅刻寸前で乗り換えの電車に飛び乗れた。僕の退屈だった日常は、この自販機のおかげで、予測不可能な宝探しのようにキラキラと輝き始めた。
ある金曜日のことだ。僕は会社で、キャリアを左右するほどの大きなミスを犯してしまった。重要な契約書の数字を、一桁間違えて提出してしまったのだ。週明けの月曜、先方に謝罪しに行かねばならない。契約は、おそらく破棄されるだろう。
重い足取りで駅に向かう。もう、あの自販機に頼るしかない。神に祈るような気持ちで百三十円を入れると、これまで見たこともない、鈍い黄金色に輝く缶が落ちてきた。
『やり直しのティータイム』
缶を握りしめた僕の目に、ふと、ある光景が飛び込んできた。駅のベンチで、小さな女の子が泣きじゃくっている。そばにいる母親は、困り果てた顔で空を見上げていた。どうやら、大切にしていた赤い風船を、空に飛ばしてしまったらしい。女の子の指から離れた赤い糸が、風に揺れている。
僕は、手の中の黄金の缶と、空に小さくなっていく赤い点を、交互に見つめた。
もしこれを飲めば、僕はミスをする前の時間に戻れるかもしれない。クビにならずに済む。僕の未来は救われる。
でも――。
「……くそっ」
僕は駆け出していた。自販機で買ったばかりの、まだ開けていないペットボトルのお茶を取り出し、中身を地面にぶちまけた。そして、その空のペットボトルをロケットに見立てて、女の子の前に差し出す。
「お嬢さん、見てて! 風船捕獲ロケット、発射!」
我ながら馬鹿げた行動だと思った。でも、泣いている女の子を放っておけなかった。女の子は一瞬きょとんとしたが、僕の必死の形相がおかしかったのか、くすりと笑った。母親も、呆れたように、でも少しだけ優しく微笑んだ。
その時だった。突風が吹き、空高くにあった赤い風船が、ふわりと高度を下げてきた。まるで意思があるかのように、近くの木の枝に、その糸を絡ませたのだ。
僕は迷わず木に駆け寄り、枝に引っかかった糸を慎重に手繰り寄せた。女の子に赤い風船を手渡すと、彼女は満面の笑みで「ありがとう、ロケットのおじちゃん!」と言った。
僕は黄金の缶、『やり直しのティータイム』を飲むことはなかった。月曜日、僕は部長と共に頭を下げ、自分のミスを正直に詫びた。結果、契約は打ち切られた。けれど、不思議と心は晴れやかだった。
その日の帰り道。僕はもう一度、あの自販機の前に立った。もう不思議な缶は出ないだろう。そう思いながら、ポケットの小銭を入れる。
ガコン。
取り出し口にあったのは、見慣れた微糖缶コーヒーだった。だが、その側面に、小さなシールが貼られている。手書きの文字で、こう書かれていた。
『今日の君は、最高にカッコよかったぜ』
僕は、思わず噴き出した。声を出して笑ったのは、久しぶりだったかもしれない。缶コーヒーを一口飲む。いつもの何倍も、それは美味しく感じられた。
僕の日常は、また歯車のように動き出すだろう。でも、もう退屈じゃない。だって、この世界のどこかには、僕のささやかな行動を見ていてくれる、遊び心のある「誰か」がいるのだから。そう思うだけで、明日を迎えるのが、少しだけ楽しみになるのだった。