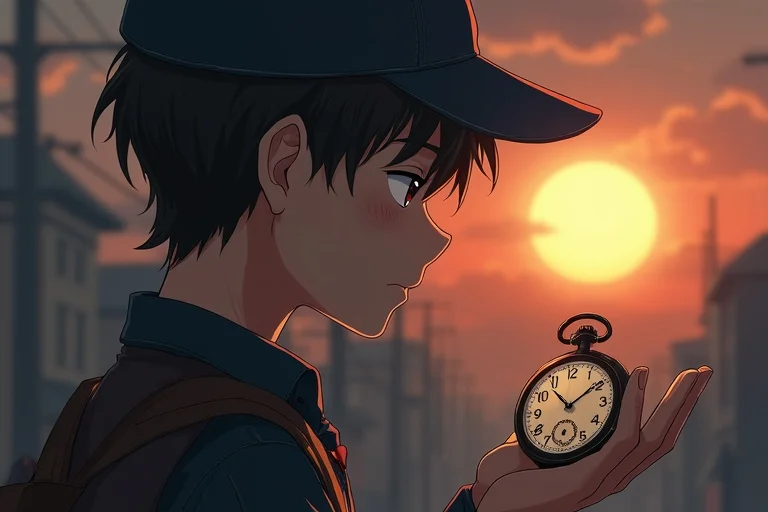第一章 鉄の匂いと家族写真
サイレンの音は、もはや日常の背景音だった。僕、健太の住む海沿いの小さな村では、空が灰色に染まるたびに、あの耳障りな不協和音が鳴り響く。大人たちは顔をこわばらせて空を睨み、僕ら子供は防空壕の湿った土の匂いをまた嗅ぐのかとうんざりする。先生は学校で、敵国の人間は血も涙もない鬼だと教えた。特に、空から鉄の卵を落としていく飛行機乗りは、人の皮を被った悪魔そのものだと。僕はそれを信じていた。出征した父さんの手紙が途絶えてから、僕の心の中の「敵」は、日に日に大きく、醜い怪物へと育っていった。
その日も、サイレンが鳴った。でも、いつもと違う轟音が空気を引き裂いた。キーンという金属の悲鳴の後、村の裏山に黒煙が立ち上るのが見えた。大人たちの制止を振り切り、僕は森へと駆け出した。恐怖よりも、野次馬根性にも似た好奇心が勝っていたのだ。悪魔が墜ちたのだ。そのざまを、この目で見てやりたかった。
息を切らして森の奥へ進むと、焦げた土と油の匂いが鼻をついた。木々がなぎ倒され、大地がえぐられた中心に、片翼のもげた銀色の機体が突き刺さっていた。それは巨大な、そして無様な鉄の骸だった。僕はゴクリと唾を飲み込み、さらに近づいた。
その時だった。折れた翼の陰で、何かが動いた。軍服を着た男だった。敵兵だ。彼は岩に背を預け、苦しげに息をしていた。足はあり得ない方向に曲がり、額からは血が流れている。僕の心臓が大きく跳ねた。憎むべき悪魔が、目の前にいる。石を拾い、力いっぱい投げつけてやろうか。そう思った瞬間、男が何かを落とした。乾いた葉の上に落ちたそれは、一枚の写真だった。
風に飛ばされそうになるそれを、僕は咄嗟に拾い上げた。そこに写っていたのは、僕と同じくらいの歳の、金髪の少女だった。隣には、花柄のワンピースを着た母親らしき女性が、優しく微笑んでいる。写真の中の彼女たちは、幸せそうだった。僕の母さんが、父さんからの手紙を読んでいた時と同じ顔をしていた。僕は、握りしめた石を、いつの間にか落としていた。目の前の男は、苦痛に顔を歪めながら、僕が持つ写真の方へ、か細い手を伸ばしていた。それは悪魔の手には見えなかった。
第二章 秘密の配給
その日から、僕の秘密が始まった。誰にも言えなかった。敵兵を助けているなどと知られたら、国賊だと罵られるだろう。でも、あの家族写真が、母親と少女の笑顔が、僕の頭からどうしても離れなかったのだ。
翌日、僕は台所から芋を一つと、水筒にこっそり水を詰めて森へ向かった。心臓は破れそうなほど鳴っていた。これは正しいことじゃない。分かっている。でも、放っておけなかった。
洞穴のようになった岩陰に、兵士はまだいた。僕の姿を見ると、警戒するように身を強張らせたが、僕が差し出した芋と水筒を見ると、彼の青い瞳がわずかに揺れた。彼はゆっくりとそれを受け取ると、飢えた獣のように芋にかじりついた。水を飲む姿は、まるで何日も砂漠を彷徨っていた旅人のようだった。
言葉は通じない。彼は僕が分からない言葉で何かを呟いたが、その声色には感謝が滲んでいた。僕らはただ、無言でそこにいた。沈黙を埋めるのは、森の木々が風に揺れる音と、遠くで聞こえるカラスの鳴き声だけだ。
僕は彼の足の傷を見た。軍服のズボンは破れ、傷口は赤黒く腫れ上がっている。このままでは、すぐに腐ってしまうだろう。僕は一度村へ戻り、薬箱から清潔な布と、小さなヨードチンキの瓶を盗み出した。再び森へ戻ると、兵士は僕の意図を察したようだった。僕が震える手で傷口に触れると、彼は歯を食いしばって痛みに耐えた。ヨードチンキが染みた時、彼の体はビクッと震えたが、決して声を上げなかった。
手当てが終わると、彼はぼろぼろの軍服のポケットを探り、何かを取り出した。それは、銀紙に包まれた小さなコンペイトウだった。角の取れた、色とりどりの星のような砂糖菓子。彼はそれを、僕の泥だらけの掌にそっと乗せた。そして、かすかに笑った。その笑顔は、写真の女性が浮かべていたものと、どこか似ている気がした。僕はその甘い星の欠片を口に含んだ。じわりと広がる優しい甘さが、僕の中で凝り固まっていた「敵」という言葉を、少しずつ溶かしていくのを感じた。
第三章 父の名を呼ぶ声
穏やかな秘密の時間は、長くは続かなかった。村に不穏な噂が流れ始めたのだ。「山に敵兵が潜んでいるらしい」。噂は瞬く間に広がり、村の男たちと憲兵が、血相を変えて山狩りを始めた。竹槍や古びた猟銃を手にした彼らの目は、獲物を追い詰める猟犬のようにギラギラと光っていた。
「見つけ次第、叩き殺せ!」「お国のためだ!」
その声が聞こえるたび、僕の心臓は冷たくなった。あの人を、殺させたくない。僕は必死だった。兵士を、もっと森の奥深く、誰も知らない洞穴へ移そうと考えた。
僕が洞穴に駆けつけると、兵士は僕の切羽詰まった表情から全てを察したようだった。彼の顔色は紙のように白く、呼吸も浅い。もう長くはないのかもしれない。僕は彼に肩を貸し、引きずるようにして歩き始めた。しかし、彼の体は鉛のように重く、数メートル進むのがやっとだった。
山狩りの声が、すぐ近くまで迫っていた。もうだめだ。そう思った時、兵士は僕の腕を掴んで立ち止まった。そして、震える手で胸のポケットから、あのボロボロの手帳を取り出した。彼は僕に何かを必死に伝えようとしていた。
「……ッ!」
彼は手帳のあるページを開き、僕に突きつけた。そこには、インクが滲み、ほとんど消えかかった文字が並んでいた。その中に、僕でも読めるカタカナがあった。
『タロウ』
息が止まった。タロウ。それは、僕の父さんの名前だ。なぜ。どうしてこの人が、父さんの名前を。混乱する僕の顔を見て、兵士は最後の力を振り絞るように、たどたどしい日本語で囁いた。
「タロウ……トモダチ……」
友だち? 父さんと、この人が? 彼は手帳の間に挟んであった、もう一枚の古い写真を抜き出した。それは、軍服ではない、普通のシャツを着た二人の若い男が、肩を組んで屈託なく笑っている写真だった。片方は、間違いなく若い頃の父さんだった。そして、もう一人は――目の前で死にかけている、この敵兵だった。
世界が、音を立てて崩れていくのが分かった。僕が憎んでいた「敵」。僕が救おうとしていた「人間」。その人は、父さんの友人だったのだ。国が線を引くより前に、彼らはただの友人同士だった。僕が信じてきた正義とは、一体何だったのか。
第四章 森に捧げる祈り
「ウォォォッ!」
山狩りの雄叫びが、木々の向こうから聞こえた。もう、すぐそこだ。
兵士は、僕の手に手帳と二枚の写真を強く握らせた。そして、僕の頭を、ごつごとした大きな手で一度だけ、優しく撫でた。彼の青い瞳には、涙が滲んでいた。それは絶望の色ではなく、何かを託すような、穏やかな光を宿していた。
次の瞬間、彼は僕を突き飛ばし、自ら洞穴の外へ飛び出した。わざと大きな物音を立て、茂みを揺らしながら。
「ここにいるぞ!」
それは、彼の母国語だったのだろう。意味は分からなかったが、魂の叫びだということは分かった。彼は、僕を逃がすために、自らおとりになったのだ。
すぐに、男たちの怒号が響き渡った。「いたぞ!」「逃がすな!」という声。そして、乾いた銃声が一声、森に轟いた。
僕はその場にうずくまり、両手で強く耳を塞いだ。何も見たくなかった。何も聞きたくなかった。ただ、掌に握りしめられた写真の感触だけが、砕け散った真実の欠片として、生々しく残っていた。
数年の月日が流れ、長く続いた戦争は終わった。
僕はもう、あの頃の少年ではなかった。父さんは、結局帰ってこなかった。
ある晴れた日、僕は一人で、あの森を訪れた。かつて山狩りの声が響いた森は、嘘のように静まり返り、鳥の声だけが聞こえていた。記憶を頼りに洞穴を探すと、そこは蔓草に覆われ、まるで自然の墓標のようにひっそりと佇んでいた。
僕は懐から、大切にしまっていた二枚の写真を取り出した。一枚は、父さんと彼の友人が笑っている写真。もう一枚は、彼が命懸けで守ろうとした、彼の家族の写真。国境線なんてなければ、彼らは互いの家族を紹介し合って、笑い続けていたのかもしれない。戦争は、そんな当たり前の未来を、いとも簡単に奪い去ったのだ。
僕は二枚の写真を、洞穴の入り口の苔むした岩の上に、そっと並べて置いた。
見上げた空には、かつて憎しみの対象だった鉄の翼の影はなく、どこまでも澄んだ青が広がっていた。錆びた翼が見た夢。それはきっと、特別なものではない。ただ、友と笑い、家族を愛し、子供の成長を見守る。そんなささやかな夢だったに違いない。
僕の心にもう、憎しみはなかった。そこにあったのは、戦争という巨大な嵐に巻き込まれ、名も知らぬまま散っていった全ての命への、静かで、深い祈りだけだった。頬を伝うものが涙だと気づいたのは、しばらく経ってからのことだった。