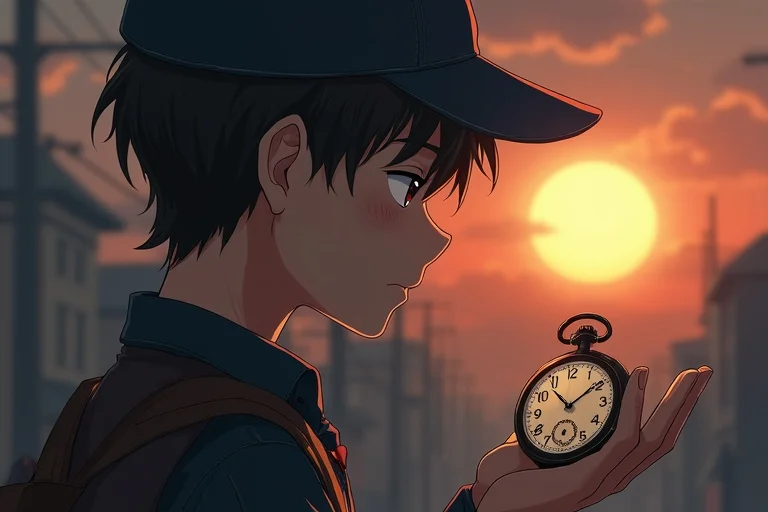第一章 敵兵の絵本
泥と硝煙の匂いが、リヒトの若い肺を満たしていた。塹壕の壁に背を預け、彼は息を殺す。数時間前まで命の応酬があった丘は、今は不気味な静寂に包まれている。月明かりが、転がる鉄兜や、無造作に横たわる影を青白く照らし出していた。影、とリヒトは思った。ほんの少し前まで、彼らも自分と同じように呼吸をし、故郷を思っていた人間だったはずだ。
斥候任務の帰りだった。味方の陣地まであと少しという場所で、彼はうつ伏せに倒れた敵兵の姿を認めた。その手に、何か場違いなものが握られている。警戒しながら近づくと、それは一冊の、くたびれた絵本だった。表紙には、羊たちが草を食む、穏やかな丘が描かれている。こんな地獄の真ん中で、なぜ。衝動的に、リヒトはその絵本を死者の手からそっと引き抜いた。
塹壕に戻り、ランプの頼りない光にかざした時、リヒトは息を呑んだ。絵本の見返し部分に、拙い、子供の文字が並んでいたのだ。そして、その文字は、紛れもない、リヒト自身の母国語で書かれていた。
『お父さんへ。はやくかえってきてね。いっしょに、ひつじの丘にいこうね。アイリスより』
心臓が氷の塊になったようだった。敵兵だ。言語も、文化も、信じる正義も違うはずの。その男が、なぜ自分の国の言葉で書かれたメッセージを、最期の瞬間まで握りしめていたのか。あり得ない。スパイか?だが、こんな絵本が何の暗号になる?
ざらついた表紙を撫でながら、リヒトは言いようのない混乱に囚われた。彼がこれまで信じてきた「敵」という概念が、指先からゆっくりと崩れていくような、不吉な予感がした。その夜、リヒトは一睡もできなかった。遠くで響く砲声と、絵本に込められた謎が、彼の心を掴んで離さなかった。
第二章 色褪せたページの囁き
戦争は終わらない。日々は、泥濘での行軍、硬いパン、そして仲間が一人、また一人と消えていく現実の繰り返しだった。そんな中で、敵兵から奪った絵本は、リヒトにとって密かな聖域となった。誰もいない夜更け、毛布にくるまり、彼は何度もそのページをめくった。
描かれているのは、戦争とは無縁の世界だった。羊飼いの少年が、迷子になった子羊を探して旅をする物語。少年は、親切なパン屋や、歌うのが好きな木こりと出会い、助けられながら進んでいく。色彩は褪せ、ページの端は擦り切れているが、そこに描かれた笑顔や、陽光の暖かさは、不思議なほど鮮やかにリヒトの心に届いた。
「またそれを見てるのか」
隣で寝転んでいた古参兵のクラウスが、呆れたように言った。
「そんなものを大事にして。故郷の恋人からでもないだろうに」
「……気休めですよ」
リヒトは慌てて絵本を隠した。この本の来歴を話す気にはなれなかった。敵兵から奪ったなどと言えば、気味悪がられるか、あるいはその場で燃やされてしまうだろう。
だが、絵本は確実にリヒトの内面を侵食していた。物語の中の少年は、困っている人を見れば、それが誰であろうと手を差し伸べる。そこには国境も、敵も味方もない。リヒトは自問した。自分は、この少年と何が違うのだろうか。引き金を引く自分と、パンを差し出す少年。どちらが、本来の人間の姿なのか。
『お父さんへ』というアイリスの言葉が、弾丸のように胸を穿つ。この絵本の持ち主だった敵兵にも、アイリスという娘がいて、父親の帰りを待っている。その父親を、自分や、自分の仲間が殺したのかもしれない。その考えに至るたび、リトマス試験紙が色を変えるように、彼の愛国心は疑念の色に染まっていった。憎むべきは悪逆非道な敵国の兵士。そう教え込まれてきたはずの信念が、一人の父親の姿を前に、脆くも揺らぎ始めていた。
第三章 野戦病院の鎮魂歌
運命が急転したのは、霧の深い朝だった。敵の一斉攻勢に巻き込まれ、リヒトは左足に銃弾を受けた。意識が遠のく中、彼が最後に見たのは、見慣れない軍服の色だった。
次に目覚めた時、リヒトは敵国の野戦病院のベッドにいた。消毒液のツンとした匂いと、呻き声が満ちている。捕虜になったのだ。絶望が全身を駆け巡ったが、不思議と恐怖はなかった。むしろ、これで終わるのだという、奇妙な安堵感があった。
彼の治療を担当したのは、白髪の混じった初老の軍医だった。ヨナス、と名乗った彼は、ぶっきらぼうだが手際は良く、リヒトの傷を淡々と手当てした。言葉は通じない。しかし、その疲れた瞳の奥に、リヒトは何か見覚えのある優しさを感じた。
数日が過ぎた夜、病院内に静かな歌声が響いた。それは、負傷して錯乱した兵士を落ち着かせるため、ヨナス軍医が口ずさんでいる子守唄だった。リヒトは凍りついた。その旋律は、知っている。あの絵本の中で、羊飼いの少年が母親から教わった歌として、楽譜と共に描かれていたものと全く同じだった。
まさか。そんな偶然があるはずがない。
リヒトは混乱した頭で記憶をたどった。軍医の顔、その佇まい。彼が時折、遠くを見るようにして漏らす溜息。
ある日、リヒトは意を決し、片言の敵国語とジェスチャーで、ヨナス軍医に話しかけた。
「あなたの……子供は……?」
軍医は一瞬驚いた顔をしたが、やがて寂しそうに微笑んだ。
「息子が一人、いる。今は遠くにいるがな。絵を描くのが好きな、優しい子だった」
リヒトの心臓が、警鐘のように鳴り響いた。彼は震える手で、枕元に隠していた絵本を取り出した。ヨナス軍医は、それを見て目を見開いた。ゆっくりと絵本を受け取り、その表紙を、まるで愛しい我が子を撫でるかのように、優しく指でなぞった。
「……これを、どこで」
声が震えている。リヒトは真実を話すしかなかった。丘の上で、亡くなった兵士が持っていたこと。そこに、自分の国の言葉でメッセージが書かれていたこと。
軍医は、リヒトの言葉を静かに聞いていた。そして、見返しの『アイリスより』という文字を見て、小さく首を振った。
「私の息子の名は、アイリスではない。それに、これは私の国の言葉だ」
「え……?」
リヒトは理解が追いつかなかった。では、この文字は?
「息子はな、戦争が始まる前、君の国に留学していたんだ。君の国の文化を、人々を、心から愛していた。この絵本は、息子が幼い頃、私が読んでやったものだ。それを……あの子は、君の国の言葉に訳して、私に送ってくれたんだよ。『父さんの国の物語は、こんなに素晴らしいんだ』と、手紙を添えてな」
衝撃の事実に、リヒトは言葉を失った。敵国の言葉だと思っていた文字は、自分の母国語に訳された、息子から父への贈り物だったのだ。
そして、軍医は静かに続けた。
「君がこれを見つけたということは……あの子は、あの丘で……」
その声は、万感の悲しみを湛えていた。敵も味方もない。ただ、息子を失った一人の父親が、そこにいた。リヒトの目の前で、世界が、信じてきたすべてが、音を立てて崩れ落ちた。自分は、この父親から、愛する息子を奪った側の人間なのだ。
第四章 物語の続き
戦争は終わった。
英雄として故郷に帰還したリヒトを待っていたのは、祝祭の喧騒と、人々の笑顔だった。だが、彼の心は、凍てついた冬の荒野のように静まり返っていた。耳には、ヨナス軍医の慟哭がこびりついて離れない。英雄ではない。自分は人殺しだ。その罪悪感が、影のように彼に付きまとった。
数年の月日が流れた。リヒトは平穏な日常に馴染むことができず、ただ無為に時を過ごしていた。彼の机の引き出しには、今もあの絵本が大切にしまわれている。
ある春の日、リヒトは決意した。彼はなけなしの金をかき集め、かつての敵国行きの船に乗った。目的は一つ。ヨナス軍医を探し出し、絵本を返し、そして謝罪すること。
多大な困難の末、リヒトは郊外の小さな診療所で働くヨナスを見つけ出した。以前よりも深く刻まれた皺と、真っ白になった髪が、彼の過ごした年月を物語っていた。リヒトは、震える手で絵本を差し出した。
「これを、お返しに……そして……本当に、申し訳ありませんでした」
頭を下げるリヒトに、しかしヨナスは静かに首を振った。
「顔を上げなさい。君を憎んではいないよ」
彼は穏やかな声で言った。
「君も、私も、ただ時代に、戦争という巨大なうねりに翻弄されただけだ。憎むべきは、我々を銃で向き合わせた、何かだ」
ヨナスは絵本を受け取らず、リヒトの手に押し返した。
「それは、息子が生きた証だ。そして、君と私を繋いだ奇跡だ。だから、君が持っていてくれ。そして……もしできるなら、息子の代わりに、この物語の続きを生きてはくれまいか」
物語の、続き。
その言葉が、リヒトの固く閉ざされた心の扉を、静かにこじ開けた。涙が、とめどなく頬を伝った。それは罪悪感の涙ではなく、許しと、そして微かな希望から生まれた、温かい涙だった。
故郷に戻ったリヒトは、ペンを取った。
彼は書き始めた。塹壕の泥の匂いを、色褪せた絵本の優しさを、野戦病院で聞いた鎮魂歌を、そして、息子を失った父親の涙を。それは、戦争の悲劇を告発する物語ではなかった。国境や憎しみを超えて、人と人とを結びつけようとした、ささやかで、しかし確かな光についての物語だった。
彼の書く一行一行が、名もなき敵兵への鎮魂となり、ヨナス軍医への返信となり、そして、自分自身への償いとなっていく。境界線の上で出会ったアルカディア(理想郷)の物語を紡ぐこと。それが、リヒトが見つけた、物語の続きを生きていくための、唯一の道筋だった。