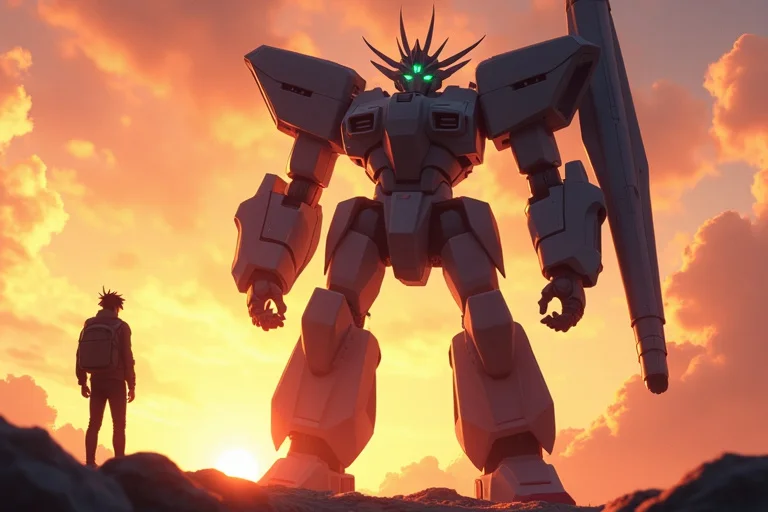第一章 錆びついた記憶の鍵
レオの仕事は、記憶を消すことだった。
冷たいコンクリートと鋼鉄でできた無機質な部屋。中央に置かれた一台の椅子。そこに座らせた「対象」のこめかみに電極を貼り付け、コンソールを操作する。彼の指先が数値を入力するたび、低い機械音が唸りを上げた。ガラスの向こう側では、上官たちが無表情にその様子を監視している。
戦争が始まって五年。レオが所属する情報統制局・特殊記憶処理班の任務は、捕らえた敵国の兵士やスパイから機密情報を引き出した後、その記憶を白紙に戻し、故郷へ送り返すことだった。表向きは「戦争のトラウマから解放する人道支援」と謳われている。レオも、当初はそう信じていた。苦痛に満ちた記憶を消し去ることは、一種の救済なのだと。彼は自らの行為を正当化し、感情を殺し、ただ淡々と任務をこなすことで、この狂った世界で正気を保っていた。
その日、椅子に座っていたのは、エリアナと名乗る女だった。敵国の野戦病院で看護師をしていたという。これまでの対象とは何かが違った。痩せてはいるが、その背筋は真っ直ぐに伸び、恐怖に震えるでもなく、ただ静かにレオを見つめている。彼女の瞳は、雨上がりの森のように深く、澄んだ色をしていた。その瞳に見つめられていると、レオは胸の奥に錆びついた鍵が差し込まれるような、鈍い痛みを感じた。
「始めろ」
インターカムから、上官の無機質な声が響く。レオは深呼吸し、コンソールの最終実行スイッチに指をかけた。機械が起動し、エリアナの身体が微かに痙攣する。彼女の記憶が、モニター上で意味をなさない光の粒子となって霧散していくのが見える。戦闘の恐怖、仲間の死、故郷の風景。それらが音もなく消えていく。いつも通りの、手順通りの作業。
だが、その時だった。消えゆく記憶の奔流の中から、一つの鮮明なイメージがモニターに映し出された。
―――どこまでも広がる、黄金色の向日葵畑。夏の日差しを浴びて、空に向かって咲き誇る無数の花々。
その光景に、レオは息を呑んだ。なぜか、ひどく懐かしい。胸の奥の錆びついた鍵が、ギリリと音を立てて回るような感覚。
処置が終わり、エリアナはぐったりと椅子にもたれかかっていた。記憶を失い、虚ろな目になるはずだった。しかし、彼女はゆっくりと顔を上げ、レオを真っ直直ぐに見つめた。そして、掠れた声で、こう呟いたのだ。
「レオ……?」
その声は、レオの心の壁をやすやすと貫いた。なぜ、彼女が自分の名前を知っている? 記録によれば、二人に接点などあるはずもない。レオの過去は、戦災孤児として軍の施設に保護された時点で始まっている。それ以前の記憶は、彼自身にもなかった。
ガラスの向こうの上官たちが訝しげな視線を向けている。レオは動揺を押し殺し、冷静を装って作業を終了させた。しかし、彼の内側で、固く閉ざされていた何かが、軋みを上げて開き始めていた。エリアナという女は、一体何者なのだ。そして、あの向日葵畑は―――。
第二章 向日葵と忘れられた旋律
レオは規則を破った。
エリアナの記憶消去が不完全だったと報告し、経過観察を理由に、彼女を独房で隔離保護する許可を取り付けた。毎夜、彼は監視の目を盗んで彼女の独房を訪れた。それは任務のためだと自分に言い聞かせたが、本当は、彼女が持つ「鍵」で、自分の失われた過去の扉を開けたいという渇望に駆られていたからだ。
「何か、覚えていることは?」
冷たい床に膝をつき、レオは鉄格子の向こうのエリアナに問いかけた。
「断片的に……」エリアナは静かに語り始めた。「黄金色の、向日葵の丘。風が吹くと、ざわざわと歌うように揺れるんです。それから……古いピアノの音。誰かが弾いてくれた、優しいメロディ」
その言葉は、レオの心象風景に淡い色彩を与えた。覚えのないはずの光景が、まるで自分の記憶の断片であるかのように、リアルな手触りをもって迫ってくる。
「そのピアノを弾いていたのは、誰だか分かるか?」
「分からない……。でも、とても大切な人だった気がする。その人と、星空の下で約束をしたの。『いつか、戦争が終わったら、またこの丘で会おう』って」
彼女の言葉を聞くたびに、レオの頭痛はひどくなった。忘れ去られたはずの何かが、脳の深い場所で疼き、叫び声を上げているようだった。彼は、自分が何者なのか、どこから来たのか、何も知らなかった。軍は、彼が瓦礫の中から救い出された戦災孤児だと説明した。両親の顔も、故郷の名も知らない。記憶がないことは、兵士として生きる上で好都合だった。過去に縛られず、未来を憂えず、ただ命令に従うことができるからだ。
しかし、エリアナと出会ってから、その空っぽの過去が、耐えがたいほどの虚無となって彼を苛み始めた。
ある夜、エリアナがふと鼻歌を歌った。それは、彼女が言っていた「古いピアノのメロディ」だった。単純で、どこか物悲しい、けれど温かい旋律。レオはそのメロディを知っていた。なぜ知っているのかは分からない。だが、その音色は血肉に染み込むように馴染み深く、彼の唇もまた、無意識のうちにその旋律をなぞっていた。
二人のハミングが、薄暗い独房で重なり合う。その瞬間、レオは確信した。自分たちの過去は、どこかで交わっている。
「君を、ここから出す」
レオは決意を固めて言った。
「なぜ? あなたは軍の人間でしょう」
「君を消すことはできない。君を消したら、俺は……俺自身のかけらを永遠に失うことになる気がするんだ」
それは、任務への裏切りであり、国家への反逆だった。しかし、レオにとって、失われた自分自身を取り戻すこと以上に優先すべきものは、もはやなかった。彼は、自分の信じてきた「正義」よりも、目の前のエリアナという存在と、彼女が呼び覚ます名もなき記憶の方に、抗いがたい真実を感じていた。
第三章 硝子の向こうの真実
脱出計画は、レオが持つ知識と技術の全てを注ぎ込んだ、危険な賭けだった。最終的な記憶消去処置を行うと偽り、エリアナを再びあの処置室へと連れ出す。そして、装置を逆用し、彼女の記憶を消すのではなく、その深層にダイブする。そこに全ての答えがあると、レオは信じていた。
処置室の椅子に座るエリアナは、不安げな表情でレオを見つめた。
「大丈夫だ。信じてくれ」
レオは彼女の手を握った。その手は、驚くほど温かかった。彼はコンソールに向き合い、指を走らせる。通常のプロトコルを書き換え、記憶の深層へとアクセスするシーケンスを起動させた。モニターに、ノイズ混じりの映像が流れ始める。それは、エリアナの記憶の海だった。
―――映像は、向日葵の丘を映し出す。空はどこまでも青く、蝉の声が降り注いでいる。そこに、二人の子供がいた。泥だらけの少年と、麦わら帽子をかぶった少女。少女は、紛れもなく幼いエリアナだった。そして、少年は―――。
レオは息を止めた。そこにいたのは、彼自身だった。忘れていた自分の顔。笑い声を上げてエリアナの手を引く、快活な少年。
記憶が奔流となってレオの脳内に流れ込んでくる。向日葵の丘は、二人が育った孤児院の裏手にあった遊び場だ。古いピアノは、孤児院の院長先生が教えてくれたもの。星空の下の約束も、全てが真実だった。エリアナは、彼の幼馴染であり、初恋の人だったのだ。
だが、衝撃はそれだけでは終わらなかった。
記憶の映像は、ある日を境に暗転する。空襲のサイレン。燃え盛る孤児院。泣き叫ぶ子供たち。その混乱の中、レオは軍の兵士に「保護」される。そして、連れて行かれたのが、今いるこの情報統制局の施設だった。
モニターに映し出されたのは、冷たい実験室と、白衣の男たち。そして、椅子に縛り付けられ、恐怖に泣き叫ぶ幼い自分の姿。彼は、敵兵の記憶を消すための新技術の、最初の被験者の一人だったのだ。エリアナとの大切な記憶、孤児院での日々、人間的な感情―――兵士として「不要」と判断されたそれらの記憶は、全て軍の手によって消去されていた。
彼が「人道支援」と信じて行ってきた記憶消去は、国家が都合の良い兵士を作り出すための、非人道的なマインドコントロールに他ならなかった。彼が消してきたのは、敵兵の記憶だけではない。彼と同じように、過去を奪われ、感情を殺された、元は名もなき市民だった者たちの記憶でもあった。
「……ああ……」
レオの口から、声にならない呻きが漏れた。足元から世界が崩れ落ちていく。信じていた正義は、巨大な嘘で塗り固められた幻想だった。自分は被害者であると同時に、同じ悲劇を他者に与える加害者でもあったのだ。
ガラスの向こうで、異変に気付いた上官が叫んでいる。警報が鳴り響き、複数の足音が廊下を駆けてくる。
レオは震える手でコンソールを操作し、エリアナの記憶へのアクセスを遮断した。そして、彼女に向き直る。彼の瞳には、絶望と、そして燃え立つような怒りの炎が宿っていた。
「行こう、エリアナ。全てを、取り戻しに」
第四章 夜明けの荒野へ
警報が鳴り響く施設の中を、二人は走った。レオは記憶処理装置の知識を逆手に取り、監視カメラの映像にゴーストを紛れ込ませ、電子ロックを誤作動させる。追手の兵士たちが現れると、彼は携帯式の小型記憶撹乱装置を起動させた。強烈な光とパルスが兵士たちの短期記憶を麻痺させ、彼らは一瞬、自分が誰で、何をしているのかを忘れて立ち尽くす。その虚ろな瞳は、かつてのレオ自身であり、彼が記憶を消してきた無数の人々と同じだった。胸を抉るような罪悪感を感じながらも、レオはエリアナの手を強く握り、前へ、ただ前へと進んだ。
いくつもの扉を抜け、最後の隔壁を爆破して外に出た時、東の空が白み始めていた。硝煙と鉄の匂いが混じる冷たい空気を、二人は貪るように吸い込む。自由だった。しかし、それは安息の始まりではなかった。背後には巨大な国家という敵がいて、目の前には戦争で荒れ果てた大地がどこまでも広がっている。
二人はしばらく、言葉もなく夜明けの空を眺めていた。失われた十数年の歳月が、重くのしかかる。
「これから、私たちはどうすればいいの?」
エリアナが、震える声で尋ねた。彼女の瞳には、取り戻した記憶の喜びと、未来への不安が入り混じっていた。
レオは彼女の記憶の中にあった、あの黄金色の丘を思い浮かべた。そこがまだ存在している保証はない。戦争で焼き尽くされているかもしれない。それでも。
「探しに行こう」
レオは、はっきりとした口調で言った。
「僕たちが失くしたものすべてを。君が覚えていた向日葵の丘を。僕が忘れてしまったピアノのメロディを。時間はかかるかもしれない。たくさんのものを失った。でも、まだ全部じゃない」
彼はエリアナの肩を抱き寄せた。
「ここから、もう一度始めよう。僕たちの物語を」
エリアナはレオの胸に顔を埋め、小さく頷いた。彼女の涙が、彼の軍服を濡らした。
二人は、不確かで危険に満ちた未来へと、一歩を踏み出した。戦争は終わらない。彼らを待つのは安寧の日々ではないだろう。だが、彼らの心には、偽りの正義から解放され、自らの意志で過去と未来を紡いでいくという、小さな、しかし何よりも確かな希望の光が灯っていた。
失われた記憶の向こう側にあった真実。それは絶望であると同時に、二人を再び結びつけた絆でもあった。夜明けの荒野に立つ二人の姿は、戦争という巨大な暴力が、人間の魂そのものを完全に奪い去ることはできないという、静かな証明のように見えた。