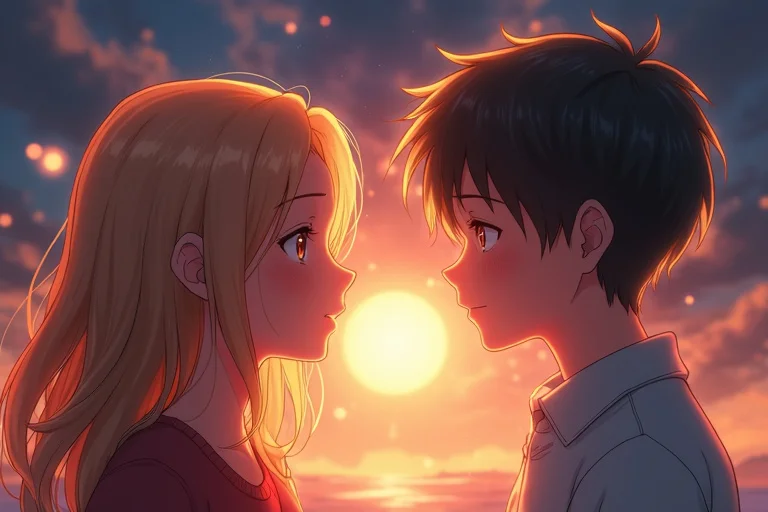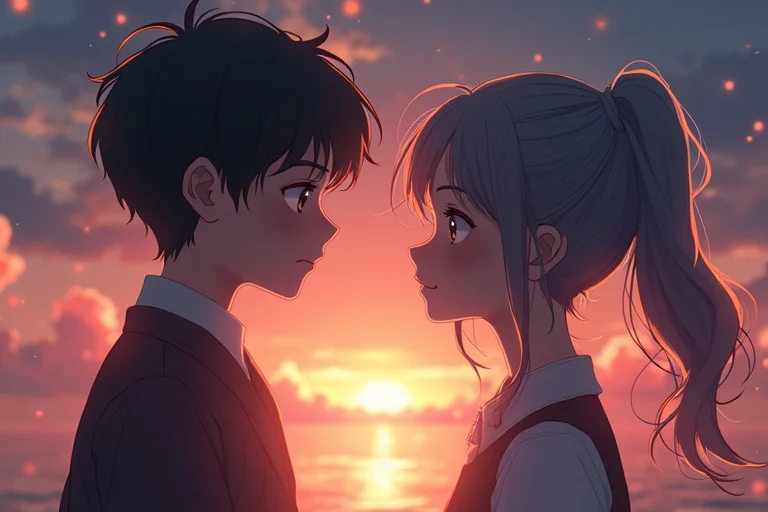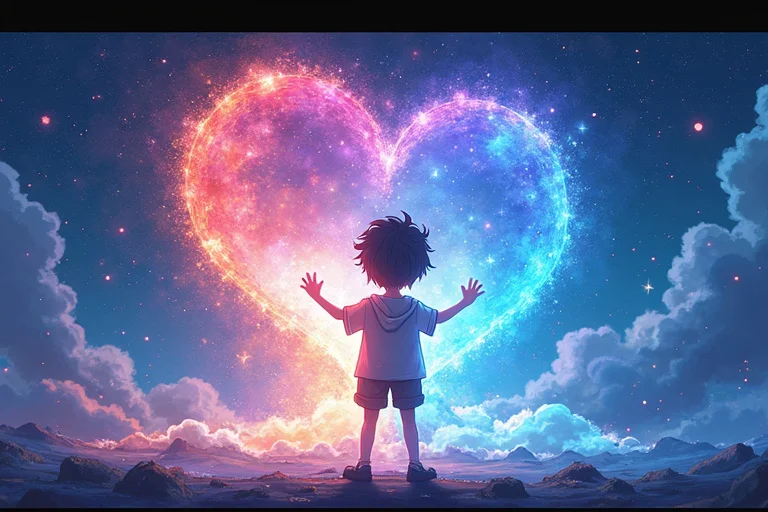第一章 夏の幻影
相葉陽介が死んで、初めての夏が来ようとしていた。
美術室の空気は、油絵の具とテレピン油の匂いが混じり合い、まるで時間が止まったかのようによどんでいる。俺、水野蒼は、窓際の一番奥、陽介がいつも使っていたイーゼルの前に立っていた。そこに掛けられたままのキャンバスには、未完の風景画が描かれている。あいつが事故に遭う数時間前まで、筆を走らせていた絵だ。
夏の入道雲が湧き上がる、どこまでも突き抜けるような青空。それが陽介の描きたかった世界だった。しかし、俺の目を釘付けにしたのは、その空ではなかった。キャンバスの右下に、ぽつんと、小さな青い花が描き加えられていたのだ。ネモフィラの花。陽介が亡くなった後、俺が一人で見に行った海辺の丘に、空を映したように咲き誇っていた花だ。
背筋に冷たいものが走った。陽介はこの花を知らない。あいつが亡くなった春に、初めて満開になった丘なのだから。そして、俺がその丘へ行ったことは、誰にも話していない。俺の記憶の中にしか存在しないはずの風景が、なぜ、陽介の未完の絵に紛れ込んでいるんだ?
「……誰が、これを」
絞り出した声は、埃っぽい美術室の静寂に吸い込まれて消えた。陽介は、俺の親友で、幼馴染で、そして、どうしようもないほどの嫉妬の対象だった。太陽みたいに笑い、その指先から生まれる線は、いとも容易く命を宿した。俺が何日もかけて捻り出す色彩を、あいつは一瞬のきらめきで掴み取ってしまう。
『蒼の絵は、静かで、水みたいで好きだよ。ずっと見ていられる』
いつだったか、そう言ってくれた陽介の言葉を、俺は素直に受け取れなかった。凡人への慰めか、気まぐれな優しさだと決めつけていた。そんな俺の卑屈な心を見透かすように、キャンバスに咲く青い花は、静かにこちらを見つめている。まるで、陽介の悪戯な笑みがそこにあるかのように。このあり得ないはずの加筆は、死んだはずの親友が俺に仕掛けた、最後の謎かけのように思えた。
第二章 残されたパレット
犯人探しは、空振りに終わった。
美術部の仲間たちに例の絵を見せ、それとなく探りを入れてみたが、誰もが首を傾げるばかり。顧問の先生でさえ、「いつの間に描かれたんだろうな」と不思議がるだけだった。陽介の絵に勝手に手出しするような人間は、この部にはいない。誰もが彼の才能を認め、その不在を心から悼んでいたからだ。
苛立ちと焦りが募る中、俺は陽介の母親から預かった段ボール箱を開けた。陽介が部屋に残していった、スケッチブックや画材の類だ。整理する気にもなれず、ずっと部屋の隅に放置していた。パラパラとスケッチブックをめくっていく。そこにいたのは、俺の知っている陽介であり、知らない陽介でもあった。走り書きのデッサン、風景のクロッキー、そして、驚くほど多くの、俺の絵の模写がそこにはあった。俺がコンクールに出して落選した絵、文化祭で隅に飾っただけの静物画。それらを、陽介は驚くほど丁寧に、慈しむように写し取っていた。
最後のページに、走り書きのメモが挟まっていた。
『蒼の青は、悲しいくらいに澄んでいる。俺には出せない色だ。あの深い青は、あいつの心そのものなんだろう。俺の空に、あの青を少しだけ分けてもらえたら、最強なんだけどな』
息が止まった。心臓を鷲掴みにされたような衝撃だった。嫉妬していたのは俺だけじゃなかったのか? いや、違う。これは嫉τόではない。憧憬だ。俺が陽介の才能に焦がれていたのと同じように、陽介もまた、俺の絵の中に何か特別なものを見出し、焦がれてくれていた。俺が卑屈なフィルター越しに見ていた世界は、あまりにも歪んでいた。あいつが向けてくれていた真っ直ぐな視線に、俺は一度だって、真正面から向き合おうとしなかった。
「……陽介」
名前を呼んでも、もちろん返事はない。ただ、絵の具が染みついたパレットの匂いが、あいつがまだ隣にいるかのような錯覚を起こさせた。涙が滲んで、スケッチブックの文字が揺れる。それでも、謎は解けない。このメモを読めば読むほど、陽介以外の誰かが、あの絵にネモフィラの花を描き加えることなど、冒涜的で許せない行為に思えてならなかった。一体、誰が、何のために。陽介の想いを踏みにじるような真似をしたんだ。
第三章 共犯者は僕だった
夏の夜だった。蒸し暑さに寝付けず、俺は吸い寄せられるように、夜の学校に忍び込んだ。懐中電灯の光が、ひっそりとした廊下を照らす。目指す場所は、美術室。あの絵が、俺を呼んでいる気がした。
月明かりが差し込む美術室は、昼間とは違う荘厳な空気をまとっていた。イーゼルにかけられた陽介の絵。その前に立つと、言いようのない感情が胸を締め付けた。陽介を失った悲しみ。自分の才能への絶望。あいつの本心に気づけなかった後悔。そして、未完のままのキャンバスが、あまりにも寂しかった。
「……完成させてやりたいよ、陽介」
呟きは、誰に言うでもなく、虚空に溶けた。その時だった。俺の右手は、まるで自分の意志ではないかのように、自然とパレットナイフを手に取った。そして、使いかけで固まり始めた青の絵の具を、迷いなくパレットに絞り出す。
何が起きているのか、自分でも分からなかった。頭の一部は冷静なまま、もう一人の自分が身体を動かしているような、奇妙な感覚。俺の指は、慣れた手つきで筆を握り、キャンバスに向かった。陽介の空と雲に、俺の青を重ねていく。陽介のタッチと、俺のタッチが混じり合う。それはまるで、二人で対話しながら、一枚の絵を編み上げていくような、不思議な時間だった。
そして、ふと我に返った時、俺は自分の足元を見て凍りついた。床に、小さな青い花びらが落ちていた。いや、花びらじゃない。乾いた絵の具の欠片だ。それは、あのネモフィラの花を描いた時と同じ色だった。
――まさか。
全身の血が逆流するような感覚に襲われる。思い出した。陽介が亡くなった数日後、悲しみに耐えきれず、俺は夜中にここへ来た。そして、陽介の絵の前に立ち、無意識のうちに筆を取っていた。陽介を失った喪失感と、彼と繋がりたいという強すぎる願いが、俺に記憶のない行動を取らせていたのだ。あのネモフィラの花は、陽介の幻影が見せた奇跡なんかじゃない。俺自身の、孤独な心が描き加えた、幻の風景だった。
犯人は、僕だった。陽介の絵を汚したのも、謎を作り出したのも、全部。俺は、陽介の親友で、共犯者だったのだ。膝から崩れ落ち、声にならない嗚咽が漏れた。月明かりに照らされた絵は、俺たちの共作を、ただ静かに見下ろしていた。
第四章 二人のアトリエ
すべてを悟った俺は、もう迷わなかった。
夜の美術室で、陽介と二人きりのアトリエで、俺は絵を完成させることを決意した。それは贖罪ではなかった。俺の中に生き続ける陽介との、最後の共同作業だった。
俺は陽介のタッチを真似るのをやめた。陽介が描いた突き抜けるような夏の空に、俺の、あの深く静かな青を重ねていく。陽介の力強い入道雲の隣に、俺の繊細で、どこか寂しげな雲を浮かばせた。陽介が遺した光と、俺が抱える影。二つが混じり合い、反発し、そして溶け合って、一つの世界を創り上げていく。キャンバスは、俺と陽介の魂が対話する場所になった。
『やっぱり、蒼の青は最高だな』
風が窓を揺らすたび、陽介の声が聞こえる気がした。俺は涙で滲む視界のまま、何度も筆を動かした。右下には、俺が最初に描き加えたネモフィラの花。そして、その隣に、陽介が好きだった向日葵を、俺が描き足した。太陽に向かって咲く、あいつみたいな花だ。
数週間後、絵は完成した。タイトルはつけなかった。ただ、『相葉陽介・水野蒼』と、二人の名前を並べて記した。完成した絵は、夏の眩しさと、その裏側にある切ないほどの静けさが同居する、不思議な力を持っていた。見る人の心を揺さぶる、と顧問の先生は言ってくれた。
秋の文化祭。その絵は、美術室の一番目立つ壁に飾られた。多くの生徒が足を止め、絵の前で何かを語り合っている。賞や名声なんて、どうでもよかった。俺たちの夏が、確かにそこにあった。それだけで、十分だった。
俺は一人、夕焼けに染まる屋上に出て、冷たい風に吹かれていた。もう、美術室で陽介の幻影を探すことはないだろう。あいつは、俺が描く絵の中に、俺の心の中に、確かな存在として生き続けていくのだから。
喪失は、終わりじゃない。何かを生み出すための、始まりなのかもしれない。空っぽになったはずのキャンバスに、俺はこれからも、君との思い出を描き足していく。
風が頬を撫でた。その風の中に、懐かしい声が重なる。
『お前の絵は、やっぱり最高だよ、蒼』
俺は空を見上げて、静かに、でも、確かに微笑んだ。空のキャンバスは、無限に広がっていた。