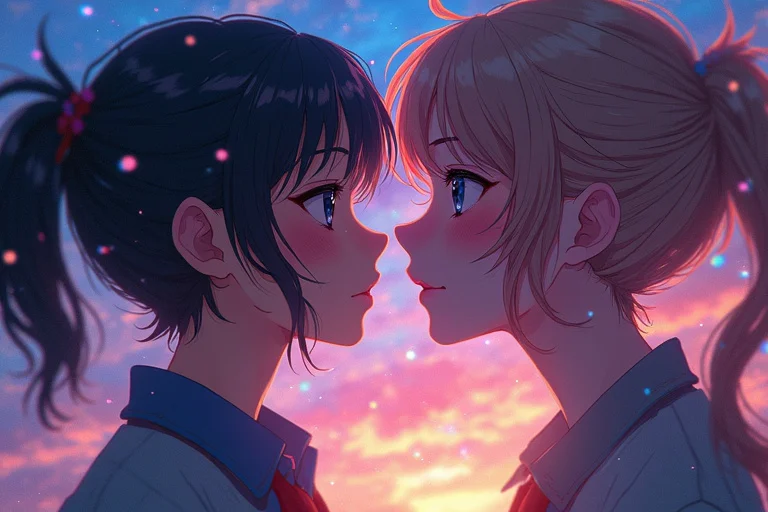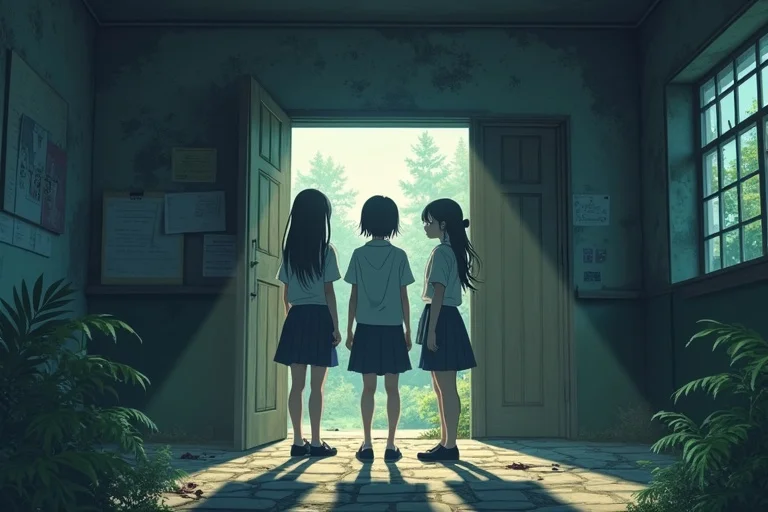「なあ高槻、何か面白いこと、ないかな」
放課後の教室。西陽が差し込む窓際で、俺、高槻蓮(たかつきれん)は頬杖をつきながら親友の悪態に相槌を打った。面白いこと。そんなものがこの平凡な町の、平凡な高校に転がっているはずもない。繰り返される授業、代わり映えのしない通学路。俺たちの世界は、退屈という名の分厚い雲に覆われているようだった。
「あるよ」
不意に、背後から弾むような声がした。振り返ると、そこに立っていたのは夏目陽葵(なつめひまり)。いつも太陽みたいに笑う、クラスの女子だ。彼女は大きな目をキラキラさせながら、一枚の設計図のような紙を俺たちの机に広げた。
「文化祭の夜にさ、この空にオーロラ、作らない?」
「はあ? オーロラ?」
あまりに突拍子もない提案に、俺も友人も呆気にとられた。陽葵は構わず続ける。
「物理部の部室で見つけたの。卒業したお兄ちゃんの置き土産。理論上は可能だって! 高出力のレーザーと、超音波で作ったエアロゾルのスクリーンに……」
専門用語を並べる陽葵の熱弁を、俺は「非現実的だ」と一蹴するつもりだった。だが、彼女の指差す設計図の緻密さと、何より「不可能に挑戦する」という馬鹿げた響きが、心の奥底で錆びついていた歯車を、ギリリと軋ませた。
「……面白そうじゃん」
俺の口から、自分でも意外な言葉がこぼれた。その瞬間、陽葵の笑顔が満開になった。俺の退屈な日常が、音を立てて崩れ始めた合図だった。
プロジェクト・オーロラ。それが俺たちの作戦名になった。
仲間はすぐに集まった。とは言っても、陽葵の熱意に当てられた物理部の変わり者たち、機材なら任せろと胸を張る放送部のオタク、そして「面白そうだから」という理由だけで首を突っ込んできた数名のクラスメイト。寄せ集めのドリームチームだ。
しかし、現実は甘くなかった。最大の壁は、予算と学校の許可だ。
生徒会長の氷川は、絵に描いたような堅物だった。「前例がない」「危険が伴う」「学校の品位を損なう」。彼の正論は、俺たちの計画を真正面から否定した。
「じゃあ、前例を作ればいい。危険がないって証明すればいい。品位って何ですか? 全員が空を見上げて感動する。それ以上に品位のあることなんて、ありますか?」
会議室で、俺は必死に食い下がっていた。隣に立つ陽葵の、真っ直ぐな視線を感じる。いつの間にか、俺はこの計画の誰よりも熱くなっていた。俺たちの熱意が伝わったのか、あるいは呆れられたのか、氷川は一つの条件を出した。
「文化祭一週間前までに、安全性を証明できる小規模なデモンストレーションを行うこと。それができなければ、計画は即刻中止だ」
そこからの日々は、まさに戦争だった。
資金集めのために校内クラウドファンディングを立ち上げ、機材のパーツを求めて街中のジャンク屋を駆けずり回った。夜な夜な物理準備室に集まっては、ああでもないこうでもないと議論を重ね、試作品のレーザーがショートしてブレーカーを落とすこと数回。失敗の連続に、仲間内で険悪な空気が流れることもあった。
「もう無理だよ……」
デモ前夜。実験はまたしても失敗に終わり、誰かが弱音を吐いた。諦めの色が、部室全体に伝染していく。俺も、唇を噛み締めることしかできなかった。
その時、陽葵がバンッ!と机を叩いた。
「まだ終わってない! 失敗したっていいじゃん! 間違えたっていい! みんなでこうして、一つのことにムキになってる今が、最高に楽しいんじゃないの!?」
彼女の涙声の叫びに、全員がハッとした。そうだ。いつの間にか俺たちは、成功という結果にばかり囚われていた。この、どうしようもなく無謀で、熱くて、キラキラした時間そのものが、宝物だったんだ。
「……ごめん。もう一回、回路図見直そう」
俺が言うと、みんなが頷いた。その夜、俺たちは奇跡的に欠陥を発見し、朝日が昇る頃、小さな箱庭のような空間に、儚く揺れるミニチュアの光のカーテンを灯すことに成功した。
そして、文化祭のフィナーレ。後夜祭の喧騒が最高潮に達した時。
全校生徒が見守る校庭の真ん中で、俺は陽葵と並んで巨大な装置の前に立っていた。隣には、いつの間にか協力を申し出てくれた生徒会長の氷川の姿もある。
「3、2、1……!」
陽葵のカウントダウンで、俺は覚悟を決めてスイッチを入れた。
ブウン、という低い唸り声と共に、装置が振動する。だが、それだけだった。夜空には、満月と星々が浮かぶだけ。会場から、クスクスという笑い声が漏れ始める。
「……ダメ、だったか」
俺が天を仰いで呟いた、その時だった。
「見て! あれ!」
誰かの叫び声。指差す先を、誰もが息を呑んで見上げた。
夜空の一点に、淡い緑色の光が灯っている。それはまるで巨大な絵筆で描かれたかのように、ゆっくりと夜空に滲み、そして、ゆらりと揺れ始めた。本物のオーロラに比べれば、あまりに拙く、不完全な光の帯。
でも、それは間違いなく、俺たちが作り上げた光だった。
次の瞬間、地鳴りのような歓声が夜空を震わせた。誰もが、ただ空を見上げていた。スマホを向ける者、隣の友人と肩を組む者、静かに涙を流す教師。退屈だったはずの世界が、俺たちの手で、七色に輝いていた。
「……やったな、高槻」
光に照らされた陽葵が、最高の笑顔で言った。
「ああ。俺たちの青春、捨てたもんじゃなかったな」
揺らめく光のカーテンの下で、俺はそう答えた。心臓が、ワクワクと音を立てて脈打っている。このどうしようもなく最高な瞬間を、俺は一生忘れないだろう。