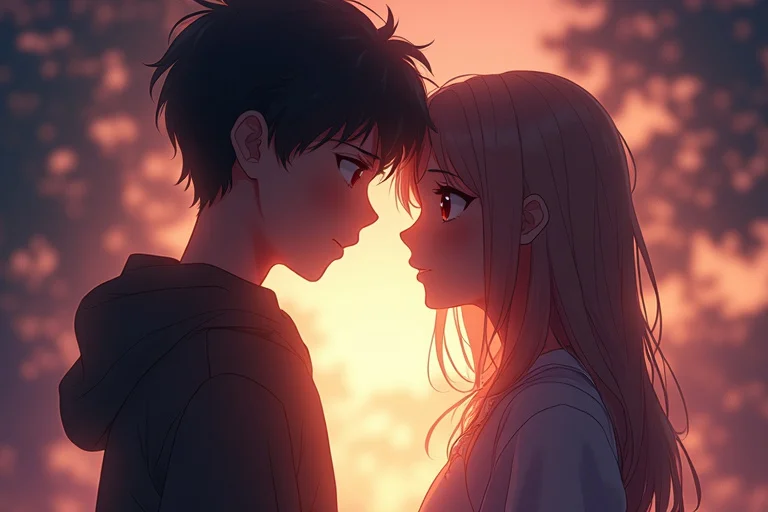「またメロンパンかよ」
昼休みの購買は戦場だ。その日の目玉商品であるはずの「激辛ヤキソバパン」は、チャイムが鳴って三分で姿を消した。棚に残るのは、いつも最後まで売れ残るメロンパンの群れ。俺、相沢海斗(あいざわかいと)は、溜息と共にその一つを手に取った。平凡な高校二年の、平凡な昼飯。世界はこんなにも退屈で、予測可能にできている。
「つまんない顔しないの、カイ。そのメロンパンだって、誰かの青春かもしれないでしょ」
背後から声をかけてきたのは、ポニーテールを揺らすクラスメイト、橘陽菜(たちばなひな)だ。彼女は退屈という言葉が辞書にないような人間で、いつだって面白そうなことの匂いを嗅ぎつけては、俺を引っ張り回す。
「青春ねぇ……。俺の青春、メロンパン味か」
「それも一興! で、今日の議題は?」
陽菜が指す『議題』とは、俺たちが勝手に名付けた「放課後探偵団」の活動のことだ。メンバーは俺と陽菜、そしてガジェットオタクの友人、鈴木健太(すずきけんた)の三人。活動内容といえば、「体育教官室から消えたホイッスルの行方」とか、「女子トイレに夜な夜な現れる謎の鼻歌の正体」とか、そんなくだらない謎を解き明かすだけのお遊びだ。
その日の放課後、俺たちは新たな『事件』の現場にいた。卒業アルバムの準備で、臨時で開放された『開かずの資料室』だ。埃っぽい空気の中、古いトロフィーや黄ばんだ賞状が詰め込まれた段ボールの山を、陽菜が猟犬のように漁っていた。
「あった! なんか面白そうなの!」
陽菜が掲げたのは、一枚のセピア色の写真だった。俺たちの高校の旧制服を着た、五人の生徒が屋上らしき場所で笑っている。だが、誰も見覚えのない顔だ。
「古い写真だな」健太がスマホのライトで照らしながら言う。
「見て、裏!」陽菜が声を弾ませた。
写真の裏には、万年筆で書かれたような、流麗な文字があった。
『青の箱舟、夏の座標』
そして、その下には意味不明な数字と記号の羅列。『N35.70 E139.77』『α-Cyg』『20:32』。
「何かの暗号?」俺が呟くと、陽菜の目がきらりと光った。「決まりだね。今日の議題は『青の箱舟を探せ!』よ!」
こうして、俺たちの、退屈を塗り替える夏が始まった。
最初の数日は手掛かりゼロだった。健太が持ち前の知識で記号の解読にあたり、俺と陽菜は校内の古株の先生に聞き込みを続けた。そして、突破口を開いたのは健太だった。
「カイ、陽菜! わかったぞ!」
健太が興奮気味に見せてきたのは、スマホの地図アプリだった。『N35.70 E139.77』は、驚くべきことに、俺たちがいるこの高校の校舎そのものを指す緯度経度だったのだ。
「じゃあ、『α-Cyg』と『20:32』は?」
「『α-Cyg』は、はくちょう座のデネブを指す恒星の符号だ。そして『20:32』は、おそらく時間」
学校。星。時間。バラバラのピースが、頭の中でカチリと音を立てた気がした。俺たちは図書室へ走り、郷土史や学校の古い記録を片っ端から調べ上げた。そして、見つけたのだ。数十年前の文集に載っていた、『天文部活動日誌』という小さな記事を。
そこには、手作りの望遠鏡で夜空を観察する生徒たちの生き生きとした姿が綴られていた。彼らは、特に夏の大三角を愛し、その中心で輝くデネブを『道標の星』と呼んでいたという。
「写真の五人は、きっと天文部員だったんだ!」陽菜が確信に満ちた声で言った。
「でも、肝心の『青の箱舟』が何なのか、わからないままじゃないか」
謎は最後のピースを残すのみとなっていた。俺たちは来る日も来る日も、放課後に集まっては頭を捻った。日はどんどん短くなり、夏の終わりがすぐそこまで迫っていた。
「……なあ、今日って何日だ?」ふと、俺はカレンダーを見た。八月三十一日。夏休み最終日。
「まさか!」健太が叫んだ。「夏至じゃない! 今日だ!」
「どういうこと?」
「デネブが南の空で最も高くなる、南中時刻! 今年の夏休み期間中で、それが『20:32』になるのは、今日だけなんだ!」
心臓が大きく跳ねた。最後の暗号は、日付を指定していたのだ。俺たちは顔を見合わせ、頷き、走り出した。目指すは、校舎の屋上。普段は固く閉ざされている、あの写真の舞台だ。
幸いにも、管理人室の鍵束から屋上の鍵を見つけ出すのは、放課後探偵団のスキルがあれば容易いことだった。錆びた扉を開けると、生ぬるい夜風が頬を撫でた。眼下には、宝石を散りばめたような街の夜景が広がっている。
「すごい……」
陽菜が感嘆の声を漏らす。空を見上げると、都会の光にも負けず、夏の大三角がくっきりと輝いていた。そして、その頂点の一つ、デネブが力強く瞬いている。
「南中時刻まで、あと一分……」
健太が腕時計を見ながら言う。俺たちは固唾を飲んで、その時を待った。そして、午後八時三十二分。デネブが真南の空に到達した、その瞬間。
「あれ!」
陽菜が指さした。給水塔の、古びた壁。デネブの光が落ちるその一点に、何かが描かれている。近づいてみると、それはペンキで描かれた、小さな青い箱の絵だった。まさしく『青の箱舟』のマーク。
マークの下のレンガが、一つだけ不自然に緩んでいた。指をかけると、ゴトリと外れ、中から小さな金属製の箱が現れた。
ゆっくりと蓋を開ける。中に入っていたのは、一本のカセットテープと、一枚の色褪せた手紙だった。俺たちは、健太がいつも持ち歩いている古いカセットプレーヤーにテープを入れた。
『……聞こえるか? こちら、北高天文部』
ノイズ混じりの、少し気恥ずかしそうな若い声。そして、楽しそうな笑い声が続く。
『俺たちは、新しい彗星を見つけた。誰にも知られていない、俺たちだけの彗星だ。名前は『青の箱舟』。この声が、いつか未来の誰かに届くことを願って、この箱舟を宇宙に、いや、時間の海に流すことにする』
手紙には、こう書かれていた。
『退屈な毎日を変えるのは、いつだってほんの少しの好奇心と、空を見上げる勇気だ。君たちの空にも、まだ見ぬ箱舟が浮かんでいるはずだ。健闘を祈る。未来の後輩たちへ』
俺たちは、言葉もなく夜空を見上げた。カセットテープからは、何十年も前の先輩たちの、夢を語る声が流れ続けている。
退屈だったはずの世界が、急にきらめいて見えた。メロンパンの味しかしなかった俺の青春に、星空の味が加わった気がした。
「ねえ、カイ」隣で陽菜が笑った。「私たちの箱舟も、探してみない?」
俺は黙って頷いた。夜空に浮かぶ無数の星が、まるで無限の冒険への招待状のように、またたいていた。俺たちの夏は、まだ始まったばかりだ。